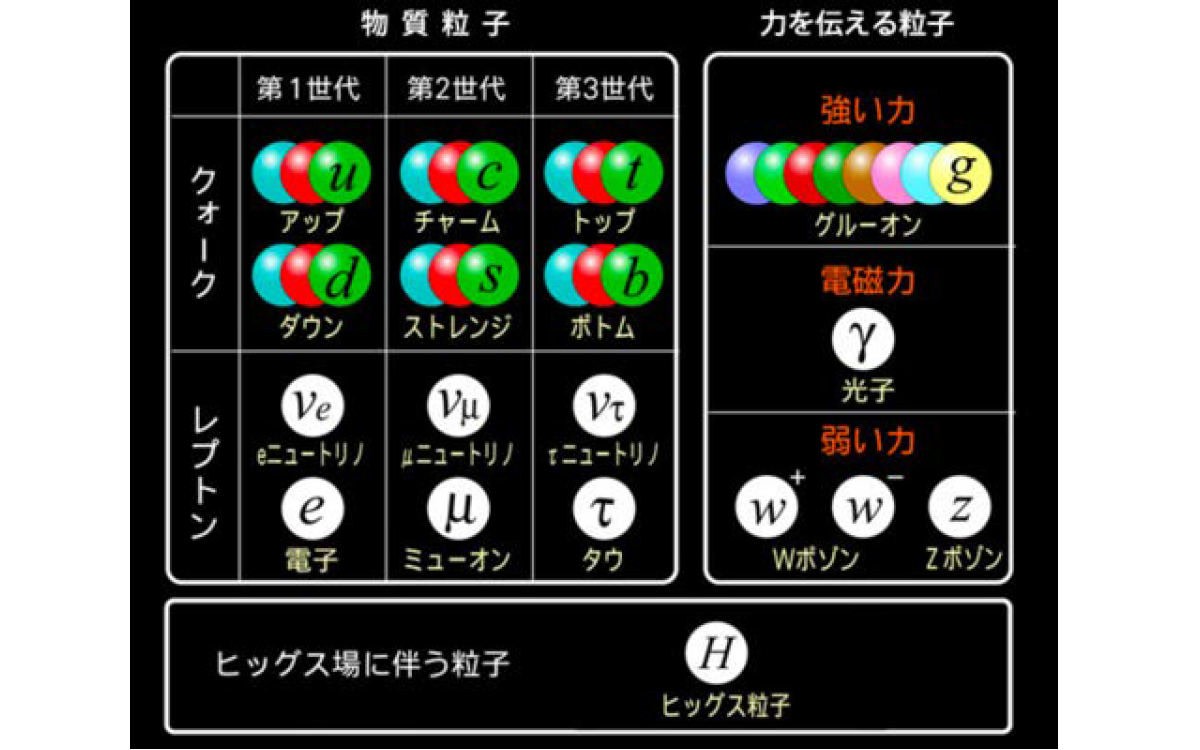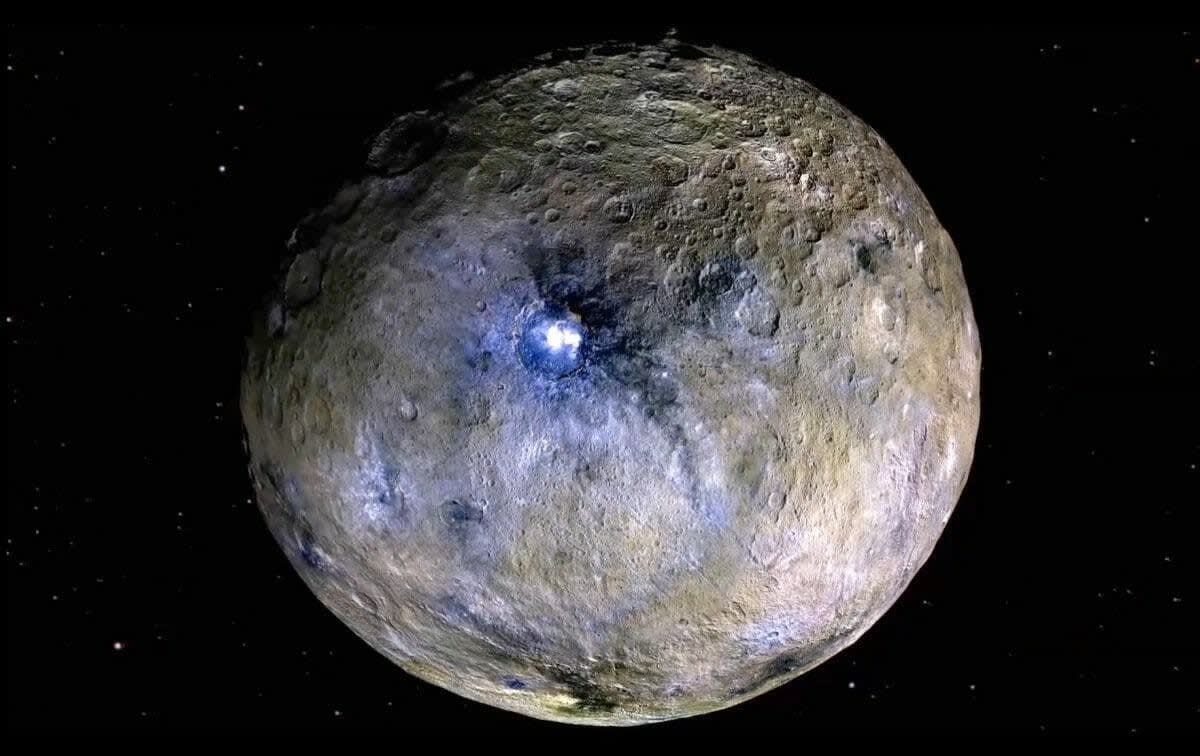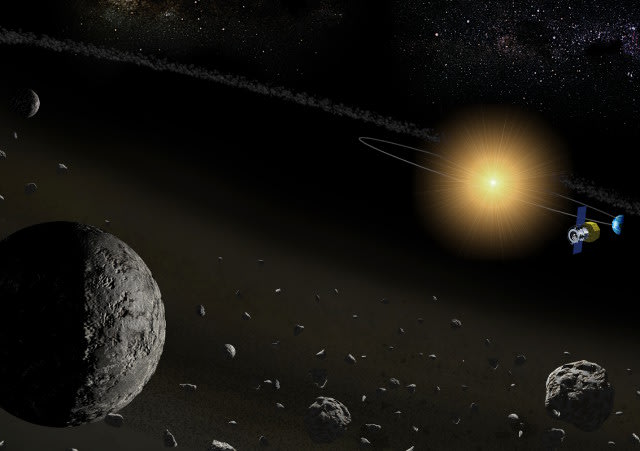国際宇宙ステーションへ物資輸送を担う無人補給船“こうのとり 9号機(HTV9)”が、8月20日に大気圏に再突入しました。
これまでの全てのミッションを成功させ、国際宇宙ステーションの運用に欠かすことのできない重要な役割を担ってきた“こうのとり”。
これにより、初号機から始まった11年間の運用を終えたことになります。
国際宇宙ステーションへの最終便“こうのとり 9号機(HTV9)”
“こうのとり 9号機(HTV9)”を搭載したH-IIBロケット9号機は、5月21日(水)午前2時31分に、種子島宇宙センターの第2発射場から予定通りに打ち上げを実施。
“こうのとり 9号機(HTV9)”は、国際宇宙ステーションのロボットアームに把持され、この後“ハーモニー・モジュール(第2結合部)”へ取り付けられれ、補給物資の搬出作業が行われています。
補給物資に含まれていたのは、JAXAが調達した国産の生鮮食品。
初搭載の“キウイフルーツ”のほか、“パプリカ”や“河内晩柑(かわちばんかん)”、“清美オレンジ”、“レモン”、“温州みかん”が国際宇宙ステーションの宇宙飛行士に届けられました。
ハッチが閉じられると“こうのとり 9号機(HTV9)”は、軌道離脱のためのエンジン噴射を実施し国際宇宙ステーションを離脱します。
そして、8月20日(水)午後3時40分(日本時間)、第3回軌道離脱マヌーバを実施した“こうのとり 9号機(HTV9)”は大気圏への再突入を無事完遂。
搭載していたゴミなどとともに、再突入時の熱や衝撃によって破壊され、燃え尽きたようです。
無人補給船“こうのとり(H-II Transfer Vehicle:HTV)”
今回でシリーズ最終号機となった“こうのとり”。
開発が始まったのは1988年、10年以上の歳月をかけて実用化され、2009年の技術実証機からは日本の物資に限らずISS国際パートナーの物資も輸送してきました。
また、“こうのとり”は大型の実験装置を国際宇宙ステーションへ輸送できる唯一の宇宙船として、国際宇宙ステーションの運用に欠かすことのできない重要な役割を担っていました。
JAXA自身も“こうのとり”の開発・打ち上げ・運用を通じて多くの技術や知見を獲得し、これまでの全てのミッションを成功させてきました。
国際宇宙ステーションのような有人施設に飛行・接近する宇宙機には、厳しい安全基準を満たすことが課せられます。
このため、JAXAが開発したのがランデブ・キュプチャでした。
これは、宇宙機を国際宇宙ステーションに対して相対停止させてロボットアームで把持する技術。
もちろん“こうのとり”に適用され、この技術はアメリカの補給機にも採用され国際標準になったそうです。
さらに、7号機での小型回収カプセル、9号機の無線LAN伝送など、“こうのとり”の運用機会を活用した技術実証を通じて、今後の有人宇宙活動の進展につながる成果を挙げてきました。
その“こうのとり”が最終号機を迎えたのは寂しいことですが、すでにJAXAは後継機となる新型の無人補給船“HTV-X”の開発を進めています。
これまでに蓄積してきた技術や知見を活かして開発される無人補給船“HTV-X”。
輸送能力や運用性を向上させ、月周回有人拠点“Gateway”への物資補給などもにも活用可能な発展性のある宇宙機になるようですよ。
こちらの記事もどうぞ
これまでの全てのミッションを成功させ、国際宇宙ステーションの運用に欠かすことのできない重要な役割を担ってきた“こうのとり”。
これにより、初号機から始まった11年間の運用を終えたことになります。
 |
| “こうのとり 9号機(HTV9)”を搭載したH-IIBロケット9号機の打ち上げ。(Credit: JAXA) |
国際宇宙ステーションへの最終便“こうのとり 9号機(HTV9)”
“こうのとり 9号機(HTV9)”を搭載したH-IIBロケット9号機は、5月21日(水)午前2時31分に、種子島宇宙センターの第2発射場から予定通りに打ち上げを実施。
“こうのとり 9号機(HTV9)”は、国際宇宙ステーションのロボットアームに把持され、この後“ハーモニー・モジュール(第2結合部)”へ取り付けられれ、補給物資の搬出作業が行われています。
 |
| 国際宇宙ステーションのロボットアームに把持された“こうのとり 9号機(HTV9)”。(Credit: JAXA/NASA) |
初搭載の“キウイフルーツ”のほか、“パプリカ”や“河内晩柑(かわちばんかん)”、“清美オレンジ”、“レモン”、“温州みかん”が国際宇宙ステーションの宇宙飛行士に届けられました。
一方で“こうのとり 9号機(HTV9)”には、国際宇宙ステーションで発生したゴミや不要になった機器などが積み込まれた。
ハッチが閉じられると“こうのとり 9号機(HTV9)”は、軌道離脱のためのエンジン噴射を実施し国際宇宙ステーションを離脱します。
そして、8月20日(水)午後3時40分(日本時間)、第3回軌道離脱マヌーバを実施した“こうのとり 9号機(HTV9)”は大気圏への再突入を無事完遂。
搭載していたゴミなどとともに、再突入時の熱や衝撃によって破壊され、燃え尽きたようです。
 |
| JAXAが調達し、国際宇宙ステーションの宇宙飛行士に届けらえた国産の生鮮食品。(Credit: JAXA) |
無人補給船“こうのとり(H-II Transfer Vehicle:HTV)”
今回でシリーズ最終号機となった“こうのとり”。
開発が始まったのは1988年、10年以上の歳月をかけて実用化され、2009年の技術実証機からは日本の物資に限らずISS国際パートナーの物資も輸送してきました。
また、“こうのとり”は大型の実験装置を国際宇宙ステーションへ輸送できる唯一の宇宙船として、国際宇宙ステーションの運用に欠かすことのできない重要な役割を担っていました。
総重量6トンという世界最大級の積載能力を持つ。大きく貢献できたのは、設計寿命を超えたバッテリーに替わる新型バッテリを6号機から継続して輸送してきたこと。
JAXA自身も“こうのとり”の開発・打ち上げ・運用を通じて多くの技術や知見を獲得し、これまでの全てのミッションを成功させてきました。
国際宇宙ステーションのような有人施設に飛行・接近する宇宙機には、厳しい安全基準を満たすことが課せられます。
このため、JAXAが開発したのがランデブ・キュプチャでした。
これは、宇宙機を国際宇宙ステーションに対して相対停止させてロボットアームで把持する技術。
もちろん“こうのとり”に適用され、この技術はアメリカの補給機にも採用され国際標準になったそうです。
さらに、7号機での小型回収カプセル、9号機の無線LAN伝送など、“こうのとり”の運用機会を活用した技術実証を通じて、今後の有人宇宙活動の進展につながる成果を挙げてきました。
その“こうのとり”が最終号機を迎えたのは寂しいことですが、すでにJAXAは後継機となる新型の無人補給船“HTV-X”の開発を進めています。
これまでに蓄積してきた技術や知見を活かして開発される無人補給船“HTV-X”。
輸送能力や運用性を向上させ、月周回有人拠点“Gateway”への物資補給などもにも活用可能な発展性のある宇宙機になるようですよ。
こちらの記事もどうぞ