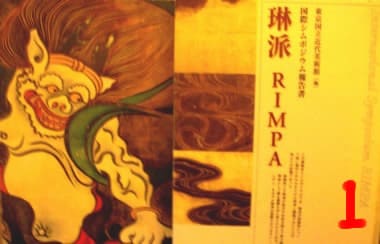
2004年8~10月にかけて東京国立近代美術館において「琳派 RIMPA」展が開催されました。今回取り上げるこの本は、その展覧会に合わせて同年8月28日に開かれた国際シンポジウムをまとめたものであります。ボクはその展覧会のことをうっすらと記憶しています。当時は日本画など興味がなかったので、その展覧会には行かなかったのですが、タイトルに「RIMPA」なる横文字があり何かとても斬新な感じがしたのでした。ただ先にも書いたように日本画には全く興味が持てず、わざわざ美術館に行こうなどと思わなかったのですが。しかし、時間がたつと(歳をとると?)その関心も変化して、一年を振り返ると日本に関連した美術の企画の展覧会の方がよく見ているじゃないということもあって、時間とは行動や趣向を少しずつも変えていくのだなということがわかります。ということで今回はその「琳派 RIMPA」展をきっかけに生まれた本を読んだそのメモのようなものです。
■琳派とは何か(村重寧)
・琳派は私淑の関係で成り立った画派と言われる。世を隔てた先人たちの芸術に傾倒して私的に学び、教わる、そうした相承関係が流れの軸をなしている。それは琳派を代表する宗達、光琳、抱一の主要な三人の画家が一時たりとも生存の時期を同じくしていない。
・日本画家・加山又造の言葉、「私のことを人は『現代の琳派』だというが、私自信は琳派をやっているという意識はない。ただ、日本の伝統の中にあるおもしろい形や美しい色を自分の感覚で新たに再現してみたい、と常に思って描いている。光琳だって同じだったと思う。」
・琳派を語る時、その特徴として「金銀を多様した華麗な装飾性」(これに加えて「日本的」「平面的」などの言葉で補われることもある)というような言葉がよく使われるが、これではあまりにちゅうしょうてきで、日本の絵画は大方これに当てはまってしまう。
・琳派の特色として指摘される「たらし込み」の技法の使用。墨を塗って乾かないうちに濃度の違う墨をその上に注ぎ、両者が複雑、混然と混ざり合って滲みを持った独特の墨面を作り出す技法は、具体的な技法であるため、琳派を特徴づけるには有効な材料と言える。
・光琳の「紅白梅図」を見ると「たらし込み」が装飾に対しても十分機能し、有効であることがわかる。現実と飾りの空間。異なる二つの傾向が互いに同化しあって、琳派特有の装飾絵画の世界を生み出した。
■近代における「琳派」の出発と研究の歩み(玉蟲敏子)
・1900年パリ万博に合わせて編纂された日本政府主導の美術史「稿本日本帝国美術略史」に一画派として「光琳派」を設定した。
・1903年東京帝室博物館で「特別展覧会」が開かれ光琳派の作品が並べられ(宗達、光琳、抱一の「風神雷神図屏風」の揃い踏み)、その年から3年かけて「光琳派画集」全五巻が刊行された。さらには三井呉服店(三越)のPR誌「みやこぶり」を刊行、光琳模様を紹介するキャンペーンが行われた。
・「風神雷神」について江戸時代なりの文脈があった。日光東照宮の陽明門の裏側に「風神雷神像」安直、浅草寺の雷門の「風神雷神像」があり江戸市民のアイドルであった。
・「琳派」という呼び方が使われたのは光琳派の略称であったことは間違いないが、当初はマイナスのニュアンスを含むが故の略称であったことをほめのかす文脈があった。
・「琳派」という伝統の系譜に収斂されていく名称を獲得したのは1972年の東京国立博物館の琳派展の功績が大きい。
■グスタフ・クリムト及び1900年前後のウィーンにおけるRIMPA-ARTの意義(ヨハネス・ヴィーニンガー)
・グスタフ・クリムトは日本美術が好きで、彼自身所有しているものがあり浮世絵はアトリエを飾っていたし、日本美術の本も持っていた。
・クリムトの作品「ダナエ」と光琳の「紅白梅図屏風」右隻がいかに似た構図であるかに驚かされる。その上ではクリムトはイメージ・ソースを隠すために光琳の構図を反転させている。
・クリムトは光琳の「紅白梅図屏風」に魅惑されたに違いない。だからこそクリムトは「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像Ⅰ」の中で「白梅」半双の構図を踏襲したのだ。
・クリムトの「接吻」の画面構成は宗達派による「伊勢物語」の逃避行の場面に似てないか?
・クリムトが「光琳画集」のようなものから日本の花の絵の図版をよく見ていたかもしれないということが想像できる。
・クリムトがウィーンで描いた作品は、琳派似通った構図と表現を持っていた。1900年から1910年という時期には、一種の「世界芸術」の形成が見られた。様々な芸術的関連は、19世紀の未知のもののコピーの段階から、1900年前後の新しいものを創り出すことに触発された段階へ、そしてさらに同時発生的なアヴァンギャルドの革新へという、異なった段階へと向かった。地理的な距離であるとか局地的にどのような運動があったなどというこ、とはともに重要性を失いつつある。
 |
琳派RIMPA―国際シムポジウム報告書 |
| 東京国立近代美術館 | |
| ブリュッケ |
 |
すぐわかる琳派の美術 |
| 仲町 啓子 | |
| 東京美術 |
 |
光琳デザイン |
| MOA美術館 | |
| 淡交社 |
 |
琳派の愉しみ (ランダムハウス講談社MOOK) |
| ランダムハウス講談社 編 | |
| 武田ランダムハウスジャパン |










 ⇒
⇒







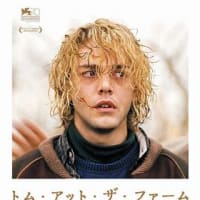









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます