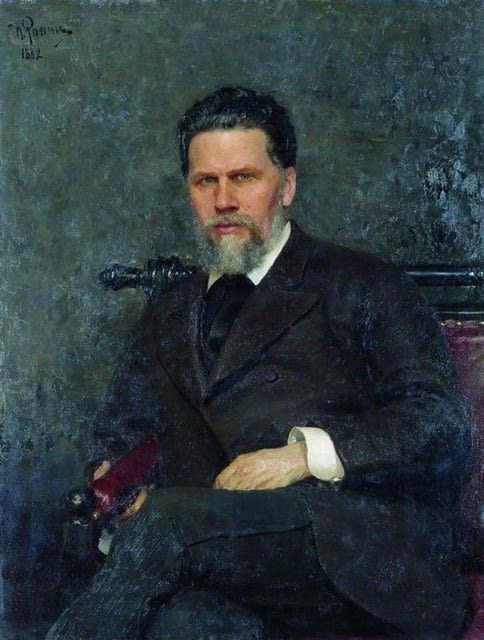【tv】100分de名著「風と共に去りぬ」(第3回)
【tv】100分de名著「風と共に去りぬ」(第3回)
運命に立ち向かう女

1回25分×4回で1つの作品を読み解く番組。2019年最初の作品はマーガレット・ミッチェル( Wikipedia)の「風と共に去りぬ」(
Wikipedia)の「風と共に去りぬ」( Wikipedia)で、講師は2015年に新訳をした翻訳家の鴻巣友季子さん。今回はその2回目。1回目の記事は
Wikipedia)で、講師は2015年に新訳をした翻訳家の鴻巣友季子さん。今回はその2回目。1回目の記事は コチラ。2回目の記事は
コチラ。2回目の記事は コチラ。
コチラ。
 伊集院光氏:スカーレットは魅力的な人。身近にいたらどうかと思うが、主人公としては惹かれる。
伊集院光氏:スカーレットは魅力的な人。身近にいたらどうかと思うが、主人公としては惹かれる。
スカーレットは作中の女性たちからは総スカンだが、読者には嫌われない。
 【現在の状況】
【現在の状況】
南北戦争後<タラ>で、父ジェラルド、妹スエレン、妹キャリーン、息子ウェイド、アシュリ、メラニー、アシュリの息子ボーと使用人たちと暮らす。北軍による軍政下で<タラ>は重税に苦しんでいる。払えないと競売にかけられて人手に渡ってしまう。スカーレットはレット・バトラーに会うためにアトランタへ。
 スカーレットはカーテンでドレスを作り、アトランタで投獄されているレットに会いに行く。優雅な暮らしをしているふりをしてレットを誘惑しようとするが、荒れた手のひらを見て嘘を見破られてしまう。結局レットから借金できず、ふてくされてアトランタの街を歩いていると、妹スエレンの婚約者フランク・ケネディとばったり出会う。戦後開業した店が繁盛している様子。スカーレットはフランクのお金が妹のものになるのが許せない。スカーレットはフランクを奪おうと決心する。お金のためにレットと結婚しようとアトランタに来た時点でモラルもないため、妹の婚約者を奪うことに良心も痛まない。
スカーレットはカーテンでドレスを作り、アトランタで投獄されているレットに会いに行く。優雅な暮らしをしているふりをしてレットを誘惑しようとするが、荒れた手のひらを見て嘘を見破られてしまう。結局レットから借金できず、ふてくされてアトランタの街を歩いていると、妹スエレンの婚約者フランク・ケネディとばったり出会う。戦後開業した店が繁盛している様子。スカーレットはフランクのお金が妹のものになるのが許せない。スカーレットはフランクを奪おうと決心する。お金のためにレットと結婚しようとアトランタに来た時点でモラルもないため、妹の婚約者を奪うことに良心も痛まない。
【性悪ヒロインの嫌われない理由】
スカーレットが嫌われない理由は著者ミッチェルの文体にある。ほぼ共感しながらも突然「何言うてんねん!」と「ツッコミ」を入れる。いかに性悪であるかを描く。ボケとツッコミ文体。19世紀半ばまでの文体は、語り手は一段高い神の視点にいて、作者が説明してくれる。ミッチェルが選んだのはスカーレットの中に入り込んで物語る文体・話法。読者はスカーレットと一体化して波乱万丈の物語を楽しむ一方、語り手のツッコミでカタルシスを得て溜飲が下がる。
 うーん💦 文体のことになると原作を読んでいないのでよく分からない。映画を見ていても理想の女性ではないスカーレットは魅力的だったのので、それはやっぱり原作の力なのか、脚本の力なのか、演出なのか、演技なのか? まあ全部でしょう。とりわけヴィヴィアン・リーの力は大きかったかなと思う。
うーん💦 文体のことになると原作を読んでいないのでよく分からない。映画を見ていても理想の女性ではないスカーレットは魅力的だったのので、それはやっぱり原作の力なのか、脚本の力なのか、演出なのか、演技なのか? まあ全部でしょう。とりわけヴィヴィアン・リーの力は大きかったかなと思う。
スカーレットの中でボケとツッコミこそが作品の真骨頂! それが一番良く描かれているのがフランクから商売の自慢話を聞くシーン。口ではフランクをほめたたえているが、頭の中では彼をバカにしている。
鴻巣友季子さんが考えるボケとツッコミ文体の妙技は、2004年宝塚歌劇団「風と共に去りぬ」。2人のスカーレット(スカーレット:龍真咲、スカーレットⅡ:凪七瑠海)が登場し、表と裏の人格を演じ分けた。ボケとツッコミ、ユーモアとアイロニーが原作の神髄に迫る演出は他にないとのこと。ちなみに龍真咲は今回の朗読を担当。
 伊集院光氏:落語的に感じる。一人芝居的。書き分けはもちろん読み分けにも技術が必要。
伊集院光氏:落語的に感じる。一人芝居的。書き分けはもちろん読み分けにも技術が必要。
生き生きとした効果が出せる反面、危険なところもある話法。地の文にも登場人物の声、視点が溶け込んでいるため、語り手と登場人物の主張を混同する読者も出てしまう。「黒人の愚かな娘め!」などの暴言もある。地の文でミッチェルがスカーレットの真似をしている。暴言の吐くヒロインを揶揄的に提示しているだけ。でも、ミッチェルが差別主義だという誤解を生むこともある。
 確かにこの辺りのことは読む側にも客観的に見る力が必要かもしれない。スカーレットが暴言を吐く=作者の思いだと考えてしまうのは短絡的だけど、そういう疑惑は浮かんでしまうのも仕方がないかも🤔
確かにこの辺りのことは読む側にも客観的に見る力が必要かもしれない。スカーレットが暴言を吐く=作者の思いだと考えてしまうのは短絡的だけど、そういう疑惑は浮かんでしまうのも仕方がないかも🤔
 【その後の状況】
【その後の状況】
スカーレットはフランク・ケネディと結婚し、フランクのお金で<タラ>を救い、レットから借りた資金で製材所を買い取る。これが大当たり! 起業家スカーレットの才能開花! スカーレットは数学脳。3桁以上の足し算を暗算で解き、その場で見積もりを出して顧客を獲得していた。
スカーレットの事業が成功すると、フランクは嫌気がさす。"女に頭脳があると知ってひどく幻滅するというのも、男にありがちなことだった"との記載あり。
 伊集院光氏:今っぽい描写。今みんなが気づき始めたこと。
伊集院光氏:今っぽい描写。今みんなが気づき始めたこと。
マンスプレイニング(mansplaining):男性(man)と説明する(explain)を足した造語。男性が女性に「上から目線」でものを教えたがる行為。
フランクは典型的なマンスプレイニング。
 伊集院光氏:ゲームに興味を持った女の子に教えたいが、その子が自分より上手くなるのはイヤ。
伊集院光氏:ゲームに興味を持った女の子に教えたいが、その子が自分より上手くなるのはイヤ。
 これ! スゴイ分かる!! 若い頃、テニス、スキー、ボーリングと友達に誘われて行く先々でマンツーで教えられちゃって、他の人は楽しそうに遊んでるのに1人だけ部活みたいになっちゃった経験何度もある😣 そういう人って上手い女子には全然話しかけなかったもの! これだ!
これ! スゴイ分かる!! 若い頃、テニス、スキー、ボーリングと友達に誘われて行く先々でマンツーで教えられちゃって、他の人は楽しそうに遊んでるのに1人だけ部活みたいになっちゃった経験何度もある😣 そういう人って上手い女子には全然話しかけなかったもの! これだ!
 【現在の状況】
【現在の状況】
フランクとの間に娘エラをもうけるも産後すぐに働く。アトランタでの事業にアシュリを雇用する。ある日、1人で馬車に乗っていた時に、スラム街で男たちに襲われる。報復のためアシュリを隊長にKKK( Wikipedia)がスラム街に討ち入り。しかし、事前に情報が洩れ返り討ちにあったアシュリたちをレットが救う。
Wikipedia)がスラム街に討ち入り。しかし、事前に情報が洩れ返り討ちにあったアシュリたちをレットが救う。
 え
え スカーレット娘もいたの?😲
スカーレット娘もいたの?😲
 伊集院光氏:アシュリがKKKのリーダーというのはスゴイ話ではないか?
伊集院光氏:アシュリがKKKのリーダーというのはスゴイ話ではないか?
KKK(クー・クラックス・クラン/クラン団)は、南北戦争後に生まれた白人優勢主義秘密結社。旧南軍士官を中心に結成なので、元南軍士官であったアシュリが加わるのは不自然なことではない。クラン団を描いたことでミッチェルは差別主義だと批判されたこともある。
 ココが重要!:作品中に兄化を描くことと賛同することは全く別!
ココが重要!:作品中に兄化を描くことと賛同することは全く別!
作中でスカーレットやレットはKKKを批判しているし、彼らの行動は逆効果であると繰り返してもいる。
討ち入りの場面は最もシリアスな題材を扱っているがタッチはコミカル。デリケートなパート。
 アシュリを中心としたクラン団は返り討ちにあう。現場でとり逃したアシュリたちを逮捕しようと憲兵隊がスカーレットやメラニーの待つ家へ来る。何も知らないとしらを切るメラニー。そこへベロベロに酔ったように見えるアシュリがレットに介抱されながら帰って来る。アシュリたちを逮捕するという憲兵隊にメラニーは何の罪で?と反論する。スカーレットはこれが芝居であることを見抜く。レットはベル・ワトリングの色宿で一晩中一緒に飲んでいたとアリバイを証言する。そんな場所に夫がいたと知りメラニーは気絶する。
アシュリを中心としたクラン団は返り討ちにあう。現場でとり逃したアシュリたちを逮捕しようと憲兵隊がスカーレットやメラニーの待つ家へ来る。何も知らないとしらを切るメラニー。そこへベロベロに酔ったように見えるアシュリがレットに介抱されながら帰って来る。アシュリたちを逮捕するという憲兵隊にメラニーは何の罪で?と反論する。スカーレットはこれが芝居であることを見抜く。レットはベル・ワトリングの色宿で一晩中一緒に飲んでいたとアリバイを証言する。そんな場所に夫がいたと知りメラニーは気絶する。
フランクは討ち入りの際、頭を撃たれて死亡。実はミッチェルはフランクが穏やかに病死するシーンを書いたが、全編読み返してみると起伏に欠けたためKKKの討ち入りを採用。ミッチェルは風刺・パロディとしてクラン団(KKK)を取り入れた。
 伊集院光氏:コント的。KKKを使って討ち入るも失敗し、酔っ払いオチ。
伊集院光氏:コント的。KKKを使って討ち入るも失敗し、酔っ払いオチ。
 安部みちこアナウンサー:メラニーの方が頭がいいのでは?
安部みちこアナウンサー:メラニーの方が頭がいいのでは?
メラニーは機転と演技力で憲兵に対応。全てインプロビゼーション(即興)。頼れるのはメラニー。スカーレットとメラニーは2人で1人の補完的関係。
スカーレット(Scarlett)⇨赤
メラニー(Melanie)⇨黒 Melanieの語源はギリシャ語の黒を意味するメラニア。メラニン色素。
メラニーは聖女イメージがあるが、実は意地悪なところもある。黒メラニー。
 メラニーの家に昔なじみの女性たちが集っていた時、噂話の中心はやりたい放題のスカーレットであった。アシュリの妹インディアはかつて恋人をスカーレットに取られたことがありスカーレットを嫌っていた。インディアはフランクの死はスカーレットのせいであり、レットと浮気していたと吹聴する。するとメラニーは怒りで震え撤回を迫る。インディアが拒否すると、ではもう同居しない方がお互いのためだと冷たく言う。そして、スカーレットの家に行かないという人は我が家への訪問もご遠慮くださいと宣言する。
メラニーの家に昔なじみの女性たちが集っていた時、噂話の中心はやりたい放題のスカーレットであった。アシュリの妹インディアはかつて恋人をスカーレットに取られたことがありスカーレットを嫌っていた。インディアはフランクの死はスカーレットのせいであり、レットと浮気していたと吹聴する。するとメラニーは怒りで震え撤回を迫る。インディアが拒否すると、ではもう同居しない方がお互いのためだと冷たく言う。そして、スカーレットの家に行かないという人は我が家への訪問もご遠慮くださいと宣言する。
 伊集院光氏:スカーレットへの愛情が頂点に達するとメラニーは強くなる気がする。
伊集院光氏:スカーレットへの愛情が頂点に達するとメラニーは強くなる気がする。
メラニーの原動力はスカーレットへの愛情? アシュリへの愛とは違う種類の愛情を注ぐ。実は恋愛小説ではなく女性同士の複雑な友情を主眼にすると面白い。
 映画でもインディアがスカーレットの悪口を言うシーンはあったけれど、メラニーがここまで激怒した印象はなかったな🤔 映画ではメラニーは正しいことはキッパリと主張するけれど、あくまで優しい聖女イメージだった。これはやっぱり2人を対比したいという意図があったのでしょう😌
映画でもインディアがスカーレットの悪口を言うシーンはあったけれど、メラニーがここまで激怒した印象はなかったな🤔 映画ではメラニーは正しいことはキッパリと主張するけれど、あくまで優しい聖女イメージだった。これはやっぱり2人を対比したいという意図があったのでしょう😌
 伊集院光氏:女っぽいこと、男っぽいことに分けられていた時代に、スカーレットとメラニーは人間ぽい。
伊集院光氏:女っぽいこと、男っぽいことに分けられていた時代に、スカーレットとメラニーは人間ぽい。
2人ともどちらも持っている。両面性。人間として魅力的。
 あくまで映画を見た印象ではやっぱりスカーレットが魅力的だけれど、スカーレットのように分かりやすく強い人よりも、メラニーのように芯の強い女性になりたいと思っていた。結局、スカーレットほどの才覚も強さもなく、メラニーの芯の強さもない中途半端なおばさんになってしまった😢
あくまで映画を見た印象ではやっぱりスカーレットが魅力的だけれど、スカーレットのように分かりやすく強い人よりも、メラニーのように芯の強い女性になりたいと思っていた。結局、スカーレットほどの才覚も強さもなく、メラニーの芯の強さもない中途半端なおばさんになってしまった😢
今回のシーンでの映画裏話は何かしら聞いたことがあった気がするけど忘れてしまったのでなし😅 そういえばカーテンで洋服を作るって『サウンド・オブ・ミュージック』でも出て来るけど、元ネタは「風と共に去りぬ」かしらね? 映画の『風と共に去りぬ』ではフォレストグリーンのベルベットのような素材のカーテンでドレス作ってたね。カーテンでドレス1着は出来ると思うけど、16歳の娘を筆頭に7人分の服を作るってどんだけカーテン大きの?😲 まぁ、あのシーン好きだけど😅
 100分de名著:毎週月曜日 午後10:25~10:50 Eテレ
100分de名著:毎週月曜日 午後10:25~10:50 Eテレ
 100分de名著
100分de名著

 Wikipediaによりますと・・・
Wikipediaによりますと・・・












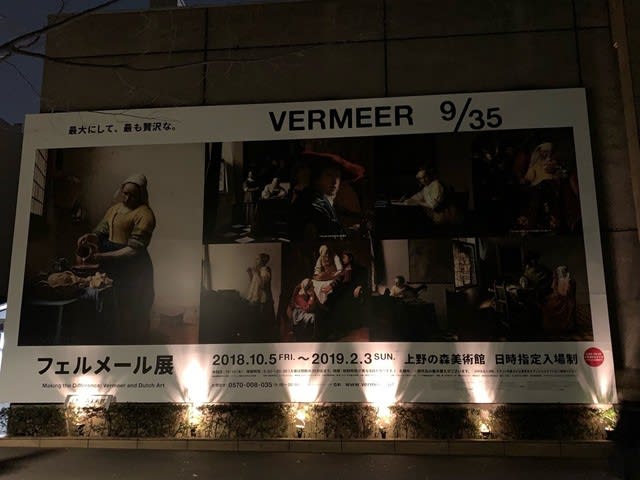




 【動画】浅田真央『メリー・ポピンズ リターンズ』魔法のエキシビション 予告編
【動画】浅田真央『メリー・ポピンズ リターンズ』魔法のエキシビション 予告編

 これね
これね 【tv】100分de名著「風と共に去りぬ」(第3回)
【tv】100分de名著「風と共に去りぬ」(第3回)
 伊集院光氏:スカーレットは魅力的な人。身近にいたらどうかと思うが、主人公としては惹かれる。
伊集院光氏:スカーレットは魅力的な人。身近にいたらどうかと思うが、主人公としては惹かれる。 【現在の状況】
【現在の状況】 スカーレットはカーテンでドレスを作り、アトランタで投獄されているレットに会いに行く。優雅な暮らしをしているふりをしてレットを誘惑しようとするが、荒れた手のひらを見て嘘を見破られてしまう。結局レットから借金できず、ふてくされてアトランタの街を歩いていると、妹スエレンの婚約者フランク・ケネディとばったり出会う。戦後開業した店が繁盛している様子。スカーレットはフランクのお金が妹のものになるのが許せない。スカーレットはフランクを奪おうと決心する。お金のためにレットと結婚しようとアトランタに来た時点でモラルもないため、妹の婚約者を奪うことに良心も痛まない。
スカーレットはカーテンでドレスを作り、アトランタで投獄されているレットに会いに行く。優雅な暮らしをしているふりをしてレットを誘惑しようとするが、荒れた手のひらを見て嘘を見破られてしまう。結局レットから借金できず、ふてくされてアトランタの街を歩いていると、妹スエレンの婚約者フランク・ケネディとばったり出会う。戦後開業した店が繁盛している様子。スカーレットはフランクのお金が妹のものになるのが許せない。スカーレットはフランクを奪おうと決心する。お金のためにレットと結婚しようとアトランタに来た時点でモラルもないため、妹の婚約者を奪うことに良心も痛まない。 うーん💦 文体のことになると原作を読んでいないのでよく分からない。映画を見ていても理想の女性ではないスカーレットは魅力的だったのので、それはやっぱり原作の力なのか、脚本の力なのか、演出なのか、演技なのか? まあ全部でしょう。とりわけヴィヴィアン・リーの力は大きかったかなと思う。
うーん💦 文体のことになると原作を読んでいないのでよく分からない。映画を見ていても理想の女性ではないスカーレットは魅力的だったのので、それはやっぱり原作の力なのか、脚本の力なのか、演出なのか、演技なのか? まあ全部でしょう。とりわけヴィヴィアン・リーの力は大きかったかなと思う。 スカーレット娘もいたの?😲
スカーレット娘もいたの?😲 ココが重要!:作品中に兄化を描くことと賛同することは全く別!
ココが重要!:作品中に兄化を描くことと賛同することは全く別!


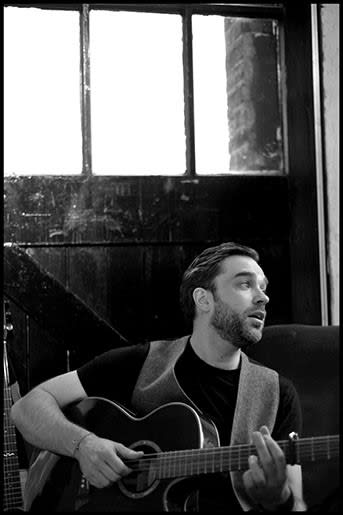



 【映画豆知識】
【映画豆知識】



 この曲は何度かミュージカル系のコンサートで聴いたことがあるので知っていたのだけど、もう余裕の歌唱。
この曲は何度かミュージカル系のコンサートで聴いたことがあるので知っていたのだけど、もう余裕の歌唱。