2017.06.24 『怪物はささやく』鑑賞@TOHOシネマズみゆき座
見たいと思って試写会応募したけどハズレ DVDでもいいかなと思っていたのだけど、お昼から用事済ませた後、ちょうど時間が合ったので日比谷へ移動して見てきた~
DVDでもいいかなと思っていたのだけど、お昼から用事済ませた後、ちょうど時間が合ったので日比谷へ移動して見てきた~

 ネタバレありです! 結末にも触れています!
ネタバレありです! 結末にも触れています!
「13歳のコナーは末期ガンの母と2人暮らし。学校では同級生にいじめられていた。辛い日々。さらに毎晩12:07になると怪物が現れて・・・」という話。これはなかなか良かった。ダークファンタジー好きとしては期待大だったのだけど、期待を裏切らない。全体的に暗く救いがあまりないのは見ていて辛いけれど、とにかく画が好き。
ファン・アントニオ・バヨナ監督作品。監督の作品は『永遠の子供たち』を見ていて、とても好きだったので今作も見てみたいと思った。公式サイトによりますと、同名の原作は47歳で亡くなったシヴォーン・ダウドの遺稿を、脚本も手掛けたパトリック・ネスが完成させたそうで、英国史上初カーネギー賞とケイト・グリーナウェイ賞をW受賞したとのこと。この原作を『パンズ・ラビリンス』(感想は コチラ)を手掛けたプロデューサーのベレン・アティエンサが気に入り、バヨナ監督を起用したというのが映画化の経緯。
コチラ)を手掛けたプロデューサーのベレン・アティエンサが気に入り、バヨナ監督を起用したというのが映画化の経緯。
コナー役のキャスティングは難航し、アティエンサは1,000人の候補に会ったのだそう。まぁ、多少盛っているとは思うけれど。最終的には『PAN ~ネバーランド、夢のはじまり~』を取り終えたばかりのルイス・マクドゥーガルに決定したとのこと。コナーの母親役にはフェリシティー・ジョーンズが決定し、祖母役を演じるのは初めてだというシガニー・ウィバーがコナーの祖母を演じている。怪物役はリーアム・ニーソンで40年の俳優人生で初となるモーションキャプチャーもこなした。コナーとのシーンは当初は別々に撮影する予定だったけれど、一緒に演じたのだそう。リーアムの動きをもとに、アニマトロにクスで撮影された怪物は、『パンズ・ラビリス』でアカデミー賞を受賞したモンセ・リーベとデヴィッド・マルティが担当。第31回ゴヤ賞では監督賞など、今年度最多の9部門で受賞。
見てから一ヶ月経ってしまったし、その後劇場鑑賞も含めて、かなりの数の映画を見ていることもあり、細かい部分を失念 怪物がコナーにする3つの話ですら記憶が曖昧に 適当なことは書けないので、いつものようにシーンごとに詳細に書いていくことはできないかもしれない。まぁ、別にどうでもいいとは思うけれど、一応断り書きとして書いておく。最近ホントに記憶力が衰えてしまって悲しい
適当なことは書けないので、いつものようにシーンごとに詳細に書いていくことはできないかもしれない。まぁ、別にどうでもいいとは思うけれど、一応断り書きとして書いておく。最近ホントに記憶力が衰えてしまって悲しい
冒頭から不穏な雰囲気。大地が割れ教会が倒れてゆく。大地の裂け目に女性が落ちそうになっている。少年は必至で彼女の手をつかんでいるが今にも離れてしまいそうになる。そこで目が覚める。時計を見ると夜中の12:07。この少年が主人公のコナー(ルイス・マクドゥーガル)で、見ている側も今後何度かこの悪夢を見ることになる。そして怪物が現れるのもこの時間。これ何故この時間だったんだっけ? これについてネタばらし的なことはあったっけ? ちょっと忘れてしまった。
コナーは母親(フェリシティー・ジョーンズ)と教会の近くの家で2人暮らし。イギリスによくある古い家は、日本人の感覚では2人で住むには広い。離婚した父親(トビー・ケベル)はアメリカに新しい家族と住んでいる。前夜、怪物に襲われる夢を見たコナーは母親のベッドにもぐり込み、優しく部屋に戻るように言われたけれど、そのまま寝たらしい。母親はどうやら具合が悪いらしく、コナーは朝食の用意をしたり洗濯機を回すなど、出来ることは自分でしている様子。母親は起き上がれないのか見送られることなく学校に向かうコナー。
学校ではどうやら孤立しているようで、2つ3つ前に座っている少年はコナーのことが気になる様子。コナーが彼を見ているのがイライラすると仲間数人といじめているらしい。うーん。確かにコナーが彼のことを見つめているともとれるけれど、見ている側としては彼の方がコナーを気にしているように思ったのだけど、作り手としてはどういう意図だったのだろう? この少年は後にコナーを殴る際、他の少年たちに手出しをしないよう指示する。自分とコナーとの間には暗黙の了解があって、コナーは自分に殴られたがっているというのだった。コナーにはゲイ的な部分があるのか、それとも後に明かされる理由により、自分を罰したいと思っていたのか? 自分にはよく分からなかった。
コナーの母親はどうやら末期ガンらしい。今までいろいろな治療をしてきたけれど効果がなく、容体が悪化して入院し、新たな治療を試みるもこちらも効果が出ない。そして、もう治療方法はない。母親が入院したことで、コナーは祖母(シガニー・ウィバー)の家で暮らすことになる。空想好きなコナーは厳格な祖母が苦手であり、祖母の家には居場所がないと感じている。事実、入れてもらえない部屋があったり、自分の部屋がなかったりする。両親の離婚、学校でのいじめ、母親の病気とただでさえ辛い日々を送るコナーにとって、ぬくもりを感じない祖母との日々は確かに苦痛かもしれない。とはいえ、この祖母もコナーを愛していないわけではないし、冷たい人というわけでもなくて、おそらく現在は娘であるコナーの母親のことでいっぱいいっぱいなのでしょう。それは責められない。
コナーを訪ねて父親がアメリカからやって来る。2人は遊園地へ行き楽しく遊ぶけれど、父親はコナーを引きとるつもりはない。遊びに来いとは言うけれど、一緒に暮らそうとは言わない。コナーがそれを本当に望んでいたかは別として、父親に捨てられた気がすると思う。そのことで父親を責めるけれど、父親の言い訳は家が狭い。それはちょっと逃げてるなと思った。おそらくは現在の奥さんが望まない、もしくはコナーを引き取るとういうこと自体言い出せないのどちらかなのだと思うけれど、いずれにしてもハッキリ言ってしまえばコナーは傷つく。でも、家が狭いなどという中途半端な言い訳は余計傷つくと思う。そして自分で本当の理由を考えて、気持ちを落ち着かせなければならなくなるので。まぁ、なんでもハッキリ言えばいいというものではないし、ハッキリ言わない含みの中から相手の思いをおもんぱかるのは日本人の美徳だったりするので、そこを否定したくはないのだけど、少なくともこの父親の説明には見ている側としても苛立ちを感じた。そりゃないだろう(*`д´)
結局、コナーは祖母の家で暮らすしかない。母親と一緒に暮らしていた家は、家自体も家具なども古い感じで、便利そうではなったけれど、とてもかわいらしい家だった。ソファで2人並んで映画(だったっけ?)を見るシーンがほほえましい。コナーの部屋も結構広くて、ちょっと古い感じ。アンティークっぽいのともちょっと違う。空想好きな少年の部屋という感じで、全体的に茶色いトーン。コナーの部屋の窓からは大きな木が見える。この部屋ならば怪物が現れても不思議はないなと思うけれど、怪物は祖母の家にも12:07になると現れる。
怪物は3つの物語をするから、4つ目はコナー自身が話せと言う。物語など知らないというけれど、真実の物語を話せという。3つの物語は3夜に分けて話される。1話目は「黒の王妃と若き王子」、2話目は「薬師の秘薬」、そして3話目が「透明人間の男」なのだけど、1話目と2話目はかろうじて覚えているんだけど、3つ目が全く思い出せない どうしたこと? まぁ、3つの話自体は特別なくてもストーリー上あまり関係ないのだけど、絵本のようなアニメとリーアム・ニーソンの語りで見せられるそれは、ちょっと皮肉がきいていて、それがおとぎ話っぽくておもしろかった。そのわり覚えてないけど でも、薬師の仕事を奪った神父の信仰が試される「薬師の秘薬」は好きだった
いつから怪物がコナーのもとに現れていたのか不明なのだけど、コナーと怪物の関係は次第に距離が縮まっていく。でも、それは友情とは違う。コナーが怪物の言われるままに感情を爆発させ2人で暴れていると、現実の世界では祖母の客間を壊滅的に破壊していたりする。コナーとしては客間を破壊している意識はないわけなのだけど、祖母としてみればショック もちろん大切な物が壊されたこともそうだけれど、やはり孫の仕打ちに傷ついてしまう。呆然とした様子で部屋を出ると、開かずの間に閉じこもってしまう。漏れてくる祖母の嗚咽にコナーも心を痛める。祖母がこもった部屋については後に明かされるけれど、その部屋の意味を知るとこの時の祖母の気持ちが分かって切ない
もちろん大切な物が壊されたこともそうだけれど、やはり孫の仕打ちに傷ついてしまう。呆然とした様子で部屋を出ると、開かずの間に閉じこもってしまう。漏れてくる祖母の嗚咽にコナーも心を痛める。祖母がこもった部屋については後に明かされるけれど、その部屋の意味を知るとこの時の祖母の気持ちが分かって切ない
この怪物主導による破壊行動の意味があまり理解できなかったのだけど、これはやっぱり気持ちを抑えがちなコナーの思いを爆発させようという意図なのかな? どうやら怪物は12:07であれば昼間でも現れるようで、ある日の昼休みランチ中のコナーをいじめる例の少年に対して、現れた怪物が煽ってコナーが彼に襲い掛かるシーンがある。もちろん怪物はコナー以外には見えていないから、単純にコナーが少年に暴力をふるっているように見える。コナーは教師に呼び出されたようで、少年の家族は訴えると言っている的なことを言われる。これ『ムーンライト』(感想は コチラ)の時にも思ったのだけど、確かに暴力はよくないけれど、その前に相手がさんざんいじめてたことにつては全くおとがめなしなの? 納得がいかない!(*`д´)
コチラ)の時にも思ったのだけど、確かに暴力はよくないけれど、その前に相手がさんざんいじめてたことにつては全くおとがめなしなの? 納得がいかない!(*`д´)
ただ、いじめ少年のセリフなどから、コナーはゲイなのかなと思わせる感じがあった。少年はそれを承知していてコナーをいじめている。コナーもそれを承知で抵抗しないというような。あくまで勝手な想像だけど、そう考えると辻褄が合う部分もあるように思う。でも、この後この少年のことは一切触れずに終わってしまうので、ちょっと中途半端な気がした。コナーの抱えている問題はいじめがなくても十分重いので、この少年との関わりも含めて丸ごといらない気もするけれど、コナーが立ち向かえる勇気が持てたという描写なのかな? そして、それでも暴力での解決はいけないということなのかしら? ちょっと意図がつかみ切れず。まぁ原作にもあることなのでしょうけれど・・・
母親の病状はひどく悪い。たまに起き上がって祖母に体を拭いてもらったりしているけれど、かなり辛そう。そしてこの背中! ガリガリ。このフェリシティー・ジョーンズの役作りはスゴイ! 病人なのだから当然スッピンで、目の下にはクマができている。そしてガリガリに痩せている。本当に病人のよう。この一瞬のシーンだけで、母親がもうダメなのだということが見ている側に伝わる。この背中は衝撃的だった。まさに女優魂。一方のシガニー・ウィバーも後半はほぼスッピンだったんじゃないかな? 祖母役は初めてだそうだけれど、女優さんが祖母役を演じるというのは思うところあるのかなと思ったりする。自分の年齢を自覚することになるから。とはいえ、祖母はコナーの母親の母なわけで、娘を失おうとしているのだから、お化粧バッチリなのは変。その辺り徹しているのはさすが。
母親がいよいよ危ないという状況の中で、コナーは怪物から4つ目の話をしろと迫られる。4つ目の話はコナー自身の真実を話さなければならない。でも何を話せばいいのか? 毎晩夢に現れたあの教会。地面が崩れ始める。また悪夢を見ているのか? そうではなさそう。母親が地面の裂け目に落ちそうになっている。コナーは必死で腕をつかんで引き上げようとする。でも重くて上がらない。そしてコナーが叫ぶ。正確なセリフは忘れてしまったけれど、手を放したかったということで、要するに母親のことを諦めたかったという意味。もちろん母親に死んで欲しいわけじゃない。でも、張り詰めた気持ちは限界に達していたということ。母親の手を放して楽になりたかった。これは辛い。そして誰も責められない。そう考えたら泣いてた
母親は結局亡くなってしまう。コナーの姿がないことに気付いた祖母は彼を探しに行く。夢で巨人が現れる木の根元で眠っていたコナーを抱き上げる祖母。
場面変わって祖母の家。コナーの部屋を用意したので案内すると言う。そこはあの開かずの間で、母親が子供の頃使っていた部屋だった。それが分かった瞬間涙腺決壊! まぁ既に泣いてたけど 死にゆく娘を思う祖母の気持ちを考えると切ない まだ娘が生きているうちにコナーに使わせられなかった気持ちも分かるし、コナーが暴れた日にこの部屋に籠って泣いていた姿がよみがえって辛い
まだ娘が生きているうちにコナーに使わせられなかった気持ちも分かるし、コナーが暴れた日にこの部屋に籠って泣いていた姿がよみがえって辛い このシーンだけでコナーと祖母の絆と新たな関係が始まったことが伝わって来る。コナーの部屋には母が子供の頃使っていた物がたくさん残されていて、その中に絵日記があった。そこには怪物のことや3つの話が描かれていた。というシーンで映画は終わり。怪物の存在については実在するのか、コナーの空想なのかどちらでも取れると思う。母親も見ていたってことで存在するという解釈でもOKだし、コナーの空想であり、それは例えば幼い頃母親が話してくれていて、それに影響されたとも考えられる。個人的には後者かなと思っているけど、ダークファンタジーなので前者でも素敵な解釈だと思う。
このシーンだけでコナーと祖母の絆と新たな関係が始まったことが伝わって来る。コナーの部屋には母が子供の頃使っていた物がたくさん残されていて、その中に絵日記があった。そこには怪物のことや3つの話が描かれていた。というシーンで映画は終わり。怪物の存在については実在するのか、コナーの空想なのかどちらでも取れると思う。母親も見ていたってことで存在するという解釈でもOKだし、コナーの空想であり、それは例えば幼い頃母親が話してくれていて、それに影響されたとも考えられる。個人的には後者かなと思っているけど、ダークファンタジーなので前者でも素敵な解釈だと思う。
キャストはフェリシティー・ジョーンズとシガニー・ウィバーについては既に書いてしまったけど、女優魂を感じた。スッピンを晒すということが体当たりの演技とも思わないし、末期ガン患者の役なのに太っているのはあり得ないと思うけど、やっぱりあの背中は衝撃だった。いろんなタイプの女優や俳優がいると思うので、オードリー・ヘプバーンのように何をやってもオードリーで、寝る時もお化粧バッチリでイメージを崩さないのもある意味女優魂だと思うけれど、個人的には役柄によってガラリと変わってしまうタイプが好きなので、今回の2人の演技や役作りは素晴らしいと思った。シガニー・ウィバーは厳しくて頑固ではあるけれど、普通のおばあちゃんに見えた。それが女優ってことだと思う。年齢的にはとっくにおばあちゃんなのに、いつまでも小さな子供の母親役とか変。それで大女優って言われても個人的にはそうは思えないし、そういう女優さんには人気があっても興味はない。あくまで個人的な好みの問題。
と、自分の女優論を熱く語ってしまった 怪物役のリーアム・ニーソンの深みのある声が良かった。怪物は悪でも善でもない。その辺りのさじ加減も見事。コナーのルイス・マクドゥーガルくんも良かった。怪物を空想してしまいそうな男の子。繊細で思慮深い。同級生の少年に複雑な気持ちを持っていることも感じさせて見事。とてもよかった。色白でひょろっとした容姿もダークファンタジーに合ってる。ホメてます!
予備知識はほぼなく見たので、怪物の造形は意外な気がした。もっと違う感じを想像していたので。あんなに大きいとも思ってなかったし、まさか木とは思わなかった。嫌いではない。コナーと母が暮らす古い家がかわいかった。特にコナーの部屋はちょっとアニメっぽいというか、おとぎ話的な感じ。いろんな物が置かれていたりするけど、散らかっている感じやゴチャゴチャ感はない。小学生の少年の部屋にしては広い気がするけど一人っ子だからね。ポップなのとは違うのだけど楽しい部屋。祖母の家のコナーの部屋(旧母の部屋)も似たテイストなので、これは母の趣味ってことかな? 住みたいかというとちょっと違うのだけど、かわいくて好きだった。祖母の堅苦しくて古い家も嫌いじゃない。全体的にダークな画も好きだった。
見てから感想書き終わるのに一ヶ月かかってしまったので、上映終了しちゃったね 両親の離婚、いじめ、母親の病死など重い内容なので、おススメしにくい感じはあるのだけど、ダークファンタジー好きな人は絶対好きだと思う。フェリシティー・ジョーンズ好きな方是非!
 『怪物はささやく』Official site
『怪物はささやく』Official site














 【動画】 浅田真央メドレーTHE ICE 2017
【動画】 浅田真央メドレーTHE ICE 2017







 子供っぽくて表現力がないとディスられてた時から、子供っぽくて稚拙な表現などと思ったことは一度もないけど、本当に大人の色気と芯の強さを纏った素晴らしい演技だった
子供っぽくて表現力がないとディスられてた時から、子供っぽくて稚拙な表現などと思ったことは一度もないけど、本当に大人の色気と芯の強さを纏った素晴らしい演技だった


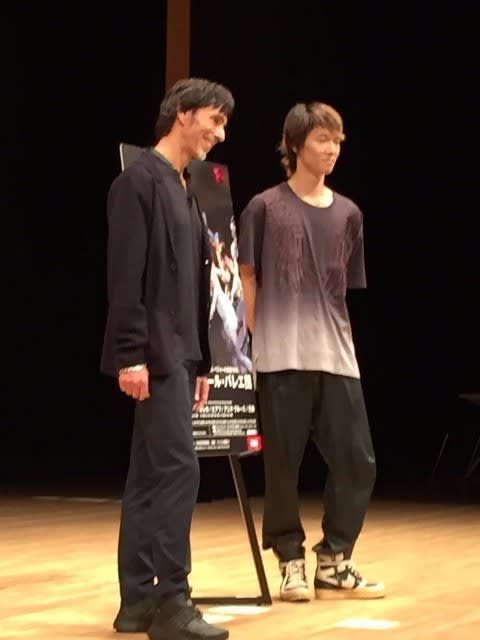







 ネタバレありです! 結末にも触れています!
ネタバレありです! 結末にも触れています! 適当なことは書けないので、いつものようにシーンごとに詳細に書いていくことはできないかもしれない。まぁ、別にどうでもいいとは思うけれど、一応断り書きとして書いておく。最近ホントに記憶力が衰えてしまって悲しい
適当なことは書けないので、いつものようにシーンごとに詳細に書いていくことはできないかもしれない。まぁ、別にどうでもいいとは思うけれど、一応断り書きとして書いておく。最近ホントに記憶力が衰えてしまって悲しい もちろん大切な物が壊されたこともそうだけれど、やはり孫の仕打ちに傷ついてしまう。呆然とした様子で部屋を出ると、開かずの間に閉じこもってしまう。漏れてくる祖母の嗚咽にコナーも心を痛める。祖母がこもった部屋については後に明かされるけれど、その部屋の意味を知るとこの時の祖母の気持ちが分かって切ない
もちろん大切な物が壊されたこともそうだけれど、やはり孫の仕打ちに傷ついてしまう。呆然とした様子で部屋を出ると、開かずの間に閉じこもってしまう。漏れてくる祖母の嗚咽にコナーも心を痛める。祖母がこもった部屋については後に明かされるけれど、その部屋の意味を知るとこの時の祖母の気持ちが分かって切ない






 声量豊かに響き渡った。
声量豊かに響き渡った。








 見れますように(人'д`o)
見れますように(人'д`o)



