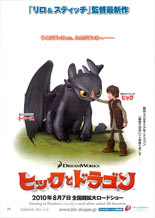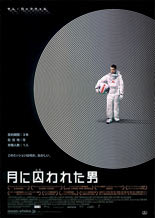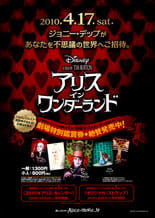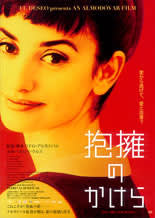'11.1.17 『ハーモニー 心をつなぐ歌』(試写会)@FS汐留
rose_chocolatさんからのお誘い。共通で仲良くさせて頂いているまっつぁんこさんご推薦。
*ネタバレありです。辛口かも?
 「暴力を振るう夫に抵抗し、誤って殺害してしまったジョンヘは、刑務所で息子ミヌを出産する。規則では一緒にいられるのは18ヶ月まで。ミヌと一度だけ外出したいジョンヘは合唱団を結成する…」という話。これは"韓流"という感じ。泣かせるように作っているので、号泣に近いくらい泣いているけど、後にあんまり残らない。あらすじだけ読むと、どうして外出と合唱が関係するのか分からないけど、これが関係してくるんです(笑)よく考えるとご都合主義で、かなり強引だけど、泣かせることに徹しているのは、ある意味潔い。そしてそれが"韓流"なのかと思った次第。ほめてます!
「暴力を振るう夫に抵抗し、誤って殺害してしまったジョンヘは、刑務所で息子ミヌを出産する。規則では一緒にいられるのは18ヶ月まで。ミヌと一度だけ外出したいジョンヘは合唱団を結成する…」という話。これは"韓流"という感じ。泣かせるように作っているので、号泣に近いくらい泣いているけど、後にあんまり残らない。あらすじだけ読むと、どうして外出と合唱が関係するのか分からないけど、これが関係してくるんです(笑)よく考えるとご都合主義で、かなり強引だけど、泣かせることに徹しているのは、ある意味潔い。そしてそれが"韓流"なのかと思った次第。ほめてます!
韓国映画は特別好きでも嫌いでもない。韓流ドラマは「チャングム」しか見たことないので、韓流を語る資格ないかもしれないけれど、とにかくあの役者達の大袈裟とも言える感情表現過多な演技、これでもかと襲い掛かる困難、でも必ず解決(けっこうご都合主義)、そして身分違いの恋など、盛り沢山で飽きさせない。そして号泣。でも、50話以上も見たのに、大作を見た余韻とか、一人の女性の一生を見た感慨みたいのがないんだよね… まぁ、どこに重きを置くかってことだと思うし、じっくり見られて余韻に浸れる韓国映画もたくさんある。でも、間違いなくこれは前者のタイプ。なので、そういうタイプの韓流ドラマや映画が好きな方は好きだと思う。
"泣かせる"ってことに重点を置いているのだと思うので、そのためには多少「?」っとなることは無視という感じ。見ているうちは多少の違和感はあっても、気にならないのだけど、こうやって冷静になってレビューを書くとなると、どうしても矛盾点なんかが気になってしまう。個人的に韓国映画にありがちなドタドタが苦手。なので前半のあまりに明る過ぎる囚人達についていけず… イヤ囚人達だって生きている以上、楽しいこともあるだろうし、明るくするなとまでは言わないけれど、あまりに自由で楽しそうな描写が続くので。
チラシによると、この合唱団は清州女子刑務所に実在するそうで、定期的に外部公演も行っているとのこと。また、この刑務所には出産および18ヶ月までの育児制度があることを知った監督が、このシナリオを書いたのだそう。なので、おそらく題材のみを借りたオリジナル・ストーリーだと思われる。最初にこれはフィクションである断りが入っているし。ジョンヘは所内を自由に歩き回っている印象だし、同室の受刑者達とおしゃべりやゲームに興じたり、お菓子を食べたりしている。その他4人と同じ房で過ごしていて、ミヌもそこで一緒に寝起きしているのだけど、実際もこうなのかな。しかも同じ部屋にいくら現在は反省し、模範的な人物だとしても、死刑囚と同じ房に入ったりしているものなんだろうか… そういう事すべてが感動させるための必要な要素なのは分かるけど、ちょっと強引さを感じることは確かで、フィクションと断ればいいというのも違う気もするんだけど、ここを強引と取るか、徹していると取るかで見方も変わるとは思う。正直に言えば作り手のスタンスとしてはその中間で、やや強引よりなのかなと思う。それが"韓流"ってことかと思うので、それはそのように楽しむべきなのかも。とはいうものの、前半はあまりに自由な明るさと、役者達の豊か過ぎる感情表現について行けず、乗り切れない。
前半部分で、ジョンヘや死刑囚の先生、心を閉ざしたユミの犯した事件をサラッと見せる手法は良かったと思う。継父に乱暴されそうになり殺してしまったユミはともかく、ダンナさんと教え子(?)の浮気現場を目撃し、2人を轢き殺した先生についても、犯罪を正当化しないまでも同情の余地を残しているのも、感動させる演出とは思うけれど、ズルイとは思わない。その方が見ている側も楽だし… 心を閉ざして自虐的になったり、攻撃的になってしまったユミの心を、ジョンヘや先生、そしてミヌの存在が溶かしていくっていうのも、音大に通っていた彼女がやっぱり歌によって支えられるというのも良かったと思う。心を開いて美しい歌声を披露した彼女が、ジョンヘに頼まれて歌唱指導し、ヒドイ音痴だったジョンヘがみるみる上達するのも王道で、『チーム☆アメリカ』の"モンタージュ"ではないけれど、練習風景や上達していく様子を、モンタージュで見せる手法まで王道。でも、その後合唱団では、完全に脇役になってしまったのは普通に考えて変だし、ちょっと残念。まぁ、あくまでジョンヘがソロを歌うための脇役に徹することも、感動のためならOKかと。
そもそも歌の下手なジョンヘが合唱団を作ったのは、慰問に来た合唱団の歌声に感動したのもあるけれど、合唱団を成功させたら、その見返りとしてミヌと外出する許可が欲しいから。まぁ、そこまで考えて始めたのかは不明。そもそも、そんな制度自体があるのか分からないけど、かなり強引… でも、お得意のドタバタ演技と演出で説得力を持たせている。信じられないかもしれないけれど、誉めてます!
結局、ほっしゃん。似の所長もジョンヘの勢いに押されて渋々OK。ジョンヘは大いに張り切るわけだけど、後に認められた外出は、ミヌを里子に出す時ということになる。この辺りの緩急のすごさも韓流だなと思うわけです。緩急って必要だとは思うけれど、まるで絶叫マシーンなみなので… そんな激しい緩急の間に、ミヌの病気、ミヌとの別れなど、感動エピソードが投げ込まれてくる。これまた感情過多ではあるけれど、野球に例えると剛速球だけどクセがないので、慣れれば打ちやすいという印象。まぁ、野球そんなに詳しくないけど(笑) とにかく、次から次へと感動エピソードやドタバタ感が投げ込まれるけど、ど真ん中ストレートなので安定感がある。打ちにくければ見逃してもOK(笑)
そんな王道ど真ん中なエピソードの中、これまた王道でありながらしっとりズッシリ心に響いたのは、ユミと母親そして、先生と娘の関係。自分も娘なので、その愛憎渦巻く感じはなんとなく分かる。まぁ、別にそんなに渦巻きませんが(笑) ユミは毎週面会に来る母親に会うことを拒むけれど、それは継父を殺してしまった時、自分は被害者でもあるのに、母に責められてしまったことに深く傷ついただけでなく、母親の夫を奪ってしまったことで自分を責めているからでもある。そして多分、汚れてしまった自分を責めてもいるんだと思う。母親だけは無条件で自分を受け止めて欲しいと思っているから、拒絶されてしまった時のショックは大きい。まして理由がそうなので、そのショックが自分に向いてしまう。そんなユミの気持ちはよく分かる。だからこそ、拒絶されて呆然としたまま帰る母親の姿に涙が止まらない。そして、母親もまた自分を責めているのが分かるから、その小さくなった背中に自分の母親を重ねてしまう。助けて欲しいという気持ちと、助けてあげたい気持ちが入り混じって辛い。
 そして死刑囚の先生。先生が罪を犯したのは、単純に2人の浮気を知ったからじゃない。一緒にいた娘が、奥の部屋から聞こえて来る会話や声の意味を理解していたから。この娘のために殺したと言うと語弊あるけど、引き金になったことは間違いない。娘の中にその記憶や、その本当の意味がきちんと整理できているのか謎だけど、娘だからこそ許せないというか、受け入れられない部分があるんだと思う。もちろん、どんな理由があるにせよ殺人は殺人ではある。ユミや先生の置かれている立場が、より"母娘"という関係を切ないものにしているのは事実だけど、自分の中にもある"母親"という存在に対して、心が揺さ振られる。先生の運命については死刑囚であることから予想はついていたので、最近、父親をおくった身としては、そう遠くない未来にやってくる母親との別れを思って号泣してしまった。もう「お母さん! おかーさーん!」です(笑)
そして死刑囚の先生。先生が罪を犯したのは、単純に2人の浮気を知ったからじゃない。一緒にいた娘が、奥の部屋から聞こえて来る会話や声の意味を理解していたから。この娘のために殺したと言うと語弊あるけど、引き金になったことは間違いない。娘の中にその記憶や、その本当の意味がきちんと整理できているのか謎だけど、娘だからこそ許せないというか、受け入れられない部分があるんだと思う。もちろん、どんな理由があるにせよ殺人は殺人ではある。ユミや先生の置かれている立場が、より"母娘"という関係を切ないものにしているのは事実だけど、自分の中にもある"母親"という存在に対して、心が揺さ振られる。先生の運命については死刑囚であることから予想はついていたので、最近、父親をおくった身としては、そう遠くない未来にやってくる母親との別れを思って号泣してしまった。もう「お母さん! おかーさーん!」です(笑)
この映画のテーマがおそらく母子なのだと思うけれど、主役のキム・ユンジンの感情過多な演技のおかげで、ちょっと乗り切れず、イヤだいぶ泣いてたけど、それはユミと先生のエピソードによって涙目になったから止まらなくなった部分は大きい。幼児の頃のミヌ役の子がホントにかわいいかったし、ラスト近くありえないくらいの感動エピソードが用意されていたにも関わらず、前述の2人よりも感動しなかったのは、自身がまだ"娘"であって、"母"ではないからというだけではない気がする。
何度も書いてるけど、とにかく感動エピソード目白押しなので、一番の見どころであるコンサート・シーンがやや盛り上がりに欠けてしまった気がしないでもない。このコンサート後に、前述のジョンヘの感動エピソードがあるのだけど、その前の成金マダムの指輪紛失、合唱団が疑われて楽屋での屈辱シーンなどは余計だったかな… 確かに、この件については不当な扱いだったけれど、このエピソードで受刑者アゲは、ちょっとズルイかも… このエピソードのおかげで、肝心のコンサート・シーンにそのわり感情移入しきれなかった上での感動エピソードは、予想できてしまったこともあって、涙目になってしまったために号泣状態だったけれど、そのわり印象に残らず。それにコレ冷静に考えたら、いくら看守がいたからといって、ロビーで受刑者が野放し状態はないよね…(笑)
そして最後、さらにもう一つドラマが… これも早い段階で予測がついたこと。先日、一気見した「森のアサガオ」でも感じたことだけど、やっぱり死刑囚の話を描いた場合、どうしたって死刑制度の是非みたいなことって言いづらい。この作品自体はそこを問うてはいないけれど、受刑者達の良い面ばかりを見せられて、若い女性刑務官との交流を見せられれば、許してあげたい気にもなるけれど、やってしまったことの責任は重いと思うし。映画では泣かせるエピソードとして描いている感じ。でも、実際の刑務所でも執行前日とかに、家族の家みたいな名前の家で、家族と最後の晩餐を取らせたりするのだろうか… だって普通に考えて気づくよね? ただ、このシーンも"母親"に涙してしまうのだけと。
日本では死刑囚はたしか刑務所にはいないと思うので、独居房かどうかという以前に、受刑者と接する機会ってないと思うのだけど、韓国はこんななのかな? 以前見た『わたしたちの幸せな時間』でも、独居ではなかった気がするのだけど、他の人も死刑囚だったと思うのだけど… いずれにせよ、ジョンヘと先生が同室であるというのも、ラストのお別れシーンがやりたいからであって、これもまた感動させるための仕掛けであることは間違いない。そしてまんまと泣いてしまう。
キャストについては、3年振りの韓国映画主演となるキム・ユンジンは感情過多な演技がちょっと… 彼女の出演作は『シュリ』しか見てないけど、こんな感じなのかな… まぁ『シュリ』とはキャラ設定が違うので、比較にはならないかもしれないけれど、前半部分のドタバタ感は明るいのとは違う気がする… まぁ、無理に明るく振る舞っているという解釈もあるけど、それにしてもなぁ。そういう演出なんだと思うし、下手なわけではないのだけど… ユミ役のカン・イェウォンが良かった。辛い体験から心を閉ざし、触れれば切れそうな佇まいがスゴイけれど、あまり台詞もないのに、母への愛憎を感じさせた。そして何と言っても先生のナ・ムニ! 死刑囚なのに威厳と気品がある。そして、そのふっくらとした表情が"お母さん"であるということ。合唱団の先生であると同時に、受刑者達のお母さんなんだと全てのシーンで感じられる。この演技と佇まいはスゴイ! ナ・ムニの演技を見るために、見る価値あり!
何度もしつこいけれど、感動させるために少々強引な部分がだいぶある。泣かせようとするあまり、涙の量と感銘度合いが比例しない状態になってしまった気もするけれど、そこに徹したのはそれはそれでスゴイと思う。とにかく泣きたい人にはオススメ。ほめてます!
 『ハーモニー 心をつなぐ歌』Official site
『ハーモニー 心をつなぐ歌』Official site
rose_chocolatさんからのお誘い。共通で仲良くさせて頂いているまっつぁんこさんご推薦。
*ネタバレありです。辛口かも?
 「暴力を振るう夫に抵抗し、誤って殺害してしまったジョンヘは、刑務所で息子ミヌを出産する。規則では一緒にいられるのは18ヶ月まで。ミヌと一度だけ外出したいジョンヘは合唱団を結成する…」という話。これは"韓流"という感じ。泣かせるように作っているので、号泣に近いくらい泣いているけど、後にあんまり残らない。あらすじだけ読むと、どうして外出と合唱が関係するのか分からないけど、これが関係してくるんです(笑)よく考えるとご都合主義で、かなり強引だけど、泣かせることに徹しているのは、ある意味潔い。そしてそれが"韓流"なのかと思った次第。ほめてます!
「暴力を振るう夫に抵抗し、誤って殺害してしまったジョンヘは、刑務所で息子ミヌを出産する。規則では一緒にいられるのは18ヶ月まで。ミヌと一度だけ外出したいジョンヘは合唱団を結成する…」という話。これは"韓流"という感じ。泣かせるように作っているので、号泣に近いくらい泣いているけど、後にあんまり残らない。あらすじだけ読むと、どうして外出と合唱が関係するのか分からないけど、これが関係してくるんです(笑)よく考えるとご都合主義で、かなり強引だけど、泣かせることに徹しているのは、ある意味潔い。そしてそれが"韓流"なのかと思った次第。ほめてます!韓国映画は特別好きでも嫌いでもない。韓流ドラマは「チャングム」しか見たことないので、韓流を語る資格ないかもしれないけれど、とにかくあの役者達の大袈裟とも言える感情表現過多な演技、これでもかと襲い掛かる困難、でも必ず解決(けっこうご都合主義)、そして身分違いの恋など、盛り沢山で飽きさせない。そして号泣。でも、50話以上も見たのに、大作を見た余韻とか、一人の女性の一生を見た感慨みたいのがないんだよね… まぁ、どこに重きを置くかってことだと思うし、じっくり見られて余韻に浸れる韓国映画もたくさんある。でも、間違いなくこれは前者のタイプ。なので、そういうタイプの韓流ドラマや映画が好きな方は好きだと思う。
"泣かせる"ってことに重点を置いているのだと思うので、そのためには多少「?」っとなることは無視という感じ。見ているうちは多少の違和感はあっても、気にならないのだけど、こうやって冷静になってレビューを書くとなると、どうしても矛盾点なんかが気になってしまう。個人的に韓国映画にありがちなドタドタが苦手。なので前半のあまりに明る過ぎる囚人達についていけず… イヤ囚人達だって生きている以上、楽しいこともあるだろうし、明るくするなとまでは言わないけれど、あまりに自由で楽しそうな描写が続くので。
チラシによると、この合唱団は清州女子刑務所に実在するそうで、定期的に外部公演も行っているとのこと。また、この刑務所には出産および18ヶ月までの育児制度があることを知った監督が、このシナリオを書いたのだそう。なので、おそらく題材のみを借りたオリジナル・ストーリーだと思われる。最初にこれはフィクションである断りが入っているし。ジョンヘは所内を自由に歩き回っている印象だし、同室の受刑者達とおしゃべりやゲームに興じたり、お菓子を食べたりしている。その他4人と同じ房で過ごしていて、ミヌもそこで一緒に寝起きしているのだけど、実際もこうなのかな。しかも同じ部屋にいくら現在は反省し、模範的な人物だとしても、死刑囚と同じ房に入ったりしているものなんだろうか… そういう事すべてが感動させるための必要な要素なのは分かるけど、ちょっと強引さを感じることは確かで、フィクションと断ればいいというのも違う気もするんだけど、ここを強引と取るか、徹していると取るかで見方も変わるとは思う。正直に言えば作り手のスタンスとしてはその中間で、やや強引よりなのかなと思う。それが"韓流"ってことかと思うので、それはそのように楽しむべきなのかも。とはいうものの、前半はあまりに自由な明るさと、役者達の豊か過ぎる感情表現について行けず、乗り切れない。
前半部分で、ジョンヘや死刑囚の先生、心を閉ざしたユミの犯した事件をサラッと見せる手法は良かったと思う。継父に乱暴されそうになり殺してしまったユミはともかく、ダンナさんと教え子(?)の浮気現場を目撃し、2人を轢き殺した先生についても、犯罪を正当化しないまでも同情の余地を残しているのも、感動させる演出とは思うけれど、ズルイとは思わない。その方が見ている側も楽だし… 心を閉ざして自虐的になったり、攻撃的になってしまったユミの心を、ジョンヘや先生、そしてミヌの存在が溶かしていくっていうのも、音大に通っていた彼女がやっぱり歌によって支えられるというのも良かったと思う。心を開いて美しい歌声を披露した彼女が、ジョンヘに頼まれて歌唱指導し、ヒドイ音痴だったジョンヘがみるみる上達するのも王道で、『チーム☆アメリカ』の"モンタージュ"ではないけれど、練習風景や上達していく様子を、モンタージュで見せる手法まで王道。でも、その後合唱団では、完全に脇役になってしまったのは普通に考えて変だし、ちょっと残念。まぁ、あくまでジョンヘがソロを歌うための脇役に徹することも、感動のためならOKかと。
そもそも歌の下手なジョンヘが合唱団を作ったのは、慰問に来た合唱団の歌声に感動したのもあるけれど、合唱団を成功させたら、その見返りとしてミヌと外出する許可が欲しいから。まぁ、そこまで考えて始めたのかは不明。そもそも、そんな制度自体があるのか分からないけど、かなり強引… でも、お得意のドタバタ演技と演出で説得力を持たせている。信じられないかもしれないけれど、誉めてます!
結局、ほっしゃん。似の所長もジョンヘの勢いに押されて渋々OK。ジョンヘは大いに張り切るわけだけど、後に認められた外出は、ミヌを里子に出す時ということになる。この辺りの緩急のすごさも韓流だなと思うわけです。緩急って必要だとは思うけれど、まるで絶叫マシーンなみなので… そんな激しい緩急の間に、ミヌの病気、ミヌとの別れなど、感動エピソードが投げ込まれてくる。これまた感情過多ではあるけれど、野球に例えると剛速球だけどクセがないので、慣れれば打ちやすいという印象。まぁ、野球そんなに詳しくないけど(笑) とにかく、次から次へと感動エピソードやドタバタ感が投げ込まれるけど、ど真ん中ストレートなので安定感がある。打ちにくければ見逃してもOK(笑)
そんな王道ど真ん中なエピソードの中、これまた王道でありながらしっとりズッシリ心に響いたのは、ユミと母親そして、先生と娘の関係。自分も娘なので、その愛憎渦巻く感じはなんとなく分かる。まぁ、別にそんなに渦巻きませんが(笑) ユミは毎週面会に来る母親に会うことを拒むけれど、それは継父を殺してしまった時、自分は被害者でもあるのに、母に責められてしまったことに深く傷ついただけでなく、母親の夫を奪ってしまったことで自分を責めているからでもある。そして多分、汚れてしまった自分を責めてもいるんだと思う。母親だけは無条件で自分を受け止めて欲しいと思っているから、拒絶されてしまった時のショックは大きい。まして理由がそうなので、そのショックが自分に向いてしまう。そんなユミの気持ちはよく分かる。だからこそ、拒絶されて呆然としたまま帰る母親の姿に涙が止まらない。そして、母親もまた自分を責めているのが分かるから、その小さくなった背中に自分の母親を重ねてしまう。助けて欲しいという気持ちと、助けてあげたい気持ちが入り混じって辛い。
 そして死刑囚の先生。先生が罪を犯したのは、単純に2人の浮気を知ったからじゃない。一緒にいた娘が、奥の部屋から聞こえて来る会話や声の意味を理解していたから。この娘のために殺したと言うと語弊あるけど、引き金になったことは間違いない。娘の中にその記憶や、その本当の意味がきちんと整理できているのか謎だけど、娘だからこそ許せないというか、受け入れられない部分があるんだと思う。もちろん、どんな理由があるにせよ殺人は殺人ではある。ユミや先生の置かれている立場が、より"母娘"という関係を切ないものにしているのは事実だけど、自分の中にもある"母親"という存在に対して、心が揺さ振られる。先生の運命については死刑囚であることから予想はついていたので、最近、父親をおくった身としては、そう遠くない未来にやってくる母親との別れを思って号泣してしまった。もう「お母さん! おかーさーん!」です(笑)
そして死刑囚の先生。先生が罪を犯したのは、単純に2人の浮気を知ったからじゃない。一緒にいた娘が、奥の部屋から聞こえて来る会話や声の意味を理解していたから。この娘のために殺したと言うと語弊あるけど、引き金になったことは間違いない。娘の中にその記憶や、その本当の意味がきちんと整理できているのか謎だけど、娘だからこそ許せないというか、受け入れられない部分があるんだと思う。もちろん、どんな理由があるにせよ殺人は殺人ではある。ユミや先生の置かれている立場が、より"母娘"という関係を切ないものにしているのは事実だけど、自分の中にもある"母親"という存在に対して、心が揺さ振られる。先生の運命については死刑囚であることから予想はついていたので、最近、父親をおくった身としては、そう遠くない未来にやってくる母親との別れを思って号泣してしまった。もう「お母さん! おかーさーん!」です(笑)この映画のテーマがおそらく母子なのだと思うけれど、主役のキム・ユンジンの感情過多な演技のおかげで、ちょっと乗り切れず、イヤだいぶ泣いてたけど、それはユミと先生のエピソードによって涙目になったから止まらなくなった部分は大きい。幼児の頃のミヌ役の子がホントにかわいいかったし、ラスト近くありえないくらいの感動エピソードが用意されていたにも関わらず、前述の2人よりも感動しなかったのは、自身がまだ"娘"であって、"母"ではないからというだけではない気がする。
何度も書いてるけど、とにかく感動エピソード目白押しなので、一番の見どころであるコンサート・シーンがやや盛り上がりに欠けてしまった気がしないでもない。このコンサート後に、前述のジョンヘの感動エピソードがあるのだけど、その前の成金マダムの指輪紛失、合唱団が疑われて楽屋での屈辱シーンなどは余計だったかな… 確かに、この件については不当な扱いだったけれど、このエピソードで受刑者アゲは、ちょっとズルイかも… このエピソードのおかげで、肝心のコンサート・シーンにそのわり感情移入しきれなかった上での感動エピソードは、予想できてしまったこともあって、涙目になってしまったために号泣状態だったけれど、そのわり印象に残らず。それにコレ冷静に考えたら、いくら看守がいたからといって、ロビーで受刑者が野放し状態はないよね…(笑)
そして最後、さらにもう一つドラマが… これも早い段階で予測がついたこと。先日、一気見した「森のアサガオ」でも感じたことだけど、やっぱり死刑囚の話を描いた場合、どうしたって死刑制度の是非みたいなことって言いづらい。この作品自体はそこを問うてはいないけれど、受刑者達の良い面ばかりを見せられて、若い女性刑務官との交流を見せられれば、許してあげたい気にもなるけれど、やってしまったことの責任は重いと思うし。映画では泣かせるエピソードとして描いている感じ。でも、実際の刑務所でも執行前日とかに、家族の家みたいな名前の家で、家族と最後の晩餐を取らせたりするのだろうか… だって普通に考えて気づくよね? ただ、このシーンも"母親"に涙してしまうのだけと。
日本では死刑囚はたしか刑務所にはいないと思うので、独居房かどうかという以前に、受刑者と接する機会ってないと思うのだけど、韓国はこんななのかな? 以前見た『わたしたちの幸せな時間』でも、独居ではなかった気がするのだけど、他の人も死刑囚だったと思うのだけど… いずれにせよ、ジョンヘと先生が同室であるというのも、ラストのお別れシーンがやりたいからであって、これもまた感動させるための仕掛けであることは間違いない。そしてまんまと泣いてしまう。
キャストについては、3年振りの韓国映画主演となるキム・ユンジンは感情過多な演技がちょっと… 彼女の出演作は『シュリ』しか見てないけど、こんな感じなのかな… まぁ『シュリ』とはキャラ設定が違うので、比較にはならないかもしれないけれど、前半部分のドタバタ感は明るいのとは違う気がする… まぁ、無理に明るく振る舞っているという解釈もあるけど、それにしてもなぁ。そういう演出なんだと思うし、下手なわけではないのだけど… ユミ役のカン・イェウォンが良かった。辛い体験から心を閉ざし、触れれば切れそうな佇まいがスゴイけれど、あまり台詞もないのに、母への愛憎を感じさせた。そして何と言っても先生のナ・ムニ! 死刑囚なのに威厳と気品がある。そして、そのふっくらとした表情が"お母さん"であるということ。合唱団の先生であると同時に、受刑者達のお母さんなんだと全てのシーンで感じられる。この演技と佇まいはスゴイ! ナ・ムニの演技を見るために、見る価値あり!
何度もしつこいけれど、感動させるために少々強引な部分がだいぶある。泣かせようとするあまり、涙の量と感銘度合いが比例しない状態になってしまった気もするけれど、そこに徹したのはそれはそれでスゴイと思う。とにかく泣きたい人にはオススメ。ほめてます!
 『ハーモニー 心をつなぐ歌』Official site
『ハーモニー 心をつなぐ歌』Official site