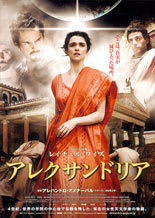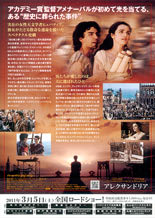'11.03.10 『トゥルー・グリット』(試写会)@一ツ橋ホール
yaplog!で当選。見たかったコレ! 試写状届いた瞬間ガッツポーズだった!
*ネタバレありです!
 「父親を雇い人チェイニーに殺されたマティは、アル中保安官コグバーンを雇う。テキサス・レンジャーのラビーフも加わり彼を追う…」 という話。これは面白かった。王道な展開で、冒頭マティの父親が殺されたと伝えられるだけで、特に大きな出来事も起きないけれど、約2時間の長さも感じさせない。じんわりと感動できて見応えのある作品となっていた。
「父親を雇い人チェイニーに殺されたマティは、アル中保安官コグバーンを雇う。テキサス・レンジャーのラビーフも加わり彼を追う…」 という話。これは面白かった。王道な展開で、冒頭マティの父親が殺されたと伝えられるだけで、特に大きな出来事も起きないけれど、約2時間の長さも感じさせない。じんわりと感動できて見応えのある作品となっていた。
1968年に連載開始されたチャールズ・ボーティスの同名小説が原作。翌1969年にはジョン・ウェイン主演で映画化されているけど、これは未見。true gritとは"真の勇気"という意味。監督はコーエン兄弟。彼らの作品は『ファーゴ』『ビッグ・リボウスキ』『バーバー』『ノーカントリー』を見た。すごいファンという感じではないけれど、見た作品はみんな好きだった。1番好きなのは『ファーゴ』かなぁ… ブシェミ出てるからね(笑) 今回の主演はジェフ・ブリッジス。『ビッグ・リボウスキ』でも主演だった。オリジナルの主演ジョン・ウェインといえば往年の名優で、もちろん知っているけど、作品を見た覚えがあまりない。たぶん、見てはいると思うけれど… ということで、つらつら書いて何が言いたいかというと、原作・前作にあまり思い入れがないけど、コーエン兄弟作品には少しありますということ。だから何という感じですが(笑)
西部劇は別に嫌いじゃないけど、特に好んで見る方ではない。何となく男くさい気がして…(笑) ジョン・ウェインといえば"西部劇"というイメージ。よく知らないけど(笑)要するにさっきから書いているように"男くさい西部劇"ということ。だからオリジナルはもっと男くさかったのかなという気がする。オリジナルは未見なので、マティがどんな描かれ方なのか不明なのだけど、今作では彼女の視点で描かれる。それがとっても見やすかった気がする。主人公はマティということになるんだと思うけれど、おそらく真の主役はコグバーンなんだと思う。ジェフ・ブリッジスも、実は自分が主役であるというように演じていたと思う。上手く言えないけど…
マティは遠く離れた街から父の遺体を引き取りに1人でやって来た。弁護士からある程度の指示を受けていたとはいえ、ひとくせある男達とも対等あるいは、それ以上に渡り合う。度胸はスゴイけれど、その向こう見ずさは弁護士も呆れるほど。到着した日、ホテル代がないからと、父の他3体の遺体と一緒に葬儀社で寝るなんて、なんてタフ(笑) しかも彼女は14歳! 同じくチェイニーを追うテキサス・レンジャーのラビーフが、寝顔はかわいかったけど、殴りたいくらいムカつく的なことを言っていたけど、ホントにスゴイ。彼女の母は父親と一緒に帰って来るよう言い付けたらしいけれど、彼女はルースターを雇い自分もチェイニーを追うつもり。一度はコグバーンに出し抜かれてしまうけど、馬で駆け、川を渡り必死に追いつく。その必死さと、逞しさにコグバーンも彼女を受け入れる。このマティを演じたヘイリー・スタインフェルドがすごく良くて、生意気過ぎず、健気過ぎず、芯が強く、自分の意志をしっかり持った少女となっている。
コーエン兄弟の作品はまぁまぁ見ている方だと思うけど、これが"コーエン節"だとつかめているのか謎(笑) でも、淡々とした中に暴力やシュールな笑いを盛り込んでいるって感じなのかな… この作品もそう。全体的に結構暴力的だったり、痛いシーンも出てくるのだけど、どこかコミカルな感じ。それに救われている部分もある。居留地に逃げ込んだチェイニーの手がかりを得るために、雑貨店(?)に立ち寄るけれど、店のバルコニーに座る先住民の子供を何故か蹴落とすコグバーン。店を出る時も蹴落とす。実は人種差別的な要素があるのかもしれないけれど、何故かクスリと笑ってしまう。コグバーンなりのコミュニケーションなのかもしれない。3人が追うチェイニーが意外にヘタレでくだらない男なのも皮肉といえる。これは今ではコーエン兄弟作品の常連と言う感じのジョシュ・ブローリンのおかげで、極悪人というよりは無知で考えが足りない男になっていて、滑稽で少し切ない感じがする。その切なさは決してチェイニーに対しての同情ではないのだけど・・・
 でも、彼が小者である分、スカッとさせる部分はチェイニーをかくまっていたお尋ね者のネッドとコグバーンの対決シーンとなっている。数としては4対1なので派手さはないけれど、でもやっぱり不利ではある(笑) このネッドが割りと敵ながらカッコイイ。悪漢ながら約束は守るみたいな。まぁ、大好きな池波正太郎先生の「鬼平犯科帖」の”本物”の大盗賊のかっこよさにはかなわないけれど(笑) でも多分、連邦保安官コグバーンの狙いは、このネッドだったのでしょう。まぁ、最終的にはラビーフも加勢するけど、このシーンはかっこよかった。西部劇というと、背中合わせにお互い決められた歩数を歩き、振り返って撃つ1対1の決闘とか、大勢の騎馬隊というイメージだけど、そういう派手さはなかったものの、緊迫感も迫力もあって見応えがあった。
でも、彼が小者である分、スカッとさせる部分はチェイニーをかくまっていたお尋ね者のネッドとコグバーンの対決シーンとなっている。数としては4対1なので派手さはないけれど、でもやっぱり不利ではある(笑) このネッドが割りと敵ながらカッコイイ。悪漢ながら約束は守るみたいな。まぁ、大好きな池波正太郎先生の「鬼平犯科帖」の”本物”の大盗賊のかっこよさにはかなわないけれど(笑) でも多分、連邦保安官コグバーンの狙いは、このネッドだったのでしょう。まぁ、最終的にはラビーフも加勢するけど、このシーンはかっこよかった。西部劇というと、背中合わせにお互い決められた歩数を歩き、振り返って撃つ1対1の決闘とか、大勢の騎馬隊というイメージだけど、そういう派手さはなかったものの、緊迫感も迫力もあって見応えがあった。
おそらくコーエン兄弟が本当に見せたかったのは、この後なんだと思う。毒ヘビに噛まれて瀕死の状態のマティを救うため、コグバーンはマティの愛馬リトル・ブラッキーを全速力で駆けさせる。馬が限界だと思えばその体にナイフを突き立てて走らせる。とうとう馬が倒れると、自らマティを抱えて走る! ここで生きてくるのが、前半部分でマティが彼を初めて見た裁判シーン。犯罪者とはいえ殺し過ぎるのではないかと裁かれていた。コグバーンは正当防衛を主張していたけれど、見ている側にも印象は悪い。でも彼は今、救うべき命を必死で救おうとしている。それは彼が正しかったということではなくて、おそらく彼の中で何かが変わったという事なんだと思う。そして、その彼の必死さによって、リトル・ブラッキーを心配するマティと、同じ気持ちで見ていた側の甘さを思い知らされる。”生きる”ということ”生き抜く”ということは、そういう事なのだということ。リトル・ブラッキーの犠牲の上にマティは生きることになる。もちろんそれは誰かを犠牲にしてまで生きろということではない。それだけ命は重いということ。この事実自体は重いのに、映し出される映像は美しい星空の下、何もない砂漠を走り抜ける2人と1頭の姿。説明過多じゃなくてもしっかり伝わる。だからこそ伝わる。ちなみにこのシーンでナイフを刺されたのは、アニマトロニクス用のロボット馬とのこと。よかった!
全体としてマティ目線で描かれている。だから最初のヤマ場である、チェイニーを含むネッド一味の待ち伏せ作戦や、意見相違によって別行動をとっていたラビーフが巻き込まれてしまう様も、遠景で映される。でも、これもよかった気がする。本来はそんな視点なわけだし。その直前に指切断とかさんざん痛い場面を見せられたので、銃撃シーンなどはそんなに見たくないかも。でも、迫力がないわけではない。馬に引きずられたラビーフの舌のエピソードは痛かった・・・(涙) そいいう、正統派じゃない痛いシーン。そこ? って感覚も好きかも(笑) そして、このシーンを遠景でしか見せなかったことが、ネッド対コグバーンの対決シーンを引き立てる形になっている。
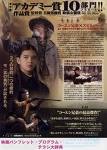 ほとんどのシーンが居留区の中で展開されるため、森の中とか自然の中のシーンが多い。なので”西部劇”という感じがあまりしない。前半の街並みとかもそんな感じではなかったかな・・・。これはマティ目線で描かれているので、いわゆるスウィング・ドアをバーンと開けて酒場に入るなんてシーンもなかったし(笑) 意外に街並み自体もゆったりとしたスケール感だったのは、自分の中で比較対象になっているマカロニ・ウエスタン映画が撮影された撮影場のスケール感だったりするのかな・・・。イヤ別にそれがダメと言っているわけではなく、あくまで好みの問題。何度も書くけど、あんまり男くさい映画が苦手というだけ。男くさいというのは荒っぽくて、お風呂も入らないような・・・(笑) コグバーンはちょっそんなタイプだったけど、比較的キレイなイメージなのはジェフ・ブリッジスのおかげかな。居留地の自然の映像がすごく良かった。シーンによってトーンや色を変えたりして、映像は全部キレイだった。
ほとんどのシーンが居留区の中で展開されるため、森の中とか自然の中のシーンが多い。なので”西部劇”という感じがあまりしない。前半の街並みとかもそんな感じではなかったかな・・・。これはマティ目線で描かれているので、いわゆるスウィング・ドアをバーンと開けて酒場に入るなんてシーンもなかったし(笑) 意外に街並み自体もゆったりとしたスケール感だったのは、自分の中で比較対象になっているマカロニ・ウエスタン映画が撮影された撮影場のスケール感だったりするのかな・・・。イヤ別にそれがダメと言っているわけではなく、あくまで好みの問題。何度も書くけど、あんまり男くさい映画が苦手というだけ。男くさいというのは荒っぽくて、お風呂も入らないような・・・(笑) コグバーンはちょっそんなタイプだったけど、比較的キレイなイメージなのはジェフ・ブリッジスのおかげかな。居留地の自然の映像がすごく良かった。シーンによってトーンや色を変えたりして、映像は全部キレイだった。
キャストについてはチラチラ書いて来たけど、マティ役のヘイリー・スタインフェルドが良かった! 一歩間違えば生意気で鼻持ちならくなりがちな役を、意志の強いしっかりした少女にしていた。適度に健気なのがいい。美少女過ぎないところも役に合っていたと思う。ラビーフ役のマット・デイモンも地味ながら好演。ラビーフも一歩間違えば足手まといな人物になりがち。でも、彼は彼なりの立場があるのだと思わせるのはさすが。コメディー担当でもあるけど、その辺りも良かったと思う。ファンの方にはラスト活躍の場がちゃんとあります(笑) ジョシュ・ブローリンの登場シーンは少ない。ネッドに持って行かれちゃった感もあるけど、ヘタレっぷりが良かった。必死に追ってきたのはこんなくだらないヤツなのかという皮肉がきいている。そして、やっぱりジェフ・ブリッジスが上手い。こういう映画の常として、コグバーンは初めはうさん臭くないとおもしろくない。敵か味方かっていう感じ。でありながら、さりげなくマティを守ってる感じや、スゴ腕であることを感じさせ過ぎずに、感じさせないとかっこよくない。見たことないので分からないけど、ジョン・ウエインだとこの辺り、うさん臭くてもカッコイイんじゃないだろうか。もちろんそれは全然OKだし、むしろそれが正統なんだと思う。だからこそジェフ・ブリッジスはあえてかっこよくなく演じたのかなと思う。意外に弱音吐いたり(笑) それが人間っぽくて良かった。そして、その感じがコーエン兄弟なのかと思う。
男くさい、いわゆるマカロニ・ウエスタンのような西部劇好きな方には、少し物足りないかもしれないけれど、"真の勇気"がしっかりと描かれている。それは正しいと思ったことをするということ。そして、その責任は取るということ。マティはこの復讐の旅で大きな代償を払った。それは自分で引き受けるしかない。
役者がいいとホントに見応えがある。約2時間あっという間だった。オススメ!
 『トゥルー・グリット』Official site
『トゥルー・グリット』Official site
*この試写会の翌日に東北関東大地震が起こった。自分も帰宅難民になった。余震が続く中、次々伝えられる被害の大きさに愕然とし、原発事故で恐怖を感じた。被災者の方に比べたら、ホントに甘いけれど、なかなか西部の世界に戻れなかった。10日が経ち、この2日天気もよく、少し気持ちが落ち着いたので、やっとレビュー書けました。遅くなってすみません
yaplog!で当選。見たかったコレ! 試写状届いた瞬間ガッツポーズだった!
*ネタバレありです!
 「父親を雇い人チェイニーに殺されたマティは、アル中保安官コグバーンを雇う。テキサス・レンジャーのラビーフも加わり彼を追う…」 という話。これは面白かった。王道な展開で、冒頭マティの父親が殺されたと伝えられるだけで、特に大きな出来事も起きないけれど、約2時間の長さも感じさせない。じんわりと感動できて見応えのある作品となっていた。
「父親を雇い人チェイニーに殺されたマティは、アル中保安官コグバーンを雇う。テキサス・レンジャーのラビーフも加わり彼を追う…」 という話。これは面白かった。王道な展開で、冒頭マティの父親が殺されたと伝えられるだけで、特に大きな出来事も起きないけれど、約2時間の長さも感じさせない。じんわりと感動できて見応えのある作品となっていた。1968年に連載開始されたチャールズ・ボーティスの同名小説が原作。翌1969年にはジョン・ウェイン主演で映画化されているけど、これは未見。true gritとは"真の勇気"という意味。監督はコーエン兄弟。彼らの作品は『ファーゴ』『ビッグ・リボウスキ』『バーバー』『ノーカントリー』を見た。すごいファンという感じではないけれど、見た作品はみんな好きだった。1番好きなのは『ファーゴ』かなぁ… ブシェミ出てるからね(笑) 今回の主演はジェフ・ブリッジス。『ビッグ・リボウスキ』でも主演だった。オリジナルの主演ジョン・ウェインといえば往年の名優で、もちろん知っているけど、作品を見た覚えがあまりない。たぶん、見てはいると思うけれど… ということで、つらつら書いて何が言いたいかというと、原作・前作にあまり思い入れがないけど、コーエン兄弟作品には少しありますということ。だから何という感じですが(笑)
西部劇は別に嫌いじゃないけど、特に好んで見る方ではない。何となく男くさい気がして…(笑) ジョン・ウェインといえば"西部劇"というイメージ。よく知らないけど(笑)要するにさっきから書いているように"男くさい西部劇"ということ。だからオリジナルはもっと男くさかったのかなという気がする。オリジナルは未見なので、マティがどんな描かれ方なのか不明なのだけど、今作では彼女の視点で描かれる。それがとっても見やすかった気がする。主人公はマティということになるんだと思うけれど、おそらく真の主役はコグバーンなんだと思う。ジェフ・ブリッジスも、実は自分が主役であるというように演じていたと思う。上手く言えないけど…
マティは遠く離れた街から父の遺体を引き取りに1人でやって来た。弁護士からある程度の指示を受けていたとはいえ、ひとくせある男達とも対等あるいは、それ以上に渡り合う。度胸はスゴイけれど、その向こう見ずさは弁護士も呆れるほど。到着した日、ホテル代がないからと、父の他3体の遺体と一緒に葬儀社で寝るなんて、なんてタフ(笑) しかも彼女は14歳! 同じくチェイニーを追うテキサス・レンジャーのラビーフが、寝顔はかわいかったけど、殴りたいくらいムカつく的なことを言っていたけど、ホントにスゴイ。彼女の母は父親と一緒に帰って来るよう言い付けたらしいけれど、彼女はルースターを雇い自分もチェイニーを追うつもり。一度はコグバーンに出し抜かれてしまうけど、馬で駆け、川を渡り必死に追いつく。その必死さと、逞しさにコグバーンも彼女を受け入れる。このマティを演じたヘイリー・スタインフェルドがすごく良くて、生意気過ぎず、健気過ぎず、芯が強く、自分の意志をしっかり持った少女となっている。
コーエン兄弟の作品はまぁまぁ見ている方だと思うけど、これが"コーエン節"だとつかめているのか謎(笑) でも、淡々とした中に暴力やシュールな笑いを盛り込んでいるって感じなのかな… この作品もそう。全体的に結構暴力的だったり、痛いシーンも出てくるのだけど、どこかコミカルな感じ。それに救われている部分もある。居留地に逃げ込んだチェイニーの手がかりを得るために、雑貨店(?)に立ち寄るけれど、店のバルコニーに座る先住民の子供を何故か蹴落とすコグバーン。店を出る時も蹴落とす。実は人種差別的な要素があるのかもしれないけれど、何故かクスリと笑ってしまう。コグバーンなりのコミュニケーションなのかもしれない。3人が追うチェイニーが意外にヘタレでくだらない男なのも皮肉といえる。これは今ではコーエン兄弟作品の常連と言う感じのジョシュ・ブローリンのおかげで、極悪人というよりは無知で考えが足りない男になっていて、滑稽で少し切ない感じがする。その切なさは決してチェイニーに対しての同情ではないのだけど・・・
 でも、彼が小者である分、スカッとさせる部分はチェイニーをかくまっていたお尋ね者のネッドとコグバーンの対決シーンとなっている。数としては4対1なので派手さはないけれど、でもやっぱり不利ではある(笑) このネッドが割りと敵ながらカッコイイ。悪漢ながら約束は守るみたいな。まぁ、大好きな池波正太郎先生の「鬼平犯科帖」の”本物”の大盗賊のかっこよさにはかなわないけれど(笑) でも多分、連邦保安官コグバーンの狙いは、このネッドだったのでしょう。まぁ、最終的にはラビーフも加勢するけど、このシーンはかっこよかった。西部劇というと、背中合わせにお互い決められた歩数を歩き、振り返って撃つ1対1の決闘とか、大勢の騎馬隊というイメージだけど、そういう派手さはなかったものの、緊迫感も迫力もあって見応えがあった。
でも、彼が小者である分、スカッとさせる部分はチェイニーをかくまっていたお尋ね者のネッドとコグバーンの対決シーンとなっている。数としては4対1なので派手さはないけれど、でもやっぱり不利ではある(笑) このネッドが割りと敵ながらカッコイイ。悪漢ながら約束は守るみたいな。まぁ、大好きな池波正太郎先生の「鬼平犯科帖」の”本物”の大盗賊のかっこよさにはかなわないけれど(笑) でも多分、連邦保安官コグバーンの狙いは、このネッドだったのでしょう。まぁ、最終的にはラビーフも加勢するけど、このシーンはかっこよかった。西部劇というと、背中合わせにお互い決められた歩数を歩き、振り返って撃つ1対1の決闘とか、大勢の騎馬隊というイメージだけど、そういう派手さはなかったものの、緊迫感も迫力もあって見応えがあった。おそらくコーエン兄弟が本当に見せたかったのは、この後なんだと思う。毒ヘビに噛まれて瀕死の状態のマティを救うため、コグバーンはマティの愛馬リトル・ブラッキーを全速力で駆けさせる。馬が限界だと思えばその体にナイフを突き立てて走らせる。とうとう馬が倒れると、自らマティを抱えて走る! ここで生きてくるのが、前半部分でマティが彼を初めて見た裁判シーン。犯罪者とはいえ殺し過ぎるのではないかと裁かれていた。コグバーンは正当防衛を主張していたけれど、見ている側にも印象は悪い。でも彼は今、救うべき命を必死で救おうとしている。それは彼が正しかったということではなくて、おそらく彼の中で何かが変わったという事なんだと思う。そして、その彼の必死さによって、リトル・ブラッキーを心配するマティと、同じ気持ちで見ていた側の甘さを思い知らされる。”生きる”ということ”生き抜く”ということは、そういう事なのだということ。リトル・ブラッキーの犠牲の上にマティは生きることになる。もちろんそれは誰かを犠牲にしてまで生きろということではない。それだけ命は重いということ。この事実自体は重いのに、映し出される映像は美しい星空の下、何もない砂漠を走り抜ける2人と1頭の姿。説明過多じゃなくてもしっかり伝わる。だからこそ伝わる。ちなみにこのシーンでナイフを刺されたのは、アニマトロニクス用のロボット馬とのこと。よかった!
全体としてマティ目線で描かれている。だから最初のヤマ場である、チェイニーを含むネッド一味の待ち伏せ作戦や、意見相違によって別行動をとっていたラビーフが巻き込まれてしまう様も、遠景で映される。でも、これもよかった気がする。本来はそんな視点なわけだし。その直前に指切断とかさんざん痛い場面を見せられたので、銃撃シーンなどはそんなに見たくないかも。でも、迫力がないわけではない。馬に引きずられたラビーフの舌のエピソードは痛かった・・・(涙) そいいう、正統派じゃない痛いシーン。そこ? って感覚も好きかも(笑) そして、このシーンを遠景でしか見せなかったことが、ネッド対コグバーンの対決シーンを引き立てる形になっている。
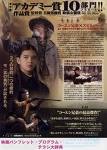 ほとんどのシーンが居留区の中で展開されるため、森の中とか自然の中のシーンが多い。なので”西部劇”という感じがあまりしない。前半の街並みとかもそんな感じではなかったかな・・・。これはマティ目線で描かれているので、いわゆるスウィング・ドアをバーンと開けて酒場に入るなんてシーンもなかったし(笑) 意外に街並み自体もゆったりとしたスケール感だったのは、自分の中で比較対象になっているマカロニ・ウエスタン映画が撮影された撮影場のスケール感だったりするのかな・・・。イヤ別にそれがダメと言っているわけではなく、あくまで好みの問題。何度も書くけど、あんまり男くさい映画が苦手というだけ。男くさいというのは荒っぽくて、お風呂も入らないような・・・(笑) コグバーンはちょっそんなタイプだったけど、比較的キレイなイメージなのはジェフ・ブリッジスのおかげかな。居留地の自然の映像がすごく良かった。シーンによってトーンや色を変えたりして、映像は全部キレイだった。
ほとんどのシーンが居留区の中で展開されるため、森の中とか自然の中のシーンが多い。なので”西部劇”という感じがあまりしない。前半の街並みとかもそんな感じではなかったかな・・・。これはマティ目線で描かれているので、いわゆるスウィング・ドアをバーンと開けて酒場に入るなんてシーンもなかったし(笑) 意外に街並み自体もゆったりとしたスケール感だったのは、自分の中で比較対象になっているマカロニ・ウエスタン映画が撮影された撮影場のスケール感だったりするのかな・・・。イヤ別にそれがダメと言っているわけではなく、あくまで好みの問題。何度も書くけど、あんまり男くさい映画が苦手というだけ。男くさいというのは荒っぽくて、お風呂も入らないような・・・(笑) コグバーンはちょっそんなタイプだったけど、比較的キレイなイメージなのはジェフ・ブリッジスのおかげかな。居留地の自然の映像がすごく良かった。シーンによってトーンや色を変えたりして、映像は全部キレイだった。キャストについてはチラチラ書いて来たけど、マティ役のヘイリー・スタインフェルドが良かった! 一歩間違えば生意気で鼻持ちならくなりがちな役を、意志の強いしっかりした少女にしていた。適度に健気なのがいい。美少女過ぎないところも役に合っていたと思う。ラビーフ役のマット・デイモンも地味ながら好演。ラビーフも一歩間違えば足手まといな人物になりがち。でも、彼は彼なりの立場があるのだと思わせるのはさすが。コメディー担当でもあるけど、その辺りも良かったと思う。ファンの方にはラスト活躍の場がちゃんとあります(笑) ジョシュ・ブローリンの登場シーンは少ない。ネッドに持って行かれちゃった感もあるけど、ヘタレっぷりが良かった。必死に追ってきたのはこんなくだらないヤツなのかという皮肉がきいている。そして、やっぱりジェフ・ブリッジスが上手い。こういう映画の常として、コグバーンは初めはうさん臭くないとおもしろくない。敵か味方かっていう感じ。でありながら、さりげなくマティを守ってる感じや、スゴ腕であることを感じさせ過ぎずに、感じさせないとかっこよくない。見たことないので分からないけど、ジョン・ウエインだとこの辺り、うさん臭くてもカッコイイんじゃないだろうか。もちろんそれは全然OKだし、むしろそれが正統なんだと思う。だからこそジェフ・ブリッジスはあえてかっこよくなく演じたのかなと思う。意外に弱音吐いたり(笑) それが人間っぽくて良かった。そして、その感じがコーエン兄弟なのかと思う。
男くさい、いわゆるマカロニ・ウエスタンのような西部劇好きな方には、少し物足りないかもしれないけれど、"真の勇気"がしっかりと描かれている。それは正しいと思ったことをするということ。そして、その責任は取るということ。マティはこの復讐の旅で大きな代償を払った。それは自分で引き受けるしかない。
役者がいいとホントに見応えがある。約2時間あっという間だった。オススメ!
 『トゥルー・グリット』Official site
『トゥルー・グリット』Official site*この試写会の翌日に東北関東大地震が起こった。自分も帰宅難民になった。余震が続く中、次々伝えられる被害の大きさに愕然とし、原発事故で恐怖を感じた。被災者の方に比べたら、ホントに甘いけれど、なかなか西部の世界に戻れなかった。10日が経ち、この2日天気もよく、少し気持ちが落ち着いたので、やっとレビュー書けました。遅くなってすみません