kahoの日記で有名になった「kaho」さんこと、遠藤高帆さんのSTAP反証論文Quality control method for RNA-seq using single nucleotide polymorphism allele frequencyが本日Genes to Cellsにでていた。STAPの反証論文としては初めてのものである(*)
ちょっと読んでみると、主にRNA-seqデーターを基に、解析を行っており、以前kahoの日記で有名になったChip-seqのインプットのデーターを基にした解析の話はでていなかった。
Chip-seqの解析はちょっと雑な感じもしたので、kahoさんの方で詰めきれなかったことがあったのだろうか。また不可思議なのは、以前NCBIにdepositしてあったChip-seqデータ(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/biosample/?term=SAMN02393426+OR+SAMN02393427+OR+SAMN02393428+OR+SAMN02393429+OR+SAMN02393430+OR+SAMN02393431+OR+SAMN02393432+OR+SAMN02393433+OR+SAMN02393434+OR+SAMN02393435)は今見れなくなっている。元論文自体リトラクトされたからその影響とも取れるのですが、置いておくとまずいことでもあったのかもしれない(**)。
論文の趣旨としては、RNA-seqに利用されている細胞のジェノタイプが129/B6のF1であることに着目して、129とB6とで配列のことなるSNPに着目し、129とB6由来の染色体アリルの混ざりぐあいを調べる(129B6F1なので本来は50%)手法を基にして、次のことを見出している。
1)ES,STAP,STAP-SCはdepositデーターのアノテーション通り129B6F1由来、FI-SCはアノテーションでは129B6F1であるが、ほとんどがB6由来の細胞であると考えられる。
2)FI-TSCは一部の遺伝子はCD1由来のSNPを持ち、その他の遺伝子に関してはB6由来のSNPをもつ。ES(B6)+TSC(CD1)といった混ざりものの細胞ではないのか?
3)STAP細胞については、ゲノム全体では129由来のアリルとB6由来のアリルの半々が混ざっているが、8番染色体に反してはB6由来のアリルが30%しか占めていない。8番染色体のトリソミーが示唆される。
4)各種遺伝子の発現ES細胞とSTAP細胞とで比べると8番染色体由来の遺伝子の発現がSTAP細胞で優位に多く、13番染色体由来の遺伝子の発現がSTAP細胞で少ない。このことからも8番染色体の数の増加、13番染色体の欠失が疑われる。
5)8番染色体はマウスの培養したES細胞に多い変異であり、STAP細胞はES細胞+体細胞の混ざったものであることが考えられる。
6)8番染色体の異常のあるES細胞はマウス個体をつくらないので、このことからもSTAP細胞よりマウス個体がつくれるSTAP幹細胞ができたというのは疑わしい。
といったことになる。
以前この研究に関する報道をうけて考察したものづくりのための研究ノート043:STAP細胞=ES細胞でない??「kahoの日記」の意外な結末!!でのべていたように
結局STAP細胞&STAP関連細胞の系統としては
1)ES細胞単独
2)ES+TS細胞
3)ES+体細胞
の3つがあるのかもしれない。少なくとも2)、3)の系統はあることがこの論文からは示唆される。
すると気になるは、ES細胞やTS細胞のソースはどこ??コンタミは意図的??ということではないだろうか?
細胞の供給者というか、事情を知りすぎた人物がいるのではないか?(***)
(*)生物学的な反証論文というのもそろそろ出そうという噂である。こんなこともあるから当初1年かかるとしていた再現実験も、11月までが目安なのだろうか?
(**)よくよくみるとSRP038104にまとめられておりました。。(10月21日追記)
(***)単独犯ではない?!これ以上は憶測になるので、書けませんね。
(10月8日追記)
トリソミー8はマウスのMDS細胞由来で、ES由来は否定できるはないかという話もでているようであるが、
1)いくらB6でも新生児マウスでMDSはそんなにおらんやろう。普通に使うadultでもそんなに見たことはない(月齢12か月とかでない限り、そんなに頻発しないのでは?)。
2)マウス由来でそれがたまたまMDSであったとしても、その後培養できないし、マウスの個体はつくれんやろう
とあまり説得力がない。
現実的には、状況証拠的なこのバイオインフォの結果だけでなく、近々出るという生物学的な反証論文も含めて、最終的には総合的に判断するということになるのだろう。
(追記)2016年3月1日追記。
個人的にはもはや興味を失っていたのだけれど、未だにこのブログのSTAP関連の項目を目にされている方が多い様なので、追記しておく。
2015年9月24日同様の趣旨からなる論文をNatureが掲載した。
1報目"Failure to replicate the STAP cell phenomenon"はボストンを中心とした幹細胞分野の大御所たちのチームによるもの
2報目"STAP cells are derived from ES cells"は理研のグループによるもの
の二つで、1はほぼ全てのSTAPのprotocolを検証し、作成できないことを示すとともに、バイオインフォマテッィクスを利用してSTAP細胞とされていたものに、ESが混ざっていることを証明したもの、2もバイオインフォマティックスを用いてESのまざりを証明したものである。
STAPの論文は途中から基本的に無理筋な感じを呈してきたが、これで完全に決着がついた。残念ながら、おそらく誰かがES細胞を混ぜて虚構の細胞を作ったことになる(結局それが誰かわからないのであるが。。)。ただこの一件で日本のサイエンスに大きな傷跡が残り、一人の偉大な科学者を失ったことは悔やまれる。
ちょっと読んでみると、主にRNA-seqデーターを基に、解析を行っており、以前kahoの日記で有名になったChip-seqのインプットのデーターを基にした解析の話はでていなかった。
Chip-seqの解析はちょっと雑な感じもしたので、kahoさんの方で詰めきれなかったことがあったのだろうか。また不可思議なのは、以前NCBIにdepositしてあったChip-seqデータ(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/biosample/?term=SAMN02393426+OR+SAMN02393427+OR+SAMN02393428+OR+SAMN02393429+OR+SAMN02393430+OR+SAMN02393431+OR+SAMN02393432+OR+SAMN02393433+OR+SAMN02393434+OR+SAMN02393435)は今見れなくなっている。元論文自体リトラクトされたからその影響とも取れるのですが、置いておくとまずいことでもあったのかもしれない(**)。
論文の趣旨としては、RNA-seqに利用されている細胞のジェノタイプが129/B6のF1であることに着目して、129とB6とで配列のことなるSNPに着目し、129とB6由来の染色体アリルの混ざりぐあいを調べる(129B6F1なので本来は50%)手法を基にして、次のことを見出している。
1)ES,STAP,STAP-SCはdepositデーターのアノテーション通り129B6F1由来、FI-SCはアノテーションでは129B6F1であるが、ほとんどがB6由来の細胞であると考えられる。
2)FI-TSCは一部の遺伝子はCD1由来のSNPを持ち、その他の遺伝子に関してはB6由来のSNPをもつ。ES(B6)+TSC(CD1)といった混ざりものの細胞ではないのか?
3)STAP細胞については、ゲノム全体では129由来のアリルとB6由来のアリルの半々が混ざっているが、8番染色体に反してはB6由来のアリルが30%しか占めていない。8番染色体のトリソミーが示唆される。
4)各種遺伝子の発現ES細胞とSTAP細胞とで比べると8番染色体由来の遺伝子の発現がSTAP細胞で優位に多く、13番染色体由来の遺伝子の発現がSTAP細胞で少ない。このことからも8番染色体の数の増加、13番染色体の欠失が疑われる。
5)8番染色体はマウスの培養したES細胞に多い変異であり、STAP細胞はES細胞+体細胞の混ざったものであることが考えられる。
6)8番染色体の異常のあるES細胞はマウス個体をつくらないので、このことからもSTAP細胞よりマウス個体がつくれるSTAP幹細胞ができたというのは疑わしい。
といったことになる。
以前この研究に関する報道をうけて考察したものづくりのための研究ノート043:STAP細胞=ES細胞でない??「kahoの日記」の意外な結末!!でのべていたように
結局STAP細胞&STAP関連細胞の系統としては
1)ES細胞単独
2)ES+TS細胞
3)ES+体細胞
の3つがあるのかもしれない。少なくとも2)、3)の系統はあることがこの論文からは示唆される。
すると気になるは、ES細胞やTS細胞のソースはどこ??コンタミは意図的??ということではないだろうか?
細胞の供給者というか、事情を知りすぎた人物がいるのではないか?(***)
(*)生物学的な反証論文というのもそろそろ出そうという噂である。こんなこともあるから当初1年かかるとしていた再現実験も、11月までが目安なのだろうか?
(**)よくよくみるとSRP038104にまとめられておりました。。(10月21日追記)
(***)単独犯ではない?!これ以上は憶測になるので、書けませんね。
(10月8日追記)
トリソミー8はマウスのMDS細胞由来で、ES由来は否定できるはないかという話もでているようであるが、
1)いくらB6でも新生児マウスでMDSはそんなにおらんやろう。普通に使うadultでもそんなに見たことはない(月齢12か月とかでない限り、そんなに頻発しないのでは?)。
2)マウス由来でそれがたまたまMDSであったとしても、その後培養できないし、マウスの個体はつくれんやろう
とあまり説得力がない。
現実的には、状況証拠的なこのバイオインフォの結果だけでなく、近々出るという生物学的な反証論文も含めて、最終的には総合的に判断するということになるのだろう。
(追記)2016年3月1日追記。
個人的にはもはや興味を失っていたのだけれど、未だにこのブログのSTAP関連の項目を目にされている方が多い様なので、追記しておく。
2015年9月24日同様の趣旨からなる論文をNatureが掲載した。
1報目"Failure to replicate the STAP cell phenomenon"はボストンを中心とした幹細胞分野の大御所たちのチームによるもの
2報目"STAP cells are derived from ES cells"は理研のグループによるもの
の二つで、1はほぼ全てのSTAPのprotocolを検証し、作成できないことを示すとともに、バイオインフォマテッィクスを利用してSTAP細胞とされていたものに、ESが混ざっていることを証明したもの、2もバイオインフォマティックスを用いてESのまざりを証明したものである。
STAPの論文は途中から基本的に無理筋な感じを呈してきたが、これで完全に決着がついた。残念ながら、おそらく誰かがES細胞を混ぜて虚構の細胞を作ったことになる(結局それが誰かわからないのであるが。。)。ただこの一件で日本のサイエンスに大きな傷跡が残り、一人の偉大な科学者を失ったことは悔やまれる。













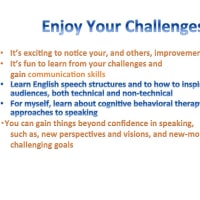
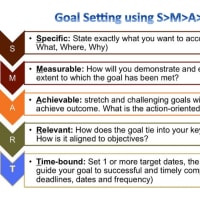
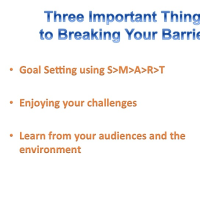
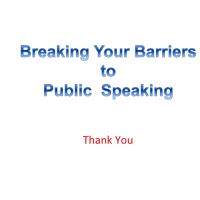
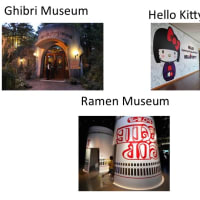

129B6のように見える。別にCD1と比較したのかな?
あとTSは、小保方さんたちがdepositしていたものが、CD1とされています(SRP038104参照)。
念のためアノテーションを引用しておくと以下のようなです。
Sample: SAMN02393453 • Generic sample from Mus musculus (less...)
Organism: Mus musculus
Attributes:
strain: CD1
development stage: Trophoblast stem cells
sample type: ChIPSeq
label: TS_H3K4me3_ChIPSeq
Sample: SAMN02393429 • Generic sample from Mus musculus (less...)
Organism: Mus musculus
Attributes:
strain: CD1
development stage: Trophoblast stem cells
sample type: RNA-seq
label: TS cell RNA-seq
若山研ではTSを129B6から作成しコントロールとして使用していたとのことなので、ひょっとしてstrainの登録ミスかと疑ってしまいました。129B6だとしたらFig4はありえませんか。
あとFig2はTSのオリジンについては何も言ってないんじゃないかなとおもっています。
2Dを言われているのだと思いますが、これはたとえばB6がA、129がTのSNPがあった時に、AA型(B6homo型) AT型(129B6hetero型)、TT型(129homo型)と分けられると思いますが、いくつかの遺伝子を見たときに、B6homo型, 129B6hetero型,129homo型の割合がどうなのかみただけのグラフだと思います。なのでexplicit
にTSのオリジンを述べているデーターではない気がしております。
ただこのグラフ、基本的に、三分類でその他というところがなく、CD1でまったく違うタイプのSNPた上の例でとえばGとかがあった場合がなぜ含まれていないのかという疑問は残りますが。。
トリソミーの件も1.5倍以上の結果、または129側からの解析結果が示されないとちょっと弱いと結論と思われます。
FigS1は、直感的には、non B6型ホモ、B6/non B6型へテロ、B6型ホモのアリルの割合をしめしたものなので、0, 50%, 100%の3ポイントからなるdiscreteなグラフとして考えるべきだと思います。
ここで重要なのは、0%のピークです。B6・129はF1(元論文でということになっています)なので、0%のピークがでません。
0%のピークがあるということは、nonB6型ホモのアリルということ、すなわち、B6とは別の系統のマウスか、B6と別の系統のマウスとのヘテロマウスならF2移行の世代のマウス(Fig1のNF, CAFはB6XBalB/cですが、3ライン掛け合わせなので、普通のF1ではない感じのようですね)だと思います。
EpiSCと似ているというのはあながち間違った意見ではなくて、129/svというストレインなので、0%のピークがあるからです。
ポジコンがないのでなんともいえませんが、以上からTSはCD-1でよいのかなと思います。
またFI_SCはES(B6)+TS(CD-1)の混ざり物というのがkahoさんの主張だったのですが、Fig1,4での主張のようにほとんどがES由来の細胞であるという主張なので、一応議論は成立しているのだと思います。
また、以下のブログではGOF(B6)の記載もあり、B6のSTAP-SCが存在し、B6のFI-SCの存在も予想されます。
http://jupiter-press.doorblog.jp/archives/40654238.html
Sample: SAMN02393427 • Generic sample from Mus musculus (less...)
Organism: Mus musculus
Attributes:
strain: 129/sv
development stage: Epi stem cells
sample type: RNA-seq
label: Epi stem cell RNA-seq
もとのnature論文が結構いい加減なデータ管理になっていたので、ご指摘のように、データベースの情報にも記載ミスがある可能性については、ゼロではないと思います。