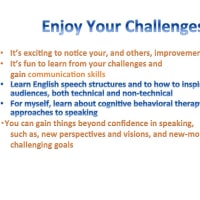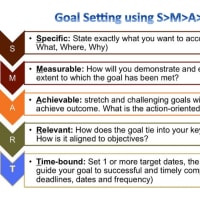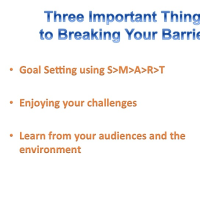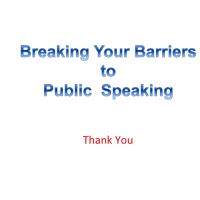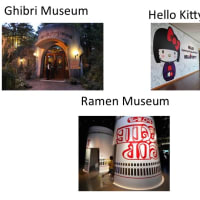最近グローバル人材育成という言葉をよく耳にする。
実際の現場でどうなっているかは不明であるが、報道だけをみているとと、グローバル人材育成推進=英語教育を強化するということに重きが置かれている気がする。
たとえば初等教育の英語を強化するなどということはその目玉の一つらしい。ただ、このグローバル人材育成推進=英語教育という方針には少し、疑問を感じる。実際のところ、言語能力の発達というものは一般の人が思っているよりも複雑で、初等教育で多少のインプットを増やしたくらいではそんなに効果がない(*)
一方英語圏で暮らしてみて初めて実感したのであるが、人付きあいから、仕事上の調整法まで、英語上のコミニュケーション能力の向上という面では、学校教育というよりは、どちらかというと、場数を踏んだ効果の方が多い気がする(**)。
特に私の場合、英語のスキルセットは短期記憶の形で保存されているようで、週末に英語を使わなかっただけで、格段に英語が下手になるくらいなので、はるか昔に習った教育の効果というものは少ないわけである(***)。
一方で大学や大学院生などの若い世代にとって、特に理工系の場合、場数を踏む機会って減っているのではないかと危惧する。
例えば理工系の場合、グローバルな場に身を置く機会として一番大きなものに、留学があるのだけれど、10年くらい前まではポスドクとしてアメリカに留学する場合給料は出してもらえるケースが多かった(****)。
ところが現在財政の崖等の問題で研究費が縮小傾向にあるせいか、多くの研究室で各人で奨学金をとってくること、もしくは何らかの自己資金で留学することが必要となってきている。
逆に日本でも不況であることには変わりはなく、留学はおろか、家庭の経済的な理由で大学を卒業できないケースも増えているというニュースもある。それに海外留学用の奨学金もそんなに門戸は広くないのが実情だ。
日本人が留学しなくなったといわれているが、経済的な側面も背景にあるのではないだろうか?
現状のグローバル人材育成は、英語の教育プログラムをつくることに終始している気がするが、実際のところは教育機関への予算配分のエクスキューズとなっているだけの気もする。
本来のグローバル人材育成は、一人でも多くの若い人に場数を踏むチャンスを与えることが一番効果的なのではないだろうか??制度上難しいのかもしれないが、下手に英語教育をするよりは、その分の予算を奨学金にして、幅広く若い人に場数を踏んできてもらうというような方向性もあってもよいのかもしれない(*****)。
(*)在留邦人の子弟の英語教育に長年かかわり、早期英語教育に警鐘をならす市川力さんの英語を子どもに教えるな (中公新書ラクレ) 新書がこの辺りの状況を詳しく説明している。
(**)英語を試す場数というだけでなく、多様な中でもまれてもサバイバルする人間力みたいなものの、本来のグローバル人材育成では必要な要素ではないだろうか?
この間大学のトランスレーショナルリサーチに関するセミナーで
Homogeneous teams are easier but weak.
Diverse teams are harder but strong.
という言葉が紹介されておりました。ローマは一日にして成らずではありませんが、グローバル人材(多様性への適応)も一日にしてならず。。深い言葉だなと思います。小手先ではうまくいかないのではないかな?
(***)英語のスキルセットが短期記憶なのはたぶん大体の日本人そうではないかと思っています。たとえば元グーグル日本支社長の村上さんの英語術も、短期記憶なことを前提にして絶えず大量の英語に触れるというもの。
ハリウッドで活躍された女優の工藤夕貴さんも、「以前、英語で喋ろうとしたら言葉が出なくなったことがあり」、それ以来、「英語脳に雑草厳禁!!」という面白い標語つくって、1日に1回は英語を聞くことを実践しておられるとか。
(****)ノーベル賞学者の小柴先生が留学した時代は、著書「やれば、できる」によると、ポスドクの給料が為替の関係もあって、当時の日本の大学教授の3倍くらいあったとか。。そこまではいかないにしても10年前と今とでは全然状況が違います。いずれにせよ前の方がハッピーだったなー。
(*****)逆に若い人たちに、場を提供して、感受性の豊かな時代に学んできてもらう方が、下手なおじさんが教育すると意気込むよりいいかもしれない。そもそも、グローバル人材育成って意気込むことろが、海外とか英語とかに多少なりとも憧れのあるおじさん的な発想だ。日本人以外だとグローバル人材育成ってそんなに特殊なことではない。ここにいる韓国人にしても、中国人にしても、インド人や、ヨーロッパ人にしても、英語で海外で職を見つけて活躍するということは、どこでも自然にやっていて、空気のように当たり前な選択肢の一つのように見える。
実際の現場でどうなっているかは不明であるが、報道だけをみているとと、グローバル人材育成推進=英語教育を強化するということに重きが置かれている気がする。
たとえば初等教育の英語を強化するなどということはその目玉の一つらしい。ただ、このグローバル人材育成推進=英語教育という方針には少し、疑問を感じる。実際のところ、言語能力の発達というものは一般の人が思っているよりも複雑で、初等教育で多少のインプットを増やしたくらいではそんなに効果がない(*)
一方英語圏で暮らしてみて初めて実感したのであるが、人付きあいから、仕事上の調整法まで、英語上のコミニュケーション能力の向上という面では、学校教育というよりは、どちらかというと、場数を踏んだ効果の方が多い気がする(**)。
特に私の場合、英語のスキルセットは短期記憶の形で保存されているようで、週末に英語を使わなかっただけで、格段に英語が下手になるくらいなので、はるか昔に習った教育の効果というものは少ないわけである(***)。
一方で大学や大学院生などの若い世代にとって、特に理工系の場合、場数を踏む機会って減っているのではないかと危惧する。
例えば理工系の場合、グローバルな場に身を置く機会として一番大きなものに、留学があるのだけれど、10年くらい前まではポスドクとしてアメリカに留学する場合給料は出してもらえるケースが多かった(****)。
ところが現在財政の崖等の問題で研究費が縮小傾向にあるせいか、多くの研究室で各人で奨学金をとってくること、もしくは何らかの自己資金で留学することが必要となってきている。
逆に日本でも不況であることには変わりはなく、留学はおろか、家庭の経済的な理由で大学を卒業できないケースも増えているというニュースもある。それに海外留学用の奨学金もそんなに門戸は広くないのが実情だ。
日本人が留学しなくなったといわれているが、経済的な側面も背景にあるのではないだろうか?
現状のグローバル人材育成は、英語の教育プログラムをつくることに終始している気がするが、実際のところは教育機関への予算配分のエクスキューズとなっているだけの気もする。
本来のグローバル人材育成は、一人でも多くの若い人に場数を踏むチャンスを与えることが一番効果的なのではないだろうか??制度上難しいのかもしれないが、下手に英語教育をするよりは、その分の予算を奨学金にして、幅広く若い人に場数を踏んできてもらうというような方向性もあってもよいのかもしれない(*****)。
(*)在留邦人の子弟の英語教育に長年かかわり、早期英語教育に警鐘をならす市川力さんの英語を子どもに教えるな (中公新書ラクレ) 新書がこの辺りの状況を詳しく説明している。
(**)英語を試す場数というだけでなく、多様な中でもまれてもサバイバルする人間力みたいなものの、本来のグローバル人材育成では必要な要素ではないだろうか?
この間大学のトランスレーショナルリサーチに関するセミナーで
Homogeneous teams are easier but weak.
Diverse teams are harder but strong.
という言葉が紹介されておりました。ローマは一日にして成らずではありませんが、グローバル人材(多様性への適応)も一日にしてならず。。深い言葉だなと思います。小手先ではうまくいかないのではないかな?
(***)英語のスキルセットが短期記憶なのはたぶん大体の日本人そうではないかと思っています。たとえば元グーグル日本支社長の村上さんの英語術も、短期記憶なことを前提にして絶えず大量の英語に触れるというもの。
ハリウッドで活躍された女優の工藤夕貴さんも、「以前、英語で喋ろうとしたら言葉が出なくなったことがあり」、それ以来、「英語脳に雑草厳禁!!」という面白い標語つくって、1日に1回は英語を聞くことを実践しておられるとか。
(****)ノーベル賞学者の小柴先生が留学した時代は、著書「やれば、できる」によると、ポスドクの給料が為替の関係もあって、当時の日本の大学教授の3倍くらいあったとか。。そこまではいかないにしても10年前と今とでは全然状況が違います。いずれにせよ前の方がハッピーだったなー。
(*****)逆に若い人たちに、場を提供して、感受性の豊かな時代に学んできてもらう方が、下手なおじさんが教育すると意気込むよりいいかもしれない。そもそも、グローバル人材育成って意気込むことろが、海外とか英語とかに多少なりとも憧れのあるおじさん的な発想だ。日本人以外だとグローバル人材育成ってそんなに特殊なことではない。ここにいる韓国人にしても、中国人にしても、インド人や、ヨーロッパ人にしても、英語で海外で職を見つけて活躍するということは、どこでも自然にやっていて、空気のように当たり前な選択肢の一つのように見える。