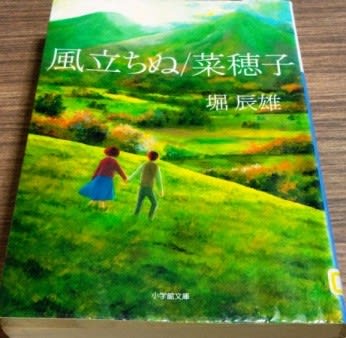
堀辰雄『菜穂子』を読んだ。
前半部分の「楡の家」は講談社文芸文庫の『風立ちぬ/ルウベンスの偽画』で、「菜穂子」は小学館文庫の『風立ちぬ/菜穂子』で読んだ。
理由は『風立ちぬ』と同じで、講談社文芸文庫は振り仮名(ルビ)が少なくて読めない漢字が多いのに対し、小学館文庫は振り仮名がたくさんついていたからである。
懶そう(ものうそう)、牢(ひとや)、廃す(よす)、稺い(おさない)、衣囊(かくし)、雪袴(たつつけ。※「たっつけ」と読むらしい。ルビでは促音はわからない)など、ルビのおかげで助かった。雪袴などは読むことができなくても、「ゆきばかま」でもどんな物かは漠然と理解できた。
為合せ(しあわせ)、佯って(いつわって)、赫かしい(かがやかしい)、縺れる(もつれる)、過ぎる(よぎる)などは、何度も出てくるので次第に覚えた。
講談社文芸文庫では『楡の家』は独立の作品として収録されているが、小学館文庫では『菜穂子』の一部(一つの章)とされている。
発表されたのは別々で、「楡の家」の第1部(旧題「物語の女」)が昭和9年10月、第2部(旧題「目覚め」)は昭和16年9月の発表である。「菜穂子」は昭和16年3月の発表で、単行本化は同年11月となっている(小学館文庫の年譜(谷田昌平編)、講談社文芸文庫の年譜(大橋千明作成)による)。
小学館文庫には、「風立ちぬ」と「楡の家」と「菜穂子」が収録されている。何でこの組み合わせなのか?と思ったが、「菜穂子」には、『風立ちぬ』の節子につき添う主人公(私=堀?)と『菜穂子』の菜穂子とが、八ヶ岳の高原のサナトリウムの廊下ですれ違う場面が出てくるから、多少のつながりがあった。
「楡の家」は、後に菜穂子が読むことになる母の日記であるから、「菜穂子」につながっているが、内容や叙述の形式は大きく異なっている。
これらの小説が、堀および芥川龍之介と、片山広子母娘との交流をモデルにしていることは、小川和佑『“美しい村”を求めてーー新・軽井沢文学散歩』(読売新聞社)などで知ることができる。年譜によると、堀、芥川と片山母娘が交流をもったのは大正13年、14年のことであり、堀に大きなショックを与えた芥川の自殺がその2年後の昭和2年のことである。
「楡の家」は、菜穂子の母親(三村夫人)が残した日記の形式をとっている。未亡人となった彼女が追分の別荘で夏を過ごした際に、森於菟彦という有名な作家から好意を寄せられ困惑する、そのことがただでさえ気難しい娘の菜穂子とのわだかまりの遠因になっているのではないかと悩む。
彼女の追分の別荘の庭に植わっているのが楡の木で、その根元に彼女は丸太のベンチをこしらえさせて、しばしば一人でその椅子に腰を下ろして物思いにふけっている。
芥川は昭和2年に自殺したが、「楡の家」の森於菟彦は自殺ではなく、旅先の北京で客死したことになっている。森の死が語られる「楡の家」(第2部)は昭和16年の作品だから、堀が芥川の死を小説に書くまでには10年以上の年月が必要で、それでも自殺と書くことはできなかった。
「菜穂子」は、その表題からも女性が主人公の物語のようであり、菜穂子の描き方も読みごたえがあるのだが(男性の作家がここまで女性を描くのか!)、それでもぼくは、この小説を「母」を求めたが、しかし結局「母」を得ることのできなかった男の切ない物語として読んだ。
冬枯れた樺の枝が冬空を背景につくった網目模様のなかに、「自分の稺い(おさない)頃死んだ母のなんとなく老けたような顔をぼんやり思い浮かべた」といった直接の表現もあるが(小学館文庫250、252頁)、明に向けられた菜穂子の空虚なまなざしに出会うたびに、菜穂子に思いを寄せる明は拒絶を感じたことだろう。
堀は、大正12年に関東大震災で母を失っている。その直後に、軽井沢で室生犀星から芥川を紹介される。片山母子と知り合うのが翌年の大正13年である。
明は菜穂子やその母だけでなく、追分の老舗旅館牡丹屋で世話になる旧知の年上女性おようさんや、雨宿りで偶然知り合った村娘の早苗にも好意を寄せるが、結局だれからも受け入れられることはない。自ら飛び込んでいこうともしない。
菜穂子は不本意で結婚した夫だけでなく、幼なじみの明に対しても屡々(しばしば)空虚な眼差しを向ける。
「菜穂子」は、人物の描写や、風景、気候などの自然描写、ストーリーの展開がいかにも小説らしく、菜穂子母子を片山母子、森於菟彦を芥川、都築明を堀と見立てて、一気に読んだ。
しかも、追分の人々がたんなる背景ではなく、生きとし生ける人間として描かれている。
吹雪の舞う冬の八ヶ岳のサナトリウムから雪の東京に逃げ帰った菜穂子で話は結ばれるのだが、戦前の昭和の追分の「ある秋の日の物語」のような読後感が残った。
そう言えば、どこかに「或る秋の日の小さな出来事」という文章があった(探すと小学館文庫164頁にあった)。
「菜穂子」は、「母」をむなしく求める物語であると同時に、堀が持つことのなかった「故郷」、「家郷」を追分に求める物語でもあった。
追分にやってきた明は、そこで「O村の特有な匂」いを感じ(218頁)、「自分の村だとか家だとか、・・・そんなものは何んにもない此のおれは一体どうすれば好いのか?」と嘆息している(228頁)。堀はそれを追分に見出したのだろう。
「菜穂子」は、“軽井沢もの”ではなく、“サナトリウムもの”でもなく、“追分”小説として読んだ。「楡の家」は追分の落葉松の林の中にあり、三村夫人と森が虹を見たのも追分のはずれだった。

※ 上の写真は、追分に建てられた堀辰雄の最後の家。旧油屋の跡地にあり、現在は堀辰雄記念館になっている。現在の油屋や古書<追分コロニー>の向かい側にある。
堀は昭和28年にこの家で亡くなり、『軽井沢を青年が守った』に登場する地元の人たち、油屋の息子や堀の書庫を建築途中だった大工らによって塩沢の火葬場に運ばれ、追分で仮葬儀が行われたという(88頁)。
2021年10月13日 記
※ ぼくは中学2年生のときの国語教科書(光村図書)に載っていた芥川龍之介の「魔術」を読んで、読書の世界に迷い込んだ(今風に言えば「はまった」)。そして、偕成社の「少年少女現代日本文学全集」で芥川、夏目漱石、菊池寛、そして堀辰雄らを読むことになった。
中学生にもなって「少年少女・・・」でもあるまいと内心でずっと恥じていたのだが、この秋、堀辰雄『風立ちぬ・美しい村』を昭和26年初版の新潮文庫で読もうとして、その漢字の難しさに音を上げた。これでは中学2年のぼくが読めないとしても当然である。新字体、新かな遣いに改められ、難読語にはルビがふられた偕成社版を選んだのは正解だった。巻頭の口絵には著者の幼少期の写真などが載っており、巻末には解説、読書指導、感想文コンクールの優秀作なども載っていた。
もし、中学校の教科書からいきなり(昭和38年当時の)岩波文庫で芥川に挑戦したり、新潮文庫の堀辰雄を読み始めたら、きっとぼくは読書嫌いになっていたと思う。
『風立ちぬ』は小学館文庫で、『菜穂子』は改版された岩波文庫で、『美しい村』は角川文庫で読んできて、つまり、新字体、新かな遣い、ルビがたくさん振ってある文庫本で読みながら、つくづくそう思った。
2021年11月2日 追記















