1月7日 土曜日
久々にメンデルスゾーンを弾く、
大好きな無言歌の中から最も好きな曲を1曲。
最近のレッスンで弾いているのはショパンのマズルカ。
ショパンは、どこか甘ったるくて軟弱で苦手なイメージ。
嫌いな訳ではない。どちらかというと感覚が近すぎて苦手なのだ。
旋律が持つスラブっぽさは私が生まれた北海道と共通する
何か寒い国の人間が持つ特有の陰鬱なものを感じるので
嫌いじゃないけど敬遠してしまうような想いを抱く。
解りすぎるものとは距離を置きたいのかもしれない。
しかし同じ寒い国でもバッハと同じ国のメンデルスゾーンが持つ
ロマンティックさは程良く好きと言える。
ショパンより甘くなくベートーベンほどは重くない。
程よいポピュラリティと複雑さを兼ね備えているのが好ましい。
彼は14歳で初めてバッハの大曲マタイ受難曲を知り
約6年後、若干20歳にして新解釈(新しいアレンジで)による
マタイ受難曲を作者であるバッハの死後約100年後に初演し
以降、大衆のバッハに対する興味と理解を印象付けて
過去の作品を再演するということを定着させた第1人者。
あんな難曲で大曲をエンタメにしたなんて(笑)凄い。
メンデルスゾーンがいなければ今日私たちは
あの美しいマタイ受難曲を聴く事が出来なかったかもしれない。
(しかし早熟の天才はこの後すぐ若干20歳にして亡くなる…)
その時の観衆には後に弁証法でお馴染み(笑)ヘーゲルや
詩人のハイネなども居たそうだ。
そして何とバイオリンソロはパガニーニ。
メンデルスゾーンの有名なニ短調のバイオリンコンチェルトを聴くと
1分半を越えたあたりで、あの有名なロマンティックなフレーズから
打って変わってバッハに影響を受けたであろう
極めて対位法的なフレーズに変化する
短いパッセージがあって、そのドラマティックでクールなアレンジに
時代を超えたポピュラリティを感じてゾクゾクする。
彼らと音楽的共通感覚を、今もって感じられる事に心が動く。
2005年12月23日
久々のピアノレッスン@谷中を振り返る
優れた表現とは、ということから広がって行った
・表象の向こうに見える本質の話
(彼は美しく見える雲を表象に、雲を形成する成分を本質に喩えた)
・客観と主観の話
私がバッハ晩年の未完の大曲『フーガの技法』に
以前から感情を超えた抽象性のようなものを
感じるという話、などから、何故そう感じるかという事になって
『作曲は感情表現を発端にしている』という事を前提に
何故多くのクラシックの作曲家が晩年の作品で対位法的で、
モノフォニーというよりは
ポリフォニックな曲を作るようになるのかという事を
ラフマニノフやショパンなどの後期作品の楽譜を用いて
視覚的にも音の流れを追いつつ説明されていく。
「感情というのは多重構造」であり
例えば最も悲しい現象である「死」についても
場合によっては(闘病生活を長く続けていた場合など)
もしかしたら本人も、家族もどこかで戦いを終えたような
一抹の「安堵感」のような感情を抱いているかもしれないし
悲しみが甘美なこともあるかもしれない。
例えば「幸福」な感情の中にも傍らでは
一抹の不安があったり(「幸福とは現象ではない」と
考えていた。心の在り方に幸福はあって
その状態は「沸き立つような幸福」というよりは
様々な感情を抱きつつもなお、幸福と思えるような
その心の在りようこそが「幸福」という事なんじゃないかと
漠然と考えていた)、感情は必ずや一様ではない、
という事で深く掘り下げて行くと対位法的な表現に到達する、
という事から発展していき
客観と主観は別のもののように思いがちだけれど
実は不可分である、とか、いつの間にか哲学講座へ…(笑)
そんな会話をしていて、ふと、このレッスンの「場」は
ちょっと特殊な在り方をしているように思えてきた。
考えてみたら、この音楽の美を追求している
ピアノ教師は私の詳しい属性を何一つ知らない。
私の年齢、出身地、学歴、既婚か未婚か、
どこに住んでいるか、どんな生い立ちで、家族構成はどんなで
どんな仕事をしていて、、、などと言う事は
一切彼は知らないし、訊かれた事もない。
彼を紹介してもらった存在の方にも一切訊かれた事はない。
これは有りそうで無いある種純粋な関係性のように思う。
唯一、彼が知っている大まかな私に関することは
私が彼から音楽を学びたいと思っていて
彼もそれを受容している、という、ただそれだけ。
属性に関係なく、私は彼から音楽を学んでいる。
例えば私と、このピアノ教師が
音楽的共通感覚の素地を持たないまま世間で
出会ったとしたら果たしてここまで
深く会話を研ぎすまそうと互いに歩み寄っただろうか。
たぶん、しなかっただろうと思う。
そういった、属性を持たない私と
教師とのある意味「抽象的な関係性」における場では
自分という存在が純化され易いために
良くも悪くも自分の本質に近いことが自ずと
露呈される事が多い。逃げ場もないし
自分の素養についても誤魔化しようがない。
考えてみれば勇気の居ることかもしれない。
内田樹「先生はえらい」より引用
『学びには二人の参加者が必要です。
送信するものと受信するものです。そして、
このドラマの主人公はあくまでも「受信者」です。
先生の発信するメッセージを弟子が、「教え」であると
思い込んで受信してしまうというときに学びは成立します。
「教え」として受信されるのであれば、極端な話、
そのメッセージは「あくび」や「しゃっくり」であったって
かまわないのです。「嘘」だってかまわないのです』
さて。ピアノレッスンのほうは、苦手なロマン派代表選手
ショパンのマズルカOP.50-2。
比較的弾き易い曲を選んだつもりだけど
それでも演奏に感情を込めるのが苦手な私、
曲に心が入って行っていない事を、すぐに指摘される。
身体がピアノから(いわゆる腰が引けている状態)離れていて
一体感がなく他人事のように、あなたは弾いていますね、
と言われる。この曲を弾く悦びが感じられない、と、、、
(彼は精神論で語ったりしない合理的な物理学者なのだが)
バッハのポリフォニーに向かうには
他の作曲家の対位法的なポリフォニーの曲を経験する
必要性がある、というのは師の考えなのだけど
難しい、、、まだまだ修行が足りないと思う。
ということで作曲家が何故晩年、対位法的な
ポリフォニックな曲を作るかというと
より深いところまで感情を掘り下げようとすると
必然的にそちらへ向かうという事だった。
多声旋律による表現はより深い豊かな感情を表現出来、
しかもその音楽的表現は感情を超える、というのが
本日の学習内容だった。
そしてここで、改めて私はクラシックが好き、というよりは
バッハの音楽から派生し広がって行った音楽が好き、という事を認識した。
<BODY>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</BODY>
久々にメンデルスゾーンを弾く、
大好きな無言歌の中から最も好きな曲を1曲。
最近のレッスンで弾いているのはショパンのマズルカ。
ショパンは、どこか甘ったるくて軟弱で苦手なイメージ。
嫌いな訳ではない。どちらかというと感覚が近すぎて苦手なのだ。
旋律が持つスラブっぽさは私が生まれた北海道と共通する
何か寒い国の人間が持つ特有の陰鬱なものを感じるので
嫌いじゃないけど敬遠してしまうような想いを抱く。
解りすぎるものとは距離を置きたいのかもしれない。
しかし同じ寒い国でもバッハと同じ国のメンデルスゾーンが持つ
ロマンティックさは程良く好きと言える。
ショパンより甘くなくベートーベンほどは重くない。
程よいポピュラリティと複雑さを兼ね備えているのが好ましい。
彼は14歳で初めてバッハの大曲マタイ受難曲を知り
約6年後、若干20歳にして新解釈(新しいアレンジで)による
マタイ受難曲を作者であるバッハの死後約100年後に初演し
以降、大衆のバッハに対する興味と理解を印象付けて
過去の作品を再演するということを定着させた第1人者。
あんな難曲で大曲をエンタメにしたなんて(笑)凄い。
メンデルスゾーンがいなければ今日私たちは
あの美しいマタイ受難曲を聴く事が出来なかったかもしれない。
(しかし早熟の天才はこの後すぐ若干20歳にして亡くなる…)
その時の観衆には後に弁証法でお馴染み(笑)ヘーゲルや
詩人のハイネなども居たそうだ。
そして何とバイオリンソロはパガニーニ。
メンデルスゾーンの有名なニ短調のバイオリンコンチェルトを聴くと
1分半を越えたあたりで、あの有名なロマンティックなフレーズから
打って変わってバッハに影響を受けたであろう
極めて対位法的なフレーズに変化する
短いパッセージがあって、そのドラマティックでクールなアレンジに
時代を超えたポピュラリティを感じてゾクゾクする。
彼らと音楽的共通感覚を、今もって感じられる事に心が動く。
2005年12月23日
久々のピアノレッスン@谷中を振り返る
優れた表現とは、ということから広がって行った
・表象の向こうに見える本質の話
(彼は美しく見える雲を表象に、雲を形成する成分を本質に喩えた)
・客観と主観の話
私がバッハ晩年の未完の大曲『フーガの技法』に
以前から感情を超えた抽象性のようなものを
感じるという話、などから、何故そう感じるかという事になって
『作曲は感情表現を発端にしている』という事を前提に
何故多くのクラシックの作曲家が晩年の作品で対位法的で、
モノフォニーというよりは
ポリフォニックな曲を作るようになるのかという事を
ラフマニノフやショパンなどの後期作品の楽譜を用いて
視覚的にも音の流れを追いつつ説明されていく。
「感情というのは多重構造」であり
例えば最も悲しい現象である「死」についても
場合によっては(闘病生活を長く続けていた場合など)
もしかしたら本人も、家族もどこかで戦いを終えたような
一抹の「安堵感」のような感情を抱いているかもしれないし
悲しみが甘美なこともあるかもしれない。
例えば「幸福」な感情の中にも傍らでは
一抹の不安があったり(「幸福とは現象ではない」と
考えていた。心の在り方に幸福はあって
その状態は「沸き立つような幸福」というよりは
様々な感情を抱きつつもなお、幸福と思えるような
その心の在りようこそが「幸福」という事なんじゃないかと
漠然と考えていた)、感情は必ずや一様ではない、
という事で深く掘り下げて行くと対位法的な表現に到達する、
という事から発展していき
客観と主観は別のもののように思いがちだけれど
実は不可分である、とか、いつの間にか哲学講座へ…(笑)
そんな会話をしていて、ふと、このレッスンの「場」は
ちょっと特殊な在り方をしているように思えてきた。
考えてみたら、この音楽の美を追求している
ピアノ教師は私の詳しい属性を何一つ知らない。
私の年齢、出身地、学歴、既婚か未婚か、
どこに住んでいるか、どんな生い立ちで、家族構成はどんなで
どんな仕事をしていて、、、などと言う事は
一切彼は知らないし、訊かれた事もない。
彼を紹介してもらった存在の方にも一切訊かれた事はない。
これは有りそうで無いある種純粋な関係性のように思う。
唯一、彼が知っている大まかな私に関することは
私が彼から音楽を学びたいと思っていて
彼もそれを受容している、という、ただそれだけ。
属性に関係なく、私は彼から音楽を学んでいる。
例えば私と、このピアノ教師が
音楽的共通感覚の素地を持たないまま世間で
出会ったとしたら果たしてここまで
深く会話を研ぎすまそうと互いに歩み寄っただろうか。
たぶん、しなかっただろうと思う。
そういった、属性を持たない私と
教師とのある意味「抽象的な関係性」における場では
自分という存在が純化され易いために
良くも悪くも自分の本質に近いことが自ずと
露呈される事が多い。逃げ場もないし
自分の素養についても誤魔化しようがない。
考えてみれば勇気の居ることかもしれない。
内田樹「先生はえらい」より引用
『学びには二人の参加者が必要です。
送信するものと受信するものです。そして、
このドラマの主人公はあくまでも「受信者」です。
先生の発信するメッセージを弟子が、「教え」であると
思い込んで受信してしまうというときに学びは成立します。
「教え」として受信されるのであれば、極端な話、
そのメッセージは「あくび」や「しゃっくり」であったって
かまわないのです。「嘘」だってかまわないのです』
さて。ピアノレッスンのほうは、苦手なロマン派代表選手
ショパンのマズルカOP.50-2。
比較的弾き易い曲を選んだつもりだけど
それでも演奏に感情を込めるのが苦手な私、
曲に心が入って行っていない事を、すぐに指摘される。
身体がピアノから(いわゆる腰が引けている状態)離れていて
一体感がなく他人事のように、あなたは弾いていますね、
と言われる。この曲を弾く悦びが感じられない、と、、、
(彼は精神論で語ったりしない合理的な物理学者なのだが)
バッハのポリフォニーに向かうには
他の作曲家の対位法的なポリフォニーの曲を経験する
必要性がある、というのは師の考えなのだけど
難しい、、、まだまだ修行が足りないと思う。
ということで作曲家が何故晩年、対位法的な
ポリフォニックな曲を作るかというと
より深いところまで感情を掘り下げようとすると
必然的にそちらへ向かうという事だった。
多声旋律による表現はより深い豊かな感情を表現出来、
しかもその音楽的表現は感情を超える、というのが
本日の学習内容だった。
そしてここで、改めて私はクラシックが好き、というよりは
バッハの音楽から派生し広がって行った音楽が好き、という事を認識した。
<BODY>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</BODY>










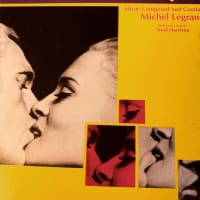


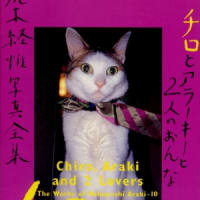





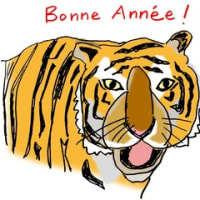
私クラシック、好きなんですよね、詳しくないから、CD等、何を買えばいいのかが分からないだけで。
うちでは、父がモーツァルト&バッハをよくかけていたので、それは少し分かる、という程度.....。
ショパンは私も甘ったるくて苦手な感じデス。
中村ケンゴさんからのblogからきました。
私は最近、音楽は好きです。
音楽が好きかという事は、世界を愛でられるかどうかのバロメーターでもあると思います。
いまは旧いロックや歌謡曲を聴きますが、こんどはクラシックを聴いてみます。
バッハはバイオリン曲が好きです。
歯切れがよくて整理された文章、きれいだと思います。
また読みに行きますね。
器楽か合奏かオーケストラが好きなのかで
決めると、自然に好みの傾向が出来てくるようです。
メンデルスゾーンは「無言歌」が聴き易いです。
有名なのは、ここにも書いたバイオリンコンチェルトの
ニ短調とかチェロソナタでしょうか。
私も食指が動いたものだけ聴いてます。あんまり賑やかなのは苦手(笑)
でも、ショパンって実はロマン派ではなかったという説を最近知って興味が沸いてます。
ようこそおいでくださいました。
コメントありがとうございます。
バッハのバイオリン曲がお好きとの事、
無伴奏のシャコンヌでしょうか。
暗さより静謐さのほうを強く感じる曲です。
日記拝見させて頂きました。強く潔い文章を
お書きになるのですね。またお邪魔させて下さい。
私も最近血中赤ワイン度数高いので(笑)
最新の日記に共感してしまいました。
紡ぎ歌、懐かしー!!
子ども時代ピアノを習っていましたが、
発表会で毎回誰かが紡ぎ歌(って子ども用のアレンジだったのかな)を弾くことになっていて、
紡ぎ歌担当の子を羨ましがった想い出があります。
バッハはヴァイオリン協奏曲が好きです。
特に「2つのヴァイオリンのための…」のヴィヴァーチェ。
なんだか個性の強い男女の会話のようにも聴こえます(私だけか)。
子供の頃のピアノレッスンではサボる事ばかり考えてました、
あの子供用のアレンジも
「子供だからって馬鹿にしてる!」とか
思って(笑)気に入らなかった記憶が…
バッハのヴァイオリンのアンサンブルは
それ以上に聴こえてくるので良いですね。
>「子供だからって馬鹿にしてる!」とか
>思って(笑)気に入らなかった記憶が…
そういう物わかりのいい子ども、好きだあ(笑)
周りにはいなかったなぁ。
自分の弾いた曲を覚えてないってどういうことだろう?
ピアノ、ちっとも身につけようと思わなかった。
歌謡曲しか知らない親に無理矢理やらされ、結局親に辞めさせられました(苦笑)。
今にしたら勿体なさすぎる。
ただ言葉にも音感が要る事はその時に叩き込まれたと信じています。
きっと親のいう事をちゃんとよく聴く素直な子だったんでしょうね…
そういう子ほど習い事でトラウマになる、と
今のピアノ教師に聴かされました!罪深い日本の音楽教育…
私はサボることばかり考えてた割には
初めて人前で弾いた曲憶えていて
今でも弾けたりします(笑)
弾く事だけは嫌いにならなかったみたいですが
音大に行っていたらイヤになっていたかも…!