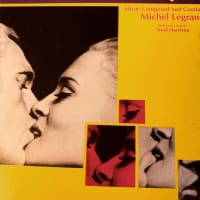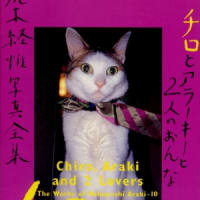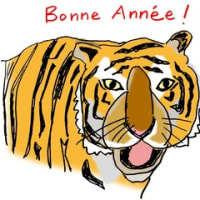前回に引き続き発表会へ向けてのレッスン。
残すところ、あと3週間。
好きこそものの上手なれ…とはよく言ったもので
本当に好きな曲を弾いていると飽くことなく
弾くほどに新たな発見がある。
私はクラシックフリークでもなくて
(バッハの音楽を特別に好きではあるけれど)
当たり前ながらピアニストになりたくてレッスンを
受けているわけじゃない(実際、なれない・笑)
ただ、可能なところまで演奏の技術を知って体得し
演奏を通して音楽の事を知りたいというだけ。
その時に使う楽器がたまたま
ピアノだったということだ。
一見相反しているように思える
ポップスとクラシックだけど
バッハから商業音楽に直結している、ということは
理論として学んだし、映画美学校の
商業音楽理論の学習と並行してクラシックピアノのレッスンの内容は
引き裂かれることなく、私の中で少しずつ統合されつつある。
ピアノ演奏の実力も情熱もモチベーションも
小学生並みのテンションだけど、さして巧くはないので
人前で弾く事にはあまり興味もなく、むしろ苦手。
でも、その事は必要だ、という事だけはわかるので
ともかく今回の発表の機会に参加することにした。
<2年前の記憶>
100名程収容可能な代々木上原のホールでの開催だった。

弾いた曲はバッハのコラールより「アリオーソ」
(「憂鬱と官能を教えた学校」でこの曲の
バークリーメソッド的ポピュラリティについての
著述を知るのは約半年後の事だ)
ピアノ用にアレンジした楽譜は往年の巨匠コルトーが書いたもの。
この曲はグールドとも密接な関わりのある映画
カートヴォネガットジュニア原作の『スローターハウス5』の
テーマ曲でもあった。今から15年程前に
レコードで毎朝聴いていた、深い思い入れのある曲。
実際の現場では弾く直前に喉はからからになり
手や足は震えるし(苦笑)
頭が真っ白になりそうで逃げ出したくなった。
だから、ただ一つの事を考える事にした。
「私が今ここに居る理由」という事だけを考えていた。
私が現在師事している教師と出会ったのは
或る理由からピアノを諦め、手放した事がきっかけだった。
そんな経緯や幾つかの喪失と獲得のことを含め
「今ここに居る理由」のことだけを考えていたら
結果的に演奏に集中することが出来たのか
初めて大勢の人前で弾いた経験はノーミスの演奏となった。
でも後で振り返ると弾いた時の記憶は最初の数秒以降
記憶から抜け落ちていた、まるで自分が
そこに居なかったみたいに(苦笑)
後日、録音されたCDを聴いた時にほんのコンマ数秒間
次の音符に移るのを躊躇していた箇所を聴いて
自分の記憶が抜け落ちていた事を自覚した。
<先日、4月8日のレッスンの備忘録>
桜吹雪舞う谷中の教師宅に心うきうきと到着。
ピアノの音が聴こえる。ああ、前の順番の生徒さんだなと
呼び鈴を押すのを数秒ためらいつつ、押した。
ピアノの音が止まり、幾分の時間差を置いて
師の「どうぞ」という声。
お邪魔しますと入ったらピアノには誰も座ってなかった。
照明も付いてない。何だかいつもと違う様相の室内。
今弾いていたのは誰だろう?と少し訝りつつ
ソファで待機していたら、師が手帳を手に、微笑しつつ
怪訝な顔で「もしかしたら、一週間間違えてない?」
「15日になってますよ」と彼は言った。
、、勘違い、、、
恥ずかしくて自分の顔が赤くなっているのがわかった…
すみません、今日は失礼しますと帰ろうとしたら
師は外出の予定があったようで、1時間は見られないけど
構わない、ということで急遽レッスンを受けることに。
僕が留守の時じゃなくて良かった、と仰った。
彼は2週間後にコンサートを控えている。
さっき聴こえていたのはその練習だったようだ。
生徒のレッスン予定が入っていなかった事を確認すべく
彼は手帳を取りに二階に上がったので
ピアノの前には誰もいなかったのだ。
以前コンサートの前にはレッスンを受け付けないと
もう一人の教師から聴いた事を思い出していた。
邪魔をしてしまった、と後悔していたら
師はレッスン前のいつもの他愛のない雑談を始めた。
そして、いつのまにかその話に引き込まれる。
お題は「春が苦手なのは何故か」(笑)
この方の話は本当に面白い。多弁なのだと思うけれど
そう感じないのは話し方がゆっくりしていて
間も感じられるからだと思う。
以前、あるレクチャーでお会いした俳優の
中島陽典さんとも、これと似たような
お話をしていたなと思いながら聴いていた。
今でこそ肉体と精神のバランスが保てる様になったけれど
常に脳から成る思考(心?)と身体とのバランスに
幼少時から違和感があり、むしろSFなんかに出て来る
「精神生命体」のようなものに子供の頃から惹かれたそうだ(!)
惑星ソラリスみたい、、、
面白いなと思うのは、何故こんなデジタルな人が
クラシックを教えてるの?ってこと。
しかも彼の演奏はとてもロマンティックなのだ。
そして私も今回弾く「甘い想い出」の演奏を
タイトルどおりに「とびきりロマンティックで甘い演奏」に
したいという気持ちが強まる。そういえばこれ
英語にしたらSweetMemoriesだ(笑)
さて。
1週間間違えたにもかかわらず今日のレッスンは
充実したものとなった。
「暗譜にしますか?それとも楽譜を見ますか?」と訊かれ
ただでさえ頭が真っ白になりそうなので暗譜は避ける。
元の楽譜に書き込んでも意味がないから、と
次回コピーしてらっしゃい、と師は言いつつ
「ちょっと待って」と咄嗟に彼は2階に上がり
コピーをしてきてくれて3枚綴りの楽譜を
その場で手際よく用意してくれた
楽譜に曲の構成について書き込みをくれて
私が弾きながら間違えがちだった部分についての留意点と
暗譜が必要な部分と、そしてそのコツを教わる。
こうして師の指摘によっていつも
モヤモヤが晴れて頭がスッキリしてくる。
今回の思いがけないレッスンが濃い内容となったので
彼は帰り際に「今日は間違えて来てくれて
良かったかもしれない」と仰った。
レッスンを通して、いつもこの教師の情熱と愛を感じて帰る。
彼の「愛と情熱」(笑)は個人に向けたものというよりは
もっと大きくて、むしろ個人を飛び越えて
「音楽」にまっすぐ向かっているのを感じる。
それを感じるとこの教師に付いて良かったと思う。
それは教師としての菊地さんに対しても同じ思いを抱く。
今回のユリイカ菊地成孔特集で興味深かったのは林拓身氏が書いた
坂本龍一に対して後藤繁雄が尋ねた質問と対比され
菊地さんに言及していたものだ。質問の内容は
「音楽の恩寵は何?」に対して坂本龍一の答えが
「数学と建築とSEXを一体化させることが出来る」
(後藤繁雄+坂本龍一「skmt」リトルモア,1999年,58頁)
という事で「なんかわからないけど気持ちイイ」と、
「根拠ある快楽を感じる『数学/建築』の部分
(理論的に構築される音の展開の気持ちよさ)」に
二分される、ということだった。
「菊地さんもまた、この音楽の持つ「数学/建築」の
側面に意識的な音楽家の一人である」という事と
坂本vs吉本のE.cafeでの対談の両者の「音楽に対する認識の違い」に触れ、
おそらく菊地さんも、坂本龍一が否定している言葉の部分を主体とした
感情表現をしすぎた「感情表現の道具」として
音楽を考えていないだろう、ということだった。
全ての芸術は確かに感情を発端としているだろうし
何らかの感情表現であるだろうけれど
それが表現者にとって「感情表現の道具」とされていたなら
私はその表現をさして好まないだろう。
感情に先立つ「音楽の為の音楽」とでもいうような表現が
結果的に聴き手に与えた何か、といった
物事のほうに近づき、触れたいと思う。
<BODY>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</BODY>
残すところ、あと3週間。
好きこそものの上手なれ…とはよく言ったもので
本当に好きな曲を弾いていると飽くことなく
弾くほどに新たな発見がある。
私はクラシックフリークでもなくて
(バッハの音楽を特別に好きではあるけれど)
当たり前ながらピアニストになりたくてレッスンを
受けているわけじゃない(実際、なれない・笑)
ただ、可能なところまで演奏の技術を知って体得し
演奏を通して音楽の事を知りたいというだけ。
その時に使う楽器がたまたま
ピアノだったということだ。
一見相反しているように思える
ポップスとクラシックだけど
バッハから商業音楽に直結している、ということは
理論として学んだし、映画美学校の
商業音楽理論の学習と並行してクラシックピアノのレッスンの内容は
引き裂かれることなく、私の中で少しずつ統合されつつある。
ピアノ演奏の実力も情熱もモチベーションも
小学生並みのテンションだけど、さして巧くはないので
人前で弾く事にはあまり興味もなく、むしろ苦手。
でも、その事は必要だ、という事だけはわかるので
ともかく今回の発表の機会に参加することにした。
<2年前の記憶>
100名程収容可能な代々木上原のホールでの開催だった。

弾いた曲はバッハのコラールより「アリオーソ」
(「憂鬱と官能を教えた学校」でこの曲の
バークリーメソッド的ポピュラリティについての
著述を知るのは約半年後の事だ)
ピアノ用にアレンジした楽譜は往年の巨匠コルトーが書いたもの。
この曲はグールドとも密接な関わりのある映画
カートヴォネガットジュニア原作の『スローターハウス5』の
テーマ曲でもあった。今から15年程前に
レコードで毎朝聴いていた、深い思い入れのある曲。
実際の現場では弾く直前に喉はからからになり
手や足は震えるし(苦笑)
頭が真っ白になりそうで逃げ出したくなった。
だから、ただ一つの事を考える事にした。
「私が今ここに居る理由」という事だけを考えていた。
私が現在師事している教師と出会ったのは
或る理由からピアノを諦め、手放した事がきっかけだった。
そんな経緯や幾つかの喪失と獲得のことを含め
「今ここに居る理由」のことだけを考えていたら
結果的に演奏に集中することが出来たのか
初めて大勢の人前で弾いた経験はノーミスの演奏となった。
でも後で振り返ると弾いた時の記憶は最初の数秒以降
記憶から抜け落ちていた、まるで自分が
そこに居なかったみたいに(苦笑)
後日、録音されたCDを聴いた時にほんのコンマ数秒間
次の音符に移るのを躊躇していた箇所を聴いて
自分の記憶が抜け落ちていた事を自覚した。
<先日、4月8日のレッスンの備忘録>
桜吹雪舞う谷中の教師宅に心うきうきと到着。
ピアノの音が聴こえる。ああ、前の順番の生徒さんだなと
呼び鈴を押すのを数秒ためらいつつ、押した。
ピアノの音が止まり、幾分の時間差を置いて
師の「どうぞ」という声。
お邪魔しますと入ったらピアノには誰も座ってなかった。
照明も付いてない。何だかいつもと違う様相の室内。
今弾いていたのは誰だろう?と少し訝りつつ
ソファで待機していたら、師が手帳を手に、微笑しつつ
怪訝な顔で「もしかしたら、一週間間違えてない?」
「15日になってますよ」と彼は言った。
、、勘違い、、、
恥ずかしくて自分の顔が赤くなっているのがわかった…
すみません、今日は失礼しますと帰ろうとしたら
師は外出の予定があったようで、1時間は見られないけど
構わない、ということで急遽レッスンを受けることに。
僕が留守の時じゃなくて良かった、と仰った。
彼は2週間後にコンサートを控えている。
さっき聴こえていたのはその練習だったようだ。
生徒のレッスン予定が入っていなかった事を確認すべく
彼は手帳を取りに二階に上がったので
ピアノの前には誰もいなかったのだ。
以前コンサートの前にはレッスンを受け付けないと
もう一人の教師から聴いた事を思い出していた。
邪魔をしてしまった、と後悔していたら
師はレッスン前のいつもの他愛のない雑談を始めた。
そして、いつのまにかその話に引き込まれる。
お題は「春が苦手なのは何故か」(笑)
この方の話は本当に面白い。多弁なのだと思うけれど
そう感じないのは話し方がゆっくりしていて
間も感じられるからだと思う。
以前、あるレクチャーでお会いした俳優の
中島陽典さんとも、これと似たような
お話をしていたなと思いながら聴いていた。
今でこそ肉体と精神のバランスが保てる様になったけれど
常に脳から成る思考(心?)と身体とのバランスに
幼少時から違和感があり、むしろSFなんかに出て来る
「精神生命体」のようなものに子供の頃から惹かれたそうだ(!)
惑星ソラリスみたい、、、
面白いなと思うのは、何故こんなデジタルな人が
クラシックを教えてるの?ってこと。
しかも彼の演奏はとてもロマンティックなのだ。
そして私も今回弾く「甘い想い出」の演奏を
タイトルどおりに「とびきりロマンティックで甘い演奏」に
したいという気持ちが強まる。そういえばこれ
英語にしたらSweetMemoriesだ(笑)
さて。
1週間間違えたにもかかわらず今日のレッスンは
充実したものとなった。
「暗譜にしますか?それとも楽譜を見ますか?」と訊かれ
ただでさえ頭が真っ白になりそうなので暗譜は避ける。
元の楽譜に書き込んでも意味がないから、と
次回コピーしてらっしゃい、と師は言いつつ
「ちょっと待って」と咄嗟に彼は2階に上がり
コピーをしてきてくれて3枚綴りの楽譜を
その場で手際よく用意してくれた
楽譜に曲の構成について書き込みをくれて
私が弾きながら間違えがちだった部分についての留意点と
暗譜が必要な部分と、そしてそのコツを教わる。
こうして師の指摘によっていつも
モヤモヤが晴れて頭がスッキリしてくる。
今回の思いがけないレッスンが濃い内容となったので
彼は帰り際に「今日は間違えて来てくれて
良かったかもしれない」と仰った。
レッスンを通して、いつもこの教師の情熱と愛を感じて帰る。
彼の「愛と情熱」(笑)は個人に向けたものというよりは
もっと大きくて、むしろ個人を飛び越えて
「音楽」にまっすぐ向かっているのを感じる。
それを感じるとこの教師に付いて良かったと思う。
それは教師としての菊地さんに対しても同じ思いを抱く。
今回のユリイカ菊地成孔特集で興味深かったのは林拓身氏が書いた
坂本龍一に対して後藤繁雄が尋ねた質問と対比され
菊地さんに言及していたものだ。質問の内容は
「音楽の恩寵は何?」に対して坂本龍一の答えが
「数学と建築とSEXを一体化させることが出来る」
(後藤繁雄+坂本龍一「skmt」リトルモア,1999年,58頁)
という事で「なんかわからないけど気持ちイイ」と、
「根拠ある快楽を感じる『数学/建築』の部分
(理論的に構築される音の展開の気持ちよさ)」に
二分される、ということだった。
「菊地さんもまた、この音楽の持つ「数学/建築」の
側面に意識的な音楽家の一人である」という事と
坂本vs吉本のE.cafeでの対談の両者の「音楽に対する認識の違い」に触れ、
おそらく菊地さんも、坂本龍一が否定している言葉の部分を主体とした
感情表現をしすぎた「感情表現の道具」として
音楽を考えていないだろう、ということだった。
全ての芸術は確かに感情を発端としているだろうし
何らかの感情表現であるだろうけれど
それが表現者にとって「感情表現の道具」とされていたなら
私はその表現をさして好まないだろう。
感情に先立つ「音楽の為の音楽」とでもいうような表現が
結果的に聴き手に与えた何か、といった
物事のほうに近づき、触れたいと思う。
<BODY>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</BODY>