
**********************
窓口のおねえさんが、わたしのファイルを取り出す。そこで、偶然に。ファイルの隙間から見えてしまった。すでに書かれて、本来であればわたしが見ることなくQ区に送られるはずだった「主治医の意見書」を。
ちらりと見て、一瞬で、体がぶるぶると怒りで震えた。
移動に助けが必要か、入浴に介助がほしいか、食事の用意や家事に支援が必要かどうかなど、さまざまある支援項目の、ほとんどの欄に、「必要ない」のチェックマークが並んでいたからである。一日たった、一時間。その最低限のヘルパーさんの支援すら、この紙一枚で、受けられなくなるかもしれない。これまで、どれほど苦難を積み重ねて、ここまでやってきたと思っているのか。たった一枚の紙きれで、すべて、粉々にするのか。
さすがに、ムーミン谷の優等生だった女子も、これには激昂した。
「ぜんぜん、何もわかってない!」と。(中略)
わたしは顔を真っ赤にし、六階病棟へ戻った。そこで激務に励むブラックベアーを発見し、
「先生!どうして何も聞かないで勝手に決めるんですか!」
とはじめて、喧嘩腰に啖呵を切った。
すると我が名医は、
「いま忙しい!医学的に正しいことを書いた!本人に聞く必要はない!」(中略)
「N・M・I」開始以来、どうも先生たちは、患者のデイリーライフにおける「難」を、病院内の世界だけで判断している傾向があると感じはじめていた。オアシスに入院し完全に保護されながら何か行動するのにかかる負荷と、オアシスの門の外で行動するのにかかる負荷は、大雑把だが百倍くらい違う。(中略)
「ぐううううううう……………」
我が名医によれば、わたしが異議申し立てする「権利」はないらしい。自分の主治医に向かって、円月殺法あるいは柳生の術を繰り出したくなった。この表現では団塊世代以上にしか意味が通じないな。つまり、ハリー・ポッターの呪いの呪文を一発唱えたくなった。夕食にでたシャケのホイル蒸しをスプーンでめった刺しにし、なんとか憤懣を抑える。
大野更紗 『困ってるひと』より ポプラ社
********************
抜粋部からだけでも判るように、この本はとても柔らかい。
書かれてある内容は、とてつもなく固く、重いのに、、、。
何しろ主人公は現代医学が解決できないと宣告している難病者なのだから。
登場人物や取り組むべき課題に絶妙のネーミングが施され、凄絶な闘病記であるはずのものが、未知のジャングルを踏み進む冒険譚になっている。
それでいて、この本一冊で、現代日本の医療の現状、社会福祉の現状が、一患者の視点から批判しつくされている。
本日のおまけ
大野更紗:本当に困っている人を助けるために
2011年9月11日 ビデオニュース・ドットコム
大野 更紗氏
東日本大震災後に発売された福島県出身の作家大野更紗氏の「困ってるひと」が話題になっている。いわゆる「闘病記」の分野では異例の9刷、11万部を記録。インターネットの連載中から、病気の患者だけでなく、若い学生から高齢者、看護師や介護士、フリーターや障がい者など、幅広い人々の共感を集めている。
大野氏は学部在学中からNGOのビルマ難民の支援活動に携わり、在日ビルマ難民の支援や民主化運動、人権問題に取り組み、在日ビルマ難民のインタビューや現地の難民キャンプ支援、講演会開催、弁護士・国会議員・ジャーナリストやメディアへの働きかけなど多彩な活動を行ってきた。
大学院に進学し、ビルマ難民支援活動を続けていた2008年、タイ・チュラロンコン大学での研究留学中に自己免疫疾患系の難病を発症し、緊急帰国。日本国内で診断がつかずに病院を転々とする、いわゆる「医療難民」となった。その後、「皮膚筋炎」と「筋膜炎脂肪織炎症候群」の病名がつき治療を開始、都内の大学病院での入院を経て、現在は通院しながら治療を続ける。痛み止めの薬が効かず、自宅では「昏睡の合間に執筆し、常に痛みを感じている」状態だという。
難病と闘いながら執筆活動をする大野氏に、震災後の社会的、医療的、経済的弱者が急増する時代の展望や、絶対的な不条理に直面した「困ってるひと」からみた真の援助と自立の可能性、メディアが描く「被災者像」と現実について、評論家の武田徹氏と社会学者の宮台真司と語ってもらった。
自身が「弱者」になって気付いたこと
武田: 大野さんは発病をきっかけに、「自分は難民じゃないかと感じた」と書かれています。闘病生活で見えてきたものについて、あらためてお話いただけますか?
大野: 私は家族と離れて暮らしているので、東京の病院に提出するための分厚い書類を用意しないといけないなど、煩雑なことがたくさんありました。そこで、親しい友人や大学の先生、ビルマで一緒に活動をしてきた仲間など、ありとあらゆる“絆”に頼り、「助けてほしい」というメッセージを発し続けたんです。当然、最初は「かわいそう」「何でもしてあげるよ」とみんなが言ってくれて、私はそれに依存していきました。
しかし、あるときから「何でもしてあげる」と言っていた彼らが「何もしてあげられない」ということに気づき、辛そうな目で私を見るようになり、だんだんと離れていくようになって。絆に頼ることによって、その絆を壊してしまった、という感覚です。そこで自分の社会関係がぷっつりと切れていく、絶対的な孤独感を覚えました。
そのときになって初めて、それまでは自分が「難」の観察者であったのに、「難」の当事者になったことに気づきました。難民を研究していたはずが、今度は自分が日本社会の中で難民化していると気がつく瞬間がやってきた。社会に揺らぎが生じたり、何か不条理が起こったりしたときには、人間は答えや救いがほしくて、自然に家族とか愛とか、ウェットなものに頼りたくなります。けれど、相手は不条理だから、答えも救いもない。そこで、人間が生きていくためには社会の制度やシステムが大切なのだと痛感します。そうして実際に日本の社会保障制度と向き合ってみると、いかにずさんなものかがわかった。日本では戦後から現在にかけて、建前と実体がいかに乖離しているかということを、発見したんです。
武田: 身体が不自由な人に対して要求するには、申請の書類の量があまりにも酷だとか、福祉制度の実体を病気になって実感したと大野さんは書いています。社会調査法の一つに「参与観察」という言葉があります。対象を知るためには観察するだけではなく、参加しなければいけないという意味ですが、参加したとしてもほとんどの場合当事者にはなれない。それが社会調査の限界だと思います。
大野さんは難民研究をする中で、自分は難民の方と同じ気持ちになれているのだと思っていた。しかし、自分が「難民」と形容されるような状態になってみて、それは間違いだったということに気づいたということですね。
大野: 4年間で築き上げてきた理屈や理性が、そこでいったん崩壊しました。援助するという行為は一体どういうことなのか。援助者と被援助者の関係は、善意とか施しで結ばれているように見えますが、それだけでは語れない部分があるということを気づかされました。
宮台: ガダルカナル島での日米の戦闘を描いた映画『シン・レッド・ライン』(テレンス・マリック監督/98年アメリカ)を思い出しました。
作中、アメリカ兵が戦闘で犠牲になる島民たちに感情移入し、そこに残ろうとする。しかし結局、現地の人たちと、それに同情して彼らと生活しようとしている兵隊の間で、時間と空間は交わりません。片方には別に帰るところがあり、片方にはそこにいるしかない人がいる。同じ空間を共有して、同じご飯を食べて生活しているように見えても、同じ時間と空間を生きられていないことの悲劇──当たり前のことですが、僕らはそれを忘れています。自分が決定的な境遇に落とし込まれないと気づかない問題かもしれませんね。
二項対立では捉えられない、グレーゾーンにある“実態”
大野: 私は難病患者になって、身体障がい者手帳が取れないことに愕然としました。なぜか取れないかというと、身体障害者手帳を申請するときに、「関節稼働域が何度」などの規定に照らし合わせて障がいを判断するからです。この「測る」という方法がエビデンスなわけですが、人間のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)とは、本当にそれで判断できるのでしょうか。実際には、私たちの生は不可知なものに満ちていて、自分だけでも判断できないし、外部者だけでも判断できないものだと思います。
今はエビデンスが持っていた権威性が終焉に向かう時代に入ったのかなと思っています。そしてそれは、エビデンスそのものの問題ではなく、エビデンスには不確実性があるという前提をみなが共有していないことが問題なのです。
だからこそ私は経済や制度など、即物的な問題がとても大事だと思っています。例えば、被災者支援をするときにお金の話をすると何となく浅ましいようなイメージを持ちますが、お金の話ほど重要な話はありません。
私は1984年生まれで高度経済成長期もバブル時代も知りませんが、あの時代は相当異常な状態だったと想像しています。おそらく、制度にいかに欠陥や不備があろうとも、何となく流れでやって来ることができた時代だと思う。しかし、今は違う。これからは20年の空白を丁寧に埋める作業をする時代です。一発逆転はできないし、あまり流行らない話なのですが。
宮台: 大野さんのおっしゃることには、社会的なニーズはあります。例えば、若い人たちとイベントをすると判で押したように「これからはお金の時代じゃない、真心の時代だ。だから私はこれからお金を目当てとしないようなNPO活動に邁進します」と言う。実は、僕はそれを聞くたびに彼らに激怒します。それは、大野さんがおっしゃったように「金がなければできないこと」が世の中にはたくさんありすぎるからです。だから、「お金がなければ助けられない問題は、お金を儲けて助けるのだ」と怒鳴るのです。「金儲け主義の後は真心の時代」──こんなクソみたいな二項対立に陥ってしまうのは、彼らが高度経済成長やバブルの異常さをうまく総括できていないからでしょう。
ヨーロッパなどでは70年代末から「良い社会を作るとは、良いことをすると儲かる社会を作ること」という合意事項がある。だからこそ、フィードインタリフ(固定価格買い取り制度)でも、投資家の計算可能性を高めて、投資家が儲けようとすれば再生可能エネルギーに投資するように誘導する。ところが日本では、未だに特措法や特別会計を作り、特殊法人のような公益法人を作り、天下りの座席を作ることによって「金をやるから良いことをやれ」という図式になっている。なおかつ、ソフトバンクの孫正義社長のような人には「あれはビジネスパーソンであり、金儲けのために言っているのだ」と、批判した気になっているバカが多い。お金儲けと社会貢献を対立させる発想が、僕にはまったく理解できません。
大野: お二人はバブルのリアルな体験がありますよね。リアルなバブル体験を経ているか経ていないかで、信条的な部分は大分違う気がするのですが、いかがですか?
宮台: 僕はもうすぐ就活をテーマにした本を出すのですが、その取材で人事担当者に話を聞くと「1986年分水嶺説」が有力だとわかります。彼らは86年以降に生まれた人は「暗い」「ぼうっとしている」「箸にも棒にもかからない」など、いろいろな言い方をしていました。それは僕の仮説でもあるのだけれど、86年以降に生まれた人は、95年のブルセラとかオウム真理教の大ブームのとき、まだ事態が飲み込めない年齢だったし、97年のアジア通貨危機に端を発する日本不況の深刻化のときに、やっと10歳。彼らからすれば、物心がついてから単に社会が暗いんです。それ以前の人は、社会の重要なエポックを経験しているので、「人生いろいろ、社会もいろいろ」という感じで、ある意味ルーズに構えられるところがある。しかし、それよりも下の世代の方々は、社会をうまく相対化して、二項図式に絡め取られないような距離を取ることが難しいのかなと思います。そういう意味で、震災や原発災害の受け止め方も、武田さんや僕の受け止め方と、大野さんやもっと若い世代の受け止め方とは大分違うのではないかと。
大野: 私も、今の若い人が直面している問題はすごく深刻だと思います。彼らは既存のメインストリームのテキストや言葉に対して、違和感を覚えているのだと思う。ツイッターとかSNS、2ちゃんねるが彼らの鬱憤を吸収してしまっている一方、マスメディアは役割を失っていて、魅力的でもなければ、自分たちのことを語ってくれるものでもない。自分より下の年齢の子と話していると、その乖離がどんどん広がっているような感覚を持っていることがわかる。そして、この乖離がこれ以上広がると、前世代との共通感覚が失われてしまうのではないかと思うんです。それをどうしていくかについて、私自身個人的には答えは出ていませんが、しっくり来るような言葉を探していくしかないのかなと考えています。
カイロジジイのHPは
http://www6.ocn.ne.jp/~tokuch/
それと、なんでもブログのランキングというものがあるそうで、ここをクリックするとブログの作者は喜ぶらしい。
にほんブログ村
にほんブログ村












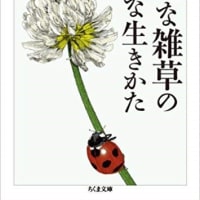







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます