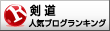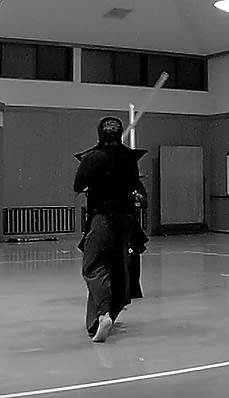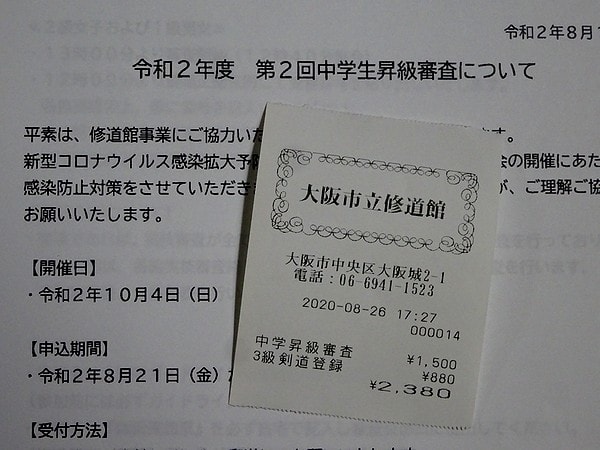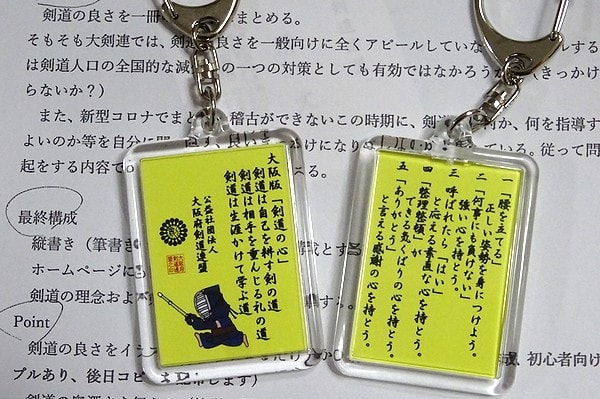大阪、難波の大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪)。
なんば養正会。大人の稽古は19時~20時15分(夜間の場合)まで。
----------------------------------------------------------

なんば養正会のホームページ。(管理人は私です)
http://doujyou.net/youseikai/
----------------------------------------------------------

(稽古風景)
19時から20時15分までの稽古。30名ちょい。
遅れて行ったので地稽古から参加。7人と稽古。

(終わりの全体礼)
【感想・反省点】
動画を見ていると・・・
出頭の面にチャレンジしている場面は増えた。でもまだまだ。
胴打ちの左手を離し過ぎるクセは直りつつある。
しかしながら・・・
自分の剣風にイヤになってくる。
動き過ぎる。すべての場面で過剰反応してしまうのである。
打つ時も思い切った捨て身の打ちではない。受けた時も返そうとするので見苦しい。
相手の打ちを避けるのも見苦しいように思った。
いま自分に一番必要なのは「不動心」かも。
なんば養正会。大人の稽古は19時~20時15分(夜間の場合)まで。
----------------------------------------------------------

なんば養正会のホームページ。(管理人は私です)
http://doujyou.net/youseikai/
----------------------------------------------------------

(稽古風景)
19時から20時15分までの稽古。30名ちょい。
遅れて行ったので地稽古から参加。7人と稽古。

(終わりの全体礼)
【感想・反省点】
動画を見ていると・・・
出頭の面にチャレンジしている場面は増えた。でもまだまだ。
胴打ちの左手を離し過ぎるクセは直りつつある。
しかしながら・・・
自分の剣風にイヤになってくる。
動き過ぎる。すべての場面で過剰反応してしまうのである。
打つ時も思い切った捨て身の打ちではない。受けた時も返そうとするので見苦しい。
相手の打ちを避けるのも見苦しいように思った。
いま自分に一番必要なのは「不動心」かも。