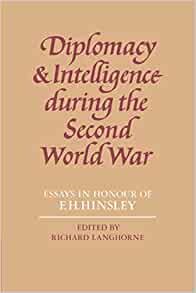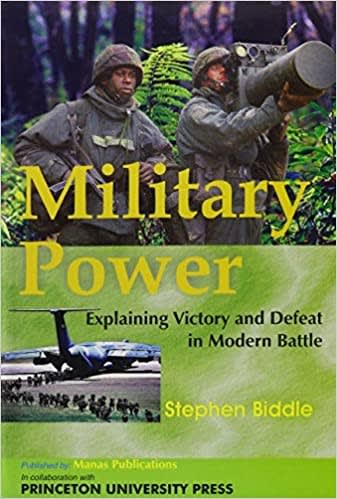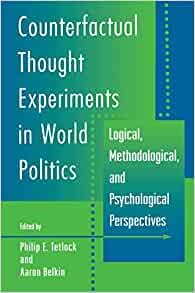現代における戦略研究の「大家」は誰かと尋ねられたら、コリン・グレイ氏(レディング大学)は外せないでしょう。かれは、戦略について、数多くの著書と数えきれないほどの論文やエッセー、記事を書いています。さらに、グレイ氏は学問領域だけにとどまらず、実務でも、レーガン政権の顧問としても活躍しました。かれは戦略の学問と実務の両方に精通した稀有な人材でした。正直に申し上げると、わたしは、グレイ氏の研究には、あまり興味がありませんでした。もちろん、かれの著作や論文を無視したわけではありません。「武器があるから戦争は起こる。だから軍縮は平和を促進する」という「俗説」がありますが、わたしはこれに疑問を抱いていました。そこで『武器は戦争を作り出さない(Weapons Don't Make War)』(カンサス大学出版局、1993年)を訪ねたのです。ここで主張されている、「政治における政策が戦略を規定するのであり、これにより兵器は意味づけられる」との主張には、半分くらい納得したのですが、その反面、テクノロジーの進歩を反映した戦力という物質的要因が政治的意思決定の選択肢を制約する結果、戦争と平和に大きな影響を与えるのではないかと思ったりもしました。また、イギリスの古き良き「ヴィクトリア朝」をほうふつとさせるようなグレイ氏の文章や論述には、違和感を覚えずにはいられませんでした。かれの古典的ともいえる研究スタイルは、簡潔性を重んじる論理実証主義の政治学の研究とは、何か相いれないものがあるように読めてしまったのです。
そうしたわけで、グレイ氏の記念碑的著作である『現代の戦略』(奥山真司訳、中央公論新社、2015年〔原著1999年〕)は、購入済みだったのですが、ぱらぱらと斜め読みしただけで、本棚に眠っていた状態でした。本書は、おそらくエドワード・ルトワック著『戦略論』と並ぶ、戦略研究の必読テキストでしょう。そうした基本書を踏まえずして戦略を研究しているというのは無責任だと思い、キチンと読むことにした次第です。ありがたいことに、奥山真司氏(国際地政学研究所)が、素晴らしい翻訳と解説の仕事をしてくださったおかげで、本書は日本語で読めるとともに理解も進みます。感謝ですね。

グレイ著『現代の戦略』は、分厚い難解な書物のようですが、核心的な主張はシンプルです。すなわち、戦略には普遍的な論理や本質、機能といったものがあり、それはクラウゼヴィッツが約200年前に示したものと変わりがない、ということです。ここで示されている戦略とは「政策の目的のための軍事力の行使と、その行使の脅しに関するもの」です。そして、戦略とは「軍事力と政治的な目的をつなげる『懸け橋』である」という位置づけになります(『現代の戦略』45ページ)。この戦略のロジックは、規模を問わずあらゆる戦争を規定するものであり、また、陸海空そして宇宙やサイバー空間にいたる全ての軍事力を使用する際の基準となるのです。こうしたグレイ氏の学問的・政策的ポジションは、保守的であり、クラウゼヴィッツの擁護者といえるでしょう。かれは、自身を「歴史を深く尊敬している社会科学系の人間」と位置づけ、戦略へのアプローチを「戦略史」と「政策科学」の融合と記しています(前掲書、23ページ)。現在の政治学が歴史学から離れて数量的になる傾向にある中で、こうした歴史に立脚したオーソドックスな戦略研究は、とても価値のあるものではないでしょうか。
『現代の戦略』は、方法論が異なる歴史学と社会科学(政策科学)を取り入れていることがメリットである反面、その方法論があまり定まっておらず、既存の研究への批判が、ややもすると「独善的」になっているようにも読めます。本書の主要な目的は、グレイ氏によれば「あらゆる時代のあらゆる戦略の経験には統一性がある」という仮説を「説明」することです(前掲書、43ページ)。これだけでは「仮説」が何を意味するのか不明瞭ですが、本書を読み進めていくと、歴史研究によくあるように、埋め込まれる暗示的な形で仮説がそれとなく示されています。すなわち、「人間と政治」、「戦争の準備(兵站、軍事組織、訓練、軍事ドクトリン、テクノロジーなど)」、「戦争そのもの(指揮、地理、摩擦、敵など)」が、「戦略パフォーマンス」を定めるということのようです(前掲書、47、53ページ)。ただし、こうした「百科全書的な」仮説は、反証可能性に乏しい「万能理論」に近いため、全ての事例が仮説に合致してしまいそうです。その一方で、かれは「戦略的なアイディア」に内包されている仮説の検証が不可能であるともいっています(前掲書、24ページ)。もし、そうであるならば、われわれはグレイ氏の「理論」が正しいかどうかをどうやって知ることができるのでしょうか。
また、グレイ氏はさまざまな国際関係論の研究成果を退けていますが、その反論の仕方が「雑」であるようです。たとえば、かれは国際関係研究について、以下のようなバッサリと切り捨てるような批判を述べています。「専門分野における深い知識のメリットがどのようなものであれ、とたえば国際関係論の理論についての現代の学術研究…の知識のほとんどは、専門家になろうと思っていない一般の人々にとっては単なる不可解なものでしかあり得ないのだ」(前掲書、196ページ)。こうした指摘は、知る人ぞ知る難解な高等数学を使った定量的な国際関係の理論にあてはまるかもしれませんが、このブログで何度も取り上げているスティーヴン・ウォルト氏の「脅威均衡理論」やジョン・ミアシャイマー氏の「攻撃的リアリズム」といった政策に関連づけられた、日常言語で書かれた研究には該当しないでしょう。
グレイ氏の戦略論の主な特徴は、わたしが読む限りでは、戦略を政策科学と扱っているにもかかわらず、そのアートの側面を重視していること、そして戦略を実践する政治指導者の力量を研究に組み込んでいることにあります。かれ曰く「戦略家という職種に求められる能力の獲得には、多大な努力が必要とされるのだ。国防大学が学生たちに大戦略を教えようとしても、戦略が『術』であるという事実によって、彼らは限界に直面してしまう。これを喩えてみると、芸術学校は技能を教えられるが、それでも能力のあるアーチストとしてどうすれば偉大な存在になれるのかを教えられないのと一緒だ…戦争と戦略において人間が最も重要である…人間の次元は、テクノロジーや計略を克服する可能性を秘めているのだ…もし戦略が正確に理解され、確実な結果を得られることが保証されるような『科学』であったとしても、個人、組織、そして政治的なプレーヤーたちは、『科学的』な戦略知識の応用を失敗させるものなのだ」ということです(前掲書、95、153-154、386ページ)。では、戦争や戦略にたずわる人や組織は、どうすればいいのでしょうか。残念ながら、グレイ氏は具体的な指針を明示しようとはしません。「戦略は実践的な分野だが、戦略理論は行動のための具体的な指針を生み出すことはできないのだ」というのが、かれの1つの答えなのです(前掲書、155ページ)。ここまで人間が戦略で大きな要因となっていると主張するのであれば、せめて戦略を成功させるコツやヒントを示してほしいと思うのは、おそらく、わたしだけではないでしょう。あえて『現代の戦略』に、戦略の行動指針のようなものを見いだすとすれば、政・軍の「統率力」(前掲書、72ページ)といった抽象的な概念と、クラウゼヴィッツが『戦争論』で強調した、摩擦、偶然、不確実性、くわえて情熱、理性といった要因に十分な注意を払うことなのかもしれません。
戦略の全体図を記述的に描き出すという『現代の戦略』で示された研究スタイルは、本書の強みであり、また、弱みでもあるようです。戦略を構成する要因の相互作用を包括的に捉えるという点において、グレイ氏の分析は卓越しています。戦略の以下のたとえは、誰をも納得させるのではないでしょうか。
「戦略には多くの次元があり、それぞれの次元の機能には大小がある。言うなれば、戦略というのはレーシングカーのようなものであり、なかでもエンジンやブレーキ、タイヤ、そしてドライバーがいるのだ。戦略パフォーマンスというのは、他のレーサーたちの意志と能力によって決定されるものであり、戦略の…次元のいずれかで失敗したり不運が起こったりすると、全体的なパフォーマンスが落ちてしまう…二つの世界大戦におけるドイツ軍…は戦闘こそ非常にうまかったが、戦争の遂行という能力は劇的に低かったのだ…『偉大な司令官』がいても、戦場で戦ってくれる兵士がいなければ意味はないし、テクノロジー面で優秀な兵器も、これを使う兵士にとっては戦術レベルにおいて効果があるだけだ」(前掲書、54-55ページ)。
ただし、こうしたアナロジーによる戦略の理解は、その実践において弱点を露呈します。グレイ氏は「戦争は政策のために行われるものであるが、(クラウゼヴィッツの)『戦争論』は政策について書かれているわけではない」と指摘しています(前掲書、164ページ)。そして、かれは『戦争論』に欠けている部分を『現代の戦略』において、継承してしまったようです。グレイ氏に師事した訳者の奥山氏は「訳者あとがき」で、本書をこう位置づけています。「気になるところは…クラウゼヴィッツをやや神格化しているように見られやすい点だ…この本もクラウゼヴィッツの『戦争論』と同じように、あくまでも教育書や哲学書という性格が強く、結果としてクラウゼヴィッツの『注釈書』であると同時に、そのエッセンスを先鋭化させた『現代版』という性格が強い」(前掲書、530ページ)。グレイ氏自身も、このことは自覚しているようで、ケン・ブース氏(アベリストウィス大学)の次の批判を受け入れています。「彼はクラウゼヴィッツの主張と格言が、(グレイ氏の研究において)理性的な議論や判断の代わりにマントラ(真言)として使われることが多いことを指摘している点で正しい」(前掲書、513ページ)。
戦略研究においてクラウゼヴィッツは、国際関係論におけるトゥキュディデスのような存在なのでしょう。ただし、国際関係論はトゥキュディデスを継承しながらも、それを科学的に乗り越えようとしてきました。リアリストたちは、国際政治の諸事象や戦争の原因を探究する際に、トゥキュディデスを参照しながらも、新しい理論を構築してきたのです。E. H. カー氏の「リアリズム」をハンス・モーゲンソー氏が発展的に「古典的リアリズム」として継承し、それをケネス・ウォルツ氏が科学的なネオリアリズムに昇華させました。その後、ネオリアリズムは、ジョン・ミアシャイマー氏によって、「攻撃的リアリズム」という新しい学派を生み出しました。リアリズムは、現在の政治学・国際関係論において、研究プログラムとして定着したといってよいでしょう。国際関係の研究者たちは、リアリズムのコア理論を受け継いだ形で、さまざまな中範囲の理論を打ち出しています。こうした科学的な学問の進展は、われわれの国際関係に対する理解を深めることに貢献しています。
グレイ氏は、現代の卓越した戦略理論家であるのは、誰もが認めるところです。『テキサス国家安全保障レヴュー』誌における、かれを偲ぶラウンドテーブルは、その素晴らしい研究足跡を称えています。ロバート・ジャーヴィス氏は、グレイ氏の研究に対する真摯な姿勢を賞賛していました(奥山氏がご自身のブログでジャーヴィス氏のグレイ氏に対する追悼文を日本語に訳されています)。グレイ氏に代表される戦略研究は、古典や歴史さらには「戦略的センス」を大切にする良い面があります。こうした立ち位置は、歴史家であり戦略家でもあるジョン・ルイス・ギャディス氏(イェール大学)に通じるところがあります。ただし、その代償は、率直にいえば、戦略研究の「科学的な」発展にブレーキをかけていることではないでしょうか。近年の大戦略の研究を包括的にレヴューした書評論文では、確かに戦略研究はその蓄積がなされているものの、この分野の問題として、適切な定義や使うべき方法論がばらばらであり、また、その目的が説明的なのか規範的なのか未分化であるため、研究プログラムとなっていない根本的問題を抱えていることが、アメリカの海軍大学の研究者たちから指摘されています(Thierry Balzacq, Peter Dombrowski, and Simon Reich, "Is Grand Strategy a Research Program?" Security Studies, Vol. 28, No. 1, October 2019, pp. 58-86)。
クラウゼヴィッツが偉大な戦略家であったことには、誰も異論はないでしょう。ただ、「個人崇拝」は科学の世界では慎むべきです。もちろん、グレイ氏は、クラウゼヴィッツを「完全無欠な戦略理論家」とみなしているわけではありません。かれが展開する『戦争論』の「限界や弱点についての議論は、クラウゼヴィッツを弁護するためのものではない」(前掲書、157ページ)ということです。ただし、グレイ氏が戦略理論を総合的なものにしようとするあまり、上述したように、それが万能理論すなわち理論のいずれかの予測がすべての結果に一致してしまうものになりがちであり、時には、トートロジーに陥ってしまっています。たとえば、「不確実性」そのものは、論理的に、反証可能な仮説を生み出しません。なぜならば、将来の出来事には必ず不確実性が伴うからです。さらに、多かれ少なかれ、戦勝は「偶然」の結果、敗戦も「偶然」の結果であれば、これは明らかにトートロジーです。どれだけ優れた理論や研究成果でも、反証可能性がなければ、それは「ドグマ」です。実証科学の観点からすれば、クラウゼヴィッツ『戦争論』に内在する諸仮説の妥当性は、優れて経験的な問題でしょう。そうであるならば、それらを反証可能な仮説に再構築する作業が、戦略研究を前進させる第1歩になります。「戦略は…社会科学」(前掲書、135ページ)であるならば、その理論は標準的な科学的手続きの厳しい検証を受けなければなりません。そうしたプロセスは、社会科学としての戦略研究をより発展させることでしょう。
そうしたわけで、グレイ氏の記念碑的著作である『現代の戦略』(奥山真司訳、中央公論新社、2015年〔原著1999年〕)は、購入済みだったのですが、ぱらぱらと斜め読みしただけで、本棚に眠っていた状態でした。本書は、おそらくエドワード・ルトワック著『戦略論』と並ぶ、戦略研究の必読テキストでしょう。そうした基本書を踏まえずして戦略を研究しているというのは無責任だと思い、キチンと読むことにした次第です。ありがたいことに、奥山真司氏(国際地政学研究所)が、素晴らしい翻訳と解説の仕事をしてくださったおかげで、本書は日本語で読めるとともに理解も進みます。感謝ですね。

グレイ著『現代の戦略』は、分厚い難解な書物のようですが、核心的な主張はシンプルです。すなわち、戦略には普遍的な論理や本質、機能といったものがあり、それはクラウゼヴィッツが約200年前に示したものと変わりがない、ということです。ここで示されている戦略とは「政策の目的のための軍事力の行使と、その行使の脅しに関するもの」です。そして、戦略とは「軍事力と政治的な目的をつなげる『懸け橋』である」という位置づけになります(『現代の戦略』45ページ)。この戦略のロジックは、規模を問わずあらゆる戦争を規定するものであり、また、陸海空そして宇宙やサイバー空間にいたる全ての軍事力を使用する際の基準となるのです。こうしたグレイ氏の学問的・政策的ポジションは、保守的であり、クラウゼヴィッツの擁護者といえるでしょう。かれは、自身を「歴史を深く尊敬している社会科学系の人間」と位置づけ、戦略へのアプローチを「戦略史」と「政策科学」の融合と記しています(前掲書、23ページ)。現在の政治学が歴史学から離れて数量的になる傾向にある中で、こうした歴史に立脚したオーソドックスな戦略研究は、とても価値のあるものではないでしょうか。
『現代の戦略』は、方法論が異なる歴史学と社会科学(政策科学)を取り入れていることがメリットである反面、その方法論があまり定まっておらず、既存の研究への批判が、ややもすると「独善的」になっているようにも読めます。本書の主要な目的は、グレイ氏によれば「あらゆる時代のあらゆる戦略の経験には統一性がある」という仮説を「説明」することです(前掲書、43ページ)。これだけでは「仮説」が何を意味するのか不明瞭ですが、本書を読み進めていくと、歴史研究によくあるように、埋め込まれる暗示的な形で仮説がそれとなく示されています。すなわち、「人間と政治」、「戦争の準備(兵站、軍事組織、訓練、軍事ドクトリン、テクノロジーなど)」、「戦争そのもの(指揮、地理、摩擦、敵など)」が、「戦略パフォーマンス」を定めるということのようです(前掲書、47、53ページ)。ただし、こうした「百科全書的な」仮説は、反証可能性に乏しい「万能理論」に近いため、全ての事例が仮説に合致してしまいそうです。その一方で、かれは「戦略的なアイディア」に内包されている仮説の検証が不可能であるともいっています(前掲書、24ページ)。もし、そうであるならば、われわれはグレイ氏の「理論」が正しいかどうかをどうやって知ることができるのでしょうか。
また、グレイ氏はさまざまな国際関係論の研究成果を退けていますが、その反論の仕方が「雑」であるようです。たとえば、かれは国際関係研究について、以下のようなバッサリと切り捨てるような批判を述べています。「専門分野における深い知識のメリットがどのようなものであれ、とたえば国際関係論の理論についての現代の学術研究…の知識のほとんどは、専門家になろうと思っていない一般の人々にとっては単なる不可解なものでしかあり得ないのだ」(前掲書、196ページ)。こうした指摘は、知る人ぞ知る難解な高等数学を使った定量的な国際関係の理論にあてはまるかもしれませんが、このブログで何度も取り上げているスティーヴン・ウォルト氏の「脅威均衡理論」やジョン・ミアシャイマー氏の「攻撃的リアリズム」といった政策に関連づけられた、日常言語で書かれた研究には該当しないでしょう。
グレイ氏の戦略論の主な特徴は、わたしが読む限りでは、戦略を政策科学と扱っているにもかかわらず、そのアートの側面を重視していること、そして戦略を実践する政治指導者の力量を研究に組み込んでいることにあります。かれ曰く「戦略家という職種に求められる能力の獲得には、多大な努力が必要とされるのだ。国防大学が学生たちに大戦略を教えようとしても、戦略が『術』であるという事実によって、彼らは限界に直面してしまう。これを喩えてみると、芸術学校は技能を教えられるが、それでも能力のあるアーチストとしてどうすれば偉大な存在になれるのかを教えられないのと一緒だ…戦争と戦略において人間が最も重要である…人間の次元は、テクノロジーや計略を克服する可能性を秘めているのだ…もし戦略が正確に理解され、確実な結果を得られることが保証されるような『科学』であったとしても、個人、組織、そして政治的なプレーヤーたちは、『科学的』な戦略知識の応用を失敗させるものなのだ」ということです(前掲書、95、153-154、386ページ)。では、戦争や戦略にたずわる人や組織は、どうすればいいのでしょうか。残念ながら、グレイ氏は具体的な指針を明示しようとはしません。「戦略は実践的な分野だが、戦略理論は行動のための具体的な指針を生み出すことはできないのだ」というのが、かれの1つの答えなのです(前掲書、155ページ)。ここまで人間が戦略で大きな要因となっていると主張するのであれば、せめて戦略を成功させるコツやヒントを示してほしいと思うのは、おそらく、わたしだけではないでしょう。あえて『現代の戦略』に、戦略の行動指針のようなものを見いだすとすれば、政・軍の「統率力」(前掲書、72ページ)といった抽象的な概念と、クラウゼヴィッツが『戦争論』で強調した、摩擦、偶然、不確実性、くわえて情熱、理性といった要因に十分な注意を払うことなのかもしれません。
戦略の全体図を記述的に描き出すという『現代の戦略』で示された研究スタイルは、本書の強みであり、また、弱みでもあるようです。戦略を構成する要因の相互作用を包括的に捉えるという点において、グレイ氏の分析は卓越しています。戦略の以下のたとえは、誰をも納得させるのではないでしょうか。
「戦略には多くの次元があり、それぞれの次元の機能には大小がある。言うなれば、戦略というのはレーシングカーのようなものであり、なかでもエンジンやブレーキ、タイヤ、そしてドライバーがいるのだ。戦略パフォーマンスというのは、他のレーサーたちの意志と能力によって決定されるものであり、戦略の…次元のいずれかで失敗したり不運が起こったりすると、全体的なパフォーマンスが落ちてしまう…二つの世界大戦におけるドイツ軍…は戦闘こそ非常にうまかったが、戦争の遂行という能力は劇的に低かったのだ…『偉大な司令官』がいても、戦場で戦ってくれる兵士がいなければ意味はないし、テクノロジー面で優秀な兵器も、これを使う兵士にとっては戦術レベルにおいて効果があるだけだ」(前掲書、54-55ページ)。
ただし、こうしたアナロジーによる戦略の理解は、その実践において弱点を露呈します。グレイ氏は「戦争は政策のために行われるものであるが、(クラウゼヴィッツの)『戦争論』は政策について書かれているわけではない」と指摘しています(前掲書、164ページ)。そして、かれは『戦争論』に欠けている部分を『現代の戦略』において、継承してしまったようです。グレイ氏に師事した訳者の奥山氏は「訳者あとがき」で、本書をこう位置づけています。「気になるところは…クラウゼヴィッツをやや神格化しているように見られやすい点だ…この本もクラウゼヴィッツの『戦争論』と同じように、あくまでも教育書や哲学書という性格が強く、結果としてクラウゼヴィッツの『注釈書』であると同時に、そのエッセンスを先鋭化させた『現代版』という性格が強い」(前掲書、530ページ)。グレイ氏自身も、このことは自覚しているようで、ケン・ブース氏(アベリストウィス大学)の次の批判を受け入れています。「彼はクラウゼヴィッツの主張と格言が、(グレイ氏の研究において)理性的な議論や判断の代わりにマントラ(真言)として使われることが多いことを指摘している点で正しい」(前掲書、513ページ)。
戦略研究においてクラウゼヴィッツは、国際関係論におけるトゥキュディデスのような存在なのでしょう。ただし、国際関係論はトゥキュディデスを継承しながらも、それを科学的に乗り越えようとしてきました。リアリストたちは、国際政治の諸事象や戦争の原因を探究する際に、トゥキュディデスを参照しながらも、新しい理論を構築してきたのです。E. H. カー氏の「リアリズム」をハンス・モーゲンソー氏が発展的に「古典的リアリズム」として継承し、それをケネス・ウォルツ氏が科学的なネオリアリズムに昇華させました。その後、ネオリアリズムは、ジョン・ミアシャイマー氏によって、「攻撃的リアリズム」という新しい学派を生み出しました。リアリズムは、現在の政治学・国際関係論において、研究プログラムとして定着したといってよいでしょう。国際関係の研究者たちは、リアリズムのコア理論を受け継いだ形で、さまざまな中範囲の理論を打ち出しています。こうした科学的な学問の進展は、われわれの国際関係に対する理解を深めることに貢献しています。
グレイ氏は、現代の卓越した戦略理論家であるのは、誰もが認めるところです。『テキサス国家安全保障レヴュー』誌における、かれを偲ぶラウンドテーブルは、その素晴らしい研究足跡を称えています。ロバート・ジャーヴィス氏は、グレイ氏の研究に対する真摯な姿勢を賞賛していました(奥山氏がご自身のブログでジャーヴィス氏のグレイ氏に対する追悼文を日本語に訳されています)。グレイ氏に代表される戦略研究は、古典や歴史さらには「戦略的センス」を大切にする良い面があります。こうした立ち位置は、歴史家であり戦略家でもあるジョン・ルイス・ギャディス氏(イェール大学)に通じるところがあります。ただし、その代償は、率直にいえば、戦略研究の「科学的な」発展にブレーキをかけていることではないでしょうか。近年の大戦略の研究を包括的にレヴューした書評論文では、確かに戦略研究はその蓄積がなされているものの、この分野の問題として、適切な定義や使うべき方法論がばらばらであり、また、その目的が説明的なのか規範的なのか未分化であるため、研究プログラムとなっていない根本的問題を抱えていることが、アメリカの海軍大学の研究者たちから指摘されています(Thierry Balzacq, Peter Dombrowski, and Simon Reich, "Is Grand Strategy a Research Program?" Security Studies, Vol. 28, No. 1, October 2019, pp. 58-86)。
クラウゼヴィッツが偉大な戦略家であったことには、誰も異論はないでしょう。ただ、「個人崇拝」は科学の世界では慎むべきです。もちろん、グレイ氏は、クラウゼヴィッツを「完全無欠な戦略理論家」とみなしているわけではありません。かれが展開する『戦争論』の「限界や弱点についての議論は、クラウゼヴィッツを弁護するためのものではない」(前掲書、157ページ)ということです。ただし、グレイ氏が戦略理論を総合的なものにしようとするあまり、上述したように、それが万能理論すなわち理論のいずれかの予測がすべての結果に一致してしまうものになりがちであり、時には、トートロジーに陥ってしまっています。たとえば、「不確実性」そのものは、論理的に、反証可能な仮説を生み出しません。なぜならば、将来の出来事には必ず不確実性が伴うからです。さらに、多かれ少なかれ、戦勝は「偶然」の結果、敗戦も「偶然」の結果であれば、これは明らかにトートロジーです。どれだけ優れた理論や研究成果でも、反証可能性がなければ、それは「ドグマ」です。実証科学の観点からすれば、クラウゼヴィッツ『戦争論』に内在する諸仮説の妥当性は、優れて経験的な問題でしょう。そうであるならば、それらを反証可能な仮説に再構築する作業が、戦略研究を前進させる第1歩になります。「戦略は…社会科学」(前掲書、135ページ)であるならば、その理論は標準的な科学的手続きの厳しい検証を受けなければなりません。そうしたプロセスは、社会科学としての戦略研究をより発展させることでしょう。