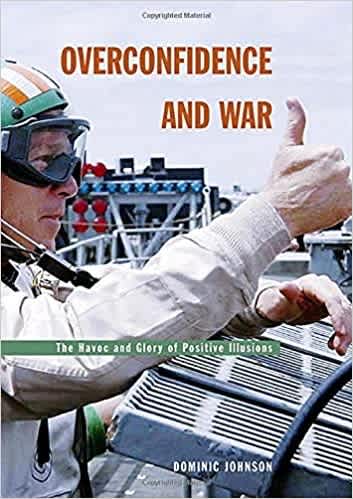「宥和政策(アピーズメント)」は、国際政治でしばしば見過ごされる、国家の対外政策の選択肢の1つです。宥和政策とは、脅威の源泉となっている国家に譲歩をして、対立を和らげようとするものです。これとは対照的な政策が「抑止」です。抑止とは一般的に、敵対行動のコストが利得を上回ることを現状維持への挑戦国に(脅しにより)伝えることで、そうした行動を未然に防ぐ政策です。国家の安全保障戦略としての宥和は、抑止に比べて、あまり評判がよくないようです。なぜなら、宥和は敵対国に「弱み」をみせることにほかならず、抑止をもろくするだけでなく、付け入るスキを与えかねないからです。このことをジョン・ミアシャイマー氏は、端的にこう述べています。
「アピーズメントは…非現実的で危険な戦略となる。危険な敵国を優しく柔和的な国に変えることなどできないし、平和を愛する国にするなどはさらにあり得ない…アピーズメントをした国は、他国に譲歩したことにより『弱い国だ』と周囲に思われがちになる。そうした国は、バランス・オブ・パワーを維持する意思がないことを周囲に示してしまうことになる。よって、アピーズメントを受けた強国が、さらに譲歩を引き出そうとしてくるのは当然だ…アピーズメント(宥和政策)は、危険な敵国をますます危険にする戦略なのである」(J.ミアシャイマー、奥山真司訳『大国政治の悲劇』五月書房、2007年、220-221ページ)。
宥和政策は、1930年代にヒトラー率いるナチス・ドイツに対してイギリスが行いましたが、これはかれのヨーロッパ支配の野望を助長させただけであり、大失敗だったとみなされています。とりわけ1938年の「ミュンヘン会談」では、イギリスのチェンバレン首相は、ヒトラーの要求に応じて、チェコスロバキアのズデーデン地方をかれに与えてしまいました。ヒトラーはこの宥和政策に満足することなく、さらなる侵略を行いました。かれはチェコスロバキア全土を征服するとともに、ポーランドに侵攻したのです。こうして「ミュンヘン」は、国際政治において、悪名高い「アナロジー」となり、第二次世界大戦後の多くの政策決定者たちにとって、「ミュンヘンの再来はごめんだ(ノー・モア・ミュンヘン)」が合言葉になりました。
このように宥和政策には、悪い印象が付きまとうのですが、実は、この外交術は国家にとって実際の政策の選択肢の1つとして、国際政治で実践されてきたのも事実です。アメリカ外交の賢人とうたわれたジョージ・ケナン氏は、「近代史において、おそらく、ミュンヘンのエピソードほど、誤解を与えるものはなかったと思う。このことは多くの人々に、どんな状況であれ、いかなる政治的便宜も図ってはいけないという考えを与えてしまった。もちろん、これは致命的に不幸な結論だ」と喝破しています(quoted in Yuen Foong Khong, Analogies at War: Korea, Dien Bien Phu, and the Vietnam Decision of 1965, Princeton University Press, 1992, p. 174)。こうした毀誉褒貶のある宥和政策をバランスよく体系的に再検討した研究が、スティーヴン・ロック氏(ヴァサー大学)による『国際政治における宥和』(ケンタッキー大学出版局、2000年)です。かれは、宥和政策は必ず失敗すると前もって決まっているわけではなく、時には、国家間の対立を緩和する有効な外交術となりうると主張しています。
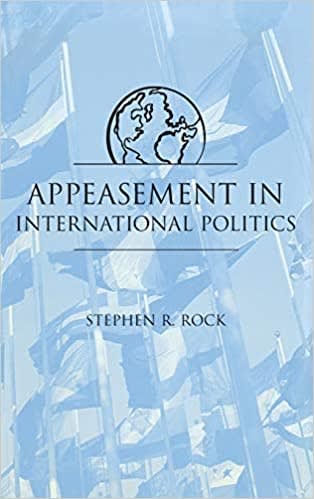
ロック氏は、宥和を「対立と不和の原因を取り除くことにより、敵国との緊張を緩和する政策」(同上書、12ページ)と広く定義しています。宥和をする国家がとる外交戦略は、敵国に何らかの妥協することであり、そのことにより当該国の行動を変化させようとするのが狙いです。そしてかれは、宥和政策が実行された5つの事例を詳細に検討します。それらは、①1896-1903年におけるイギリスのアメリカに対する宥和、②1936-1939年におけるイギリスのドイツに対する宥和、③1941-1945年における英米のソ連に対する宥和、④1989-1990年におけるアメリカのイラクに対する宥和、⑤1988-1994年におけるアメリカの北朝鮮に対する宥和、です。これらの事例分析の結果、ロック氏は、①、③、⑤では宥和政策が成功した一方で、②、④では、宥和政策が失敗したと結論づけています。
①において、イギリスはアメリカの高圧的な姿勢に対して、モンロードクトリンを受け入れてベネズエラの国境問題で譲歩し、アラスカの境界線の要求を受諾するとともに、クレイトン・ブルワー条約の破棄に応じました。その結果、イギリスとアメリカの関係は改善されたのです。③も宥和の成功例とされています。アメリカとイギリスは、ソ連が単独でドイツと講和することを防ぎ、対日参戦を行なわせ、国際連合に加入させることを狙っていました。スターリンの影響圏拡大の野心を拒否してしまうと、上記の目的は達成できなくなるのではないかと、両国の指導者は恐れていました。そうならないようアメリカとイギリスは、ソ連が東ヨーロッパに勢力を拡張するのを容認したのです。第二次世界大戦後、アメリカとイギリスはソ連と冷戦で対立することになりましたが、戦時中の宥和政策の目的は達成されました。④において、アメリカは韓国から戦術核兵器をすべて撤去するとともに、北朝鮮に軽水炉原発と重油を供与する譲歩を行いました。こうしたアメリカの「アメ」を与える政策は、「枠組み合意」として結実し、北朝鮮から核兵器開発の「凍結」を引き出したと、同書では肯定的に評価されています。
②の宥和の失敗については、あまり多くを語る必要はないでしょう。ただ、この事例研究で興味深いのは、ロック氏が英仏の対独宥和について、以下のように分析していることです。
「ヒトラーは…英仏の妥協を優柔不断や弱さの明確な現れとみなさなかった。十分に驚くべきことであるが、かれにとって、ミュンヘン会談は苦い外交的敗北だった」(同上書、50ページ)。
どういうことでしょうか。ヒトラーはチェコスロバキアを戦争によって征服することをもくろんでいたところ、イギリスとフランスが譲歩をしてきたので、取引を成立させざるを得なかった。かれにとって、ミュンヘン会談の結果は本意ではなく、自分自身の指導者としての資質を疑うことにつながった。このことはヒトラーにとって「トラウマ」となり、かれがポーランド危機に際して恐れたことは、イギリスとフランスが軍事介入してくることではなく、拒否できないような合意を持ちかけてくることであった。つまり、ナチス・ドイツはミュンヘン宥和によってますます危険になったのではなく、元から十分に危険だったのです。したがって、この事例の教訓は、「ナチス・ドイツのような戦争を求める国家は、宥和することができない。なぜならば、(譲歩による)誘引は、たとえ受け入れられたとしても、そうした国家が目的(すなわち戦争、引用者)を実行するのを遅らせるにすぎないからだ」(同上書、157ページ)ということになります。
④において、アメリカはサダム・フセインが君臨するイラクを宥和することに失敗しました。ブッシュ政権は、イラン・イラク戦争が終わったあとも、バクダッドと緊密な関係を維持しようとしました。そうすることで、アメリカはイラクの行動が好ましい方向に進むことを期待したのです。湾岸危機の際、イラクが軍事動員をかけた時も、それはクウェートから領土と経済の譲歩を引き出すことを狙った、ブラフによる脅しだとアメリカはみていました。しかし、イラクの威嚇は本物であり、隣国クウェートに実際に軍事侵攻しました。なお、アメリカの駐イラク大使が、イラクの指導者に、アメリカはアラブ内の紛争に関して選択肢をもっていないと語ったことは、イラクに侵略のゴーサインと受け止められたと、後に批判されています。
ロック氏は、これらの事例研究から、宥和政策の理論を構築しています。かれによれば、宥和政策の成否は、敵国の「性格」や譲歩による誘引の性質などによります。宥和の対象国が安全保障上の不安を抱えている場合、「再保障」の役割を果たす譲歩が有効に働くと、ロック氏は主張します。これを例証する事例が、イギリスのアメリカに対する宥和政策です。他方、国家が戦争を志向している場合、宥和は効きません。ナチス・ドイツがそうです。また、宥和政策が成功する必要条件は、誘引が敵国の必要性や要求に見合うことだと、かれは主張します。たとえば、アメリカとイギリスの対ソ宥和は、スターリンの領土的野心をある程度は満たすものだったので、うまくいきました。これに対して、アメリカのイラクに対する宥和政策が失敗したのは、譲歩が不十分だったということになるようです(アメリカがイラクに大規模な経済援助を与えれば、イラクのクウェート侵略は防げたのだろうかという、興味深い「反実仮想」が残ります…)。
ロック氏の宥和政策の研究は、外交における譲歩の有用性を再考する意義深いものだと思います。学術研究の1つの価値は、先行研究の隙間を埋めることにあります。国際政治において汚名を着せられた宥和政策について、その成否を事例研究により理論化したことは、高く評価されてよいでしょう。その一方で、『国際政治における宥和』に問題がないわけではありません。第1に、宥和の対象国の類型化は分析的に有用かもしれませんが、やや恣意的であるとともに、実際には、どのようにして敵国の「性格」や「意図」を知ることができるのでしょうか。歴史の後知恵を使えば、ヒトラーは「例外」もしくは「外れ値」のような存在であり、宥和することは不可能だったと結論づけられるかもしれませんが、当事者だったチェンバレン首相は、どうすれば、そうした結論にたどり着けたでしょうか。ロック氏は、「政策決定者のための教訓」として「敵を知ること。これは目下のところ、最も重要な教訓だ」(同上書、169ページ)と指摘していますが、不確実性の高い国際政治の世界では、これは極めて難しいです。
第2に、事例のコード化の問題が指摘できます。アメリカのクリントン政権の北朝鮮に対する宥和政策は、「成功」とカテゴライズされていますが、はたしてそうでしょうか。北朝鮮は、「枠組み合意」で核兵器開発を凍結したはずだったにもかかわらず、2002年に、米朝協議において、ウラン濃縮施設建設計画を含む核兵器開発を継続していたことを認めました。アメリカの北朝鮮への宥和政策の最大の目的であった「核兵器開発の凍結」は、実は、達成されていなかったのです。こうした北朝鮮の「裏切り」行為は、『国際政治における宥和』が刊行された後に発覚したので、この事実でもって同書を批判するのはフェアーではないかもしれません。しかしながら、北朝鮮がアメリカから「アメ(軽水炉原発・重油)」をもらいながら、ひそかに核兵器開発を存続させることは、十分に予測できたはずです。なぜならば、それが北朝鮮にとって、一挙両得で最も利益になるからです。
手前味噌で恐縮ですが、わたしは、北朝鮮が「枠組み合意」を結んだにもかかわらず、核開発を継続するであろうことを指摘していました。拙稿「対北朝鮮の理論的分析—日本の安全保障政策へのインプリケーションー」『新防衛論集(現国際安全保障)』第27巻第2号(1999年9月)において、米朝のペイオフ構造は、ゲーム理論でいう「囚人のジレンマ」であれば、北朝鮮は「裏切り行為(核開発の継続)」にインセンティブを持つのみならず、「デッド・ロック」の可能性さえあり、そうであれば北朝鮮は核兵器開発を放棄しないだろうと予測しました。
ロック氏は、事例研究から宥和に関して13の命題を導出しています。ここですべての命題を吟味することは、スペースの都合でできませんが、それらのロジックは概して、宥和する対象国は、「安全保障追求アクター(security seeker)」とか「強欲国家(greedy state)」いったようにカテゴライズすることができ、また、それぞれの性質を持つ国家の要求を満たすことが重要であるとの想定が根底にあるように読めました。もちろん、かれは宥和による譲歩が敵対国によって収奪されうることも十分に理解しており、こうした過ちを避ける方法にも言及しています。たとえば、対象国が強欲により動機づけられていればいるほど、宥和が弱さや優柔不断の兆候と解釈される蓋然性は高まるとの命題を示しています。確かに、国家の「性格分類」は、宥和理論の構築において意味のあることでしょうが、理論的な根本問題として、そもそも国家は上記のように分類できるものであるのか(言い換えれば、国家は、カテゴリーに応じた固有で不変の選好を持つアクターなのか)、政策立案に際しては、仮に分類できるとして、宥和する側が、どのようにすれば敵対国の「真の性質」を把握できるのか、ということでしょう。さらには、敵対国が安全保障追求アクターだと認識して譲歩したところ、実は、強欲国家だったことが判明して、譲歩は収奪されるばかりであり、戦争への動機を捨てさせることにつながらなかったとしたら、こうした対外政策は悲劇的な失敗になります。
なお、「エンゲージメント(関与政策)」は、宥和の1つの形態です。アメリカのクリントン政権は、台頭する中国に対して、「エンゲージメント」で臨みました。その基本的な想定は、中国を国際秩序に引き込めば、同国は「責任ある利害関係者」となり、現行ルールに基づき行動するようになるだろうという期待です。世界の国際政治学界でも、中国は「現状維持勢力」であるという言説が有力であり、その平和的台頭を疑う対中封じ込め論は少数派でした。中国が現状維持の安全保障追求者であるならば、宥和理論で示されているように、譲歩をすれば「食欲が満たされて」おとなしくなるはずでした。はたして、こうした宥和理論から導かれた対中政策は、うまくいったといえるでしょうか。少なくとも、(攻撃的)リアリストの答えは、「ノー」です。アメリカのトランプ政権も、2018年、対中エンゲージメントは終わったと示唆しました。一般的で雑駁なむすびになりますが、宥和政策は敵対国にパワーを明け渡す危険がある以上、国際政治のバランス・オブ・パワー原則に反するので、衰退国家が自らの脆弱性ゆえに攻撃的行動にでている場合は「再保障(安心供与」としての効果が見込めるかもしれませんが、台頭する野心的な現実打破国への適用は控えるべきだと思います。
「アピーズメントは…非現実的で危険な戦略となる。危険な敵国を優しく柔和的な国に変えることなどできないし、平和を愛する国にするなどはさらにあり得ない…アピーズメントをした国は、他国に譲歩したことにより『弱い国だ』と周囲に思われがちになる。そうした国は、バランス・オブ・パワーを維持する意思がないことを周囲に示してしまうことになる。よって、アピーズメントを受けた強国が、さらに譲歩を引き出そうとしてくるのは当然だ…アピーズメント(宥和政策)は、危険な敵国をますます危険にする戦略なのである」(J.ミアシャイマー、奥山真司訳『大国政治の悲劇』五月書房、2007年、220-221ページ)。
宥和政策は、1930年代にヒトラー率いるナチス・ドイツに対してイギリスが行いましたが、これはかれのヨーロッパ支配の野望を助長させただけであり、大失敗だったとみなされています。とりわけ1938年の「ミュンヘン会談」では、イギリスのチェンバレン首相は、ヒトラーの要求に応じて、チェコスロバキアのズデーデン地方をかれに与えてしまいました。ヒトラーはこの宥和政策に満足することなく、さらなる侵略を行いました。かれはチェコスロバキア全土を征服するとともに、ポーランドに侵攻したのです。こうして「ミュンヘン」は、国際政治において、悪名高い「アナロジー」となり、第二次世界大戦後の多くの政策決定者たちにとって、「ミュンヘンの再来はごめんだ(ノー・モア・ミュンヘン)」が合言葉になりました。
このように宥和政策には、悪い印象が付きまとうのですが、実は、この外交術は国家にとって実際の政策の選択肢の1つとして、国際政治で実践されてきたのも事実です。アメリカ外交の賢人とうたわれたジョージ・ケナン氏は、「近代史において、おそらく、ミュンヘンのエピソードほど、誤解を与えるものはなかったと思う。このことは多くの人々に、どんな状況であれ、いかなる政治的便宜も図ってはいけないという考えを与えてしまった。もちろん、これは致命的に不幸な結論だ」と喝破しています(quoted in Yuen Foong Khong, Analogies at War: Korea, Dien Bien Phu, and the Vietnam Decision of 1965, Princeton University Press, 1992, p. 174)。こうした毀誉褒貶のある宥和政策をバランスよく体系的に再検討した研究が、スティーヴン・ロック氏(ヴァサー大学)による『国際政治における宥和』(ケンタッキー大学出版局、2000年)です。かれは、宥和政策は必ず失敗すると前もって決まっているわけではなく、時には、国家間の対立を緩和する有効な外交術となりうると主張しています。
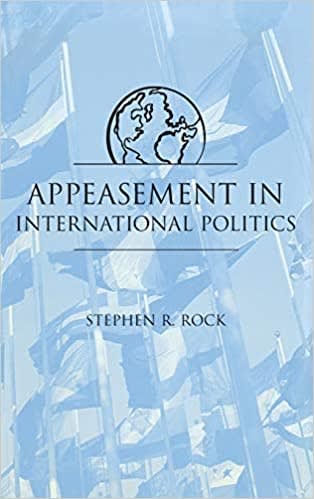
ロック氏は、宥和を「対立と不和の原因を取り除くことにより、敵国との緊張を緩和する政策」(同上書、12ページ)と広く定義しています。宥和をする国家がとる外交戦略は、敵国に何らかの妥協することであり、そのことにより当該国の行動を変化させようとするのが狙いです。そしてかれは、宥和政策が実行された5つの事例を詳細に検討します。それらは、①1896-1903年におけるイギリスのアメリカに対する宥和、②1936-1939年におけるイギリスのドイツに対する宥和、③1941-1945年における英米のソ連に対する宥和、④1989-1990年におけるアメリカのイラクに対する宥和、⑤1988-1994年におけるアメリカの北朝鮮に対する宥和、です。これらの事例分析の結果、ロック氏は、①、③、⑤では宥和政策が成功した一方で、②、④では、宥和政策が失敗したと結論づけています。
①において、イギリスはアメリカの高圧的な姿勢に対して、モンロードクトリンを受け入れてベネズエラの国境問題で譲歩し、アラスカの境界線の要求を受諾するとともに、クレイトン・ブルワー条約の破棄に応じました。その結果、イギリスとアメリカの関係は改善されたのです。③も宥和の成功例とされています。アメリカとイギリスは、ソ連が単独でドイツと講和することを防ぎ、対日参戦を行なわせ、国際連合に加入させることを狙っていました。スターリンの影響圏拡大の野心を拒否してしまうと、上記の目的は達成できなくなるのではないかと、両国の指導者は恐れていました。そうならないようアメリカとイギリスは、ソ連が東ヨーロッパに勢力を拡張するのを容認したのです。第二次世界大戦後、アメリカとイギリスはソ連と冷戦で対立することになりましたが、戦時中の宥和政策の目的は達成されました。④において、アメリカは韓国から戦術核兵器をすべて撤去するとともに、北朝鮮に軽水炉原発と重油を供与する譲歩を行いました。こうしたアメリカの「アメ」を与える政策は、「枠組み合意」として結実し、北朝鮮から核兵器開発の「凍結」を引き出したと、同書では肯定的に評価されています。
②の宥和の失敗については、あまり多くを語る必要はないでしょう。ただ、この事例研究で興味深いのは、ロック氏が英仏の対独宥和について、以下のように分析していることです。
「ヒトラーは…英仏の妥協を優柔不断や弱さの明確な現れとみなさなかった。十分に驚くべきことであるが、かれにとって、ミュンヘン会談は苦い外交的敗北だった」(同上書、50ページ)。
どういうことでしょうか。ヒトラーはチェコスロバキアを戦争によって征服することをもくろんでいたところ、イギリスとフランスが譲歩をしてきたので、取引を成立させざるを得なかった。かれにとって、ミュンヘン会談の結果は本意ではなく、自分自身の指導者としての資質を疑うことにつながった。このことはヒトラーにとって「トラウマ」となり、かれがポーランド危機に際して恐れたことは、イギリスとフランスが軍事介入してくることではなく、拒否できないような合意を持ちかけてくることであった。つまり、ナチス・ドイツはミュンヘン宥和によってますます危険になったのではなく、元から十分に危険だったのです。したがって、この事例の教訓は、「ナチス・ドイツのような戦争を求める国家は、宥和することができない。なぜならば、(譲歩による)誘引は、たとえ受け入れられたとしても、そうした国家が目的(すなわち戦争、引用者)を実行するのを遅らせるにすぎないからだ」(同上書、157ページ)ということになります。
④において、アメリカはサダム・フセインが君臨するイラクを宥和することに失敗しました。ブッシュ政権は、イラン・イラク戦争が終わったあとも、バクダッドと緊密な関係を維持しようとしました。そうすることで、アメリカはイラクの行動が好ましい方向に進むことを期待したのです。湾岸危機の際、イラクが軍事動員をかけた時も、それはクウェートから領土と経済の譲歩を引き出すことを狙った、ブラフによる脅しだとアメリカはみていました。しかし、イラクの威嚇は本物であり、隣国クウェートに実際に軍事侵攻しました。なお、アメリカの駐イラク大使が、イラクの指導者に、アメリカはアラブ内の紛争に関して選択肢をもっていないと語ったことは、イラクに侵略のゴーサインと受け止められたと、後に批判されています。
ロック氏は、これらの事例研究から、宥和政策の理論を構築しています。かれによれば、宥和政策の成否は、敵国の「性格」や譲歩による誘引の性質などによります。宥和の対象国が安全保障上の不安を抱えている場合、「再保障」の役割を果たす譲歩が有効に働くと、ロック氏は主張します。これを例証する事例が、イギリスのアメリカに対する宥和政策です。他方、国家が戦争を志向している場合、宥和は効きません。ナチス・ドイツがそうです。また、宥和政策が成功する必要条件は、誘引が敵国の必要性や要求に見合うことだと、かれは主張します。たとえば、アメリカとイギリスの対ソ宥和は、スターリンの領土的野心をある程度は満たすものだったので、うまくいきました。これに対して、アメリカのイラクに対する宥和政策が失敗したのは、譲歩が不十分だったということになるようです(アメリカがイラクに大規模な経済援助を与えれば、イラクのクウェート侵略は防げたのだろうかという、興味深い「反実仮想」が残ります…)。
ロック氏の宥和政策の研究は、外交における譲歩の有用性を再考する意義深いものだと思います。学術研究の1つの価値は、先行研究の隙間を埋めることにあります。国際政治において汚名を着せられた宥和政策について、その成否を事例研究により理論化したことは、高く評価されてよいでしょう。その一方で、『国際政治における宥和』に問題がないわけではありません。第1に、宥和の対象国の類型化は分析的に有用かもしれませんが、やや恣意的であるとともに、実際には、どのようにして敵国の「性格」や「意図」を知ることができるのでしょうか。歴史の後知恵を使えば、ヒトラーは「例外」もしくは「外れ値」のような存在であり、宥和することは不可能だったと結論づけられるかもしれませんが、当事者だったチェンバレン首相は、どうすれば、そうした結論にたどり着けたでしょうか。ロック氏は、「政策決定者のための教訓」として「敵を知ること。これは目下のところ、最も重要な教訓だ」(同上書、169ページ)と指摘していますが、不確実性の高い国際政治の世界では、これは極めて難しいです。
第2に、事例のコード化の問題が指摘できます。アメリカのクリントン政権の北朝鮮に対する宥和政策は、「成功」とカテゴライズされていますが、はたしてそうでしょうか。北朝鮮は、「枠組み合意」で核兵器開発を凍結したはずだったにもかかわらず、2002年に、米朝協議において、ウラン濃縮施設建設計画を含む核兵器開発を継続していたことを認めました。アメリカの北朝鮮への宥和政策の最大の目的であった「核兵器開発の凍結」は、実は、達成されていなかったのです。こうした北朝鮮の「裏切り」行為は、『国際政治における宥和』が刊行された後に発覚したので、この事実でもって同書を批判するのはフェアーではないかもしれません。しかしながら、北朝鮮がアメリカから「アメ(軽水炉原発・重油)」をもらいながら、ひそかに核兵器開発を存続させることは、十分に予測できたはずです。なぜならば、それが北朝鮮にとって、一挙両得で最も利益になるからです。
手前味噌で恐縮ですが、わたしは、北朝鮮が「枠組み合意」を結んだにもかかわらず、核開発を継続するであろうことを指摘していました。拙稿「対北朝鮮の理論的分析—日本の安全保障政策へのインプリケーションー」『新防衛論集(現国際安全保障)』第27巻第2号(1999年9月)において、米朝のペイオフ構造は、ゲーム理論でいう「囚人のジレンマ」であれば、北朝鮮は「裏切り行為(核開発の継続)」にインセンティブを持つのみならず、「デッド・ロック」の可能性さえあり、そうであれば北朝鮮は核兵器開発を放棄しないだろうと予測しました。
ロック氏は、事例研究から宥和に関して13の命題を導出しています。ここですべての命題を吟味することは、スペースの都合でできませんが、それらのロジックは概して、宥和する対象国は、「安全保障追求アクター(security seeker)」とか「強欲国家(greedy state)」いったようにカテゴライズすることができ、また、それぞれの性質を持つ国家の要求を満たすことが重要であるとの想定が根底にあるように読めました。もちろん、かれは宥和による譲歩が敵対国によって収奪されうることも十分に理解しており、こうした過ちを避ける方法にも言及しています。たとえば、対象国が強欲により動機づけられていればいるほど、宥和が弱さや優柔不断の兆候と解釈される蓋然性は高まるとの命題を示しています。確かに、国家の「性格分類」は、宥和理論の構築において意味のあることでしょうが、理論的な根本問題として、そもそも国家は上記のように分類できるものであるのか(言い換えれば、国家は、カテゴリーに応じた固有で不変の選好を持つアクターなのか)、政策立案に際しては、仮に分類できるとして、宥和する側が、どのようにすれば敵対国の「真の性質」を把握できるのか、ということでしょう。さらには、敵対国が安全保障追求アクターだと認識して譲歩したところ、実は、強欲国家だったことが判明して、譲歩は収奪されるばかりであり、戦争への動機を捨てさせることにつながらなかったとしたら、こうした対外政策は悲劇的な失敗になります。
なお、「エンゲージメント(関与政策)」は、宥和の1つの形態です。アメリカのクリントン政権は、台頭する中国に対して、「エンゲージメント」で臨みました。その基本的な想定は、中国を国際秩序に引き込めば、同国は「責任ある利害関係者」となり、現行ルールに基づき行動するようになるだろうという期待です。世界の国際政治学界でも、中国は「現状維持勢力」であるという言説が有力であり、その平和的台頭を疑う対中封じ込め論は少数派でした。中国が現状維持の安全保障追求者であるならば、宥和理論で示されているように、譲歩をすれば「食欲が満たされて」おとなしくなるはずでした。はたして、こうした宥和理論から導かれた対中政策は、うまくいったといえるでしょうか。少なくとも、(攻撃的)リアリストの答えは、「ノー」です。アメリカのトランプ政権も、2018年、対中エンゲージメントは終わったと示唆しました。一般的で雑駁なむすびになりますが、宥和政策は敵対国にパワーを明け渡す危険がある以上、国際政治のバランス・オブ・パワー原則に反するので、衰退国家が自らの脆弱性ゆえに攻撃的行動にでている場合は「再保障(安心供与」としての効果が見込めるかもしれませんが、台頭する野心的な現実打破国への適用は控えるべきだと思います。