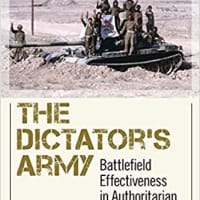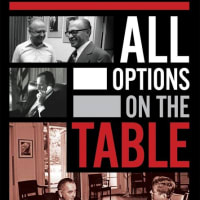国際関係論は、戦争の原因を究明することに力を注いできたあまり、もしかしたら平和の原因を解明することをややもすれば後回しにしてきたのかもしれません。戦争は起こったことですので、注目を集めやすい事象です。ところが、平和は、戦争がない状態と定義するならば、起こらなかったことですので、見過ごされやすかったのみならず、因果的推論が難しい現象なのかもしれません。X国とY国の間で戦争が起こらなかった場合、X国がY国の戦争を抑止した結果なのか、それともY国がそもそも戦争を起こす気はなかった結果なのかは、Y国の国家戦略に関する機密文書が開示され、同国の指導者の戦争の意志の有無を確認しない限り、分かりません(くわえて、和戦に関する一次史料が入手できたとしても、その解釈という厄介な問題も残ります)。しかしながら、国家は自分の手の内を明らかにするような行為には、とりわけ独裁国家や専制国家がそうであるように、概して後ろ向きです。さらに観察をややこしくするのは、国家の指導者は攻撃する気がないにもかかわらず、身の安全を確保しようとして、外交術の1つであるブラフをしばしば使うことです。リアリストが強調するように、アナーキーは相手国の意図を正確に知ることを困難にします。何が国家間の不戦を引き起こすのかは、何が国家を戦争に駆り立てるのかを明らかにするより、難しい研究課題なのかもしれません。
ジョン・ミューラー氏(オハイオ州立大学)による『終末からの退却—主要戦争の退化—(Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Major war)』(ベイシック・ブックス、1989年)は、既存の実証的国際関係研究の空白を埋める「平和の起源」を雄弁に論じた、政治学者による労作です。おそらく本書は、「戦争退化理論」の嚆矢ではないでしょうか。かれは、戦争に対する人々の嫌悪に注目します。第一次世界大戦が起こるまでは、世界に戦争に対する一種の「ロマンティシズム」がありました。これが戦争の温床になっていたのです。しかしながら、この「大戦争」は、人間の戦争に対する意識を大きく変えました。すなわち、先進国の人々は、戦争を忌み嫌うようになり、非道徳的で、非文明的なものだとみなすようになったのです。その結果、先進諸国の間では、戦争が起こらなくなったということです。

ミューラー氏は、戦争が放棄されるようになったのは、その物質的な損害や犠牲の大きさゆえのことではないといっています。17世紀の30年戦争や19世紀のナポレオン戦争は、ヨーロッパにおぞましい破壊や殺戮をもたらしました。しかしながら、戦争は国際社会の制度として残ったのです。戦争を時代遅れの遺物にしたきっかけは、第一次世界大戦でした。欧米世界では、それ以前から戦争の不毛さや非経済性を訴える「平和運動」が行われていました。誰もが予想しなかった第一次世界大戦の長期化と消耗は、こうした平和運動が示した戦争のむなしさを例証するものと、多くの人々は受け取りました。その結果、制度としての大戦争は廃れたのです。
にもかかわらず、その20年後に第二次世界大戦が勃発してしまったのは、ヨーロッパでは、誰もが「大戦」を繰り返したくないと思っていたところ、戦争のリスクを顧みないアドルフ・ヒトラーという人物が登場して、この一人の男が引き起こした結果だということです。ですから、第二次世界大戦は必然でも不可避でもなく、人々が戦争の不毛さをさらに学習する機会を与えたのものと理解できます。それ以前から、大戦争は人々にとって考えられないことになっていたのです。第二次世界大戦後、世界は冷戦に突入しましたが、大戦争は起こりませんでした。このことは核兵器の存在とは無関係だとミューラー氏は主張します。冷戦期において、世界が大戦争の惨禍にまみえなかったのは、それがもはや国家の国政術の選択肢になりえないものになったからなのです。かつて世界に存在した「決闘」や「奴隷制」が現在において消え去ったのと同じように、大戦争も退化したのです。
先進諸国以外の世界では、いまだに戦争は起こっています。しかしながら、ミューラー氏は、戦争への嫌悪という理念は世界に広がっていく見込みがあり、開発途上国からなる世界は、ヨーロッパと同じ道を歩むだろうと見立てています。要するに、「戦争は人間本性の必然性でもなければ、宇宙の不可避なものでもない。奴隷制や決闘と同じように、それは単なる一つの世界的制度に過ぎず、人間一人一人は戦争なくしても豊かに暮らせる」(同書、264ページ)のです。
『終末からの退却』は、戦争の不在という「平和」のメカニズムを解明しようとした、意欲的で論争的な研究です。ミューラー氏の主張が本当に正しければ、人類は野蛮な戦争から解放されつつあることになり、これほど喜ばしいことはないでしょう。ただし、この「戦争退化説」が妥当かどうかは、科学的に検証されなければなりません。望ましいことと今あることの区別は大切です。あらゆる理論は、その構成が論理的に正しいかどうか、経験的に裏づけられるかどうか、希望的観測を排除して、キチンと検証されなければなりません。わたしが『終末からの退却』を読んで気になったことは、以下の通りです。
第1に、ミューラー氏が擁護する個人の分析レベルにもとづく「戦争退化説」は、歴史証拠による検証が「あまい」ように思います。かれは同書において、第一次世界大戦後の「国際関係史」を数百ページにわたって綴っていますが、それは戦間期や冷戦期に関する歴史の叙述になっており、政治学の体系的な理論検証にはなっていないといわざるを得ません。言い換えれば、本書の事例研究は、記述的な叙述にとどまっており、分析的な説明には程遠いのです。第2に、仮説と証拠の重大な不一致があります。かれは第一次世界大戦が人々の戦争への意識を変えたエビデンスを提示しています。たとえば、「多くの人々にとって、それから本当の脅威と真の敵は戦争それ自体になった…1914年以降、仮想的な戦争を描いた文献は、古臭く、英雄的で、攻撃的な態度のものが、コンスタントに減少してきた」(同書、59ページ)ことが、その1つです。読み物は時代を映す鏡として、一定の価値があるので、データとして使うことには、ある程度、納得できます。問題は、その後、ファシストのムッソリーニやナチズムのヒトラーによる戦争が起こったことです。こうした理論的な矛盾について、ミューラー氏は、第二次大戦をこれら指導者の「特異な」個人的属性のせいだと片付けています。ムッソリーニやヒトラーは、もしかしたら「歴史の例外」人物だったのかもしれません。とりわけ後者について、ミューラー氏は「ヒトラーは現象でも傀儡でもなかった。かれがナチズムを発明したのであり…第二次世界大戦を引き起こしたのだ」(同書、65ページ)と断言しています。確かに、これら独裁者の好戦性とは対照的に、イタリアやドイツの人々は、はじめのうちは戦争に乗り気ではありませんでした。ですが、第一次大戦後、ヨーロッパで戦争は考えられない嫌悪すべきものとして衰退していたはずだったにもかかわらず、結局、イタリアとドイツは歴史の流れに逆行するような大戦争に突き進んでいきました。なぜそうなったのかナゾは残ります。そのナゾをミューラー氏は十分に説明できていません。
第3に、ミューラー氏の有名な「核兵器は冷戦期の大戦争の不在と無関係である」という仮説への疑問です。この仮説について、かれは以下のように述べています。
「(核兵器)なしでも、第二次世界大戦の記憶は鮮明で効果的な(大戦争への)抑止力として成り立っていただろう…第二次大戦を繰り返すことへの恐怖は、心に焼き付く印象的なものとして、弱いものでは決してなく、現状維持に原則として満足する指導者は、いずれの災厄(大戦争もしくは核戦争、引用者)にもつながりかねないと感じる、いかなることも避けようと努めるだろう。15階の窓から飛び降りることは、5階の窓から飛び降りることを考えるより少し怖いものだが、最低限、生きることに満足する人なら、どちらの行為もまず確実にしない」(同書、116ページ)。
こうした卓越した例えは、読み手に、核抑止は大戦争の防止に余分な影響を与えたに過ぎず、大戦争へのエスカレーションへの恐怖こそが、国家の指導者に武力行使を思いとどまらせたことを説得するものです。しかしながら、このような反実仮想は、社会科学の標準的な手続きからすれば、それに必要な条件を満たさないものだと否定できます。ラーズ=エリック・セダーマン氏(チューリッヒ工科大学)は、この「核兵器無関係説」を次のように退けます。「ミューラーの説明の問題は、かれが戦後の歴史で実際に起こったこと(キューバミサイル危機を含めて!)を明示的になぞっている一方で、核技術をたんに『消し去っている』ことにある。このことは歴史を表面的に書き換えている明白な例である。なぜなら、核兵器が存在する戦後世界において実際に起こった危機が、非核の事例で実際に起こるとは考えにくからだ…核ミサイル不在の状況において、このような危機が起こるのをどうやって想像できようか」("Running History: Counterfactual Simulation in World Politics," in Philip E. Tetlock and Aaron Belkin, eds., Counterfactual Thought Experiments in World Politics: Logical, Methodological, and Psychological Perspectives, Princeton University Press, 1996, p. 253)。
最後に、ミューラー氏の主張は、暗黙裡に、商業的リベラリズムの仮説に立脚して、冷戦後世界における戦争の衰退を予測していますが、こうした楽観的な見方は、単純には受け入れられないでしょう。かれは「アジアにおけるシンガポールや台湾…の相対的な繁栄が模倣のモデルになるのであれば、戦争は衰退するだろう」(同書、256ページ)と、カント由来の交易が戦争を抑制する効果に期待を寄せています。さらに戦争への嫌悪といった「精神的な革命」が起こったことは、戦争の魅力を減少させるとして、「インドとパキスタンは何度も戦ったが、1971年以後は戦っていない」(同書、256ページ)ことを例に挙げて、自説に説得力を持たせようとしています。しかしながら、豊かになった中国は、ミューラー氏の予言とは異なり、戦争を考えられないものだとみなしていません。中国国防省の呉謙報道官は、2021年1月28日の記者会見で、「台湾独立を目指す勢力に、本気で告げる。火遊びをする者はやけどを負う。台湾独立は戦争を意味する」と恫喝しています。経済成長にあるインドとパキスタンは、1999年に「カーギル危機」で多くの犠牲者を出す軍事衝突を引き起こしています。リアリストが主張するように、現代世界において、ナショナリズムといった第一次大戦以前から根強く残るイデオロギーは、国家を動かす要因として、いまだに強く作用しているのです。
『終末からの退却』は、平和の起源を人間本性の変化に求める意欲的な研究です。この本は、国際関係論を学ぶ人にとって重要な参考文献であり、一般に広く読まれている書物でもあります。なお、ミューラー氏の研究意欲は衰えることなく、近著『戦争の愚かさ(The Stupidity of War: American Foreign Policy and the Case for Complacency) 』(ケンブリッジ大学出版局、2021年)において、戦争への忌避が大戦争を衰退させている今日、アメリカは「宥和政策」を外交の手段として活用すべきだと説いています。両著とも、現在世界において戦争は退化していることを前提として書かれていますが、タニシャ・ファザール氏(ミネソタ大学)が『フォーリン・アフェアーズ』誌の書評エッセーで指摘しているように、2011年頃から紛争が増えてきたとのデータ(ウプサラ紛争データベース計画)もあります。ミューラー氏の著作は、読み物としては興味を引くのですが、「戦争退化」理論はロジックとしても経験的にも確かなものとはいえそうにないので、国家の安全保障に責任を負う意志決定者は、こうした理論を安易に政策のガイダンスにできないと思います。
ジョン・ミューラー氏(オハイオ州立大学)による『終末からの退却—主要戦争の退化—(Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Major war)』(ベイシック・ブックス、1989年)は、既存の実証的国際関係研究の空白を埋める「平和の起源」を雄弁に論じた、政治学者による労作です。おそらく本書は、「戦争退化理論」の嚆矢ではないでしょうか。かれは、戦争に対する人々の嫌悪に注目します。第一次世界大戦が起こるまでは、世界に戦争に対する一種の「ロマンティシズム」がありました。これが戦争の温床になっていたのです。しかしながら、この「大戦争」は、人間の戦争に対する意識を大きく変えました。すなわち、先進国の人々は、戦争を忌み嫌うようになり、非道徳的で、非文明的なものだとみなすようになったのです。その結果、先進諸国の間では、戦争が起こらなくなったということです。

ミューラー氏は、戦争が放棄されるようになったのは、その物質的な損害や犠牲の大きさゆえのことではないといっています。17世紀の30年戦争や19世紀のナポレオン戦争は、ヨーロッパにおぞましい破壊や殺戮をもたらしました。しかしながら、戦争は国際社会の制度として残ったのです。戦争を時代遅れの遺物にしたきっかけは、第一次世界大戦でした。欧米世界では、それ以前から戦争の不毛さや非経済性を訴える「平和運動」が行われていました。誰もが予想しなかった第一次世界大戦の長期化と消耗は、こうした平和運動が示した戦争のむなしさを例証するものと、多くの人々は受け取りました。その結果、制度としての大戦争は廃れたのです。
にもかかわらず、その20年後に第二次世界大戦が勃発してしまったのは、ヨーロッパでは、誰もが「大戦」を繰り返したくないと思っていたところ、戦争のリスクを顧みないアドルフ・ヒトラーという人物が登場して、この一人の男が引き起こした結果だということです。ですから、第二次世界大戦は必然でも不可避でもなく、人々が戦争の不毛さをさらに学習する機会を与えたのものと理解できます。それ以前から、大戦争は人々にとって考えられないことになっていたのです。第二次世界大戦後、世界は冷戦に突入しましたが、大戦争は起こりませんでした。このことは核兵器の存在とは無関係だとミューラー氏は主張します。冷戦期において、世界が大戦争の惨禍にまみえなかったのは、それがもはや国家の国政術の選択肢になりえないものになったからなのです。かつて世界に存在した「決闘」や「奴隷制」が現在において消え去ったのと同じように、大戦争も退化したのです。
先進諸国以外の世界では、いまだに戦争は起こっています。しかしながら、ミューラー氏は、戦争への嫌悪という理念は世界に広がっていく見込みがあり、開発途上国からなる世界は、ヨーロッパと同じ道を歩むだろうと見立てています。要するに、「戦争は人間本性の必然性でもなければ、宇宙の不可避なものでもない。奴隷制や決闘と同じように、それは単なる一つの世界的制度に過ぎず、人間一人一人は戦争なくしても豊かに暮らせる」(同書、264ページ)のです。
『終末からの退却』は、戦争の不在という「平和」のメカニズムを解明しようとした、意欲的で論争的な研究です。ミューラー氏の主張が本当に正しければ、人類は野蛮な戦争から解放されつつあることになり、これほど喜ばしいことはないでしょう。ただし、この「戦争退化説」が妥当かどうかは、科学的に検証されなければなりません。望ましいことと今あることの区別は大切です。あらゆる理論は、その構成が論理的に正しいかどうか、経験的に裏づけられるかどうか、希望的観測を排除して、キチンと検証されなければなりません。わたしが『終末からの退却』を読んで気になったことは、以下の通りです。
第1に、ミューラー氏が擁護する個人の分析レベルにもとづく「戦争退化説」は、歴史証拠による検証が「あまい」ように思います。かれは同書において、第一次世界大戦後の「国際関係史」を数百ページにわたって綴っていますが、それは戦間期や冷戦期に関する歴史の叙述になっており、政治学の体系的な理論検証にはなっていないといわざるを得ません。言い換えれば、本書の事例研究は、記述的な叙述にとどまっており、分析的な説明には程遠いのです。第2に、仮説と証拠の重大な不一致があります。かれは第一次世界大戦が人々の戦争への意識を変えたエビデンスを提示しています。たとえば、「多くの人々にとって、それから本当の脅威と真の敵は戦争それ自体になった…1914年以降、仮想的な戦争を描いた文献は、古臭く、英雄的で、攻撃的な態度のものが、コンスタントに減少してきた」(同書、59ページ)ことが、その1つです。読み物は時代を映す鏡として、一定の価値があるので、データとして使うことには、ある程度、納得できます。問題は、その後、ファシストのムッソリーニやナチズムのヒトラーによる戦争が起こったことです。こうした理論的な矛盾について、ミューラー氏は、第二次大戦をこれら指導者の「特異な」個人的属性のせいだと片付けています。ムッソリーニやヒトラーは、もしかしたら「歴史の例外」人物だったのかもしれません。とりわけ後者について、ミューラー氏は「ヒトラーは現象でも傀儡でもなかった。かれがナチズムを発明したのであり…第二次世界大戦を引き起こしたのだ」(同書、65ページ)と断言しています。確かに、これら独裁者の好戦性とは対照的に、イタリアやドイツの人々は、はじめのうちは戦争に乗り気ではありませんでした。ですが、第一次大戦後、ヨーロッパで戦争は考えられない嫌悪すべきものとして衰退していたはずだったにもかかわらず、結局、イタリアとドイツは歴史の流れに逆行するような大戦争に突き進んでいきました。なぜそうなったのかナゾは残ります。そのナゾをミューラー氏は十分に説明できていません。
第3に、ミューラー氏の有名な「核兵器は冷戦期の大戦争の不在と無関係である」という仮説への疑問です。この仮説について、かれは以下のように述べています。
「(核兵器)なしでも、第二次世界大戦の記憶は鮮明で効果的な(大戦争への)抑止力として成り立っていただろう…第二次大戦を繰り返すことへの恐怖は、心に焼き付く印象的なものとして、弱いものでは決してなく、現状維持に原則として満足する指導者は、いずれの災厄(大戦争もしくは核戦争、引用者)にもつながりかねないと感じる、いかなることも避けようと努めるだろう。15階の窓から飛び降りることは、5階の窓から飛び降りることを考えるより少し怖いものだが、最低限、生きることに満足する人なら、どちらの行為もまず確実にしない」(同書、116ページ)。
こうした卓越した例えは、読み手に、核抑止は大戦争の防止に余分な影響を与えたに過ぎず、大戦争へのエスカレーションへの恐怖こそが、国家の指導者に武力行使を思いとどまらせたことを説得するものです。しかしながら、このような反実仮想は、社会科学の標準的な手続きからすれば、それに必要な条件を満たさないものだと否定できます。ラーズ=エリック・セダーマン氏(チューリッヒ工科大学)は、この「核兵器無関係説」を次のように退けます。「ミューラーの説明の問題は、かれが戦後の歴史で実際に起こったこと(キューバミサイル危機を含めて!)を明示的になぞっている一方で、核技術をたんに『消し去っている』ことにある。このことは歴史を表面的に書き換えている明白な例である。なぜなら、核兵器が存在する戦後世界において実際に起こった危機が、非核の事例で実際に起こるとは考えにくからだ…核ミサイル不在の状況において、このような危機が起こるのをどうやって想像できようか」("Running History: Counterfactual Simulation in World Politics," in Philip E. Tetlock and Aaron Belkin, eds., Counterfactual Thought Experiments in World Politics: Logical, Methodological, and Psychological Perspectives, Princeton University Press, 1996, p. 253)。
最後に、ミューラー氏の主張は、暗黙裡に、商業的リベラリズムの仮説に立脚して、冷戦後世界における戦争の衰退を予測していますが、こうした楽観的な見方は、単純には受け入れられないでしょう。かれは「アジアにおけるシンガポールや台湾…の相対的な繁栄が模倣のモデルになるのであれば、戦争は衰退するだろう」(同書、256ページ)と、カント由来の交易が戦争を抑制する効果に期待を寄せています。さらに戦争への嫌悪といった「精神的な革命」が起こったことは、戦争の魅力を減少させるとして、「インドとパキスタンは何度も戦ったが、1971年以後は戦っていない」(同書、256ページ)ことを例に挙げて、自説に説得力を持たせようとしています。しかしながら、豊かになった中国は、ミューラー氏の予言とは異なり、戦争を考えられないものだとみなしていません。中国国防省の呉謙報道官は、2021年1月28日の記者会見で、「台湾独立を目指す勢力に、本気で告げる。火遊びをする者はやけどを負う。台湾独立は戦争を意味する」と恫喝しています。経済成長にあるインドとパキスタンは、1999年に「カーギル危機」で多くの犠牲者を出す軍事衝突を引き起こしています。リアリストが主張するように、現代世界において、ナショナリズムといった第一次大戦以前から根強く残るイデオロギーは、国家を動かす要因として、いまだに強く作用しているのです。
『終末からの退却』は、平和の起源を人間本性の変化に求める意欲的な研究です。この本は、国際関係論を学ぶ人にとって重要な参考文献であり、一般に広く読まれている書物でもあります。なお、ミューラー氏の研究意欲は衰えることなく、近著『戦争の愚かさ(The Stupidity of War: American Foreign Policy and the Case for Complacency) 』(ケンブリッジ大学出版局、2021年)において、戦争への忌避が大戦争を衰退させている今日、アメリカは「宥和政策」を外交の手段として活用すべきだと説いています。両著とも、現在世界において戦争は退化していることを前提として書かれていますが、タニシャ・ファザール氏(ミネソタ大学)が『フォーリン・アフェアーズ』誌の書評エッセーで指摘しているように、2011年頃から紛争が増えてきたとのデータ(ウプサラ紛争データベース計画)もあります。ミューラー氏の著作は、読み物としては興味を引くのですが、「戦争退化」理論はロジックとしても経験的にも確かなものとはいえそうにないので、国家の安全保障に責任を負う意志決定者は、こうした理論を安易に政策のガイダンスにできないと思います。