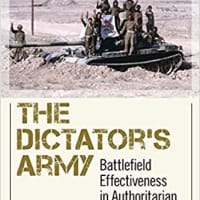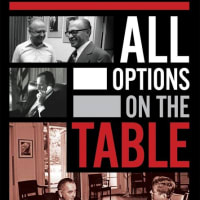国際政治の世界では、日常生活とは異なり、暴力(軍事力)による威嚇は国家戦略の重要な1つの手段として行われています。「(懲罰的)抑止」は、その典型例でしょう。国家の安全保障戦略の柱である抑止は、相手に耐え難い損害を与える威嚇により、自らが望まない行動を思いとどまらせることを目的としています。冷戦期の米ソの核戦略は、こうした抑止を中心に構築されていました。冷戦後、大国の安全保障戦略における核兵器への依存度は低下しましたが、今でも抑止の威嚇を操作することは国家の生き残りのための重要な外交術であり続けています。では、国家の指導者は、相手国の威嚇が本物かどうかをどのように判断しているのでしょうか。もし国家が威嚇を実行しなかったら、その信ぴょう性は失われたり、評判は悪くなったりするのでしょうか。こうした安全保障における重大なテーマに取り組んだ研究書が、ダリル・プレス『信ぴょう性の判断ー指導者は軍事的威嚇をどのように評価するのかー』(コーネル大学出版局、2005年)です。この図書は、国際政治学者のみならず軍事専門家にもインパクトを与えたようで、International Studies Review誌やMillennium誌のみならずThe Journal of Military History誌にも、書評が掲載されました。アメリカの海軍大学院の教官も書評を執筆しています。
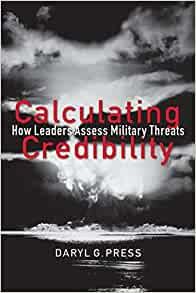
本書において、ダリル・プレス氏(ダートマス大学)は、威嚇の信ぴょう性(credibility)に関して大きく2つの理論を構築して、それぞれの妥当性をシッカリとデザインされた事例研究により検証しています。1つめの理論は、「過去の行動理論(Past Action Theory)」です。これは一般的な人間によくみられる行動にもとづいています。すなわち、国家の意思決定者は、敵対国が発する威嚇の信ぴょう性について、過去に公約(コミットメント)を守ったのか、それとも破ったのかの記録から判断するとの推論です。敵対国が過去に威嚇を実行する決意を示していれば、その信ぴょう性は高いことになります。逆に、敵対国が過去に公約や約束を破っていれば、威嚇の信ぴょう性は低いことになります。もう1つの理論が「現状計算理論(Current Calculus Theory)」です。これは、政策決定者は、敵対国の威嚇を当該国が持つパワーや利益から計算して、その信ぴょう性を評価するという仮説です。国際危機において、敵対国のパワーが強く、争点に関する利害が強い場合、その威嚇は信ぴょう性があると判断されるということです。
これら2つの理論は、①1938-39年の「宥和危機」、②1958-61年の「ベルリン危機」、③1962年の「キューバ危機」の事例により検証されます。プレス氏は、公式声明ではなく政府内部での議論を機密解除された膨大な一次資料を使って、それそれの危機における関係国の指導者の威嚇に関する思考を「過程追跡」しています。また、かれは事例研究の方法として、ハリー・エクスタイン氏が構築した「再適合事例(most-likely case)」を採用しています。これは理論が上手く説明できそうな事例を指します。理論によって都合がよく、検証に通りやすい事例ということです。ですから、逆説的ですが、理論がこんな簡単な事例群でさえ説明できないのであれば、その力はとても弱いことになります。上記の3つの事例は、信ぴょう性に関する通説である「過去の行動理論」にとって都合のよいものです。それぞれの危機は、その性質が似通っているだけでなく、同じ場所で連続して起きており、関係国にとって重大な出来事です。ですから、危機に直面した指導者は、敵対国の威嚇の信ぴょう性を過去の行動から容易に判断できるはずなのです。
ところが驚くことに、直感に反して、「過去の行動理論」は、これらの簡単な事例を十分には説明できないとプレス氏は主張します。つまり、「過去の行動理論」は間違いだということです。ナチス・ドイツは、ヴェルサイユ条約に反して、ラインラントに進駐しました。そして同国はオーストリアを併合しました。こうしたドイツの侵略的行動に対して、イギリスやフランスは具体的な行動をとることなく、事実上、黙認しました。「過去の行動理論」が正しければ、ヒトラーやドイツの軍事指導者は、イギリスやフランスは優柔不断で低い信ぴょう性しか持っていないと判断するはずです。しかしながら、ヒトラーも将軍たちも、チェコスロバキアやポーランドへの侵攻計画を立案する際に、イギリスやフランスのドイツに対する「警告(威嚇)」の信ぴょう性を議論していないのです。かれらは、イギリスやフランスの出方をバランス・オブ・パワーから推察していたのです。1938年にナチス・ドイツがチェコスロバキアに侵攻しようとした際、同国の将軍たちは、ドイツは英仏の軍事行動を排除するのに十分な軍事力をまだ持つに至っていないと判断していました。こうした判断のもと、ヒトラーは(不本意ながら)「ミュンヘン協定」により、ズデーデン地方を獲得することで危機を収束させました。1939年になると、バランス・オブ・パワーは、ドイツの軍事力の拡充やソ連との不可侵条約の締結により、ドイツ優位になりました。ポーランド危機に際して、イギリスとフランスはドイツの侵略を看過しないと威嚇していたのですが、ドイツはそれを軽く見てポーランドに侵攻しました。ここでのポイントは、ドイツがイギリスやフランスの過去の「宥和」から学習して、侵略をしても両国は見逃すだろうと判断したのではなく、自分が強くなったのだから、両国は手出しできないはずだと計算して、ポーランドに兵力を進めたということです。こうした事実は、「過去の行動理論」ではなく、「現状計算理論」を裏づけるものなのです。
1958-61年にかけてのベルリン危機の事例も、「過去の行動理論」では説明できません。ソ連はアメリカやイギリスに対して、ベルリン問題で「最後通牒」を何度も突き付けました。フルシチョフ首相は、西ベルリンの地位に関する再交渉に応じなければ、同市を封鎖すると、西側諸国を繰り返し脅したのです。しかしながら、そうした威嚇は実行されませんでした。「過去の行動理論」が正しければ、何度も約束を破る人は信頼されなくなるのと同じように、ソ連の威嚇は不実行にともない、その信ぴょう性は低下するはずです。しかしながら、アメリカやイギリスの指導者は、ソ連のベルリン封鎖の脅しは、時間と共にますます信ぴょう性を増してきており、戦争の危険が高まっていると判断していたのです。こうした計算には、ソ連が核戦力においてアメリカに近づいてきたことが背景にありました。すなわち、アメリカやイギリスの政策決定者は、ソ連とのバランス・オブ・パワーの観点から、その威嚇の信ぴょう性を評価していたのです。このことは「現状計算理論」の仮説を裏づけるということです。
1962年のキューバ・ミサイル危機におけるアメリカのソ連に対する脅威認識も、やはり「過去の行動理論」の予測と一致しません。キューバ危機は、ベルリン危機の最終年の翌年に起こりました。ソ連のキューバにおける核ミサイル基地の建設に対して、ケネディ政権は、海上封鎖で応じました。この危機は最終的に、ソ連がキューバから核ミサイルを撤去するのと引き換えに、アメリカはキューバ不侵攻を約束するとともに、トルコに配備していたジュピターミサイル撤去を密約することで収束しました。危機への対応を協議する際、アメリカの指導者は、しきりにソ連が西ベルリンに侵攻することを恐れていました(ルメイ将軍だけは例外)。国家安全保障会議エクスコムのメンバーは、フルシチョフ首相の脅しは、ベルリン危機で一度も実行されなかったにもかかわらず、その信ぴょう性が高いと考えていたのです。すなわち、アメリカがキューバを攻撃すれば、ソ連は報復としてベルリンで軍事攻勢にでる可能性が高いと判断していたのです。ケネディ政権は、ソ連が核戦力を増強していることから、モスクワの威嚇の信ぴょう性を計算していました。そして、ソ連との核戦争を何としても避けたいとの選好が、アメリカに比較的柔和な「海上封鎖」を選択させました。こうしたキューバ危機の経緯は、「現状計算理論」で説明できるということです。
要するに、上記のいずれの危機の事例においても、政策決定者は、敵対国の威嚇の信ぴょう性を評価する際、その国の過去の行動に重きを置いていませんでした。そうではなく、かれらはバランス・オブ・パワーを脅しの信ぴょう性の判断基準としていたのです。プレス氏は上記書において、「リアリズム」には言及していませんが、この研究成果は、国家間の権力闘争を研究プログラムの中核とするリアリズムに、新しい重要な理論を追加していると思います。リアリストのジョン・ミアシャイマー氏が、「アメリカの対外政策に携わるエリートたちは、ただちにプレス氏の研究成果に耳を傾けるべきだ」と称賛して、本書を推奨する所以です(上記書の裏表紙の推薦文より)。
この研究結果から得られる政策的含意としては、「国家は信ぴょう性(信頼性)確保のための戦争を行うべきではない」(同書、160ページ)ことが挙げられます。なぜならば「危機において敵国に折れても、国家の信ぴょう性や自国のパワーに対する認識は傷つかない」(同書、157ページ)からです。こうした議論が正しいとするならば、たとえば、アメリカのヴェトナム戦争への軍事介入は、深刻な間違いだったことになります。アメリカは、共産主義の脅威から南ヴェトナムを救わなければ、同盟国を守る信ぴょう性に傷がつき、ソ連や中国に誤ったメッセージを送ることになることを深く懸念していました。しかしながら、もし信ぴょう性は行動ではなくバランス・オブ・パワーで決まるのであれば、アメリカはその国力をヴェトナム戦争で低下させてしまったために、皮肉にも、意図せざる結果により、その信ぴょう性も低下させることになってしまいました。威嚇に信ぴょう性を持たせるためには、強い軍事力を持つべきだというのがプレス氏の結論なのです。
『信ぴょう性の判断』は、直感や通説に反する理論を構築したこと、優れた研究デザインにもとづき、一次資料を使って丁寧に理論を検証したこと、政策立案に役立つ知見を導き出したことなどにおいて、とても高く評価できるものであるのは間違いありません。ただし、わたしは「過去の行動理論」の棄却には、もっと慎重になるべきだとと思います。なぜならば、威嚇の信ぴょう性を過去の行動から推察した重要な事例があるからです。それはヴェトナムへの軍事介入を議論したジョンソン政権の事例です。先のブログ「歴史の教訓とアナロジー」で書いたように、ジョンソン政権は、ヴェトナムへ兵力を投入する際、「朝鮮戦争のアナロジー」から、北ヴェトナムへの攻撃を控えました。北ベトナムを大規模な空軍力で攻撃してしまうと、朝鮮戦争の時と同じように、中国の軍事介入を招くことになり、泥沼の米中戦争になることをアメリカの指導者は恐れたのです。このように、この事例は「過去の行動理論」で上手く説明できるのです。プレス氏は、このことに気づいていたようで、上記書の注で以下のように述べています。
「わたしが文献の中で見つけた、国家の過去の行動が信ぴょう性の評価に使われた1つの事例は、ジョンソン政権の判断、すなわち、朝鮮戦争(からの推論)にもとづき、もしアメリカが北ヴェトナムを侵略したならば、中国が介入するだろうというものである」(167ページ)。
プレス氏が、「現状計算理論」に不利で「過去の行動理論」に有利なヴェトナム戦争の事例を注でさらっと言及するにとどめたのは、合点がいきません。理論を検証する際に、事例の選択バイアスがあると批判されても仕方ないように思うのですが、どうなのでしょうか。あえてプレス氏の肩を持つとすれば、『信ぴょう性の判断』における研究は、国際危機を事例の母集団としているので、「戦争」の事例は代表性がないといえるかもしれません。しかしながら、こうした考えられる自説の擁護は、戦争につながった戦間期の対独宥和を事例として選択していることと矛盾します。現状維持国が挑戦国の要求に屈したとしても、その信ぴょう性は低下しないとの命題が間違っていた場合、国家がこうした誤った理論にもとづき行動してしまうと、その代償は高くつきます。挑戦国に優柔不断とみられて、さらなる敵対行動を促してしまったならば、抑止は破綻してしまいます。バランス・オブ・パワーが威嚇の信ぴょう性を左右するのは、おそらく間違いないのでしょうが、「歴史のアナロジー」は危機における国家の政策決定者のパーセプションに影響しないと断言するには、まだ早いといったほうがよいように思います。
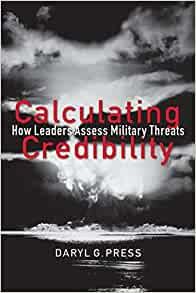
本書において、ダリル・プレス氏(ダートマス大学)は、威嚇の信ぴょう性(credibility)に関して大きく2つの理論を構築して、それぞれの妥当性をシッカリとデザインされた事例研究により検証しています。1つめの理論は、「過去の行動理論(Past Action Theory)」です。これは一般的な人間によくみられる行動にもとづいています。すなわち、国家の意思決定者は、敵対国が発する威嚇の信ぴょう性について、過去に公約(コミットメント)を守ったのか、それとも破ったのかの記録から判断するとの推論です。敵対国が過去に威嚇を実行する決意を示していれば、その信ぴょう性は高いことになります。逆に、敵対国が過去に公約や約束を破っていれば、威嚇の信ぴょう性は低いことになります。もう1つの理論が「現状計算理論(Current Calculus Theory)」です。これは、政策決定者は、敵対国の威嚇を当該国が持つパワーや利益から計算して、その信ぴょう性を評価するという仮説です。国際危機において、敵対国のパワーが強く、争点に関する利害が強い場合、その威嚇は信ぴょう性があると判断されるということです。
これら2つの理論は、①1938-39年の「宥和危機」、②1958-61年の「ベルリン危機」、③1962年の「キューバ危機」の事例により検証されます。プレス氏は、公式声明ではなく政府内部での議論を機密解除された膨大な一次資料を使って、それそれの危機における関係国の指導者の威嚇に関する思考を「過程追跡」しています。また、かれは事例研究の方法として、ハリー・エクスタイン氏が構築した「再適合事例(most-likely case)」を採用しています。これは理論が上手く説明できそうな事例を指します。理論によって都合がよく、検証に通りやすい事例ということです。ですから、逆説的ですが、理論がこんな簡単な事例群でさえ説明できないのであれば、その力はとても弱いことになります。上記の3つの事例は、信ぴょう性に関する通説である「過去の行動理論」にとって都合のよいものです。それぞれの危機は、その性質が似通っているだけでなく、同じ場所で連続して起きており、関係国にとって重大な出来事です。ですから、危機に直面した指導者は、敵対国の威嚇の信ぴょう性を過去の行動から容易に判断できるはずなのです。
ところが驚くことに、直感に反して、「過去の行動理論」は、これらの簡単な事例を十分には説明できないとプレス氏は主張します。つまり、「過去の行動理論」は間違いだということです。ナチス・ドイツは、ヴェルサイユ条約に反して、ラインラントに進駐しました。そして同国はオーストリアを併合しました。こうしたドイツの侵略的行動に対して、イギリスやフランスは具体的な行動をとることなく、事実上、黙認しました。「過去の行動理論」が正しければ、ヒトラーやドイツの軍事指導者は、イギリスやフランスは優柔不断で低い信ぴょう性しか持っていないと判断するはずです。しかしながら、ヒトラーも将軍たちも、チェコスロバキアやポーランドへの侵攻計画を立案する際に、イギリスやフランスのドイツに対する「警告(威嚇)」の信ぴょう性を議論していないのです。かれらは、イギリスやフランスの出方をバランス・オブ・パワーから推察していたのです。1938年にナチス・ドイツがチェコスロバキアに侵攻しようとした際、同国の将軍たちは、ドイツは英仏の軍事行動を排除するのに十分な軍事力をまだ持つに至っていないと判断していました。こうした判断のもと、ヒトラーは(不本意ながら)「ミュンヘン協定」により、ズデーデン地方を獲得することで危機を収束させました。1939年になると、バランス・オブ・パワーは、ドイツの軍事力の拡充やソ連との不可侵条約の締結により、ドイツ優位になりました。ポーランド危機に際して、イギリスとフランスはドイツの侵略を看過しないと威嚇していたのですが、ドイツはそれを軽く見てポーランドに侵攻しました。ここでのポイントは、ドイツがイギリスやフランスの過去の「宥和」から学習して、侵略をしても両国は見逃すだろうと判断したのではなく、自分が強くなったのだから、両国は手出しできないはずだと計算して、ポーランドに兵力を進めたということです。こうした事実は、「過去の行動理論」ではなく、「現状計算理論」を裏づけるものなのです。
1958-61年にかけてのベルリン危機の事例も、「過去の行動理論」では説明できません。ソ連はアメリカやイギリスに対して、ベルリン問題で「最後通牒」を何度も突き付けました。フルシチョフ首相は、西ベルリンの地位に関する再交渉に応じなければ、同市を封鎖すると、西側諸国を繰り返し脅したのです。しかしながら、そうした威嚇は実行されませんでした。「過去の行動理論」が正しければ、何度も約束を破る人は信頼されなくなるのと同じように、ソ連の威嚇は不実行にともない、その信ぴょう性は低下するはずです。しかしながら、アメリカやイギリスの指導者は、ソ連のベルリン封鎖の脅しは、時間と共にますます信ぴょう性を増してきており、戦争の危険が高まっていると判断していたのです。こうした計算には、ソ連が核戦力においてアメリカに近づいてきたことが背景にありました。すなわち、アメリカやイギリスの政策決定者は、ソ連とのバランス・オブ・パワーの観点から、その威嚇の信ぴょう性を評価していたのです。このことは「現状計算理論」の仮説を裏づけるということです。
1962年のキューバ・ミサイル危機におけるアメリカのソ連に対する脅威認識も、やはり「過去の行動理論」の予測と一致しません。キューバ危機は、ベルリン危機の最終年の翌年に起こりました。ソ連のキューバにおける核ミサイル基地の建設に対して、ケネディ政権は、海上封鎖で応じました。この危機は最終的に、ソ連がキューバから核ミサイルを撤去するのと引き換えに、アメリカはキューバ不侵攻を約束するとともに、トルコに配備していたジュピターミサイル撤去を密約することで収束しました。危機への対応を協議する際、アメリカの指導者は、しきりにソ連が西ベルリンに侵攻することを恐れていました(ルメイ将軍だけは例外)。国家安全保障会議エクスコムのメンバーは、フルシチョフ首相の脅しは、ベルリン危機で一度も実行されなかったにもかかわらず、その信ぴょう性が高いと考えていたのです。すなわち、アメリカがキューバを攻撃すれば、ソ連は報復としてベルリンで軍事攻勢にでる可能性が高いと判断していたのです。ケネディ政権は、ソ連が核戦力を増強していることから、モスクワの威嚇の信ぴょう性を計算していました。そして、ソ連との核戦争を何としても避けたいとの選好が、アメリカに比較的柔和な「海上封鎖」を選択させました。こうしたキューバ危機の経緯は、「現状計算理論」で説明できるということです。
要するに、上記のいずれの危機の事例においても、政策決定者は、敵対国の威嚇の信ぴょう性を評価する際、その国の過去の行動に重きを置いていませんでした。そうではなく、かれらはバランス・オブ・パワーを脅しの信ぴょう性の判断基準としていたのです。プレス氏は上記書において、「リアリズム」には言及していませんが、この研究成果は、国家間の権力闘争を研究プログラムの中核とするリアリズムに、新しい重要な理論を追加していると思います。リアリストのジョン・ミアシャイマー氏が、「アメリカの対外政策に携わるエリートたちは、ただちにプレス氏の研究成果に耳を傾けるべきだ」と称賛して、本書を推奨する所以です(上記書の裏表紙の推薦文より)。
この研究結果から得られる政策的含意としては、「国家は信ぴょう性(信頼性)確保のための戦争を行うべきではない」(同書、160ページ)ことが挙げられます。なぜならば「危機において敵国に折れても、国家の信ぴょう性や自国のパワーに対する認識は傷つかない」(同書、157ページ)からです。こうした議論が正しいとするならば、たとえば、アメリカのヴェトナム戦争への軍事介入は、深刻な間違いだったことになります。アメリカは、共産主義の脅威から南ヴェトナムを救わなければ、同盟国を守る信ぴょう性に傷がつき、ソ連や中国に誤ったメッセージを送ることになることを深く懸念していました。しかしながら、もし信ぴょう性は行動ではなくバランス・オブ・パワーで決まるのであれば、アメリカはその国力をヴェトナム戦争で低下させてしまったために、皮肉にも、意図せざる結果により、その信ぴょう性も低下させることになってしまいました。威嚇に信ぴょう性を持たせるためには、強い軍事力を持つべきだというのがプレス氏の結論なのです。
『信ぴょう性の判断』は、直感や通説に反する理論を構築したこと、優れた研究デザインにもとづき、一次資料を使って丁寧に理論を検証したこと、政策立案に役立つ知見を導き出したことなどにおいて、とても高く評価できるものであるのは間違いありません。ただし、わたしは「過去の行動理論」の棄却には、もっと慎重になるべきだとと思います。なぜならば、威嚇の信ぴょう性を過去の行動から推察した重要な事例があるからです。それはヴェトナムへの軍事介入を議論したジョンソン政権の事例です。先のブログ「歴史の教訓とアナロジー」で書いたように、ジョンソン政権は、ヴェトナムへ兵力を投入する際、「朝鮮戦争のアナロジー」から、北ヴェトナムへの攻撃を控えました。北ベトナムを大規模な空軍力で攻撃してしまうと、朝鮮戦争の時と同じように、中国の軍事介入を招くことになり、泥沼の米中戦争になることをアメリカの指導者は恐れたのです。このように、この事例は「過去の行動理論」で上手く説明できるのです。プレス氏は、このことに気づいていたようで、上記書の注で以下のように述べています。
「わたしが文献の中で見つけた、国家の過去の行動が信ぴょう性の評価に使われた1つの事例は、ジョンソン政権の判断、すなわち、朝鮮戦争(からの推論)にもとづき、もしアメリカが北ヴェトナムを侵略したならば、中国が介入するだろうというものである」(167ページ)。
プレス氏が、「現状計算理論」に不利で「過去の行動理論」に有利なヴェトナム戦争の事例を注でさらっと言及するにとどめたのは、合点がいきません。理論を検証する際に、事例の選択バイアスがあると批判されても仕方ないように思うのですが、どうなのでしょうか。あえてプレス氏の肩を持つとすれば、『信ぴょう性の判断』における研究は、国際危機を事例の母集団としているので、「戦争」の事例は代表性がないといえるかもしれません。しかしながら、こうした考えられる自説の擁護は、戦争につながった戦間期の対独宥和を事例として選択していることと矛盾します。現状維持国が挑戦国の要求に屈したとしても、その信ぴょう性は低下しないとの命題が間違っていた場合、国家がこうした誤った理論にもとづき行動してしまうと、その代償は高くつきます。挑戦国に優柔不断とみられて、さらなる敵対行動を促してしまったならば、抑止は破綻してしまいます。バランス・オブ・パワーが威嚇の信ぴょう性を左右するのは、おそらく間違いないのでしょうが、「歴史のアナロジー」は危機における国家の政策決定者のパーセプションに影響しないと断言するには、まだ早いといったほうがよいように思います。