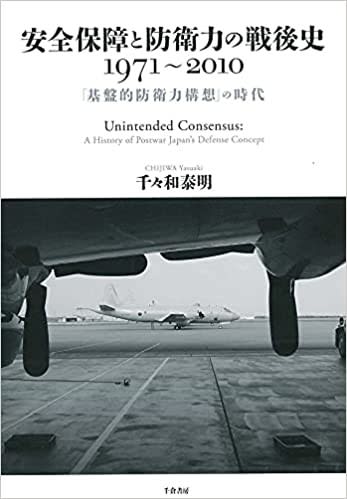巨大な「官僚機構」である軍事組織は、イノベーションが苦手であるといわれています。そもそも官僚機構は、変化しないことを前提に構築されています。官僚機構に関わった人なら誰もが経験するように、そのメンバーは「前例主義」や「標準作業手続き」、「レッド・テープ(繁文縟礼:非能率的な煩雑で複雑な順序や方法)」といった強固な行動基準に制約されるため、よほどのことがない限り、そこから逸脱する変化を追求しようとはしないのです。その一方で、軍事組織は困難を乗り越えてイノベーションを実践することがあります。どのような条件の下で軍事組織はイノベーションを成し遂げられるのでしょうか。この難問に挑んだのが、スティーヴン・ピーター・ローゼン『次の戦争で勝利すること―イノベーションと近代軍隊―』(コーネル大学出版局、1991年)です。タイトルは過激なように見えますが、本書の内容は組織論に準じた機構改革の分析であり、広い意味では政治学に含まれます。アメリカの政治学界では、『次の戦争で勝利すること』は高く評価されており、1992年の「エドガー・ファーニス賞」を授与されています。
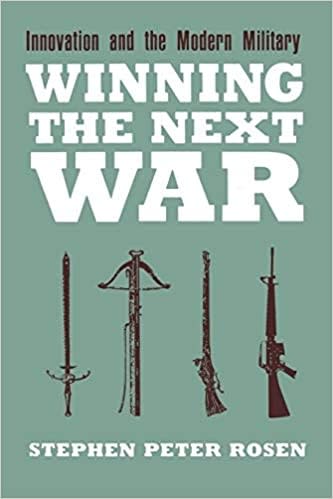
著者のスティーヴン・ローゼン氏(ハーバード大学)は、軍事組織は実戦で自らの作戦行動の成否を確かめられる戦時の方が、イノベーションを達成しやすいと思われがちですが、実は、平時のほうがイノベーションを成功させやすいと主張しています。また、組織は失敗を学習して変革するという通念がありますが、かれは、失敗はイノベーションの必要条件ではなく、それがなくても軍事組織は変われることを主にアメリカ軍の事例で示しています。戦間期にアメリカ軍は航空母艦の開発・運用や揚陸(水陸両用)戦闘、戦後にはヘリコプターによる兵力の機動運用いうイノベーションを成し遂げました。これらはアメリカ軍が戦争に負けた失敗を学習した結果ではありません。そうではなく国際安全保障環境の構造的変化への軍部の認識が、その源泉だということです。アメリカは米西戦争によってフィリピンを植民地化して、グアムに前進基地を築いて、太平洋に進出しました。これによりアメリカは太平洋における軍事大国になりました。他方、第一次世界大戦により、西太平洋のマリアナ諸島等が日本の委任統治領になったことで、その戦略的優位は損なわれました。そこでアメリカ軍は、広大な大洋における戦闘を考えなければならなくなりました。その結果、アメリカ海軍、海兵隊、アメリカ陸軍は、それぞれの新しい戦争における役割を見いだしたということです。
ローゼン氏によれば、平時における軍事イノベーションには、共通パターンがあります。第1に、軍事計画にたずさわる将校は、外部の安全保障環境の変化に直面した際、イノベーションを考えるように促されます。なぜならば、安全保障環境が変化したにもかかわらず、軍事組織がそれに適応しなければ、次の戦争で敗北を喫する恐れがあるからです。すなわち、将校は、将来の戦争がどのように行われ、どうすれば勝てるのかを考えさせられるのです。ここでのポイントは、軍事イノベーションは、仮想敵国に対する研究やインテリジェンスによって達成されるとは限らないことです。アメリカ軍の航空母艦の開発や運用は、外国の勢力に対抗するためのインテリジェンスによって実現したわけではありません。仮想敵国の情報は、矛盾含みで不確実かつあいまいなことがしばしばです。こうした不確実性を乗り越えるために、将校は、「新しい戦勝理論(new theory of victory)」を構築して、それをシミュレーションや訓練・演習により時間をかけて確実なものにしていくのです。これには古い作戦ドクトリンを変更する複雑な組織的な手続きを踏まなければならないために、長い時間がかかります。軍事組織が戦時ではなく平時にイノベーションを成し遂げやすいのは、それを戦術や作戦レベルにおけるドクトリンとして確実に定着させるための十分な時間をとれるからだということです(同書、57-75ページ)。
第2に、軍事組織における昇任人事がイノベーションのカギを握っています。新しい安全保障環境に適応する軍事組織のイノベーションは、将校団の世代交代によって促されますが、それにも長い時間がかかります。アメリカ海軍の空母機動部隊の場合、このイノベーションを志向する上級将校が、その実現に向けた新しい昇任システムを導入しました。この手続きにより、航空術に携わった下級将校たちが上級将校へと昇進していくと共に、空母の建設が海軍において戦艦より優先されるようになり、その運用ドクトリンが策定されていきました。そして最終的には、複数の空母から構成される打撃群が、正式な海軍のドクトリンになったのです。それまでにかかった時間は、約25年ということです。海兵隊による揚陸戦闘というイノベーションも同じく長い時間がかかりました。揚陸・水陸両用戦闘が最初に公式に注目されたのは、1905年のことでした。水陸両用作戦の概念を提唱したのは、海兵隊幕僚のアール・エリス少佐でした。この斬新なコンセプトは、海兵隊司令官に就任したルジューン少将やルーフス・レーン准将により支持されました。海兵隊の水陸両用作戦の演習は、プエルトリコ沖のクレブラ島で行われ、その後、1940年にはノース・カロライナ州のニューリバーで全面的揚陸戦闘演習が実施されました。注目すべきことは、海兵隊がクレブラでの演習で起こりそうな失敗を冒して、それを克服するために、海兵隊学校での訓練により、克服していったことです。これらの訓練が、水陸両用作戦の概念と原則の正しさを証明したのです(野中郁次郎『アメリカ海兵隊―非営利方組織の自己改革―』中央公論新社、1995年、3-52ページ)。海兵隊による揚陸作戦が定着するまでに、約一世代かかったことになります。ヘリコプターによる兵力の機動も、陸軍で作戦行動として実施されるまでには、その着想から長い時間がかかりました。要するに、平時のイノベーションのプロセスは長いのです。イノベーションの実現のために変革された昇任システムにより、将校団は時間をかけて陣容が変化しますが、そのプロセスは下級将校が上層部へ昇りつめる割合と速度によるということです(同書、76-105ページ)。
もちろん、戦時における軍事組織のイノベーションも可能です。たとえば、第二次世界大戦におけるアメリカ軍の戦略爆撃のターゲティング、潜水艦による商船への攻撃などがあります。これらのイノベーションは成功しましたが、平時におけるイノベーションに比べると、軍事組織を劇的に変化させたわけではありません。戦時のイノベーションが小規模になる理由は、戦争を行っている軍事組織がイノベーションに長い時間をかける余裕を持てないことにあります。戦時の経験を学習することにより得た新しい軍事機能を短期間で実践するのは、軍事組織にとって困難な課題なのです。アメリカは、戦略的ターゲッティングにおいて、大戦が終了する数か月まで効果的な目標を設定できませんでした。商船への潜水艦による攻撃の戦略的影響は、戦後になるまで理解されませんでした。つまり、戦時のイノベーションは可能なのですが、それは戦略オプションとしての強固な分析なくして行われざるを得ないのです(同書、109-182ページ)。最後に、大陸間弾道ミサイル(ICBM)のような軍事技術のイノベーションについては、どのように説明できるのでしょうか。このような新しい技術には不確実性が伴います。軍事組織は、こうした不確実性に対して、関連する情報を獲得するとともに、複数の柔軟な選択肢を持ちながら、大量調達を先延ばしにすることで対応します。ICBMのケースでは、アメリカ軍は、巡航ミサイルの選択肢も視野に入れながら、時間をかけて技術イノベーションを進めました。そして、ICBMが巡航ミサイルより、敵の防御を突破する速度と非脆弱性において優れていることが明確になった時点で、アメリカ軍は、それを採用したのです(同書、185-250ページ)。
これらの軍事イノベーションから、ローゼン氏は、いくつかの教訓を引き出しています。第1に、軍事組織の本格的なイノベーションには、長い時間がかかることです。軍事組織は、時間が取れる平時の方が戦時よりイノベーションを進めやすいのです。第2に、軍事イノベーションは予算との関係が薄いことです。戦間期の航空母艦や揚陸戦闘といったイノベーションは、軍備管理協定等の影響もあり、アメリカの軍事予算が制約を受けてた時期に起こりました。予算より重要なのは軍事組織における人材等であると、かれは以下のように指摘しています。
「イノベーションを開始すること、そして、それを戦略的に有用なオプションを提供する段階にもっていくことが達成されたのは、予算が厳しい時であった。カネよりも、有能な人材、時間、そして情報がイノベーションのカギとなる資源であり続けたのだ」(同書、252ページ)。
第3に、敵の能力や行動に関するインテリジェンスは、アメリカ軍のイノベーションにはあまり関係していません。アメリカ軍のイノベーションは、仮想敵国に対応して生まれたのではなく、安全保障環境の変化がもたらしたのです。第4に、文民の政治的指導者や民間の科学者が軍事イノベーションに果たす役割は、小さいということです。軍事ドクトリンに関する先行研究であるバリー・ポーゼン氏の『軍事ドクトリンの源泉』は、バランス・オブ・パワーの変化を受けて文民政治家が軍事組織に介入することにより、イノベーションは達成されやすいと説明していました。しかしながら、ローゼン氏は、そうではないと主張しています。シビリアン・コントロールの制度をとる国家において、戦争の可否や軍事予算を決めるのは文民政治家ですが、かれらは軍事組織のイノベーションにおいては、既に進行している改革を保護したり促進したりする役割を主に担うのです。たとえば、戦間期におけるイギリスの防空におけるレーダーや戦闘機、高射砲の導入の事例では、第一次世界大戦後から空軍が進めてきた防空システム構築を文民政治家が強化したのであり、それは軍事組織のイノベーションの必要条件でも十分条件でもなかったのです。
イギリスの防空システムの構築で重要な役割を果たしたのは、戦闘機兵団司令官のヒュー・ダウディング大将でした。かれは防空におけるレーダーの重要性に早くから気づき、その開発を推進しました。そして、かれは、レーダーによる早期警戒のネットワークと邀撃戦闘機の地上管制をリンクさせて、一元的指揮下で統合運用される防空システムの基礎を作りました。ダウディングは爆撃機にプライオリティをおく空軍の指導層に対して防空における戦闘機の重要性を説き、それを文民の政治指導者が支持することで、戦闘機の生産が優先されることになりました。さらに、ミュンヘン危機において防空システムの不具合を経験した空軍は、多くの権限を下級司令部に委譲して、即応できる体制を整えました(野中郁次郎ほか『戦略の本質』日本経済新聞社、2005年、98-104ページ)。こうしてイギリスは、来るバトル・オブ・ブリテンでドイツ空軍からの爆撃を耐え抜く軍事態勢を築けたのです。要するに、軍事組織では、新しいミッションや任務がシミュレーションを通して規定され、このイノベーションを専門とする将校のための新しいキャリアや昇任パターンが構築されます。このようにして、軍事組織は外部の安全保障環境の変化に適応するのです(同書、251-261ページ)。
ローゼン氏の軍事組織のイノベーションに関する説明は、ポーゼン氏の理論と同じように、国際システムの軍事組織への影響を指摘している点で共通しています。ただし、軍事イノベーションに果たす文民政治家の役割については、意見が異なっています。軍事イノベーションにおける文民の役割に関する競合する仮説のどちらが妥当であるかを判断するには、追加の事例研究による検証が必要でしょう。ローゼン氏の研究は、主にアメリカ軍のイノベーションを対象にしていますので、その理論の適用範囲(scope conditions)は狭いものかもしれません。実際に、かれは、自分の分析はアメリカと戦略文化が異なる他国の軍事組織には当てはまらないかもしれないと示唆しています。他方、ポーゼン氏の仮説も、第二次世界大戦前後のイギリス、フランス、ドイツの事例から引き出されたものなので、どこまで一般性があるかは疑問です。欧米の事例から構築されたり検証されたりした理論は、アジアの事例によりテストすることにより、その一般性を確かめるのに役立つでしょう。たとえば、日本の陸上自衛隊は、アメリカ海兵隊のような機能をはたす「水陸機動隊」を創設しました。これは自衛隊発足以来、最大の改革(イノベーション)といわれています。この新しい部隊が、どのようなプロセスで構築されたのか、すなわち、文民政治家のイニシアティヴがあったのか、それとも防衛省や自衛隊の幹部によるアイディアで主導されたのかを調べることにより、軍事組織のイノベーションに関する理論を発展させられます。
最後に、日本における軍事イノベーションの社会科学的研究について少し触れながら、この記事を締めくくりたいと思います。残念ながら、我が国では、軍事組織のイノベーションは、あまり熱心に研究されているとは言い難いようです。Google Scholarで「軍事」と「イノベーション」をキーワードにして検索してみると、経営学やマーケッティング論に関連した文献は数多くヒットしますが、軍事イノベーションの文献はかなり少ないです。そのような学術的状況において、日本海軍と海上自衛隊のイノベーションの盛衰を教育と人材の観点から分析した、北川敬三『軍事組織の知的イノベーション―ドクトリンと作戦術の創造力―』(勁草書房、2020年)は貴重な研究でしょう。ローゼン氏と北川氏(海上自衛隊)の研究に共通するところは、平時の軍事組織におけるイノベーションに果たす人材の重要性を指摘している点です。軍事組織の効率性を左右するイノベーションは、国家の安全保障を支える重要な要因です。軍事力を分析する際に、われわれは物質的要因である武器・装備や予算などに目を奪われがちですが、可視化の難しいイノベーションはもっと注目されるべき変数であることは間違いなさそうです。
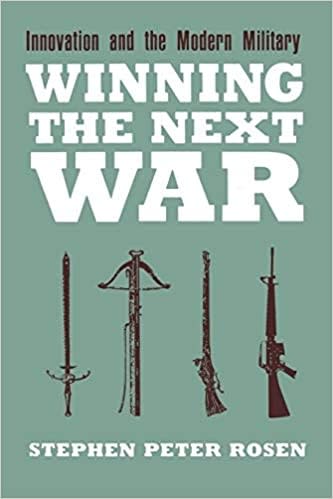
著者のスティーヴン・ローゼン氏(ハーバード大学)は、軍事組織は実戦で自らの作戦行動の成否を確かめられる戦時の方が、イノベーションを達成しやすいと思われがちですが、実は、平時のほうがイノベーションを成功させやすいと主張しています。また、組織は失敗を学習して変革するという通念がありますが、かれは、失敗はイノベーションの必要条件ではなく、それがなくても軍事組織は変われることを主にアメリカ軍の事例で示しています。戦間期にアメリカ軍は航空母艦の開発・運用や揚陸(水陸両用)戦闘、戦後にはヘリコプターによる兵力の機動運用いうイノベーションを成し遂げました。これらはアメリカ軍が戦争に負けた失敗を学習した結果ではありません。そうではなく国際安全保障環境の構造的変化への軍部の認識が、その源泉だということです。アメリカは米西戦争によってフィリピンを植民地化して、グアムに前進基地を築いて、太平洋に進出しました。これによりアメリカは太平洋における軍事大国になりました。他方、第一次世界大戦により、西太平洋のマリアナ諸島等が日本の委任統治領になったことで、その戦略的優位は損なわれました。そこでアメリカ軍は、広大な大洋における戦闘を考えなければならなくなりました。その結果、アメリカ海軍、海兵隊、アメリカ陸軍は、それぞれの新しい戦争における役割を見いだしたということです。
ローゼン氏によれば、平時における軍事イノベーションには、共通パターンがあります。第1に、軍事計画にたずさわる将校は、外部の安全保障環境の変化に直面した際、イノベーションを考えるように促されます。なぜならば、安全保障環境が変化したにもかかわらず、軍事組織がそれに適応しなければ、次の戦争で敗北を喫する恐れがあるからです。すなわち、将校は、将来の戦争がどのように行われ、どうすれば勝てるのかを考えさせられるのです。ここでのポイントは、軍事イノベーションは、仮想敵国に対する研究やインテリジェンスによって達成されるとは限らないことです。アメリカ軍の航空母艦の開発や運用は、外国の勢力に対抗するためのインテリジェンスによって実現したわけではありません。仮想敵国の情報は、矛盾含みで不確実かつあいまいなことがしばしばです。こうした不確実性を乗り越えるために、将校は、「新しい戦勝理論(new theory of victory)」を構築して、それをシミュレーションや訓練・演習により時間をかけて確実なものにしていくのです。これには古い作戦ドクトリンを変更する複雑な組織的な手続きを踏まなければならないために、長い時間がかかります。軍事組織が戦時ではなく平時にイノベーションを成し遂げやすいのは、それを戦術や作戦レベルにおけるドクトリンとして確実に定着させるための十分な時間をとれるからだということです(同書、57-75ページ)。
第2に、軍事組織における昇任人事がイノベーションのカギを握っています。新しい安全保障環境に適応する軍事組織のイノベーションは、将校団の世代交代によって促されますが、それにも長い時間がかかります。アメリカ海軍の空母機動部隊の場合、このイノベーションを志向する上級将校が、その実現に向けた新しい昇任システムを導入しました。この手続きにより、航空術に携わった下級将校たちが上級将校へと昇進していくと共に、空母の建設が海軍において戦艦より優先されるようになり、その運用ドクトリンが策定されていきました。そして最終的には、複数の空母から構成される打撃群が、正式な海軍のドクトリンになったのです。それまでにかかった時間は、約25年ということです。海兵隊による揚陸戦闘というイノベーションも同じく長い時間がかかりました。揚陸・水陸両用戦闘が最初に公式に注目されたのは、1905年のことでした。水陸両用作戦の概念を提唱したのは、海兵隊幕僚のアール・エリス少佐でした。この斬新なコンセプトは、海兵隊司令官に就任したルジューン少将やルーフス・レーン准将により支持されました。海兵隊の水陸両用作戦の演習は、プエルトリコ沖のクレブラ島で行われ、その後、1940年にはノース・カロライナ州のニューリバーで全面的揚陸戦闘演習が実施されました。注目すべきことは、海兵隊がクレブラでの演習で起こりそうな失敗を冒して、それを克服するために、海兵隊学校での訓練により、克服していったことです。これらの訓練が、水陸両用作戦の概念と原則の正しさを証明したのです(野中郁次郎『アメリカ海兵隊―非営利方組織の自己改革―』中央公論新社、1995年、3-52ページ)。海兵隊による揚陸作戦が定着するまでに、約一世代かかったことになります。ヘリコプターによる兵力の機動も、陸軍で作戦行動として実施されるまでには、その着想から長い時間がかかりました。要するに、平時のイノベーションのプロセスは長いのです。イノベーションの実現のために変革された昇任システムにより、将校団は時間をかけて陣容が変化しますが、そのプロセスは下級将校が上層部へ昇りつめる割合と速度によるということです(同書、76-105ページ)。
もちろん、戦時における軍事組織のイノベーションも可能です。たとえば、第二次世界大戦におけるアメリカ軍の戦略爆撃のターゲティング、潜水艦による商船への攻撃などがあります。これらのイノベーションは成功しましたが、平時におけるイノベーションに比べると、軍事組織を劇的に変化させたわけではありません。戦時のイノベーションが小規模になる理由は、戦争を行っている軍事組織がイノベーションに長い時間をかける余裕を持てないことにあります。戦時の経験を学習することにより得た新しい軍事機能を短期間で実践するのは、軍事組織にとって困難な課題なのです。アメリカは、戦略的ターゲッティングにおいて、大戦が終了する数か月まで効果的な目標を設定できませんでした。商船への潜水艦による攻撃の戦略的影響は、戦後になるまで理解されませんでした。つまり、戦時のイノベーションは可能なのですが、それは戦略オプションとしての強固な分析なくして行われざるを得ないのです(同書、109-182ページ)。最後に、大陸間弾道ミサイル(ICBM)のような軍事技術のイノベーションについては、どのように説明できるのでしょうか。このような新しい技術には不確実性が伴います。軍事組織は、こうした不確実性に対して、関連する情報を獲得するとともに、複数の柔軟な選択肢を持ちながら、大量調達を先延ばしにすることで対応します。ICBMのケースでは、アメリカ軍は、巡航ミサイルの選択肢も視野に入れながら、時間をかけて技術イノベーションを進めました。そして、ICBMが巡航ミサイルより、敵の防御を突破する速度と非脆弱性において優れていることが明確になった時点で、アメリカ軍は、それを採用したのです(同書、185-250ページ)。
これらの軍事イノベーションから、ローゼン氏は、いくつかの教訓を引き出しています。第1に、軍事組織の本格的なイノベーションには、長い時間がかかることです。軍事組織は、時間が取れる平時の方が戦時よりイノベーションを進めやすいのです。第2に、軍事イノベーションは予算との関係が薄いことです。戦間期の航空母艦や揚陸戦闘といったイノベーションは、軍備管理協定等の影響もあり、アメリカの軍事予算が制約を受けてた時期に起こりました。予算より重要なのは軍事組織における人材等であると、かれは以下のように指摘しています。
「イノベーションを開始すること、そして、それを戦略的に有用なオプションを提供する段階にもっていくことが達成されたのは、予算が厳しい時であった。カネよりも、有能な人材、時間、そして情報がイノベーションのカギとなる資源であり続けたのだ」(同書、252ページ)。
第3に、敵の能力や行動に関するインテリジェンスは、アメリカ軍のイノベーションにはあまり関係していません。アメリカ軍のイノベーションは、仮想敵国に対応して生まれたのではなく、安全保障環境の変化がもたらしたのです。第4に、文民の政治的指導者や民間の科学者が軍事イノベーションに果たす役割は、小さいということです。軍事ドクトリンに関する先行研究であるバリー・ポーゼン氏の『軍事ドクトリンの源泉』は、バランス・オブ・パワーの変化を受けて文民政治家が軍事組織に介入することにより、イノベーションは達成されやすいと説明していました。しかしながら、ローゼン氏は、そうではないと主張しています。シビリアン・コントロールの制度をとる国家において、戦争の可否や軍事予算を決めるのは文民政治家ですが、かれらは軍事組織のイノベーションにおいては、既に進行している改革を保護したり促進したりする役割を主に担うのです。たとえば、戦間期におけるイギリスの防空におけるレーダーや戦闘機、高射砲の導入の事例では、第一次世界大戦後から空軍が進めてきた防空システム構築を文民政治家が強化したのであり、それは軍事組織のイノベーションの必要条件でも十分条件でもなかったのです。
イギリスの防空システムの構築で重要な役割を果たしたのは、戦闘機兵団司令官のヒュー・ダウディング大将でした。かれは防空におけるレーダーの重要性に早くから気づき、その開発を推進しました。そして、かれは、レーダーによる早期警戒のネットワークと邀撃戦闘機の地上管制をリンクさせて、一元的指揮下で統合運用される防空システムの基礎を作りました。ダウディングは爆撃機にプライオリティをおく空軍の指導層に対して防空における戦闘機の重要性を説き、それを文民の政治指導者が支持することで、戦闘機の生産が優先されることになりました。さらに、ミュンヘン危機において防空システムの不具合を経験した空軍は、多くの権限を下級司令部に委譲して、即応できる体制を整えました(野中郁次郎ほか『戦略の本質』日本経済新聞社、2005年、98-104ページ)。こうしてイギリスは、来るバトル・オブ・ブリテンでドイツ空軍からの爆撃を耐え抜く軍事態勢を築けたのです。要するに、軍事組織では、新しいミッションや任務がシミュレーションを通して規定され、このイノベーションを専門とする将校のための新しいキャリアや昇任パターンが構築されます。このようにして、軍事組織は外部の安全保障環境の変化に適応するのです(同書、251-261ページ)。
ローゼン氏の軍事組織のイノベーションに関する説明は、ポーゼン氏の理論と同じように、国際システムの軍事組織への影響を指摘している点で共通しています。ただし、軍事イノベーションに果たす文民政治家の役割については、意見が異なっています。軍事イノベーションにおける文民の役割に関する競合する仮説のどちらが妥当であるかを判断するには、追加の事例研究による検証が必要でしょう。ローゼン氏の研究は、主にアメリカ軍のイノベーションを対象にしていますので、その理論の適用範囲(scope conditions)は狭いものかもしれません。実際に、かれは、自分の分析はアメリカと戦略文化が異なる他国の軍事組織には当てはまらないかもしれないと示唆しています。他方、ポーゼン氏の仮説も、第二次世界大戦前後のイギリス、フランス、ドイツの事例から引き出されたものなので、どこまで一般性があるかは疑問です。欧米の事例から構築されたり検証されたりした理論は、アジアの事例によりテストすることにより、その一般性を確かめるのに役立つでしょう。たとえば、日本の陸上自衛隊は、アメリカ海兵隊のような機能をはたす「水陸機動隊」を創設しました。これは自衛隊発足以来、最大の改革(イノベーション)といわれています。この新しい部隊が、どのようなプロセスで構築されたのか、すなわち、文民政治家のイニシアティヴがあったのか、それとも防衛省や自衛隊の幹部によるアイディアで主導されたのかを調べることにより、軍事組織のイノベーションに関する理論を発展させられます。
最後に、日本における軍事イノベーションの社会科学的研究について少し触れながら、この記事を締めくくりたいと思います。残念ながら、我が国では、軍事組織のイノベーションは、あまり熱心に研究されているとは言い難いようです。Google Scholarで「軍事」と「イノベーション」をキーワードにして検索してみると、経営学やマーケッティング論に関連した文献は数多くヒットしますが、軍事イノベーションの文献はかなり少ないです。そのような学術的状況において、日本海軍と海上自衛隊のイノベーションの盛衰を教育と人材の観点から分析した、北川敬三『軍事組織の知的イノベーション―ドクトリンと作戦術の創造力―』(勁草書房、2020年)は貴重な研究でしょう。ローゼン氏と北川氏(海上自衛隊)の研究に共通するところは、平時の軍事組織におけるイノベーションに果たす人材の重要性を指摘している点です。軍事組織の効率性を左右するイノベーションは、国家の安全保障を支える重要な要因です。軍事力を分析する際に、われわれは物質的要因である武器・装備や予算などに目を奪われがちですが、可視化の難しいイノベーションはもっと注目されるべき変数であることは間違いなさそうです。