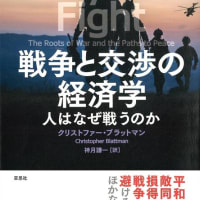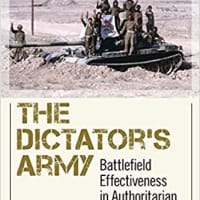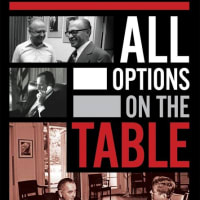1938年の「ミュンヘン宥和」の広く信じられている1つの教訓は、ヒトラーが助長して冒険的行動に走ったのは、チェンバレンがヒトラーの現状打破行動をミュンヘン会談で容認したからだというものです。すなわち、ヒトラーはイギリス(そしてフランス)は「弱腰」であり、不当な要求をつきつけても、それを受け入れるだろうと「学習」した結果、チェコスロバキア全土を占領するとともに、ポーランドに侵攻したというストーリーです。このロジックを裏づけるとされる1つの歴史証拠は、ヒトラーの「われわれの敵は虫けらだ。わたしはかれらをミュンヘンで見た」という発言です。はたしてヒトラーは、イギリスやフランスの指導者はあまりに優柔不断で臆病だから、ドイツに対して戦争で対抗することができないだろうと判断して、東欧へと勢力を拡大したのでしょうか。
この重要な難問に挑んだのが、以前のブログ記事で紹介したダリル・プレス氏(ダートマス大学)です。かれは自著『信ぴょう性の計算―どのように指導者は』軍事的威嚇を評価するのか―(コーネル大学出版局、2005年)の第2章「『宥和危機』―1938-39年におけるドイツによるイギリスとフランスの信ぴょう性の評価―」において、この問題を詳しく分析しています。上記の疑問に対するプレス氏の答えは「ノー」です。確かに、ヒトラーは英仏の軍事的威嚇を一貫して低く評価していましたが、その理由は、イギリスやフランスが、ドイツのラインラント進駐やオーストリア併合、ズデーデン地方の割譲において、実力で阻止しようとせず妥協を重ねたことから、英仏が弱腰であると判断してつけあがったわけではなく、バランス・オブ・パワーや利益の観点から、両国の脅しの信ぴょう性を判断して行動したということです。少し長くなりますが、かれの分析を以下に引用してみましょう。
「同盟国(英仏、引用者)の信ぴょう性についてのドイツの議論と行動は、ほとんど常にパワーと利益についてだった…イギリスやフランスの過去の行為やそれが示すところのイギリスとフランスの将来の行動についてではなかった…これらの議論において、ヒトラーは、これまでのイギリスやフランスの優柔不断さの例を指摘することで、かれの侵略的政策を支えることができたはずだが、かれはパワーと利益に議論の焦点を当てたのだ…ズデーデン危機の後でさえ、ヒトラーはイギリスとフランスの信ぴょう性を主にバランス・オブ・パワーに基礎をおいて評価しつづけた。1939年8月14日、ヒトラーは上級軍事顧問に会い、イギリスはポーランドを防衛するために戦うことはないと納得させた…ヒトラーはその理由をこう説明した。『イギリスは、大きくなり過ぎた自身の帝国ゆえに、過剰な重荷を背負っている…フランスは新兵の補充に事欠いており、装備が貧弱で、あまりに多くの植民地の負担がある…フランスとイギリスがとれる軍事的措置は何か。ジークフリート線への突入はあり得ない。ベルギーとオランダを通過する北方への展開は迅速な勝利をもたらさない。このどれもポーランドの助けにはならないだろう…これらすべての要因はイギリスやフランスが戦争を開始することへの反駁なのである』」(同書、69-71ページ)。
ヒトラーは、ドイツ参謀本部の上級将校たちとは異なり、イギリスやフランスの軍事力について、一貫して低く評価していました。たとえば、ミュンヘン危機において、ドイツの将軍たちは、ドイツのチェコスロバキアへの侵略がフランスとイギリスの軍事介入を招き、ドイツを敗北へと追い込むことを深く懸念していました。他方、ヒトラーはこうした見方に反対でした。ドイツはチェコスロバキアを一撃で倒して既成事実化するだろうから、こうした迅速な勝利は戦争の拡大を防ぐことになると、かれは考えていました。こうしたバランス・オブ・パワーの楽観的な計算こそが、ヒトラーを大胆な冒険的拡張行動に走らせたのです。要するに、抑止の威嚇の信ぴょう性は、相手国が過去に対決姿勢で臨んできたのか弱腰だったのかといった行動に対する評価ではなく、バランス・オブ・パワーの認識に左右されるということです。
それでは、ヒトラーの「虫けら」発言は、どのように解釈すればよいのでしょうか。歴史資料は複数の解釈ができるために、「動かぬ証拠」として扱うことは難しいものです。これはヒトラーがイギリスやフランスの指導者を見下していた証拠になるのかもしれませんが、プレス氏は、これは、かれの主張の中のささいな一部分にすぎないとみなしています。ヒトラーの「虫けら」発言は、ソ連の意図と行動を分析する議論の間に挟まれた、1つの文章に過ぎないということです(同書、73-74ページ)。他方、国際関係研究の重鎮であるアレキサンダー・ジョージ氏とドイツ政治外交史の第一人者であったゴードン・クレイグ氏は、『軍事力と現代外交』(有斐閣、1997年)において、イギリスやフランスの宥和政策がヒトラーを大胆にしたことを示唆しながら、「虫けら」発言に触れています(『軍事力と現代外交』84-85ページ)。確かに、イギリスとフランスの宥和的姿勢が、ヒトラーの行動に全く影響しなかったとは言えないでしょうが、因果効果の相対的な重みをつけるとすれば、バランス・オブ・パワーに分があるように、わたしは思います。
最後に、プレス氏の宥和政策に対する評価を紹介して、この記事を締めくくることにします。かれはこんな見解を述べています。
「もし引き下がったことがイギリスやフランスの信ぴょう性を傷つけていなかったとすると、宥和はナチス・ドイツとの取引にとって好ましい政策だったのだろうか。答えはノーである。宥和が同盟側の信ぴょう性を粉砕したわけではないが、それは恐ろしく高くついた。ドイツを宥和することは、国内の反対勢力に対するヒトラーの立場を強め、かれの政策はドイツを破滅的な戦争へと導くと予想した者たちの立場を弱めてしまった…さらに、宥和は、ドイツがパワーの頂点に達するまで戦争を引き延ばしてしまったことにより、高くついた。ズデーデン危機の間、1938年秋までならば、ドイツは連合国により打ち負すことができたであろう」(同書、77ページ)。
プレス氏の1つの目の論点は、ウィンストン・チャーチルがチェンバレン首相の対独宥和を批判した論拠に重なります(冨田浩司『危機の指導者チャーチル』新潮社、2011年、176ページ)。2つ目の論点については、先のブログ記事で紹介したユアン・コーン氏の「ミュンヘン危機」に関する反実仮想分析と部分的に一致するところがありそうです。いずれにしても、国際関係研究の主要ないくつかの分析は、1930年代におけるイギリスやフランスのドイツに対する宥和政策が間違いだったことを示唆しているといえそうです。
追記:ランドール・シュウェラー氏(オハイオ州立だ学)は、「ミュンヘンのアナロジー…は、それを採用する人を揶揄する意味で使われる。ミュンヘン会談と第二次世界大戦に関してナイーブだったというのが、その中心的な主張であるが、ヒトラーほど邪悪で宥和できないような指導者はほとんど存在しないため、過度に使用され不適切な例えになっている。こうして、このアナロジーは指導者をタカ派で過度な競争的政策へと誤導したり、そうした政策を正当化するために意図して使われて、大衆を誤解させるのだ」と注意を促しています。ジェフリー・レコード氏(航空戦大学)は、ヒトラーは歴史に類を見ない戦争に執着する抑止できない「外れ値」のような存在だったので、スターリンや毛沢東、サダム・フセインといった独裁者でさえ比較の対象にならず、国家安全保障の議論において、政策エリートは「ミュンヘンの教訓」を持ち出すのをやめるべきだと主張しています("Retiring Hitler and “Appeasement” from the National Security Debate." The US Army War College Quarterly: Parameters, Vol. 38, No. 2, Summer 2008, pp. 91-101)。
このような「ヒトラー例外説」は、デーヴィッド・ウェルチ氏(ウォータールー大学)もおおむね支持しています。かれは「ヒトラーは戦争を欲し、その見込みにスリルを見出し、リスクを取ることを楽しみ、そして明らかに侵攻と支配から大きな満足感を得ていた」と分析しています(『苦渋の選択―対外政策変更に関する理論』田所昌幸監訳、千倉書房、2016年〔原著2005年〕、97ページ)。歴史家のD.C.ワット氏も「彼(ヒトラー)を抑止できるものは何もなかった」と言っています(『第二次世界大戦はこうして始まった(下)』河出書房新社、1995年〔原著1989年〕427ページ)。このブログで以前に紹介したジョン・ミューラー氏(オハイオ州立大学)も、同じような見方をしています。
この重要な難問に挑んだのが、以前のブログ記事で紹介したダリル・プレス氏(ダートマス大学)です。かれは自著『信ぴょう性の計算―どのように指導者は』軍事的威嚇を評価するのか―(コーネル大学出版局、2005年)の第2章「『宥和危機』―1938-39年におけるドイツによるイギリスとフランスの信ぴょう性の評価―」において、この問題を詳しく分析しています。上記の疑問に対するプレス氏の答えは「ノー」です。確かに、ヒトラーは英仏の軍事的威嚇を一貫して低く評価していましたが、その理由は、イギリスやフランスが、ドイツのラインラント進駐やオーストリア併合、ズデーデン地方の割譲において、実力で阻止しようとせず妥協を重ねたことから、英仏が弱腰であると判断してつけあがったわけではなく、バランス・オブ・パワーや利益の観点から、両国の脅しの信ぴょう性を判断して行動したということです。少し長くなりますが、かれの分析を以下に引用してみましょう。
「同盟国(英仏、引用者)の信ぴょう性についてのドイツの議論と行動は、ほとんど常にパワーと利益についてだった…イギリスやフランスの過去の行為やそれが示すところのイギリスとフランスの将来の行動についてではなかった…これらの議論において、ヒトラーは、これまでのイギリスやフランスの優柔不断さの例を指摘することで、かれの侵略的政策を支えることができたはずだが、かれはパワーと利益に議論の焦点を当てたのだ…ズデーデン危機の後でさえ、ヒトラーはイギリスとフランスの信ぴょう性を主にバランス・オブ・パワーに基礎をおいて評価しつづけた。1939年8月14日、ヒトラーは上級軍事顧問に会い、イギリスはポーランドを防衛するために戦うことはないと納得させた…ヒトラーはその理由をこう説明した。『イギリスは、大きくなり過ぎた自身の帝国ゆえに、過剰な重荷を背負っている…フランスは新兵の補充に事欠いており、装備が貧弱で、あまりに多くの植民地の負担がある…フランスとイギリスがとれる軍事的措置は何か。ジークフリート線への突入はあり得ない。ベルギーとオランダを通過する北方への展開は迅速な勝利をもたらさない。このどれもポーランドの助けにはならないだろう…これらすべての要因はイギリスやフランスが戦争を開始することへの反駁なのである』」(同書、69-71ページ)。
ヒトラーは、ドイツ参謀本部の上級将校たちとは異なり、イギリスやフランスの軍事力について、一貫して低く評価していました。たとえば、ミュンヘン危機において、ドイツの将軍たちは、ドイツのチェコスロバキアへの侵略がフランスとイギリスの軍事介入を招き、ドイツを敗北へと追い込むことを深く懸念していました。他方、ヒトラーはこうした見方に反対でした。ドイツはチェコスロバキアを一撃で倒して既成事実化するだろうから、こうした迅速な勝利は戦争の拡大を防ぐことになると、かれは考えていました。こうしたバランス・オブ・パワーの楽観的な計算こそが、ヒトラーを大胆な冒険的拡張行動に走らせたのです。要するに、抑止の威嚇の信ぴょう性は、相手国が過去に対決姿勢で臨んできたのか弱腰だったのかといった行動に対する評価ではなく、バランス・オブ・パワーの認識に左右されるということです。
それでは、ヒトラーの「虫けら」発言は、どのように解釈すればよいのでしょうか。歴史資料は複数の解釈ができるために、「動かぬ証拠」として扱うことは難しいものです。これはヒトラーがイギリスやフランスの指導者を見下していた証拠になるのかもしれませんが、プレス氏は、これは、かれの主張の中のささいな一部分にすぎないとみなしています。ヒトラーの「虫けら」発言は、ソ連の意図と行動を分析する議論の間に挟まれた、1つの文章に過ぎないということです(同書、73-74ページ)。他方、国際関係研究の重鎮であるアレキサンダー・ジョージ氏とドイツ政治外交史の第一人者であったゴードン・クレイグ氏は、『軍事力と現代外交』(有斐閣、1997年)において、イギリスやフランスの宥和政策がヒトラーを大胆にしたことを示唆しながら、「虫けら」発言に触れています(『軍事力と現代外交』84-85ページ)。確かに、イギリスとフランスの宥和的姿勢が、ヒトラーの行動に全く影響しなかったとは言えないでしょうが、因果効果の相対的な重みをつけるとすれば、バランス・オブ・パワーに分があるように、わたしは思います。
最後に、プレス氏の宥和政策に対する評価を紹介して、この記事を締めくくることにします。かれはこんな見解を述べています。
「もし引き下がったことがイギリスやフランスの信ぴょう性を傷つけていなかったとすると、宥和はナチス・ドイツとの取引にとって好ましい政策だったのだろうか。答えはノーである。宥和が同盟側の信ぴょう性を粉砕したわけではないが、それは恐ろしく高くついた。ドイツを宥和することは、国内の反対勢力に対するヒトラーの立場を強め、かれの政策はドイツを破滅的な戦争へと導くと予想した者たちの立場を弱めてしまった…さらに、宥和は、ドイツがパワーの頂点に達するまで戦争を引き延ばしてしまったことにより、高くついた。ズデーデン危機の間、1938年秋までならば、ドイツは連合国により打ち負すことができたであろう」(同書、77ページ)。
プレス氏の1つの目の論点は、ウィンストン・チャーチルがチェンバレン首相の対独宥和を批判した論拠に重なります(冨田浩司『危機の指導者チャーチル』新潮社、2011年、176ページ)。2つ目の論点については、先のブログ記事で紹介したユアン・コーン氏の「ミュンヘン危機」に関する反実仮想分析と部分的に一致するところがありそうです。いずれにしても、国際関係研究の主要ないくつかの分析は、1930年代におけるイギリスやフランスのドイツに対する宥和政策が間違いだったことを示唆しているといえそうです。
追記:ランドール・シュウェラー氏(オハイオ州立だ学)は、「ミュンヘンのアナロジー…は、それを採用する人を揶揄する意味で使われる。ミュンヘン会談と第二次世界大戦に関してナイーブだったというのが、その中心的な主張であるが、ヒトラーほど邪悪で宥和できないような指導者はほとんど存在しないため、過度に使用され不適切な例えになっている。こうして、このアナロジーは指導者をタカ派で過度な競争的政策へと誤導したり、そうした政策を正当化するために意図して使われて、大衆を誤解させるのだ」と注意を促しています。ジェフリー・レコード氏(航空戦大学)は、ヒトラーは歴史に類を見ない戦争に執着する抑止できない「外れ値」のような存在だったので、スターリンや毛沢東、サダム・フセインといった独裁者でさえ比較の対象にならず、国家安全保障の議論において、政策エリートは「ミュンヘンの教訓」を持ち出すのをやめるべきだと主張しています("Retiring Hitler and “Appeasement” from the National Security Debate." The US Army War College Quarterly: Parameters, Vol. 38, No. 2, Summer 2008, pp. 91-101)。
このような「ヒトラー例外説」は、デーヴィッド・ウェルチ氏(ウォータールー大学)もおおむね支持しています。かれは「ヒトラーは戦争を欲し、その見込みにスリルを見出し、リスクを取ることを楽しみ、そして明らかに侵攻と支配から大きな満足感を得ていた」と分析しています(『苦渋の選択―対外政策変更に関する理論』田所昌幸監訳、千倉書房、2016年〔原著2005年〕、97ページ)。歴史家のD.C.ワット氏も「彼(ヒトラー)を抑止できるものは何もなかった」と言っています(『第二次世界大戦はこうして始まった(下)』河出書房新社、1995年〔原著1989年〕427ページ)。このブログで以前に紹介したジョン・ミューラー氏(オハイオ州立大学)も、同じような見方をしています。