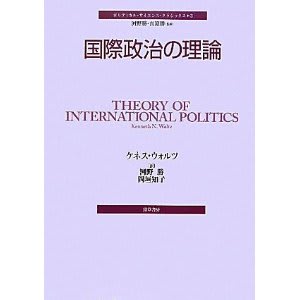リチャード・ドーキンス氏は、生物学者としてのみならず、科学の啓蒙者としても有名です。今回のブログのテーマである、科学教育の必要性についても、説得力のある主張を展開しています。
なぜ文系の学生も科学を学ぶべきなのか?その1つの理由は、ドーキンス氏によれば、「大人の環境に適応して生き抜くためだ」ということです。かれは、著書Unweaving the Rainbow, New York: Penguin, 1998(福岡伸一訳『虹の解体』早川書房、2001年)で、こう述べています。
「子ども時代は多くの人にとって、確実で安心できる失われた理想郷であり、一種の天国である。…〔他方〕大人の世界は冷たく虚しいようなものかもしれない。…きちんと成長しないということは、『幼虫』の性質を(それは長所だった)子ども時代から(それが短所になる)大人時代になるまで持ち続けることである。子どもの頃は何でも信じる性質が役に立った。…しかし時が経っても幼虫の性質から抜け出せなければ、〔インチキ家やだまそうとする者の〕格好の餌食となってしまう」(原著、142-143ページ、邦訳、184-195ページ〔〕内は引用者)。

では、どうすればよいのでしょうか?大人の世界で生きるのに必要なのが、「科学的思考」や「批判的思考」であり、しかも、それは意識して学ばないと、つまり教育しないと身につかないということです。再び、ドーキンス氏の主張に耳を傾けてみましょう。
「批判する能力が後に育つとすれば、それは子ども時代の傾向から出てくることはない。むしろ子ども時代の傾向に反するものなのだ。…われわれは、子どもの何でも信じる性質を、大人の科学に基づく建設的な懐疑主義に替えなければならない」(原著、142-143ページ、邦訳、195-196ページ)。
科学の批判的思考は、大学に入学したばかりの、多くの文系の学生のにとっては、自らの世界観を覆すものかもしれません(とりわけ、「科学的」リアリズムや進化生物学の唯物論など)。ですから、多くの若い学生が、科学を近寄りがたく受け入れがたいものとして遠ざけるのも分かる気がします。私自身も、「心やさしい」若者が、「科学」に対して、『虹の解体』の序文の冒頭にあるような反応を示すことを経験していますから。
しかし、そうした反応は、科学の一面だけを見ていることに由来するのではないでしょうか?ドーキンス氏が強調するように、科学は、われわれの「好奇心(the sense of wonder)」を喚起したり満たしたりしてくれるものでもあります。社会科学でも自然科学でも、それは同じでしょう。もちろん、「国際学」もそうだと私は言いたいのですが、そうは言っても、ピンと来ないかもしれません。そこで、私の言語による説明能力不足を補うために、Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (New York: W. W. Norton, 1997). ジャレド・ダイアモンド、倉骨彰訳『銃・病原菌・鉄』草思社、2012年をお勧めしたいと思います。

この本を読んでいただければ、このブログで言いたいことがスッキリと理解して頂けるでしょう。
なぜ文系の学生も科学を学ぶべきなのか?その1つの理由は、ドーキンス氏によれば、「大人の環境に適応して生き抜くためだ」ということです。かれは、著書Unweaving the Rainbow, New York: Penguin, 1998(福岡伸一訳『虹の解体』早川書房、2001年)で、こう述べています。
「子ども時代は多くの人にとって、確実で安心できる失われた理想郷であり、一種の天国である。…〔他方〕大人の世界は冷たく虚しいようなものかもしれない。…きちんと成長しないということは、『幼虫』の性質を(それは長所だった)子ども時代から(それが短所になる)大人時代になるまで持ち続けることである。子どもの頃は何でも信じる性質が役に立った。…しかし時が経っても幼虫の性質から抜け出せなければ、〔インチキ家やだまそうとする者の〕格好の餌食となってしまう」(原著、142-143ページ、邦訳、184-195ページ〔〕内は引用者)。

では、どうすればよいのでしょうか?大人の世界で生きるのに必要なのが、「科学的思考」や「批判的思考」であり、しかも、それは意識して学ばないと、つまり教育しないと身につかないということです。再び、ドーキンス氏の主張に耳を傾けてみましょう。
「批判する能力が後に育つとすれば、それは子ども時代の傾向から出てくることはない。むしろ子ども時代の傾向に反するものなのだ。…われわれは、子どもの何でも信じる性質を、大人の科学に基づく建設的な懐疑主義に替えなければならない」(原著、142-143ページ、邦訳、195-196ページ)。
科学の批判的思考は、大学に入学したばかりの、多くの文系の学生のにとっては、自らの世界観を覆すものかもしれません(とりわけ、「科学的」リアリズムや進化生物学の唯物論など)。ですから、多くの若い学生が、科学を近寄りがたく受け入れがたいものとして遠ざけるのも分かる気がします。私自身も、「心やさしい」若者が、「科学」に対して、『虹の解体』の序文の冒頭にあるような反応を示すことを経験していますから。
しかし、そうした反応は、科学の一面だけを見ていることに由来するのではないでしょうか?ドーキンス氏が強調するように、科学は、われわれの「好奇心(the sense of wonder)」を喚起したり満たしたりしてくれるものでもあります。社会科学でも自然科学でも、それは同じでしょう。もちろん、「国際学」もそうだと私は言いたいのですが、そうは言っても、ピンと来ないかもしれません。そこで、私の言語による説明能力不足を補うために、Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (New York: W. W. Norton, 1997). ジャレド・ダイアモンド、倉骨彰訳『銃・病原菌・鉄』草思社、2012年をお勧めしたいと思います。

この本を読んでいただければ、このブログで言いたいことがスッキリと理解して頂けるでしょう。