「冷戦」は、過去の国際政治の出来事となりました。冷戦が終了したのは、もう30年以上前のことになります。アメリカのブッシュ大統領とソ連のゴルバチョフ書記長(後に大統領)がマルタ島の会談において、「冷戦の終焉」を宣言した1989年にさかのぼります。そして、その2年後、冷戦の片方の主役だったソ連そのものは崩壊してしまいました。ソ連なき後、アメリカは国際システムにおける単独の「大国」となり、世界は「単極構造」になりました。こうした歴史証拠は、アメリカがソ連に冷戦で「勝利」したことを示唆しています。国際関係論の標準的な教科書も、このような見方を紹介しています。テキストとして高い評価を得ているジョセフ・ナイ氏(ハーバード大学)とデイヴィッド・ウエルチ氏(ウォータールー大学)による『国際紛争—歴史と理論―(原書第10版)』(田中明彦/村田晃嗣訳、有斐閣、2017年)によれば、直接的な言い方ではありませんが、以下のような説明を記述しています。
「なぜ冷戦は終結したのか?まず、(アメリカの)封じ込めが成功したという見方が可能である。第二次世界大戦の直後にケナンは、アメリカがソ連の拡張を阻止できれば、そのイデオロギーの影響力が強まる見込みはなく、ソ連の共産主義は次第に限界を迎えるであろう、と主張した…大局的に見ればケナンは正しかった」(上記書、209ページ)。
アメリカが冷戦に勝利したという見方は、定量的分析でも示されています。ブルース・ブエノ・デ・メスキータ氏(ニューヨーク大学)によれば、「期待効用モデル」によるシミュレーションは、アメリカが高い確率でソ連に冷戦で平和的に勝つと「予測」しており、実際にそうなったということです(Bruce Bueno de Mesquita, "The End of the Cold War: Predicting an Emergent Property," Journal of Conflict Resolution, Vol. 42, No. 2, April 1998, pp. 131-155)。歴史学のあるテキストは、「東ヨーロッパ諸国の自由化・民主化、西ドイツの東ドイツ吸収によるドイツ統一と統一ドイツのNATO帰属は、いずれもアメリカの要求に沿った結果であった。その意味でアメリカは確かに冷戦に勝利を収めた」と解説しています(佐々木卓也『冷戦』有斐閣、2011年、188ページ)。
冷戦の「勝者」はアメリカであるというのが、いわばオーソドックスな「通説」となっているのです。他方、この一般的な学説に強く異議を唱える大規模な研究があります。その1つが、国際関係研究の重鎮であるリチャード・ルボウ氏(キングスカレッジ)とジャニス・グロス・ステイン氏(トロント大学)が著した労作『われわれは皆、冷戦に敗北したのだ(We All Lost the Cold War)』(プリンストン大学出版局、1994年)です。同書は、500ページ以上の大著です。注だけでも150ページ以上あります(これだけで単著になりそうです)。両氏が、膨大な資料を駆使して、本書を執筆したことが分かります。
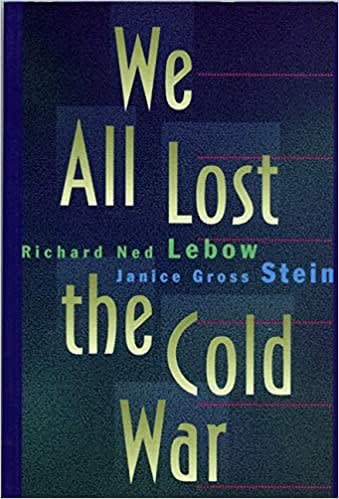
本書の主張は明確です。冷戦中にアメリカとソ連がとった威嚇に依拠した「抑止」や「強制」の戦略は、無駄に冷戦を長引かせた。また、アメリカがソ連を屈服させたというもっともらしい主張も、実は証拠に乏しい。したがって、アメリカが冷戦でソ連に勝ったという説明は間違いであり、両国が「再保障(reassurance)」戦略を賢く選択していたら、冷戦はもっと早く終わっただろう。その意味で、アメリカもソ連も冷戦の「敗者」なのだ、ということです。こうしたかれらの主張は、以前にこのブログで紹介した、ロバート・ジャーヴィス氏も交えた共同研究『心理学と抑止』の延長線上にあります。
ルボウ氏とステイン氏は、1962年のキューバ危機と1973年の中東における10月戦争(第4次中東戦争)に関して、冷戦前後に解禁された旧ソ連の機密文書や要人へのインタヴューを活用して徹底的な事例研究を行っています。そして、こうした緻密で詳細な事例の調査から、米ソの抑止政策や強要政策が、双方のケースにおいて所期の目的を達成できず、むしろ裏目にでてしまったことを丹念に実証しています。
キューバ危機の事例からみていきましょう。アメリカは、自国の勢力圏とみなしている西半球におけるキューバに社会主義政権が誕生したことをに反発して、同政権を倒すための「ピッグス湾侵攻作戦」を行いましたが、これは無残な失敗に終わりました。ソ連が、この失敗をアメリカの「弱さ」とみなして攻勢にでてくるのを恐れたケネディ大統領は、断固とした決意を示すことが不可欠だと考えました。かれはソ連が攻撃的兵器をキューバに導入することは受け入れられないことを明確に強く表明しました。また、ベルリン危機に対処するため、アメリカは西ドイツの米軍も急速に強化しました。さらに、アメリカは戦略核戦力を増強するとともに、ソ連の隣国であるトルコにジュピターミサイルも配備しました。ケネディは、一連のアメリカの措置がソ連に対する防御的で慎重なものだと考えていました。他方、ソ連は、こうしたアメリカの「抑止」戦略がソ連の脆弱性を悪化させるものと受け取りました。
アメリカの「威嚇」を受けたソ連は、キューバに核ミサイル基地を建設することで対応しました。ソ連は、自らの脆弱性を挽回するために、核兵器をキューバに導入したのです。フルシチョフ首相は、アメリカがキューバにおけるソ連の核ミサイルを受け入れるだろうと楽観視していました。なぜなら、ソ連はアメリカがトルコで行ったのと同じことをキューバでしているに過ぎないと、自らを正当化したからです。こうしてアメリカの対ソ抑止政策は失敗に終わりました。アメリカの抑止はソ連の攻勢を阻止すのではなく、かえってソ連を挑発してしまったのです。
ソ連のキューバにおける核ミサイル導入に対して、アメリカは威嚇による強制外交で応じました。ケネディ政権は、優勢な戦略核戦力とカリブ海における通常戦力の優位を利用して、キューバに向かうソ連艦船に対して「海上封鎖」を実施したのです。こうしたアメリカの軍事的措置は、キューバへの侵攻や空爆といった直接の軍事行動をほのめかすものでもありました。この危機が米ソの戦争へとエスカレートすることを恐れたフルシチョフは、アメリカのキューバ不侵攻の約束と引き換えに、キューバから核ミサイルを撤去することに同意しました。さらにかれは、トルコからジュピターミサイルを撤去することを追加でアメリカに要求しました。国家安全保障会議エクスコムにおけるアメリカの指導者の議論は、新たなソ連の要求への対応をめぐって紛糾しましたが、ケネディはキューバ不侵攻を約束するとともに、ソ連のドブルイニン駐米大使を通じて、トルコのミサイル撤去をフルシチョフと密約しました。それでもソ連が納得しない場合、ケネディはジュピター撤去を公にすることも覚悟していました。こうして米ソが相互に妥協することにより、核戦争の危険性を孕んだキューバ危機は収束したのです。
キューバ危機の分析から、ルボウ氏とステイン氏は、アメリカの強い決意がバーゲニングパワーとして、ソ連の妥協を引き出したという通説を否定します。そうではなく、武力行使のインセンティヴを削減する「再保障」が、危機の収束において役割を果たしたのです。かれらは以下のように主張しています。
「(アメリカの)威嚇と軍事行動を通じた決意の示威と…危機の結果の間の因果的関連は、一般に考えられているほど強くないし直線的でもない…停止・臨検の発表後、フルシチョフはアメリカによるキューバへの攻撃の恐れを強くした。攻撃を防止するために、かれは妥協的なメッセージをケネディに送った…フルシチョフは…止めることのできないエスカレーション…を懸念(するあまり)、ケネディが空爆や侵攻のどちらにも、前にもまして反対するようになっていたことを認識していなかった…このミサイル危機の『隠れた物語』は、再保障が(米ソ)相互の妥協と危機の解決を促進する重要な役割を果たしていたことだ…フルシチョフの視点からすれば、再保障の最も重要な形態は、ケネディが…キューバにおけるミサイル発見を利用して、カストロ(政権)を転覆することでソ連に恥をかかせる行動をとらなかったことだ。ケネディの自制はフルシチョフの恐怖をやわらげた…フルシチョフはアメリカの決意を甘く見てキューバにミサイルを送ったのでもなければ、アメリカの決意を注視してミサイルを撤去したのでもない。ミサイルは脆弱性と恐怖を克服するために配備されたのであり、部分的には、アメリカの再保障がそれらの脆弱性や恐怖を緩和したから取り去らわれたのだ」(上記書、308-309、318ページ)。
そして、かれらは1つの興味深い反実仮想を披露しています。すなわち、「もしケネディが1963年11月に暗殺されず、フルシチョフが1964年10月に職務から追放されていなければ、冷戦は実際より、もっと早く終わっていただろう」(上記書、145ページ)ということです。
10月戦争の事例をみてみましょう。エジプトとシリアは、イスラエルに奇襲攻撃を行いました。当時、イスラエルはアラブ諸国に対して、軍事力とくに空軍力で圧倒的に優勢だったので、同諸国からの戦争は抑止できると考えていました。また、エジプトやシリアの同盟国だったソ連も、これらの国家がイスラエルに戦争しても負けることが見込まれるので、両国に自制を促していました。エジプトのサダト大統領は、六日戦争(第3次中東戦争)で失ったシナイ半島などの領土を外交で取り戻すことに「絶望」していました。そこでサダトは、戦略的に不利であることを承知のうえで、シリアと共謀してイスラエルとの戦争を選んだのです。不意を突かれたイスラエルは、エジプトとシリアの攻撃に対して、緒戦では劣勢を強いられました。しかしながら、戦局は軍事力でまさるイスラエルの優勢に傾き、エジプトやシリアは追い詰められました。ソ連は中東の主要国であるエジプトが壊滅的な敗北を喫するのを恐れました。そこでソ連は、イスラエルの同盟国であるアメリカに対して強制外交を行いました。すなわち、ソ連はイスラエルが停戦に応じなければ、この戦争に単独で軍事介入するとアメリカを脅したのです。ソ連は、こうした威嚇により、アメリカがイスラエルに対して停戦受諾を強いることに期待したのです。これに対して、アメリカはソ連の軍事介入を抑止するために、「デフコンⅢ(Defense Condition Ⅲ)」を全世界の米軍に発令しました。アメリカの通常戦力ならびに核戦力は高度な警戒態勢に入ったのです。
ソ連の強制政策は裏目にでました。そもそもアメリカは戦後の中東和平交渉で主導権を握るために、エジプトの決定的な敗北を望んでいませんでした。エジプトがアメリカの同盟国であるイスラエルに完敗してしまえば、同国はますますソ連を頼るようになってしまいます。そうなると、アメリカが単独で中東和平交渉を進めることは難しくなります。こうした戦争の結末を避けるには、イスラエルが限定的な勝利を収めるとともに、エジプトに余力を残させることが必要だとアメリカの指導者たちは判断していたのです。こうした戦略をとるキッシンジャー国務長官は、ソ連による単独介入の脅しを受ける前から、イスラエルに停戦を促していました。しかしながら、戦争を有利に進めるイスラエルは、停戦よりも継戦を選好していたので、なかなか戦闘をやめようとしなかったのです。このような最中に、ソ連はアメリカに単独の軍事介入を示唆してきたのです。アメリカは、イスラエルに停戦の受け入れをより強く求めてしまうと、ソ連に屈したとみなされることになるのを恐れました。そこで、アメリカは外交上の「評判」を落とさないために、イスラエルへの停戦受け入れの働きかけを中断してしまったのです。
アメリカの抑止行動も見当違いでした。アメリカはソ連に中東への軍事侵攻を思いとどまらせるために、米軍に軍事アラートをかけました。これによりソ連が引き下がることに期待したのです。ところが、ソ連の指導者は、アメリカのアラートに驚き、そして怒りさえ覚えました。なぜなら、ブレジネフ書記長をはじめとする政治局のメンバーたちは、ソ連軍を中東に派遣するつもりは、戦争開始当初からなかったからです。ソ連の単独介入の脅しは、たんなるブラフだったのです。つまり、アメリカのソ連に対する威嚇は、まったく意味がなかったということです。その後、10月戦争は急展開を見せて収束しました。エジプトが停戦を監視する国連平和維持軍の受け入れを表明したことで、イスラエルそして米ソもこれに同意しました。同時に、アメリカはアラート態勢を解除しました。こうして米ソの核戦争の危機を孕んだ10月戦争は終わったのです。
アメリカとソ連が威嚇にもとづく抑止や強制の政策を実行したことは、結局のところ、両国の対立を長引かせるだけだったと、ルボウ氏やステイン氏は推論しています。かれらの主張は、要約すれば以下の通りです。
「ワシントンとモスクワにおいて、この対立はデタントに反対する立場を強めてしまった…1973年10月の危機は、デタント終焉の始まり、そして10年以上続く米ソ間の第二次冷戦の開始として刻印されたのだ…影響力のあるアメリカの政治指導者やコメンテーターは…ソ連が拡張主義や攻撃的意図によって動機づけられていると主張した。かれらはソ連に裏切られたと断固言い張った…ブレジネフはアメリカ軍の世界規模でのアラートを予期していなかった…ソ連におけるデタントの反対論も大きくなった…怒りと失望に包まれたニクソン、キッシンジャー、ブレジネフは、自国においてデタントを支持することをますます控えてしまったのだ…1973年において、抑止や強制は解決策ではなく問題の一部分であった」(上記書、287-288、320ページ)。
10月危機の頃のアメリカとソ連は、デタントで協調的な関係を築こうとしていました。にもかかわらず、米ソは強制外交や抑止政策で相手を威嚇してしまったために、こうした和解的な雰囲気を自ら壊してしまい、無駄に冷戦を長引かせてしまったということです。
大国政治における再保障を重視するルボウ氏とステイン氏は、冷戦終結の「通説」にも懐疑的です。かれらは、アメリカとの競争で経済を弱体化したソ連が、アメリカに屈した結果、冷戦が終わったという学説に反対しています。第1に、ソ連の国家歳入に占める軍事費の割合は、スターリン時代からゴルバチョフ政権まで、継続して約25%であり、それが削減されたのは、ようやく1989年になってのことです。アメリカのレーガン政権の軍拡にソ連が付いていけなくなったのであれば、ゴルバチョフは経済を立て直そうとして軍事費を削減するはずなのに、そうしなかったのは「通説」に合致しないということです(上記書、372ページ)。第2に、ソ連の指導者が国内政治経済の改革に着手して、対外政策で劇的な妥協(アフガニスタンからの撤退や軍縮の提案など)を実行したことが、冷戦を終焉に導いた重要な要因だと指摘されています。ゴルバチョフの協調的な対外政策が、アメリカの指導者に安心感を与えた結果、米ソ関係は劇的に改善されたのです(上記書、あとがき)。「対立は攻撃的反応を最も誘発しやすい…和解は最も互恵的になりやすい…もしアメリカの政策が、ソ連の指導者が改革にコミットした際に何らかのインパクトを与えたとするなら、それは抑止戦略が冷戦をおそらく長引かせてしまったのだ…抑止戦略は…冷戦期における超大国の関係にとって、広範囲での否定的な成り行きだったのだ」(上記書、376ページ)というのが、かれらの結論なのです。
『われわれは皆、冷戦に敗北したのだ』は、主に冷戦期における米ソ間の2つの危機を膨大な資料に基づいて実証しています。それぞれの危機の分析だけで数百ページの文量になります。一つ一つの危機の議論だけでも、立派な単著になるくらい充実しています。そして、ルボウ氏とステイン氏は、2つの危機から重要な教訓を引き出しています。すなわち、威嚇に依拠した抑止政策や強制外交は「自己充足的予言」、すなわち、これらの政策が避けようとしていた事態をかえって招いてしまうために、米ソの対立を無用に悪化させたということです。たとえば、キューバ危機において、アメリカは避けたかったソ連のキューバへの核ミサイル導入を抑止の威嚇で招来してしまいました。10月戦争において、ソ連は避けたかったアメリカのイスラエルへの停戦受け入れの圧力の中断を強制外交の威嚇により実現してしまいました。もし米ソが、威嚇の逆説的な効果に気づいて、賢明な妥協的政策をとっていれば、冷戦はもっと早く終わっていただろうと、かれらは示唆しています。
わたしは『われわれは皆、冷戦に敗北したのだ』を読んで、ルボウ氏とステイン氏の2つの危機に関する実証分析に圧倒されました。まるで歴史小説を読んでいるかのように、どんどん本書に引き込まれていきました。かれらの筆致は圧倒的です。ただし、ここで述べられている研究内容に、全面的に賛成できるかと問われれば、そうではありません。第1に、冷戦終結の「通説」を支持する歴史証拠を見つけるのは、難しいことではありません。ゴルバチョフは、1986年10月の政治局の会合で「(アメリカから)再び軍拡競争を押し付けられたら、われわれは敗北するだろう」と指摘していました(岡田美保「ソ連の弱さの自覚と対外政策の転換―INF交渉の再検討―」『国際政治』第157号、2009年9月、20ページに引用)。また、かれはソ連の軍事費を削減する必要性を痛切に感じていました。ゴルバチョフは1988年2月の政治局会議において、こう発言してます。「今、明らかなことは、大幅な軍事支出の削減なくして、われわれはペレストロイカが取り組む諸問題を解決することができないのだ」(William C. Wohlforth, "Realism and the End of the Cold War," International Security, Vol. 19, No. 3, Winter 1994/95, p. 112に引用)。そして、ソ連は翌年の1989年、実際に軍事支出を低下させました。こうしたエビデンスは、オーソドックスな冷戦終結の見方を裏づけるものでしょう。
第2に、『われわれは皆、冷戦に敗北したのだ』が導いた「理論」は、どこまで一般性を持ちうるのでしょうか。たとえば、かれらは冷戦の終結過程で、米ソが相互に「再保障(安心供与)」政策をとったことが重要だと指摘する反面、レーガン政権の「対ソ強硬策」はソ連の行動インパクトを与えなかったと主張しています。しかしながら、かれらのロジックすなわち「対立は攻撃的反応を誘発しやすい」のであれば、新冷戦においてアメリカがソ連を「悪の帝国」と非難して、大規模な軍拡とSDI構想などを推進したことは、ソ連を「攻撃的反応」に導くはずです。ですが、ソ連はゴルバチョフ政権の1年目あたりまではアメリカに反発していましたが、その後は、中距離核兵器の撤廃や通常兵力の一方的削減、アフガニスタンからの撤退など、次々と譲歩を行いました。上記書の出版後、ルボウ氏はジョージ・ブレスラウアー氏(カリフォルニア大学バークレー校)との共著論文で、冷戦終結過程において、ゴルバチョフの欠くことのできない主導力を強調すると同時に、レーガン政権の最大の圧力と決意が、後にかれが示した取引への前向きな姿勢と強硬なレトリックの放棄と相まって、役割を果たしたとする命題を考慮に値すると立場を微妙に修正しています(George Breslauer and Richard N. Lebow, "Leadership and the End of the Cold War," in Richard K. Hermann and Richard Ned Lebow, eds., Ending the Cold War, Palgrave Macmillan, 2004, p. 184)。要するに、ルボウ氏とステイン氏が信奉する「仮説」は、2つの危機を説明できるかもしれませんが、それ以外の事例には条件付きでしか当てはまらないかもしれません。おそらく、かれらの「再保障」理論は紛争当事者の関係が「スパイラルモデル」に適合する前提条件下で作用する因果メカニズムにもとづいているということでしょう。
第3に、『われわれは皆、冷戦に敗北したのだ』の主旨が、どこまで政策に役立つのか疑問です。歴史の後知恵を使えば、キューバ危機や10月危機における米ソの指導者の政策選好を明らかできるでしょう。しかしながら、その当時、米ソの政策決定者は、どうやって相手の意図を確実に知ることができたのでしょうか。かれらは「機会主義的な拡張主義」の国家には、威嚇による抑止戦略は有効であると留保しています(上記書、322ページ)。問題は、敵対国が機会主義的かどうかを確認することです。もし敵対国がこうした選好をもつアクターだった時に、国家が、そうした略奪的な国家に弱みや優柔不断な姿勢をみせたとすれば、その政策は破滅的な結末をもたらすでしょう。ルボウ氏とステイン氏の「理論」は、暗黙の前提として、国家は機会主義的な拡張主義者ではないことになっています。かれらの理論には、「現状維持バイアス」がかかっているのです。攻撃的リアリズムの大国政治の理論が示すように、国家が機会主義的にパワーの拡大を目指す選好を持っているという「公理」は現実的です。にもかかわらず、米ソが2つの危機において、結局は相互に抑制的な政策をとって対立を収束させたのは、かれらも部分的に認めているように、大局的に見れば、核兵器による「抑止」が相手に一方的な犠牲を強いて利益を得る収奪的行動を抑えたと説明できないでしょうか。米ソの指導者は、どちらの危機においても、対立が破滅的な損害をもたらす核戦争にエスカレートすることを恐れて、相手国の意図が完全には分からない中、危機を収束させるよう努力しています。米ソが機会主義的に行動するチャンスは、ほとんど紛争のエスカレーションによる核戦争の恐怖が消し去ったとも説明できます。
最後に、ルボウ氏とステイン氏は、同書において、冷戦期におけるアメリカの対ソ戦略の大枠を提言した、ジョージ・ケナン氏の新聞記事を引用して称えていますが(上記書、5ページ)、不思議なことに、かれが主張した「封じ込め(containment)」には、(わたしが読み落としていなければ)まったく言及していません。ケナン氏の対ソ封じ込めのアイディアは、政治的手段を重視する洗練されたものでした。この封じ込めは、冷戦が深刻化するにしたがい、かれの意図した戦略構想から離れて、どんどん軍事化していきました。ですが、封じ込め戦略そのものは、ソ連に便宜を図る妥協的なものではなく、対決を志向するものであったことに変わりありません。かれらは、封じ込め戦略と冷戦の終焉の関係をどのように考えているのか、気になるところです。抑止を志向する封じ込め戦略は、自説と相いれないから、あえて触れなかったのだろうというのは、深読みしすぎでしょうか。
『われわれは皆、冷戦に敗北したのだ』は、上述した理論的、方法論的な問題はありますが、気の遠くなるような数の資料から、冷戦期における米ソの核戦争の危機を分析して、威嚇にもとづく抑止戦略や強制外交の危険性を訴える、読み応えある学術書です。本書では、このブログで紹介しきれない、その他の示唆に富む仮説が豊富に提示されています。そして、それらの仮説は、後の研究者が支持したり否定したりすることを通して、国際政治における核兵器の政治的な意味に対する、われわれの理解を深めることに貢献しています。たとえば、ルボウ氏とステイン氏は、「実際あるいは想像上の核の優位を利用して政治的利得を稼ごうとする指導者の試みは成功しそうにない」(上記書、364ページ)という命題を提示しています。こうした初期的な命題は、核兵器による強制外交は成功しにくいことを実証した、トッド・セクサー氏(ヴァージニア大学)とマシュー・ファーマン氏(テキサスA&M大学)の『核兵器と強制外交』(ケンブリッジ大学出版局、2017年)に結実していきます。他方、マシュー・クローニグ氏(ジョージタウン大学)は、自著『アメリカ核戦略の論理』(オックスフォード大学出版局、2018年)において、核戦力の優位は国家の安全保障上の目的を達成するのに貢献していると、かれらの理論をくつがえす主張をしています。これらの学問的成果を生み出す元となった『われわれは皆、冷戦に敗北したのだ』は、とりわけ核戦略や危機管理を研究する上では、欠くことのできない必読文献だと思います。
「なぜ冷戦は終結したのか?まず、(アメリカの)封じ込めが成功したという見方が可能である。第二次世界大戦の直後にケナンは、アメリカがソ連の拡張を阻止できれば、そのイデオロギーの影響力が強まる見込みはなく、ソ連の共産主義は次第に限界を迎えるであろう、と主張した…大局的に見ればケナンは正しかった」(上記書、209ページ)。
アメリカが冷戦に勝利したという見方は、定量的分析でも示されています。ブルース・ブエノ・デ・メスキータ氏(ニューヨーク大学)によれば、「期待効用モデル」によるシミュレーションは、アメリカが高い確率でソ連に冷戦で平和的に勝つと「予測」しており、実際にそうなったということです(Bruce Bueno de Mesquita, "The End of the Cold War: Predicting an Emergent Property," Journal of Conflict Resolution, Vol. 42, No. 2, April 1998, pp. 131-155)。歴史学のあるテキストは、「東ヨーロッパ諸国の自由化・民主化、西ドイツの東ドイツ吸収によるドイツ統一と統一ドイツのNATO帰属は、いずれもアメリカの要求に沿った結果であった。その意味でアメリカは確かに冷戦に勝利を収めた」と解説しています(佐々木卓也『冷戦』有斐閣、2011年、188ページ)。
冷戦の「勝者」はアメリカであるというのが、いわばオーソドックスな「通説」となっているのです。他方、この一般的な学説に強く異議を唱える大規模な研究があります。その1つが、国際関係研究の重鎮であるリチャード・ルボウ氏(キングスカレッジ)とジャニス・グロス・ステイン氏(トロント大学)が著した労作『われわれは皆、冷戦に敗北したのだ(We All Lost the Cold War)』(プリンストン大学出版局、1994年)です。同書は、500ページ以上の大著です。注だけでも150ページ以上あります(これだけで単著になりそうです)。両氏が、膨大な資料を駆使して、本書を執筆したことが分かります。
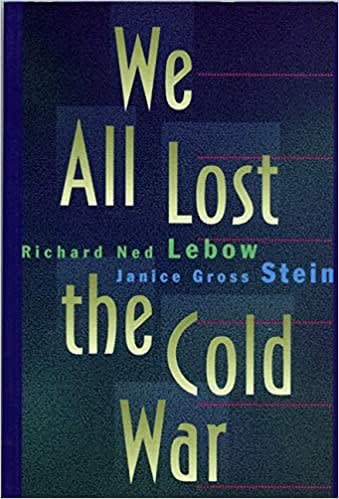
本書の主張は明確です。冷戦中にアメリカとソ連がとった威嚇に依拠した「抑止」や「強制」の戦略は、無駄に冷戦を長引かせた。また、アメリカがソ連を屈服させたというもっともらしい主張も、実は証拠に乏しい。したがって、アメリカが冷戦でソ連に勝ったという説明は間違いであり、両国が「再保障(reassurance)」戦略を賢く選択していたら、冷戦はもっと早く終わっただろう。その意味で、アメリカもソ連も冷戦の「敗者」なのだ、ということです。こうしたかれらの主張は、以前にこのブログで紹介した、ロバート・ジャーヴィス氏も交えた共同研究『心理学と抑止』の延長線上にあります。
ルボウ氏とステイン氏は、1962年のキューバ危機と1973年の中東における10月戦争(第4次中東戦争)に関して、冷戦前後に解禁された旧ソ連の機密文書や要人へのインタヴューを活用して徹底的な事例研究を行っています。そして、こうした緻密で詳細な事例の調査から、米ソの抑止政策や強要政策が、双方のケースにおいて所期の目的を達成できず、むしろ裏目にでてしまったことを丹念に実証しています。
キューバ危機の事例からみていきましょう。アメリカは、自国の勢力圏とみなしている西半球におけるキューバに社会主義政権が誕生したことをに反発して、同政権を倒すための「ピッグス湾侵攻作戦」を行いましたが、これは無残な失敗に終わりました。ソ連が、この失敗をアメリカの「弱さ」とみなして攻勢にでてくるのを恐れたケネディ大統領は、断固とした決意を示すことが不可欠だと考えました。かれはソ連が攻撃的兵器をキューバに導入することは受け入れられないことを明確に強く表明しました。また、ベルリン危機に対処するため、アメリカは西ドイツの米軍も急速に強化しました。さらに、アメリカは戦略核戦力を増強するとともに、ソ連の隣国であるトルコにジュピターミサイルも配備しました。ケネディは、一連のアメリカの措置がソ連に対する防御的で慎重なものだと考えていました。他方、ソ連は、こうしたアメリカの「抑止」戦略がソ連の脆弱性を悪化させるものと受け取りました。
アメリカの「威嚇」を受けたソ連は、キューバに核ミサイル基地を建設することで対応しました。ソ連は、自らの脆弱性を挽回するために、核兵器をキューバに導入したのです。フルシチョフ首相は、アメリカがキューバにおけるソ連の核ミサイルを受け入れるだろうと楽観視していました。なぜなら、ソ連はアメリカがトルコで行ったのと同じことをキューバでしているに過ぎないと、自らを正当化したからです。こうしてアメリカの対ソ抑止政策は失敗に終わりました。アメリカの抑止はソ連の攻勢を阻止すのではなく、かえってソ連を挑発してしまったのです。
ソ連のキューバにおける核ミサイル導入に対して、アメリカは威嚇による強制外交で応じました。ケネディ政権は、優勢な戦略核戦力とカリブ海における通常戦力の優位を利用して、キューバに向かうソ連艦船に対して「海上封鎖」を実施したのです。こうしたアメリカの軍事的措置は、キューバへの侵攻や空爆といった直接の軍事行動をほのめかすものでもありました。この危機が米ソの戦争へとエスカレートすることを恐れたフルシチョフは、アメリカのキューバ不侵攻の約束と引き換えに、キューバから核ミサイルを撤去することに同意しました。さらにかれは、トルコからジュピターミサイルを撤去することを追加でアメリカに要求しました。国家安全保障会議エクスコムにおけるアメリカの指導者の議論は、新たなソ連の要求への対応をめぐって紛糾しましたが、ケネディはキューバ不侵攻を約束するとともに、ソ連のドブルイニン駐米大使を通じて、トルコのミサイル撤去をフルシチョフと密約しました。それでもソ連が納得しない場合、ケネディはジュピター撤去を公にすることも覚悟していました。こうして米ソが相互に妥協することにより、核戦争の危険性を孕んだキューバ危機は収束したのです。
キューバ危機の分析から、ルボウ氏とステイン氏は、アメリカの強い決意がバーゲニングパワーとして、ソ連の妥協を引き出したという通説を否定します。そうではなく、武力行使のインセンティヴを削減する「再保障」が、危機の収束において役割を果たしたのです。かれらは以下のように主張しています。
「(アメリカの)威嚇と軍事行動を通じた決意の示威と…危機の結果の間の因果的関連は、一般に考えられているほど強くないし直線的でもない…停止・臨検の発表後、フルシチョフはアメリカによるキューバへの攻撃の恐れを強くした。攻撃を防止するために、かれは妥協的なメッセージをケネディに送った…フルシチョフは…止めることのできないエスカレーション…を懸念(するあまり)、ケネディが空爆や侵攻のどちらにも、前にもまして反対するようになっていたことを認識していなかった…このミサイル危機の『隠れた物語』は、再保障が(米ソ)相互の妥協と危機の解決を促進する重要な役割を果たしていたことだ…フルシチョフの視点からすれば、再保障の最も重要な形態は、ケネディが…キューバにおけるミサイル発見を利用して、カストロ(政権)を転覆することでソ連に恥をかかせる行動をとらなかったことだ。ケネディの自制はフルシチョフの恐怖をやわらげた…フルシチョフはアメリカの決意を甘く見てキューバにミサイルを送ったのでもなければ、アメリカの決意を注視してミサイルを撤去したのでもない。ミサイルは脆弱性と恐怖を克服するために配備されたのであり、部分的には、アメリカの再保障がそれらの脆弱性や恐怖を緩和したから取り去らわれたのだ」(上記書、308-309、318ページ)。
そして、かれらは1つの興味深い反実仮想を披露しています。すなわち、「もしケネディが1963年11月に暗殺されず、フルシチョフが1964年10月に職務から追放されていなければ、冷戦は実際より、もっと早く終わっていただろう」(上記書、145ページ)ということです。
10月戦争の事例をみてみましょう。エジプトとシリアは、イスラエルに奇襲攻撃を行いました。当時、イスラエルはアラブ諸国に対して、軍事力とくに空軍力で圧倒的に優勢だったので、同諸国からの戦争は抑止できると考えていました。また、エジプトやシリアの同盟国だったソ連も、これらの国家がイスラエルに戦争しても負けることが見込まれるので、両国に自制を促していました。エジプトのサダト大統領は、六日戦争(第3次中東戦争)で失ったシナイ半島などの領土を外交で取り戻すことに「絶望」していました。そこでサダトは、戦略的に不利であることを承知のうえで、シリアと共謀してイスラエルとの戦争を選んだのです。不意を突かれたイスラエルは、エジプトとシリアの攻撃に対して、緒戦では劣勢を強いられました。しかしながら、戦局は軍事力でまさるイスラエルの優勢に傾き、エジプトやシリアは追い詰められました。ソ連は中東の主要国であるエジプトが壊滅的な敗北を喫するのを恐れました。そこでソ連は、イスラエルの同盟国であるアメリカに対して強制外交を行いました。すなわち、ソ連はイスラエルが停戦に応じなければ、この戦争に単独で軍事介入するとアメリカを脅したのです。ソ連は、こうした威嚇により、アメリカがイスラエルに対して停戦受諾を強いることに期待したのです。これに対して、アメリカはソ連の軍事介入を抑止するために、「デフコンⅢ(Defense Condition Ⅲ)」を全世界の米軍に発令しました。アメリカの通常戦力ならびに核戦力は高度な警戒態勢に入ったのです。
ソ連の強制政策は裏目にでました。そもそもアメリカは戦後の中東和平交渉で主導権を握るために、エジプトの決定的な敗北を望んでいませんでした。エジプトがアメリカの同盟国であるイスラエルに完敗してしまえば、同国はますますソ連を頼るようになってしまいます。そうなると、アメリカが単独で中東和平交渉を進めることは難しくなります。こうした戦争の結末を避けるには、イスラエルが限定的な勝利を収めるとともに、エジプトに余力を残させることが必要だとアメリカの指導者たちは判断していたのです。こうした戦略をとるキッシンジャー国務長官は、ソ連による単独介入の脅しを受ける前から、イスラエルに停戦を促していました。しかしながら、戦争を有利に進めるイスラエルは、停戦よりも継戦を選好していたので、なかなか戦闘をやめようとしなかったのです。このような最中に、ソ連はアメリカに単独の軍事介入を示唆してきたのです。アメリカは、イスラエルに停戦の受け入れをより強く求めてしまうと、ソ連に屈したとみなされることになるのを恐れました。そこで、アメリカは外交上の「評判」を落とさないために、イスラエルへの停戦受け入れの働きかけを中断してしまったのです。
アメリカの抑止行動も見当違いでした。アメリカはソ連に中東への軍事侵攻を思いとどまらせるために、米軍に軍事アラートをかけました。これによりソ連が引き下がることに期待したのです。ところが、ソ連の指導者は、アメリカのアラートに驚き、そして怒りさえ覚えました。なぜなら、ブレジネフ書記長をはじめとする政治局のメンバーたちは、ソ連軍を中東に派遣するつもりは、戦争開始当初からなかったからです。ソ連の単独介入の脅しは、たんなるブラフだったのです。つまり、アメリカのソ連に対する威嚇は、まったく意味がなかったということです。その後、10月戦争は急展開を見せて収束しました。エジプトが停戦を監視する国連平和維持軍の受け入れを表明したことで、イスラエルそして米ソもこれに同意しました。同時に、アメリカはアラート態勢を解除しました。こうして米ソの核戦争の危機を孕んだ10月戦争は終わったのです。
アメリカとソ連が威嚇にもとづく抑止や強制の政策を実行したことは、結局のところ、両国の対立を長引かせるだけだったと、ルボウ氏やステイン氏は推論しています。かれらの主張は、要約すれば以下の通りです。
「ワシントンとモスクワにおいて、この対立はデタントに反対する立場を強めてしまった…1973年10月の危機は、デタント終焉の始まり、そして10年以上続く米ソ間の第二次冷戦の開始として刻印されたのだ…影響力のあるアメリカの政治指導者やコメンテーターは…ソ連が拡張主義や攻撃的意図によって動機づけられていると主張した。かれらはソ連に裏切られたと断固言い張った…ブレジネフはアメリカ軍の世界規模でのアラートを予期していなかった…ソ連におけるデタントの反対論も大きくなった…怒りと失望に包まれたニクソン、キッシンジャー、ブレジネフは、自国においてデタントを支持することをますます控えてしまったのだ…1973年において、抑止や強制は解決策ではなく問題の一部分であった」(上記書、287-288、320ページ)。
10月危機の頃のアメリカとソ連は、デタントで協調的な関係を築こうとしていました。にもかかわらず、米ソは強制外交や抑止政策で相手を威嚇してしまったために、こうした和解的な雰囲気を自ら壊してしまい、無駄に冷戦を長引かせてしまったということです。
大国政治における再保障を重視するルボウ氏とステイン氏は、冷戦終結の「通説」にも懐疑的です。かれらは、アメリカとの競争で経済を弱体化したソ連が、アメリカに屈した結果、冷戦が終わったという学説に反対しています。第1に、ソ連の国家歳入に占める軍事費の割合は、スターリン時代からゴルバチョフ政権まで、継続して約25%であり、それが削減されたのは、ようやく1989年になってのことです。アメリカのレーガン政権の軍拡にソ連が付いていけなくなったのであれば、ゴルバチョフは経済を立て直そうとして軍事費を削減するはずなのに、そうしなかったのは「通説」に合致しないということです(上記書、372ページ)。第2に、ソ連の指導者が国内政治経済の改革に着手して、対外政策で劇的な妥協(アフガニスタンからの撤退や軍縮の提案など)を実行したことが、冷戦を終焉に導いた重要な要因だと指摘されています。ゴルバチョフの協調的な対外政策が、アメリカの指導者に安心感を与えた結果、米ソ関係は劇的に改善されたのです(上記書、あとがき)。「対立は攻撃的反応を最も誘発しやすい…和解は最も互恵的になりやすい…もしアメリカの政策が、ソ連の指導者が改革にコミットした際に何らかのインパクトを与えたとするなら、それは抑止戦略が冷戦をおそらく長引かせてしまったのだ…抑止戦略は…冷戦期における超大国の関係にとって、広範囲での否定的な成り行きだったのだ」(上記書、376ページ)というのが、かれらの結論なのです。
『われわれは皆、冷戦に敗北したのだ』は、主に冷戦期における米ソ間の2つの危機を膨大な資料に基づいて実証しています。それぞれの危機の分析だけで数百ページの文量になります。一つ一つの危機の議論だけでも、立派な単著になるくらい充実しています。そして、ルボウ氏とステイン氏は、2つの危機から重要な教訓を引き出しています。すなわち、威嚇に依拠した抑止政策や強制外交は「自己充足的予言」、すなわち、これらの政策が避けようとしていた事態をかえって招いてしまうために、米ソの対立を無用に悪化させたということです。たとえば、キューバ危機において、アメリカは避けたかったソ連のキューバへの核ミサイル導入を抑止の威嚇で招来してしまいました。10月戦争において、ソ連は避けたかったアメリカのイスラエルへの停戦受け入れの圧力の中断を強制外交の威嚇により実現してしまいました。もし米ソが、威嚇の逆説的な効果に気づいて、賢明な妥協的政策をとっていれば、冷戦はもっと早く終わっていただろうと、かれらは示唆しています。
わたしは『われわれは皆、冷戦に敗北したのだ』を読んで、ルボウ氏とステイン氏の2つの危機に関する実証分析に圧倒されました。まるで歴史小説を読んでいるかのように、どんどん本書に引き込まれていきました。かれらの筆致は圧倒的です。ただし、ここで述べられている研究内容に、全面的に賛成できるかと問われれば、そうではありません。第1に、冷戦終結の「通説」を支持する歴史証拠を見つけるのは、難しいことではありません。ゴルバチョフは、1986年10月の政治局の会合で「(アメリカから)再び軍拡競争を押し付けられたら、われわれは敗北するだろう」と指摘していました(岡田美保「ソ連の弱さの自覚と対外政策の転換―INF交渉の再検討―」『国際政治』第157号、2009年9月、20ページに引用)。また、かれはソ連の軍事費を削減する必要性を痛切に感じていました。ゴルバチョフは1988年2月の政治局会議において、こう発言してます。「今、明らかなことは、大幅な軍事支出の削減なくして、われわれはペレストロイカが取り組む諸問題を解決することができないのだ」(William C. Wohlforth, "Realism and the End of the Cold War," International Security, Vol. 19, No. 3, Winter 1994/95, p. 112に引用)。そして、ソ連は翌年の1989年、実際に軍事支出を低下させました。こうしたエビデンスは、オーソドックスな冷戦終結の見方を裏づけるものでしょう。
第2に、『われわれは皆、冷戦に敗北したのだ』が導いた「理論」は、どこまで一般性を持ちうるのでしょうか。たとえば、かれらは冷戦の終結過程で、米ソが相互に「再保障(安心供与)」政策をとったことが重要だと指摘する反面、レーガン政権の「対ソ強硬策」はソ連の行動インパクトを与えなかったと主張しています。しかしながら、かれらのロジックすなわち「対立は攻撃的反応を誘発しやすい」のであれば、新冷戦においてアメリカがソ連を「悪の帝国」と非難して、大規模な軍拡とSDI構想などを推進したことは、ソ連を「攻撃的反応」に導くはずです。ですが、ソ連はゴルバチョフ政権の1年目あたりまではアメリカに反発していましたが、その後は、中距離核兵器の撤廃や通常兵力の一方的削減、アフガニスタンからの撤退など、次々と譲歩を行いました。上記書の出版後、ルボウ氏はジョージ・ブレスラウアー氏(カリフォルニア大学バークレー校)との共著論文で、冷戦終結過程において、ゴルバチョフの欠くことのできない主導力を強調すると同時に、レーガン政権の最大の圧力と決意が、後にかれが示した取引への前向きな姿勢と強硬なレトリックの放棄と相まって、役割を果たしたとする命題を考慮に値すると立場を微妙に修正しています(George Breslauer and Richard N. Lebow, "Leadership and the End of the Cold War," in Richard K. Hermann and Richard Ned Lebow, eds., Ending the Cold War, Palgrave Macmillan, 2004, p. 184)。要するに、ルボウ氏とステイン氏が信奉する「仮説」は、2つの危機を説明できるかもしれませんが、それ以外の事例には条件付きでしか当てはまらないかもしれません。おそらく、かれらの「再保障」理論は紛争当事者の関係が「スパイラルモデル」に適合する前提条件下で作用する因果メカニズムにもとづいているということでしょう。
第3に、『われわれは皆、冷戦に敗北したのだ』の主旨が、どこまで政策に役立つのか疑問です。歴史の後知恵を使えば、キューバ危機や10月危機における米ソの指導者の政策選好を明らかできるでしょう。しかしながら、その当時、米ソの政策決定者は、どうやって相手の意図を確実に知ることができたのでしょうか。かれらは「機会主義的な拡張主義」の国家には、威嚇による抑止戦略は有効であると留保しています(上記書、322ページ)。問題は、敵対国が機会主義的かどうかを確認することです。もし敵対国がこうした選好をもつアクターだった時に、国家が、そうした略奪的な国家に弱みや優柔不断な姿勢をみせたとすれば、その政策は破滅的な結末をもたらすでしょう。ルボウ氏とステイン氏の「理論」は、暗黙の前提として、国家は機会主義的な拡張主義者ではないことになっています。かれらの理論には、「現状維持バイアス」がかかっているのです。攻撃的リアリズムの大国政治の理論が示すように、国家が機会主義的にパワーの拡大を目指す選好を持っているという「公理」は現実的です。にもかかわらず、米ソが2つの危機において、結局は相互に抑制的な政策をとって対立を収束させたのは、かれらも部分的に認めているように、大局的に見れば、核兵器による「抑止」が相手に一方的な犠牲を強いて利益を得る収奪的行動を抑えたと説明できないでしょうか。米ソの指導者は、どちらの危機においても、対立が破滅的な損害をもたらす核戦争にエスカレートすることを恐れて、相手国の意図が完全には分からない中、危機を収束させるよう努力しています。米ソが機会主義的に行動するチャンスは、ほとんど紛争のエスカレーションによる核戦争の恐怖が消し去ったとも説明できます。
最後に、ルボウ氏とステイン氏は、同書において、冷戦期におけるアメリカの対ソ戦略の大枠を提言した、ジョージ・ケナン氏の新聞記事を引用して称えていますが(上記書、5ページ)、不思議なことに、かれが主張した「封じ込め(containment)」には、(わたしが読み落としていなければ)まったく言及していません。ケナン氏の対ソ封じ込めのアイディアは、政治的手段を重視する洗練されたものでした。この封じ込めは、冷戦が深刻化するにしたがい、かれの意図した戦略構想から離れて、どんどん軍事化していきました。ですが、封じ込め戦略そのものは、ソ連に便宜を図る妥協的なものではなく、対決を志向するものであったことに変わりありません。かれらは、封じ込め戦略と冷戦の終焉の関係をどのように考えているのか、気になるところです。抑止を志向する封じ込め戦略は、自説と相いれないから、あえて触れなかったのだろうというのは、深読みしすぎでしょうか。
『われわれは皆、冷戦に敗北したのだ』は、上述した理論的、方法論的な問題はありますが、気の遠くなるような数の資料から、冷戦期における米ソの核戦争の危機を分析して、威嚇にもとづく抑止戦略や強制外交の危険性を訴える、読み応えある学術書です。本書では、このブログで紹介しきれない、その他の示唆に富む仮説が豊富に提示されています。そして、それらの仮説は、後の研究者が支持したり否定したりすることを通して、国際政治における核兵器の政治的な意味に対する、われわれの理解を深めることに貢献しています。たとえば、ルボウ氏とステイン氏は、「実際あるいは想像上の核の優位を利用して政治的利得を稼ごうとする指導者の試みは成功しそうにない」(上記書、364ページ)という命題を提示しています。こうした初期的な命題は、核兵器による強制外交は成功しにくいことを実証した、トッド・セクサー氏(ヴァージニア大学)とマシュー・ファーマン氏(テキサスA&M大学)の『核兵器と強制外交』(ケンブリッジ大学出版局、2017年)に結実していきます。他方、マシュー・クローニグ氏(ジョージタウン大学)は、自著『アメリカ核戦略の論理』(オックスフォード大学出版局、2018年)において、核戦力の優位は国家の安全保障上の目的を達成するのに貢献していると、かれらの理論をくつがえす主張をしています。これらの学問的成果を生み出す元となった『われわれは皆、冷戦に敗北したのだ』は、とりわけ核戦略や危機管理を研究する上では、欠くことのできない必読文献だと思います。















