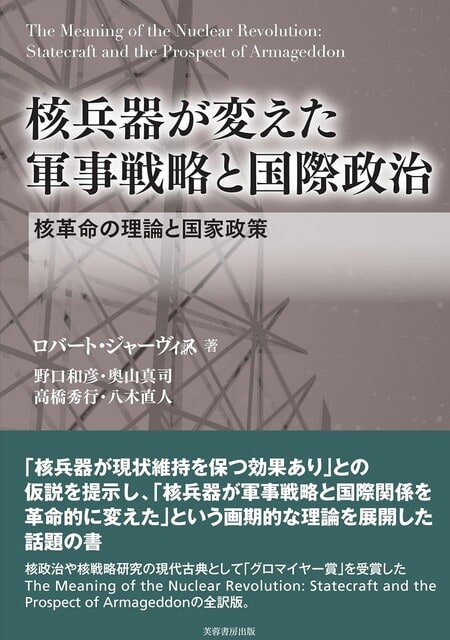私の大好きなマンガに『スラム ダンク』があります。バスケを題材にした作品です。後半に、こんなストーリーがあります。
バスケ全国大会での試合こと。インターハイ常連のT高校の南選手が、S高校のエース・流川選手に攻撃で肘打ちをして片目を「潰して」しまいます。南選手は、どうしても勝ちたかった。なぜなら、彼が慕っていた北野元監督の戦法「ラン&ガン」で勝てば、北野元監督が正しかったことが実証され、再び、T高校の監督に復帰できると期待していたからです。
その北野氏は、なぜ、監督を解任されたのか。T高校の理事長の説明は、こうです。「全国ベスト8くらいじゃ新聞もTVも扱ってくれへん。投資している意味がないやろ。私は経営者なんでね」。

このストーリーを読んだ読者は、何を思われたでしょうか。多くの人が、きっと悪者探しをしたのではないでしょうか。「理事長は教育者として失格だ!」、「いや、反則行為をした南選手が悪い」などなど。これらの倫理的判断は決して間違ってはいないでしょう。ひるがえって、では、悪者を批判すれば、こうしたスポーツに関する問題は、解決するのでしょうか。
人を動かす最も重要な1つの要因は、「インセンティブ」です。この理事長は、学校経営の最高責任者として、教育マーケットにおいて、バスケを利用して知名度を高めようとしました。当然のことでしょう。南選手は、試合に勝利しようとします。当然のことでしょう。そして、ダーディな肘打ちを使う誘惑に負けてしまったのです。どちらの行動にも、インセンティブがからんでいます。こうしたインセンティブを極力低めるか、もしくは、ディスインセンティブにしなければ、合理性の観点からすれば、こうした問題行為は繰り返されるでしょう。
要するに、スポーツにおけるさまざまな問題に対する、合理主義を重んじる政治学者からの1つの処方箋は、好ましくない行動を誘発しそうなインセンティブを下げるか、なくしてしまう「仕組み」、すなわち「システム」を作るということです。では、どうすればよいのか。よいお手本があります。それはアメリカのカレッジ・スポーツのシステムです。以下は、スタンフォード大学アメフト部アシスタントの河田剛氏の好著『不合理だらけの日本スポーツ界』からの引用です。どの指摘も傾聴に値すると思います。

・コンプライアンス
「学校側としては、勝ちたいがために現場の暴走で大きな問題が発生したり(することは)絶対に避けたい…また、教育機関として、学生アスリートがその道を逸脱するようなことがあってはならない。…それを監視・マネジメントするような部門(コンプライアント・オフィス)が存在するのは、必然なのである」(62-63ページ)。そして、アメリカには、全米大学体育協会(NCAA)があり、各大学の体育会を統括して、未然にスポーツ事故や障害につながる反則行為を防ぐためのシステムを構築しています。その歴史は、100年以上です。かのセオドア・ルーズベルト大統領が、この組織の創設のイニシアチブをとりました。ちなみに、ペンシルバニア州立大学は、コーチの不祥事で、NCAAから、約66億円の罰金を科せられたことがあったそうです。
また、スポーツ競技では勝利が最大の目的ですから、各選手は、高校や大学で練習を優先して勉強を疎かにしがちです。これも選手のインセンティブを考慮すれば、当然のことでしょう。勝利を義務づけられた監督も、そのような指導をするインセンティブを持ったとしても、仕方ないでしょう。学校も、体育会の勝利をマーケティングで利用するインセンティブを持つことでしょう。ですが、その結果、多くのスポーツエリートは、セカンドキャリで、その「つけ」を払うことになります。そうならないようにするには、スポーツ選手が勉強するインセンティブを高め、学校経営者そして監督には、勉強を二の次にして練習させる選手指導をやめさせたり、黙認することを許さないシステムを作らなければなりません。再び、河田氏の著書から引用します。
・セカンドキャリア
「日本を代表するプロスポーツにおいて、引退者が『華麗なる転身』をはたしたストーリーをどれほど聞いたことがあるだろうか」(17ページ)。「日本ではきわめてまれなことであるが、アメリカには腐るほどある」(138ページ)。なぜか?「(多くのアメリカの大学では)ある一定の成績を取らなければ、自分のライフワークとも言えるスポーツの練習や試合に参加することは許されない。つまり、勉強せざるを得ないシステムが存在する」(9ページ)。
今こそ、「ガラパゴス化」した日本の学生スポーツのシステムを全面的に刷新するときではないでしょうか。我が国にも、セオドア・ルーズベルト大統領のような人士がいることを信じたいです。
バスケ全国大会での試合こと。インターハイ常連のT高校の南選手が、S高校のエース・流川選手に攻撃で肘打ちをして片目を「潰して」しまいます。南選手は、どうしても勝ちたかった。なぜなら、彼が慕っていた北野元監督の戦法「ラン&ガン」で勝てば、北野元監督が正しかったことが実証され、再び、T高校の監督に復帰できると期待していたからです。
その北野氏は、なぜ、監督を解任されたのか。T高校の理事長の説明は、こうです。「全国ベスト8くらいじゃ新聞もTVも扱ってくれへん。投資している意味がないやろ。私は経営者なんでね」。

このストーリーを読んだ読者は、何を思われたでしょうか。多くの人が、きっと悪者探しをしたのではないでしょうか。「理事長は教育者として失格だ!」、「いや、反則行為をした南選手が悪い」などなど。これらの倫理的判断は決して間違ってはいないでしょう。ひるがえって、では、悪者を批判すれば、こうしたスポーツに関する問題は、解決するのでしょうか。
人を動かす最も重要な1つの要因は、「インセンティブ」です。この理事長は、学校経営の最高責任者として、教育マーケットにおいて、バスケを利用して知名度を高めようとしました。当然のことでしょう。南選手は、試合に勝利しようとします。当然のことでしょう。そして、ダーディな肘打ちを使う誘惑に負けてしまったのです。どちらの行動にも、インセンティブがからんでいます。こうしたインセンティブを極力低めるか、もしくは、ディスインセンティブにしなければ、合理性の観点からすれば、こうした問題行為は繰り返されるでしょう。
要するに、スポーツにおけるさまざまな問題に対する、合理主義を重んじる政治学者からの1つの処方箋は、好ましくない行動を誘発しそうなインセンティブを下げるか、なくしてしまう「仕組み」、すなわち「システム」を作るということです。では、どうすればよいのか。よいお手本があります。それはアメリカのカレッジ・スポーツのシステムです。以下は、スタンフォード大学アメフト部アシスタントの河田剛氏の好著『不合理だらけの日本スポーツ界』からの引用です。どの指摘も傾聴に値すると思います。

・コンプライアンス
「学校側としては、勝ちたいがために現場の暴走で大きな問題が発生したり(することは)絶対に避けたい…また、教育機関として、学生アスリートがその道を逸脱するようなことがあってはならない。…それを監視・マネジメントするような部門(コンプライアント・オフィス)が存在するのは、必然なのである」(62-63ページ)。そして、アメリカには、全米大学体育協会(NCAA)があり、各大学の体育会を統括して、未然にスポーツ事故や障害につながる反則行為を防ぐためのシステムを構築しています。その歴史は、100年以上です。かのセオドア・ルーズベルト大統領が、この組織の創設のイニシアチブをとりました。ちなみに、ペンシルバニア州立大学は、コーチの不祥事で、NCAAから、約66億円の罰金を科せられたことがあったそうです。
また、スポーツ競技では勝利が最大の目的ですから、各選手は、高校や大学で練習を優先して勉強を疎かにしがちです。これも選手のインセンティブを考慮すれば、当然のことでしょう。勝利を義務づけられた監督も、そのような指導をするインセンティブを持ったとしても、仕方ないでしょう。学校も、体育会の勝利をマーケティングで利用するインセンティブを持つことでしょう。ですが、その結果、多くのスポーツエリートは、セカンドキャリで、その「つけ」を払うことになります。そうならないようにするには、スポーツ選手が勉強するインセンティブを高め、学校経営者そして監督には、勉強を二の次にして練習させる選手指導をやめさせたり、黙認することを許さないシステムを作らなければなりません。再び、河田氏の著書から引用します。
・セカンドキャリア
「日本を代表するプロスポーツにおいて、引退者が『華麗なる転身』をはたしたストーリーをどれほど聞いたことがあるだろうか」(17ページ)。「日本ではきわめてまれなことであるが、アメリカには腐るほどある」(138ページ)。なぜか?「(多くのアメリカの大学では)ある一定の成績を取らなければ、自分のライフワークとも言えるスポーツの練習や試合に参加することは許されない。つまり、勉強せざるを得ないシステムが存在する」(9ページ)。
今こそ、「ガラパゴス化」した日本の学生スポーツのシステムを全面的に刷新するときではないでしょうか。我が国にも、セオドア・ルーズベルト大統領のような人士がいることを信じたいです。