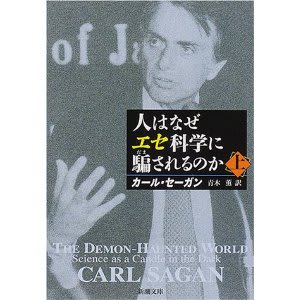戦争原因研究は、国際政治学や安全保障論の中心を構成する1つの分野です。近年の戦争原因研究は、主に国家の政治体制に着目した定量的アプローチが興隆する一方で、個人レベルに依拠したアプローチに回帰するものもあります。以前のブログで、後者の1つとして神経科学から戦争原因を究明しようとした研究を紹介しましたが、今日、ここで取り上げる、Richard Ned Lebow, Why Nations Fight: Past and Future Motives for War (Cambridge: Cambridge University Press, 2010) は、国際政治学の新しいアプローチに基づきつつも、伝統的な政治学や社会学の知見を援用したものと言えるでしょう。
リチャード・ルボウ氏(キングス・カレッジ)は、本書において、戦争原因のコンストラクティヴィスト分析を展開しています。すなわち、戦争とは文化的・社会的に構成されるものだ、ということです。ルボウは、戦争の原因として、政策決定者の「動機」に着目します。そして、国家の指導者を戦争へと動機づける複数の要因の中でも、彼が強調するのが「地位や名声(standing)」(と復讐)です。同書によれば、近代以降の戦争の58%は、国家の「地位や名声」を求める争いということです(p. 171-172)。戦争に勝利することこそが国家に名誉ある地位をもたらすと考え、国家は戦争へと動機づけられたということになります。

私がみるところ、ルボウ氏の著作は、戦争原因研究にいくつかの重要な貢献を行っています。第1に、コンストラクティヴィズムから戦争原因に接近したことです。その結果、既存の主要な国際関係理論が見過ごしてきた、「名声」「名誉」「精神」「欲望」「自尊心」といった非物質的要因の国際的出来事に対する影響を見直すことになりました。これは、戦争原因研究の「政治思想的アプローチ」への回帰と呼べるものかもしれません。第2に、これまでの安全保障を重視した戦争原因理論に対抗する有力な理論を提供したことです。合理的な戦争原因理論は、一般的に、国家(そして政治指導者の)「生き残り」に関連づけて、戦争の発生を説明してきました。しかし、ルボウ氏は、国家が安全保障を求めて戦争を起こすことは、一般に考えられているよりも少なく、近代以降の戦争の内の18%に過ぎないと主張しています(p. 156)そうであれば、多くの既存の戦争原因研究は、安全保障を過度に重視するバイアスがかかっているため、間違っているということになります。これに代替するのが、ルボウ氏の戦争原因の「動機理論」ということでしょう。
このルボウ氏の刺激的な主張については、安全保障研究の専門誌 Security Studies の最新号(第21巻第2号、2012年4・6月)が、特集を組んでいます。シンポジウム形式で、国際政治学の重鎮ロバート・ジャービス氏(コロンビア大学)やリチャード・ベッツ氏(コロンビア大学)らが、書評エッセーを寄稿し、それらにルボウ氏が答えています。私が印象的だったのは、両者ともに、動機のコーディングやカテゴリーの分類に問題を見出していたことです(「コーディング」=「符号化」。光の長い波長は「赤」、短い波長は「青」といったように変換すること。戦争原因の動機理論でいえば、Xは名声、Yは安全保障などと、アクターの行為を動機に変換すること)。実は、私も同書を読んだ時に、全く同じような疑問を持ちました。たとえば、政治指導者が、開戦の際に「国家の栄光や名誉」に言及するには、よくあることです。しかし、こうした発言は、戦争を起こした真の動機を必ずしも表していないでしょう。本当の理由をオブラートに包み込んで隠すのは、人間の営為では、よくあることだからです。
もちろん、こうした批判にルボウ氏も反論していますので、詳しくは、上記の専門雑誌に掲載されている、彼の応答を読んで下さい。私がルボウ氏の応答エッセーを読んで、あらためて考えさせられたことは、「合理性(rationality)」についてです。ルボウ氏は、以下のように主張します。
「合理的行動を多かれ少なかれ所与とする合理主義者とは対照的に、私は数多くの事例研究において、政策決定の非(不)合理性を立証した。…普遍的合理性など存在しない。合理的と考えられるものは、動機と文化価値で変わる関数なのだ」(Richard Ned Lebow, "The Causes of War: A Reply to My Critics," Security Studies, Vol. 21, No. 2, 2012, p. 365)。
こうしたロジックから、ルボウ氏は、将来の平和について、楽観的な見通しを立てています。イラク戦争に象徴されるように、現在の国際社会では、戦争を始めることは、国家の地位や名誉を高めるというよりは、むしろ、国家に「悪評」を与えることになるため、国家間戦争はますます時代遅れの「非合理的」行為になり、消えていくことになるだろう、ということです。確かに、ルボウ氏の言うことには一理あるようにも思いますが、こうした議論は、かつてジャック・スナイダー氏(コロンビア大学)が、コンストラクティヴィズムを「理想主義のバージョンアップ版」と批判したことに重なります(Jack Snyder, "One World, Rival Theories," Foreign Policy, No. 145, 2004, pp. 53-62)。安全保障ではなく、ランクや名誉こそが、国家を戦争へと導く、もっと強力な原動力なのでしょうか?残念ながら、ルボウ氏の研究が示した証拠は、ベッツ氏も指摘したように、弱いと言わざるを得ないでしょう。ですので、こうした結論に飛びつくのには、より慎重になるべきではないかと私は思っています。
リチャード・ルボウ氏(キングス・カレッジ)は、本書において、戦争原因のコンストラクティヴィスト分析を展開しています。すなわち、戦争とは文化的・社会的に構成されるものだ、ということです。ルボウは、戦争の原因として、政策決定者の「動機」に着目します。そして、国家の指導者を戦争へと動機づける複数の要因の中でも、彼が強調するのが「地位や名声(standing)」(と復讐)です。同書によれば、近代以降の戦争の58%は、国家の「地位や名声」を求める争いということです(p. 171-172)。戦争に勝利することこそが国家に名誉ある地位をもたらすと考え、国家は戦争へと動機づけられたということになります。

私がみるところ、ルボウ氏の著作は、戦争原因研究にいくつかの重要な貢献を行っています。第1に、コンストラクティヴィズムから戦争原因に接近したことです。その結果、既存の主要な国際関係理論が見過ごしてきた、「名声」「名誉」「精神」「欲望」「自尊心」といった非物質的要因の国際的出来事に対する影響を見直すことになりました。これは、戦争原因研究の「政治思想的アプローチ」への回帰と呼べるものかもしれません。第2に、これまでの安全保障を重視した戦争原因理論に対抗する有力な理論を提供したことです。合理的な戦争原因理論は、一般的に、国家(そして政治指導者の)「生き残り」に関連づけて、戦争の発生を説明してきました。しかし、ルボウ氏は、国家が安全保障を求めて戦争を起こすことは、一般に考えられているよりも少なく、近代以降の戦争の内の18%に過ぎないと主張しています(p. 156)そうであれば、多くの既存の戦争原因研究は、安全保障を過度に重視するバイアスがかかっているため、間違っているということになります。これに代替するのが、ルボウ氏の戦争原因の「動機理論」ということでしょう。
このルボウ氏の刺激的な主張については、安全保障研究の専門誌 Security Studies の最新号(第21巻第2号、2012年4・6月)が、特集を組んでいます。シンポジウム形式で、国際政治学の重鎮ロバート・ジャービス氏(コロンビア大学)やリチャード・ベッツ氏(コロンビア大学)らが、書評エッセーを寄稿し、それらにルボウ氏が答えています。私が印象的だったのは、両者ともに、動機のコーディングやカテゴリーの分類に問題を見出していたことです(「コーディング」=「符号化」。光の長い波長は「赤」、短い波長は「青」といったように変換すること。戦争原因の動機理論でいえば、Xは名声、Yは安全保障などと、アクターの行為を動機に変換すること)。実は、私も同書を読んだ時に、全く同じような疑問を持ちました。たとえば、政治指導者が、開戦の際に「国家の栄光や名誉」に言及するには、よくあることです。しかし、こうした発言は、戦争を起こした真の動機を必ずしも表していないでしょう。本当の理由をオブラートに包み込んで隠すのは、人間の営為では、よくあることだからです。
もちろん、こうした批判にルボウ氏も反論していますので、詳しくは、上記の専門雑誌に掲載されている、彼の応答を読んで下さい。私がルボウ氏の応答エッセーを読んで、あらためて考えさせられたことは、「合理性(rationality)」についてです。ルボウ氏は、以下のように主張します。
「合理的行動を多かれ少なかれ所与とする合理主義者とは対照的に、私は数多くの事例研究において、政策決定の非(不)合理性を立証した。…普遍的合理性など存在しない。合理的と考えられるものは、動機と文化価値で変わる関数なのだ」(Richard Ned Lebow, "The Causes of War: A Reply to My Critics," Security Studies, Vol. 21, No. 2, 2012, p. 365)。
こうしたロジックから、ルボウ氏は、将来の平和について、楽観的な見通しを立てています。イラク戦争に象徴されるように、現在の国際社会では、戦争を始めることは、国家の地位や名誉を高めるというよりは、むしろ、国家に「悪評」を与えることになるため、国家間戦争はますます時代遅れの「非合理的」行為になり、消えていくことになるだろう、ということです。確かに、ルボウ氏の言うことには一理あるようにも思いますが、こうした議論は、かつてジャック・スナイダー氏(コロンビア大学)が、コンストラクティヴィズムを「理想主義のバージョンアップ版」と批判したことに重なります(Jack Snyder, "One World, Rival Theories," Foreign Policy, No. 145, 2004, pp. 53-62)。安全保障ではなく、ランクや名誉こそが、国家を戦争へと導く、もっと強力な原動力なのでしょうか?残念ながら、ルボウ氏の研究が示した証拠は、ベッツ氏も指摘したように、弱いと言わざるを得ないでしょう。ですので、こうした結論に飛びつくのには、より慎重になるべきではないかと私は思っています。