国家の指導者は、不確実性の高い国際政治の世界において、情報を取捨選択する基準として、歴史のアナロジーをしばしば用います。権力の座にある政策決定者は、現在に直面している状況と似ている参考になりそうな過去の歴史の出来事を探り当てて、そこから「教訓」となりそうな推論を引き出そうとします。そして、自分自身が類似すると判断した歴史事象から、反実仮想を行い、対外政策を打ち出すということです。現在において、歴史の教訓として、最も言及されるものの1つが「ミュンヘン宥和」でしょう。これは戦間期のヨーロッパにおける個別事象なのですが、「脅威と認識する国家には妥協してはいけない。そうした宥和は、相手に付け入るスキを与え、こうした国家をつけあがらせることにつながり、さらなる要求を助長するだけだ。相手国からの不当な要求は、最初から、断固として拒否しなければならない。対決的な姿勢こそが、戦争を避けるために必要なのだ」という「一般命題」として受け取られているようです。
「ミュンヘン宥和」とは、1938年9月、ナチス・ドイツのヒトラーがチェコスロバキアのズデーデン地方の併合を要求したことに対して、イギリスのチェンバレン首相(とフランスのダラディエ首相、イタリアのムッソリーニ)が、チェコスロバキア政府を説得して、ヒトラーの要求を呑んでしまったことです。この歴史の出来事は、後の指導者や政治コメンテーター、研究者などに、大きな影響を与えました。ここから1つの「歴史の教訓」が生まれました。イギリスがドイツのズデーデン地方の割譲を要求したことに対して、戦争のリスクを冒してでも拒否していれば、ドイツは引き下がらざるを得なかっただろうから、第二次世界大戦は防げたはずであるという推論です。
この仮説は正しいのでしょうか。起こらなかったことを論証するのは難しい作業ですが、歴史から「正しい教訓」を引き出すためには、「歴史のイフ」を問わなければなりません。すなわち、出来事を引き起こした前提が変化すれば、結果がどう変わったかを確定するということです。こうした研究のことを政治学では「反実仮想実験」といいます。反実仮想は、突拍子もない「歴史のイフ」を問うものではありません。反実仮想には、一定のルールがあります。その1つに、歴史の書き換えは最低限にすることがあります。たとえば、太平洋戦争において日本がF-35戦闘機を多数保有していれば、アメリカに勝利できたであろうといった反実仮想は成立しません。なぜならば、75年前に、日本陸海軍がステルス戦闘機を獲得できた可能性はゼロだからです。
それでは、1938年にイギリスがドイツに譲歩しなければ、歴史はどうなっていたのでしょうか。この難問に1つの解答を与えたのが、ユアン・フーン・コーン氏(シンガポール国立大学)です。かれは、今から4半世紀前に行われた「反実仮想研究」のプロジェクト(於カリフォルニア大学バークレー校)に参加して、上記の「歴史のイフ」に挑みました。こうした意欲的な研究を収めた貴重な文献が、フィリップ・テトロック、アーロン・ベルキン編『世界政治おける反実仮想実験(Counterfactual Thought Experiments in World Politics) 』(プリンストン大学出版局、1996年)です。このアンソロジーに、かれは「ヒトラーとの対決とその帰結」を寄稿しました。そこから導かれた結論は、今でもわれわれに大きな示唆を与えてくれます。かれは次のように主張しています。「もしイギリスがヒトラーに立ち向かっていたら、かれは引き下がり、そして第二次世界大戦は避けられただろうか?この問いに対する答えは、より不確かなものだ。対決はおそらくドイツから3つのうちの1つの反応を引き出したであろう。すなわち、ヒトラーが引き下がったこと、反ヒトラーのクーデターが起こったこと、戦争のいずれかだ…1938年におけるヒトラーとの対決は、1つのもっともらしい反実仮想である。ここから起こりそうな結果が示唆することは、宥和の結果と比べれば、これはマシな政策でもあっただろう」(同書、118ページ)。
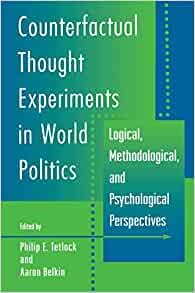
チェンバレンは、ヒトラーを宥和しました。こうした戦争のリスクを避ける戦略をとった背景には、主に3つの要因がありました。第1に、イギリスの政治家のみならず国民には、第一次世界大戦の恐怖が強く残っていたことです。第2に、イギリスの軍備は、ドイツと対決するのに十分な戦力に達していませんでした。第3に、チェンバレンが外交を選好する強固な信念を持っていたことです。かれは、フランスは頼りなく、アメリカは孤立主義にあり、ソ連は信用できないと思っていました。これらが、イギリスにドイツに対して単独で立ち向かうことを忌避させたのです。そして、チェンバレンは誰よりも、宥和政策の必要性と効果を信じていました。かれはイギリスの権力のトップに君臨する政治家として、ドイツの拡張を抑止することより宥和することを選好したということです(同書、100-105ページ)。
当時、イギリスにはドイツに対して対決姿勢でのぞむべきだと考える政治家もいました。アンソニー・イーデン、ダフ・クーパー、そしてウィンストン・チャーチルです。ここで興味深い反実仮想が浮かびます。ミュンヘン宥和の前提を変えて、もし彼らのうち2人以上が1938年9月時点でチェンバレン政権の閣僚だったならば、ヒトラーに立ち向かった可能性はグンと上がるのです。こうした反実仮想は、最小限の歴史の書き換えという研究の方法論上の手続きに則ったものなので妥当だといえるでしょう。それでは、イギリスがナチスドイツに断固とした姿勢を示して、ズデーデン併合の要求を拒否したならば、どうなっていたでしょうか。通説は、イギリスに加えて、フランスやソ連もドイツに立ちむかったであろうから、ヒトラーは引き下がらざろう得なかったというものです。しかしながら、歴史証拠は別の展開も示唆しています。当時、ドイツは戦争を遂行する準備が十分にできていませんでしたので、軍の将校たちには、ヒトラーの強引な政策に反対する者もいました。ヒトラーが戦争を起こしたとしても、こうした反ヒトラーの勢力が、イギリスの対決姿勢に促され、かれを権力の座から引きずりおろして、和平に向かっただろうとのシナリオも考えられます(同書、105-114ページ)。
もう1つのシナリオは、1938年時点で、戦争は起こっていだろうというものです。チャーチルは、対独抑止が失敗した場合、戦争に突入する心構えでした。ヒトラーが抑止できたかどうかは、意見が分かれるところです。有力な1つの見方は、ヒトラーは交渉よりも戦争を選好していたので、抑止は効かなかったという推論です。ヒトラーは戦争をせずにミュンヘン協定を結んだことは間違いだったと悔いていたというのが、その根拠です。このことは、イギリスが威嚇すればドイツは戦争へと突き進んでいただろうとの結論に結びつきます。要するに、戦争は1938年9月時点で起こっていたということです。それでは実際に起こった1939年の戦争と起こったであろう1938年の戦争では、どちらが望ましい結果といえるでしょうか。前者のケースでは、イギリスがドイツ空軍の攻撃に対する防空能力を築く時間を稼げたぶん、その脆弱性は減少したといえます。他方、後者のケースでは、ドイツはイギリスに加えて、ポーランドより軍備で優るチェコスロバキアと戦うことになります。さらに、独ソ不可侵条約締結前ですので、ドイツはソ連の動向を心配するのみならず、西部方面でフランスと対決しなければなりません(同書、115-117ページ)。いずれにせよ、大規模な戦争になっていたと考えられます。
それでは、対決と宥和の相対的な政策の長所について、総合的には、どのような評価を下せるでしょうか。コーン氏による反実仮想を用いた「ミュンヘン危機」の分析は、以下のような結論に達します。
「最初の2つの結果、すなわちヒトラーが引き下がること、反ヒトラーのクーデターが起こることは、はるかに望ましいだろう…(1938年に起こったであろう戦争は)1939年に実際に宣言された戦争の軌跡とほぼ同じような成り行きになると考えるに十分だろう…われわれは興味深い結論にたどりつく。すなわち、対決は宥和より好ましかったであろうということだ。なぜならば、その最悪の結果は『1939年の成り行きより悪くはない』だろうからだ」(同書、117ページ)。
「ミュンヘン宥和」から歴史の教訓を引き出すということは、1つの事例から推論される因果メカニズムを他の事例に適用するということです。それでは、1938年の「ミュンヘン危機」の教訓は、どこまで一般化できるでしょうか。リアリズムのような構造的な一般理論に懐疑的なリチャード・ルボウ氏(キングス・カレッジ)は、理論的志向の研究者が陥りやすい、傾聴に値する「罠」を以下のように指摘しています。
「国際関係理論において、研究者は第一次世界大戦のような重要な事例をより広範囲で稀ではない出来事の集合を代表する事例だと黙って思い込む。この思い込みは、重要な原因を重要な出来事の属性とする認知バイアスを反映するものといえる」(Forbidden Fruit: Counterfactuals and International Relations, Princeton University Press, 2010, p. 18)
かれが警告していることには、理論家のみならず政策指向の評論家や政治指導者も耳を傾けるべきでしょう。特定の重要な歴史事象から抽出された仮定の原因は、結果を広く説明できるとは限らないということです。社会科学のジャーゴンを使って言い換えれば、戦争回避という従属変数(結果)は、対決という独立変数(原因)が引き起こすとは限らず、これらの変数間の因果関係は条件付きで成立するものにすぎないということでしょう。「ミュンヘン宥和」は重要な歴史の出来事ですが、この事例を使った反実仮想実験は、いくつかの研究スタイルのうちの「個別・具体的(idiographic)」なものに過ぎません(同書、7-8ページ)。この事例から引き出された因果的推論を現在世界における政策決定のガイダンスにするには、科学的方法のいくつかのステップを踏まなければなりません。この推論を反証可能な因果仮説として構築したうえで、その適用範囲を定めたり、仮説の先行条件や拡大条件を明確にするための検証を行なうことが第1歩です。こうした科学的な手続きを経なければ、この歴史の教訓が、どの政策課題にあてはまるのかは分かりません。
ザックリと結論めいたことをいえば、他の条件が等しければ(ceteris paribus)、抑止は「現状打破国」に勢力拡大行動を思いとどまらせる戦略として有効でしょう。しかしながら、現実世界では、こうした条件が整うことは滅多にありません。抑止は宥和より常に望ましい結果をもたらすとは限らないのです。相手国との対決を企図する抑止は国家の安全保障にとって万能な戦略ではなく、条件次第では、避けようとした結果を招く「自己敗北的予言」になったり、相手の武力行使を挑発したりすることもあります。たとえば、抑止の対象国が損失回避の高いインセンティヴを持っている場合、抑止の威嚇はかえって冒険的な行動を引き出しがちです(対日石油禁輸を受けての日本の真珠湾攻撃やキューバ危機におけるソ連の核ミサイル導入、第4次中東戦争におけるエジプトのイスラエルへの奇襲攻撃など)。反実仮想の判断は歴史からのいななる学習にとっても必要条件です。その一方で、個別具体的事例研究の反実仮想による抽象的な因果推論は、そのまま現実世界の事例に適用できないことをわれわれは心に留めるできべきでしょう。
「ミュンヘン宥和」とは、1938年9月、ナチス・ドイツのヒトラーがチェコスロバキアのズデーデン地方の併合を要求したことに対して、イギリスのチェンバレン首相(とフランスのダラディエ首相、イタリアのムッソリーニ)が、チェコスロバキア政府を説得して、ヒトラーの要求を呑んでしまったことです。この歴史の出来事は、後の指導者や政治コメンテーター、研究者などに、大きな影響を与えました。ここから1つの「歴史の教訓」が生まれました。イギリスがドイツのズデーデン地方の割譲を要求したことに対して、戦争のリスクを冒してでも拒否していれば、ドイツは引き下がらざるを得なかっただろうから、第二次世界大戦は防げたはずであるという推論です。
この仮説は正しいのでしょうか。起こらなかったことを論証するのは難しい作業ですが、歴史から「正しい教訓」を引き出すためには、「歴史のイフ」を問わなければなりません。すなわち、出来事を引き起こした前提が変化すれば、結果がどう変わったかを確定するということです。こうした研究のことを政治学では「反実仮想実験」といいます。反実仮想は、突拍子もない「歴史のイフ」を問うものではありません。反実仮想には、一定のルールがあります。その1つに、歴史の書き換えは最低限にすることがあります。たとえば、太平洋戦争において日本がF-35戦闘機を多数保有していれば、アメリカに勝利できたであろうといった反実仮想は成立しません。なぜならば、75年前に、日本陸海軍がステルス戦闘機を獲得できた可能性はゼロだからです。
それでは、1938年にイギリスがドイツに譲歩しなければ、歴史はどうなっていたのでしょうか。この難問に1つの解答を与えたのが、ユアン・フーン・コーン氏(シンガポール国立大学)です。かれは、今から4半世紀前に行われた「反実仮想研究」のプロジェクト(於カリフォルニア大学バークレー校)に参加して、上記の「歴史のイフ」に挑みました。こうした意欲的な研究を収めた貴重な文献が、フィリップ・テトロック、アーロン・ベルキン編『世界政治おける反実仮想実験(Counterfactual Thought Experiments in World Politics) 』(プリンストン大学出版局、1996年)です。このアンソロジーに、かれは「ヒトラーとの対決とその帰結」を寄稿しました。そこから導かれた結論は、今でもわれわれに大きな示唆を与えてくれます。かれは次のように主張しています。「もしイギリスがヒトラーに立ち向かっていたら、かれは引き下がり、そして第二次世界大戦は避けられただろうか?この問いに対する答えは、より不確かなものだ。対決はおそらくドイツから3つのうちの1つの反応を引き出したであろう。すなわち、ヒトラーが引き下がったこと、反ヒトラーのクーデターが起こったこと、戦争のいずれかだ…1938年におけるヒトラーとの対決は、1つのもっともらしい反実仮想である。ここから起こりそうな結果が示唆することは、宥和の結果と比べれば、これはマシな政策でもあっただろう」(同書、118ページ)。
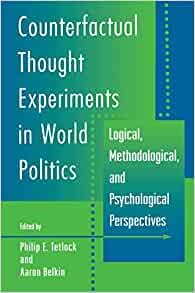
チェンバレンは、ヒトラーを宥和しました。こうした戦争のリスクを避ける戦略をとった背景には、主に3つの要因がありました。第1に、イギリスの政治家のみならず国民には、第一次世界大戦の恐怖が強く残っていたことです。第2に、イギリスの軍備は、ドイツと対決するのに十分な戦力に達していませんでした。第3に、チェンバレンが外交を選好する強固な信念を持っていたことです。かれは、フランスは頼りなく、アメリカは孤立主義にあり、ソ連は信用できないと思っていました。これらが、イギリスにドイツに対して単独で立ち向かうことを忌避させたのです。そして、チェンバレンは誰よりも、宥和政策の必要性と効果を信じていました。かれはイギリスの権力のトップに君臨する政治家として、ドイツの拡張を抑止することより宥和することを選好したということです(同書、100-105ページ)。
当時、イギリスにはドイツに対して対決姿勢でのぞむべきだと考える政治家もいました。アンソニー・イーデン、ダフ・クーパー、そしてウィンストン・チャーチルです。ここで興味深い反実仮想が浮かびます。ミュンヘン宥和の前提を変えて、もし彼らのうち2人以上が1938年9月時点でチェンバレン政権の閣僚だったならば、ヒトラーに立ち向かった可能性はグンと上がるのです。こうした反実仮想は、最小限の歴史の書き換えという研究の方法論上の手続きに則ったものなので妥当だといえるでしょう。それでは、イギリスがナチスドイツに断固とした姿勢を示して、ズデーデン併合の要求を拒否したならば、どうなっていたでしょうか。通説は、イギリスに加えて、フランスやソ連もドイツに立ちむかったであろうから、ヒトラーは引き下がらざろう得なかったというものです。しかしながら、歴史証拠は別の展開も示唆しています。当時、ドイツは戦争を遂行する準備が十分にできていませんでしたので、軍の将校たちには、ヒトラーの強引な政策に反対する者もいました。ヒトラーが戦争を起こしたとしても、こうした反ヒトラーの勢力が、イギリスの対決姿勢に促され、かれを権力の座から引きずりおろして、和平に向かっただろうとのシナリオも考えられます(同書、105-114ページ)。
もう1つのシナリオは、1938年時点で、戦争は起こっていだろうというものです。チャーチルは、対独抑止が失敗した場合、戦争に突入する心構えでした。ヒトラーが抑止できたかどうかは、意見が分かれるところです。有力な1つの見方は、ヒトラーは交渉よりも戦争を選好していたので、抑止は効かなかったという推論です。ヒトラーは戦争をせずにミュンヘン協定を結んだことは間違いだったと悔いていたというのが、その根拠です。このことは、イギリスが威嚇すればドイツは戦争へと突き進んでいただろうとの結論に結びつきます。要するに、戦争は1938年9月時点で起こっていたということです。それでは実際に起こった1939年の戦争と起こったであろう1938年の戦争では、どちらが望ましい結果といえるでしょうか。前者のケースでは、イギリスがドイツ空軍の攻撃に対する防空能力を築く時間を稼げたぶん、その脆弱性は減少したといえます。他方、後者のケースでは、ドイツはイギリスに加えて、ポーランドより軍備で優るチェコスロバキアと戦うことになります。さらに、独ソ不可侵条約締結前ですので、ドイツはソ連の動向を心配するのみならず、西部方面でフランスと対決しなければなりません(同書、115-117ページ)。いずれにせよ、大規模な戦争になっていたと考えられます。
それでは、対決と宥和の相対的な政策の長所について、総合的には、どのような評価を下せるでしょうか。コーン氏による反実仮想を用いた「ミュンヘン危機」の分析は、以下のような結論に達します。
「最初の2つの結果、すなわちヒトラーが引き下がること、反ヒトラーのクーデターが起こることは、はるかに望ましいだろう…(1938年に起こったであろう戦争は)1939年に実際に宣言された戦争の軌跡とほぼ同じような成り行きになると考えるに十分だろう…われわれは興味深い結論にたどりつく。すなわち、対決は宥和より好ましかったであろうということだ。なぜならば、その最悪の結果は『1939年の成り行きより悪くはない』だろうからだ」(同書、117ページ)。
「ミュンヘン宥和」から歴史の教訓を引き出すということは、1つの事例から推論される因果メカニズムを他の事例に適用するということです。それでは、1938年の「ミュンヘン危機」の教訓は、どこまで一般化できるでしょうか。リアリズムのような構造的な一般理論に懐疑的なリチャード・ルボウ氏(キングス・カレッジ)は、理論的志向の研究者が陥りやすい、傾聴に値する「罠」を以下のように指摘しています。
「国際関係理論において、研究者は第一次世界大戦のような重要な事例をより広範囲で稀ではない出来事の集合を代表する事例だと黙って思い込む。この思い込みは、重要な原因を重要な出来事の属性とする認知バイアスを反映するものといえる」(Forbidden Fruit: Counterfactuals and International Relations, Princeton University Press, 2010, p. 18)
かれが警告していることには、理論家のみならず政策指向の評論家や政治指導者も耳を傾けるべきでしょう。特定の重要な歴史事象から抽出された仮定の原因は、結果を広く説明できるとは限らないということです。社会科学のジャーゴンを使って言い換えれば、戦争回避という従属変数(結果)は、対決という独立変数(原因)が引き起こすとは限らず、これらの変数間の因果関係は条件付きで成立するものにすぎないということでしょう。「ミュンヘン宥和」は重要な歴史の出来事ですが、この事例を使った反実仮想実験は、いくつかの研究スタイルのうちの「個別・具体的(idiographic)」なものに過ぎません(同書、7-8ページ)。この事例から引き出された因果的推論を現在世界における政策決定のガイダンスにするには、科学的方法のいくつかのステップを踏まなければなりません。この推論を反証可能な因果仮説として構築したうえで、その適用範囲を定めたり、仮説の先行条件や拡大条件を明確にするための検証を行なうことが第1歩です。こうした科学的な手続きを経なければ、この歴史の教訓が、どの政策課題にあてはまるのかは分かりません。
ザックリと結論めいたことをいえば、他の条件が等しければ(ceteris paribus)、抑止は「現状打破国」に勢力拡大行動を思いとどまらせる戦略として有効でしょう。しかしながら、現実世界では、こうした条件が整うことは滅多にありません。抑止は宥和より常に望ましい結果をもたらすとは限らないのです。相手国との対決を企図する抑止は国家の安全保障にとって万能な戦略ではなく、条件次第では、避けようとした結果を招く「自己敗北的予言」になったり、相手の武力行使を挑発したりすることもあります。たとえば、抑止の対象国が損失回避の高いインセンティヴを持っている場合、抑止の威嚇はかえって冒険的な行動を引き出しがちです(対日石油禁輸を受けての日本の真珠湾攻撃やキューバ危機におけるソ連の核ミサイル導入、第4次中東戦争におけるエジプトのイスラエルへの奇襲攻撃など)。反実仮想の判断は歴史からのいななる学習にとっても必要条件です。その一方で、個別具体的事例研究の反実仮想による抽象的な因果推論は、そのまま現実世界の事例に適用できないことをわれわれは心に留めるできべきでしょう。
























