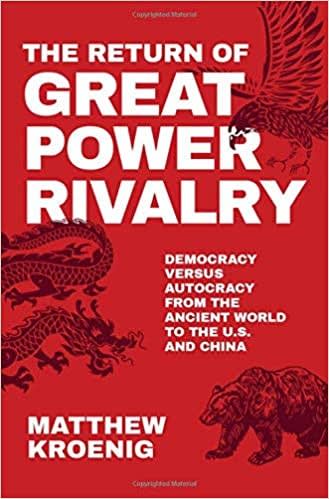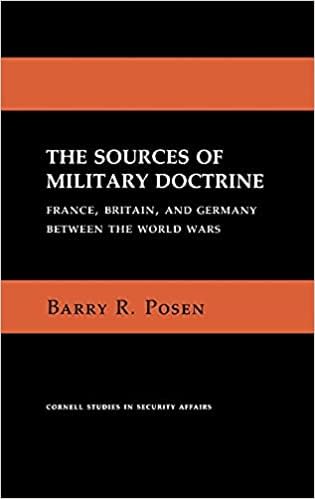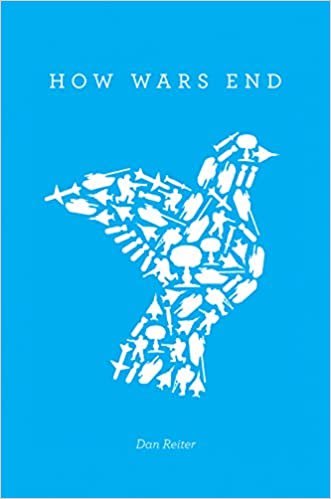国際関係の主要な大理論は概して大国の行動を説明することに主眼があるため、中小国がとる戦略の分析に、うまくあてはまらないことがあります。国家の行動を教科書的に分類すれば、それらは主に①バランシング行動(台頭国への対抗行動)、②バンドワゴニング行動、③バックパッシング行動(対抗措置をとる「責務」を他国に転嫁する行動)となるでしょう。もちろん、これらのカテゴリーが、中小国の行動をまったく説明できないわけではありません。大国の脅威に直面した小国は、有効な同盟パートナーを見つけられない場合、その生き残り戦略として、大国の慈悲に期待して、脅威の源泉となる大国と連携する行動をとることがあります。こうした対外政策は、バンドワゴニング行動として説明できます。たとえば、第二次世界大戦後、フィンランドが採用した対ソ戦略は、バンドワゴニング行動として理解できます。他方、この数十年で、東南アジア諸国の行動原理を説明する概念として「ヘッジング戦略」という用語がしばしば使われるようになりました(ヘッジングについては、John D. Ciorciari and Jürgen Haacke, "Hedging in International Relations: An Introduction," International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 19, Issue. 3, September 2019が先行研究をレヴューしてまとめています。なお同号はヘッジングを特集しています)。このヘッジング行動は、大国間競争が繰り広げられる国際政治の世界において、中小国が存立を維持するために英知を結集して構築した賢い戦略であると評価できます。
ヘッジング行動は、バランシング行動とバンドワゴニング行動の中間に位置づけられるようです。このようにヘッジング行動は記述的には説明できます。しかしながら、これを理論的に首尾一貫したロジックで説明するのは、かなり難しい作業ではないでしょうか。このあいまいな理論的に位置づけになる国家行動は、いったいどのようなロジックで解明したらよいのでしょうか。いうまでもなく、国家がとる行動は複合的な要因から成り立っているため、バランシング行動やバンドワゴニング行動といった「理念型」にピッタリと当てはまる事例は、むしろ少ないのかもしれません。その一方で、社会科学としての国際関係論が、複雑な事象をできるだけ単純化して明らかにすることを主な使命としているのであれば、国家の戦略は、より簡潔な理論やモデルで説明されるべきでしょう。どうしても既存の簡潔な理論では説明できない「逸脱事例」を観察した場合、その理論に別の変数を加えて複雑化することで、こうした事例を説明するのが方法論上の一般的な研究手続きといえます。
それでは、東南アジア諸国の対外政策は、国際関係の典型的な行動パターンにあてはまらないのでしょうか。デーヴィッド・シャンボー氏(ジョージ・ワシントン大学)は、そうだと主張しています。かれは論文「東南アジアにおける米中ライバル関係」("U.S.-China Rivalry in Southeast Asia: Power Shift or Competitive Coexistence?" International Security, Vol. 42, No. 4, Spring 2018)において、こういっています。
「いくつかの指標は、特定の問題に関するバンドワゴニング行動を含めて、中国が東南アジア地域全般により食い込んできていることを示しているが、わたしは、この地域における全体的な戦略バランスは流動的で競合的だと主張したい…(ASEAN)諸国は長い間、ワシントンと北京の両方とのつながりをうまく調整しようと努める『ヘッジング政策』を追求してきたのだ。ただし、2016-17年以来、ほとんどのASEAN諸国は北京にかなり接近していることが明らかになってきた」(上記論文、86-87ページ)。
シャンボー氏は中国やアジア国際関係研究の専門家です。とりわけ、中国の対外関係に関する注目すべき論文を数多く執筆しています(たとえば、「中国のシンクタンク」の分析など)。地域研究は、簡潔性をある程度は犠牲にしてでも、観察の対象をできるだけ詳細かつ正確に分析する傾向にあります。ですから、かれが地域研究者として、ASEAN諸国の行動を上記のように説明するのは理解できます。ただ、こうしたあいまいな説明には代償がつきものです。
シャンボー氏は、ASEAN10カ国の行動の特徴を複数の理念型で記述的に説明しています。かれは、これらの国々が中国にどのくらい近いかの尺度で、その政策を6つに分類しています。①「降伏主義」がカンボジアです。中国の「クライアント国家」ということです。②「チェーファー」がミャンマーとラオスになります。これは中国にかなり依存せざるを得ない国家ということです。③「連携的便宜主義」がマレーシアとタイになります。これは中国と極めて緊密な関係にあるものの、アメリカとの関係も同時に維持している国家のタイプです。④「チルター」がフィリピンとブルネイです。中国に傾いている国家ということです。⑤「均衡的ヘッジャ―」がヴェトナムとシンガポールです。アメリカと防衛でつながる一方、中国とも広範な関係を維持している国家になります。⑥「外れ値」がインドネシアです。わが道を進む国家ということのようです。このように東南アジア諸国は、6つの国家行動のカテゴリーに収められています(上記論文、100-103ページ)。
こうした記述的な分析は、東南アジア諸国の行動パターンを分類して理解するには役立ちますが、そこには因果的推論がほとんど欠如しています。すなわち、シャンボー氏の論文は、ASEAN諸国の対米中戦略を整理したにすぎず、何がヘッジング政策の源泉なのかは不明なままだということです。さらには、ヘッジング行動の先行条件や拡大条件も明示されていません。こうした理論的な欠落は、ASEAN諸国がどのような行動をとるのかを予測する際に混乱をきたすのみならず、アメリカがとるべき戦略の提言も矛盾したものになります。たとえば、シャンボー氏は、アメリカは東南アジア地域から離れていることが、中国との競争において不利に働いていると指摘しています。そうであれば、アメリカはASEAN諸国に「接近」するべきでしょう。しかしながら、かれはこうもいっています。「多くの東南アジア諸国は、オフショア・バランサーとしてのアメリカに視線を向けており、これはアメリカができる、とるべき1つの役割なのだ」(上記論文、127ページ)。オフショア・バランシングは、一種のバックパッシングです。つまり、アメリカがオフショア・バランシング戦略をとるということは、中国が地域覇権を打ち立てるのを阻止する「責任」を東南アジア諸国は多かれ少なかれ引き受けるということです。アメリカは沖合に引いたまま東南アジア諸国に近づくことなくして、どうやって、これらの諸国に対中バランシング行動をとらせるのでしょうか。
さらに、シャンボー氏は「(ワシントンは)東南アジア地域において、中国を封じ込める調整された戦略を構築する、いかなる誘惑も避けるべきだ。なぜなら、どの東南アジア諸国もそのような動きには、ついて行かないだろう」(上記論文、126ページ)と警告しています。ところが、その直後に、「中国が東南アジア地域で過剰拡張して自己主張をあまりに強めてきた場合、その時は、アメリカは物理的プレゼンスを提供するとともに、東南アジア諸国にとって信頼できるパートナーとして認識される必要がある」(上記論文、127ページ)とも助言しています。これは両立しない政策提言ではないでしょうか。第1に、なぜ東南アジア諸国は、中国にバンドワゴンしないで、突然、アメリカに「ついて行く」ことになるのか不明です。このような政策を提言するには、まず中国のパワーの上昇がASEAN諸国の政策選好に及ぼす因果効果を定式化しなければなりません。すなわち、東南アジアにおけるバランス・オブ・パワーが、ASEAN諸国にとって著しく不利に傾いた場合、これらの諸国は「ヘッジング戦略」を放棄して、アメリカとの「同盟」を模索するという仮説を立て、それが妥当であることを実証するということです。しかしながら、上記の論文では、こうした理論的な作業は行われていません。第2に、こうしたアドバイスは論理的に矛盾しています。東南アジア地域におけるアメリカの「物理的プレゼンス」は、軍の前方展開のことでしょう。これは「対中封じ込め戦略」の推奨とも理解できますが、にもかかわらず、かれは東南アジア諸国の同意を得られない「封じ込め政策」は、アメリカのとるべき戦略ではではないともいっているのです。ジョーゼフ・ヘラーの小説『キャッチ22』のようです。
こうした政策提言の混乱は、どうやら東南アジア諸国の戦略的行動を説明する一貫した理論が、シャンボー氏の上記の研究で欠如していることに求められそうです。「ヘッジング政策」という概念は、東南アジア諸国の行動を描写するには便利な道具かもしれません。しかしながら、そのロジックには因果関係が欠けているために、残念ながら、東南アジア諸国の行動を分析できる「科学的な」ツールにはなっていないと思います。「ヘッジング」を国家行動の「理論」とするためには、その因果メカニズムをまずは明確にすることが必要ではないでしょうか。
ヘッジング行動は、バランシング行動とバンドワゴニング行動の中間に位置づけられるようです。このようにヘッジング行動は記述的には説明できます。しかしながら、これを理論的に首尾一貫したロジックで説明するのは、かなり難しい作業ではないでしょうか。このあいまいな理論的に位置づけになる国家行動は、いったいどのようなロジックで解明したらよいのでしょうか。いうまでもなく、国家がとる行動は複合的な要因から成り立っているため、バランシング行動やバンドワゴニング行動といった「理念型」にピッタリと当てはまる事例は、むしろ少ないのかもしれません。その一方で、社会科学としての国際関係論が、複雑な事象をできるだけ単純化して明らかにすることを主な使命としているのであれば、国家の戦略は、より簡潔な理論やモデルで説明されるべきでしょう。どうしても既存の簡潔な理論では説明できない「逸脱事例」を観察した場合、その理論に別の変数を加えて複雑化することで、こうした事例を説明するのが方法論上の一般的な研究手続きといえます。
それでは、東南アジア諸国の対外政策は、国際関係の典型的な行動パターンにあてはまらないのでしょうか。デーヴィッド・シャンボー氏(ジョージ・ワシントン大学)は、そうだと主張しています。かれは論文「東南アジアにおける米中ライバル関係」("U.S.-China Rivalry in Southeast Asia: Power Shift or Competitive Coexistence?" International Security, Vol. 42, No. 4, Spring 2018)において、こういっています。
「いくつかの指標は、特定の問題に関するバンドワゴニング行動を含めて、中国が東南アジア地域全般により食い込んできていることを示しているが、わたしは、この地域における全体的な戦略バランスは流動的で競合的だと主張したい…(ASEAN)諸国は長い間、ワシントンと北京の両方とのつながりをうまく調整しようと努める『ヘッジング政策』を追求してきたのだ。ただし、2016-17年以来、ほとんどのASEAN諸国は北京にかなり接近していることが明らかになってきた」(上記論文、86-87ページ)。
シャンボー氏は中国やアジア国際関係研究の専門家です。とりわけ、中国の対外関係に関する注目すべき論文を数多く執筆しています(たとえば、「中国のシンクタンク」の分析など)。地域研究は、簡潔性をある程度は犠牲にしてでも、観察の対象をできるだけ詳細かつ正確に分析する傾向にあります。ですから、かれが地域研究者として、ASEAN諸国の行動を上記のように説明するのは理解できます。ただ、こうしたあいまいな説明には代償がつきものです。
シャンボー氏は、ASEAN10カ国の行動の特徴を複数の理念型で記述的に説明しています。かれは、これらの国々が中国にどのくらい近いかの尺度で、その政策を6つに分類しています。①「降伏主義」がカンボジアです。中国の「クライアント国家」ということです。②「チェーファー」がミャンマーとラオスになります。これは中国にかなり依存せざるを得ない国家ということです。③「連携的便宜主義」がマレーシアとタイになります。これは中国と極めて緊密な関係にあるものの、アメリカとの関係も同時に維持している国家のタイプです。④「チルター」がフィリピンとブルネイです。中国に傾いている国家ということです。⑤「均衡的ヘッジャ―」がヴェトナムとシンガポールです。アメリカと防衛でつながる一方、中国とも広範な関係を維持している国家になります。⑥「外れ値」がインドネシアです。わが道を進む国家ということのようです。このように東南アジア諸国は、6つの国家行動のカテゴリーに収められています(上記論文、100-103ページ)。
こうした記述的な分析は、東南アジア諸国の行動パターンを分類して理解するには役立ちますが、そこには因果的推論がほとんど欠如しています。すなわち、シャンボー氏の論文は、ASEAN諸国の対米中戦略を整理したにすぎず、何がヘッジング政策の源泉なのかは不明なままだということです。さらには、ヘッジング行動の先行条件や拡大条件も明示されていません。こうした理論的な欠落は、ASEAN諸国がどのような行動をとるのかを予測する際に混乱をきたすのみならず、アメリカがとるべき戦略の提言も矛盾したものになります。たとえば、シャンボー氏は、アメリカは東南アジア地域から離れていることが、中国との競争において不利に働いていると指摘しています。そうであれば、アメリカはASEAN諸国に「接近」するべきでしょう。しかしながら、かれはこうもいっています。「多くの東南アジア諸国は、オフショア・バランサーとしてのアメリカに視線を向けており、これはアメリカができる、とるべき1つの役割なのだ」(上記論文、127ページ)。オフショア・バランシングは、一種のバックパッシングです。つまり、アメリカがオフショア・バランシング戦略をとるということは、中国が地域覇権を打ち立てるのを阻止する「責任」を東南アジア諸国は多かれ少なかれ引き受けるということです。アメリカは沖合に引いたまま東南アジア諸国に近づくことなくして、どうやって、これらの諸国に対中バランシング行動をとらせるのでしょうか。
さらに、シャンボー氏は「(ワシントンは)東南アジア地域において、中国を封じ込める調整された戦略を構築する、いかなる誘惑も避けるべきだ。なぜなら、どの東南アジア諸国もそのような動きには、ついて行かないだろう」(上記論文、126ページ)と警告しています。ところが、その直後に、「中国が東南アジア地域で過剰拡張して自己主張をあまりに強めてきた場合、その時は、アメリカは物理的プレゼンスを提供するとともに、東南アジア諸国にとって信頼できるパートナーとして認識される必要がある」(上記論文、127ページ)とも助言しています。これは両立しない政策提言ではないでしょうか。第1に、なぜ東南アジア諸国は、中国にバンドワゴンしないで、突然、アメリカに「ついて行く」ことになるのか不明です。このような政策を提言するには、まず中国のパワーの上昇がASEAN諸国の政策選好に及ぼす因果効果を定式化しなければなりません。すなわち、東南アジアにおけるバランス・オブ・パワーが、ASEAN諸国にとって著しく不利に傾いた場合、これらの諸国は「ヘッジング戦略」を放棄して、アメリカとの「同盟」を模索するという仮説を立て、それが妥当であることを実証するということです。しかしながら、上記の論文では、こうした理論的な作業は行われていません。第2に、こうしたアドバイスは論理的に矛盾しています。東南アジア地域におけるアメリカの「物理的プレゼンス」は、軍の前方展開のことでしょう。これは「対中封じ込め戦略」の推奨とも理解できますが、にもかかわらず、かれは東南アジア諸国の同意を得られない「封じ込め政策」は、アメリカのとるべき戦略ではではないともいっているのです。ジョーゼフ・ヘラーの小説『キャッチ22』のようです。
こうした政策提言の混乱は、どうやら東南アジア諸国の戦略的行動を説明する一貫した理論が、シャンボー氏の上記の研究で欠如していることに求められそうです。「ヘッジング政策」という概念は、東南アジア諸国の行動を描写するには便利な道具かもしれません。しかしながら、そのロジックには因果関係が欠けているために、残念ながら、東南アジア諸国の行動を分析できる「科学的な」ツールにはなっていないと思います。「ヘッジング」を国家行動の「理論」とするためには、その因果メカニズムをまずは明確にすることが必要ではないでしょうか。