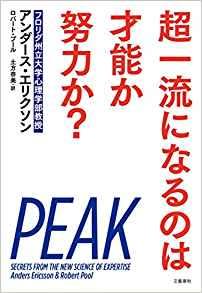ある調査によると、小学生男子がなりたい職業の第1位は、「学者・博士」のようです。確かに、メディアには、〇〇大学教授といった「学者」を肩書にする人物がしばしば登場して、さまざまな問題にコメントをよせたり、意見を発したりしています。優れた研究成果を残した学者は、社会から高い尊敬を集めます。こうしたことから、小学生が「学者・博士」に憧れても、不思議ではありません。
私は小学生の「夢」を壊したいと思いませんが、「学者・博士」の実態が、どれだけ世間で理解されているのか、とても気になっています。おそらく、ほとんど理解されてないのでしょう。
第1に、博士号を取得しても、大学で学問を生業にできる研究者は、ごく一部です。ある教育社会学者によれば、大学教員のポストは、今や博士24人に1人です。とても狭き門をくぐらないと、大学教授にはなれません。いわゆる文系では、アカポスをめぐる競争率は、理系より高くなります。その結果、一生涯「フリーター」の博士もは珍しくないのです。これには多くの人達は驚くでしょうが、偽らざる実態です。
第2に、大学教員の最高位である教授は、世の中の多くの人がイメージするほど、給与が高くありません。大学教授(60歳)の平均年収は、大手企業の課長クラスと指摘されています。しかも、大学教員の就職は、一般企業や公務員より、はるかに遅い。博士号を取得するまでに時間がかかり、さらに、専任教員や研究員のポストを得るための「就活期間」も決して短くありません。30歳代半ばから40歳前後といったところでしょう。20歳代で正職がみつかる学者は、そうとうな幸運に恵まれいます。したがって、生涯賃金は、大手企業のビジネスパーソンに比べると、さらに下がります。さらに、多くの「学者」は、大学院時代に受けていた奨学金を返済しなければなりません。
運良く大学教員のポストを得たとしても、その仕事の実際はどうでしょうか。興味のある人は、櫻田大造『大学教員採用・人事のカラクリ』中公新書、2011年を読んで下さい。
キャリア教育は、今では子どもの時からから行われています。果たして、「職業としての学問」は、どのくらい小学生に教えられているのでしょうか。わたしは学者を目指して大学院に進学する際、ゼミナールの先生から「一生、定職につけず、フリーターで終わる覚悟がなければやめるべきだ」とアドバイスされました。これはとてもよい助言でした。
わたしは、かなり悲壮な覚悟で研究者を目指したのです。そして大学での正規の仕事すなわち正教授職に就けたのは幸運以外のなにものでもありません。社会学の巨人であるマック・ウェーバーでさえ「この世の中で大学の教師ほど、偶然によって決まる仕事をわたしはほかに知らないほどです。実際のところわたしがかつてごく若い頃に、一つの学科の正教授に就任できたのも、まったくの偶然によるものでした…わたしが選ばれたのは僥倖のおかげだったので、これをとくに強調したいのです」と言っているくらいです(マックス・ウェーバー『職業としての政治/職業としての学問』中山元訳、日経BP、2009年、168-169頁)。
現在、学者を目指して大学院やポスドクで頑張っている若い人たちは、こうしたアドバイスを受けているのか、気になるところです。「こんなはずではなかった」と後悔していなければよいのですが…。
私は小学生の「夢」を壊したいと思いませんが、「学者・博士」の実態が、どれだけ世間で理解されているのか、とても気になっています。おそらく、ほとんど理解されてないのでしょう。
第1に、博士号を取得しても、大学で学問を生業にできる研究者は、ごく一部です。ある教育社会学者によれば、大学教員のポストは、今や博士24人に1人です。とても狭き門をくぐらないと、大学教授にはなれません。いわゆる文系では、アカポスをめぐる競争率は、理系より高くなります。その結果、一生涯「フリーター」の博士もは珍しくないのです。これには多くの人達は驚くでしょうが、偽らざる実態です。
第2に、大学教員の最高位である教授は、世の中の多くの人がイメージするほど、給与が高くありません。大学教授(60歳)の平均年収は、大手企業の課長クラスと指摘されています。しかも、大学教員の就職は、一般企業や公務員より、はるかに遅い。博士号を取得するまでに時間がかかり、さらに、専任教員や研究員のポストを得るための「就活期間」も決して短くありません。30歳代半ばから40歳前後といったところでしょう。20歳代で正職がみつかる学者は、そうとうな幸運に恵まれいます。したがって、生涯賃金は、大手企業のビジネスパーソンに比べると、さらに下がります。さらに、多くの「学者」は、大学院時代に受けていた奨学金を返済しなければなりません。
運良く大学教員のポストを得たとしても、その仕事の実際はどうでしょうか。興味のある人は、櫻田大造『大学教員採用・人事のカラクリ』中公新書、2011年を読んで下さい。
キャリア教育は、今では子どもの時からから行われています。果たして、「職業としての学問」は、どのくらい小学生に教えられているのでしょうか。わたしは学者を目指して大学院に進学する際、ゼミナールの先生から「一生、定職につけず、フリーターで終わる覚悟がなければやめるべきだ」とアドバイスされました。これはとてもよい助言でした。
わたしは、かなり悲壮な覚悟で研究者を目指したのです。そして大学での正規の仕事すなわち正教授職に就けたのは幸運以外のなにものでもありません。社会学の巨人であるマック・ウェーバーでさえ「この世の中で大学の教師ほど、偶然によって決まる仕事をわたしはほかに知らないほどです。実際のところわたしがかつてごく若い頃に、一つの学科の正教授に就任できたのも、まったくの偶然によるものでした…わたしが選ばれたのは僥倖のおかげだったので、これをとくに強調したいのです」と言っているくらいです(マックス・ウェーバー『職業としての政治/職業としての学問』中山元訳、日経BP、2009年、168-169頁)。
現在、学者を目指して大学院やポスドクで頑張っている若い人たちは、こうしたアドバイスを受けているのか、気になるところです。「こんなはずではなかった」と後悔していなければよいのですが…。