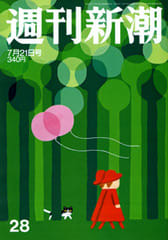『読売新聞』の、日本テレビのドラマ「ピースボート―Piece Vote―」に関する記事の中でコメントしました。
このドラマ、データ放送との連動を行っているのですが、これまでの“連動”とはひと味違う、より積極的なトライであり、試みだと思っています。
データ放送連動ドラマ
投稿を瞬時にテロップ表示
日テレ系「ピースボート」
投稿を瞬時にテロップ表示
日テレ系「ピースボート」
4日にスタートした日本テレビ系の深夜ドラマ「ピースボート―Piece Vote―」(月曜後11・58)は、データ放送と連動して放送中に視聴者が投稿するコメントを瞬時に画面表示するドラマ初の試みに挑んでいる。
24日の地上デジタル放送完全移行を控え、通信と連携する次世代型ドラマとなるか。(井上晋治)
企画した福井雄太プロデューサーは、入社3年目の24歳。データ放送は、身近な若者の生活スタイルやテレビ離れを考慮した上で、ドラマに取り入れたという。
「今の若者は録画視聴などの影響で、かつてのように放送時に番組を見て、その話題を共有し、翌日盛り上がるということが少なくなった。ならば、番組を見た感想を即時に画面上で交換できれば、視聴者同士がテレビの話題で共有感を持てるのでは、と考えた」と狙いを話す。
データ放送の連動は、2007年に開発された独自技術「TVメッセンジャー」を活用。視聴者から寄せられる投稿コメントを番組に反映させるシステムで、プロ野球などのスポーツ中継やバラエティー番組での利用事例がある。
同システムは公序良俗に反する不適切な言葉の検索が可能で、今回のドラマでは約1100~1200語を登録。放送時は二重三重のチェックの網をかけ、表示の可否を判断する。
投稿文は20字以内で、通信機能を備えたデジタルテレビ、パソコン、携帯電話などから送信可能だ。投稿数は初回の1500件から2回目は2000件に増え、反応は上々だ。
うち採用されたのは初回で150件、2回目で300件。初回の画面には「ワクワクします」「採用された!」など前向きな声のほか、「ドラマに集中できん!」といった指摘も。記者もパソコンから3度投稿を試みたが、残念ながら不採用に終わった。
福井プロデューサーは、「制作者の意図を反映させたくないので、ドラマの内容批判など遠慮のない意見を多少の誤字脱字も含めて流している。ドラマを楽しむ道具の一つとして利用されれば」と話す。
こうした試みについて、上智大の碓井広義教授(メディア論)は、「匿名の投稿故に内容の真偽の判別が困難というのは弱点だが、ネット世代の作り手を起用した局や、同世代の若者の関心をテレビに呼び戻そうという作り手の意欲は評価したい」と話している。
(読売新聞 2011.07.19)

・・・・まさに「こうした試み」は、肝心のドラマ自体(中身)が面白くないと、本末転倒な、トホホなことになるので(笑)、制作陣はぜひ頑張ってください。