●本日午前7時雨 18.1℃ 涼しい朝です。
18.1℃ 涼しい朝です。
 【Meteor-M N2】07:36 ◆受信周波数137.100MHz 今朝も海岸線がピタリ合っています。北海道と九州の一部以外は日本列島雲
【Meteor-M N2】07:36 ◆受信周波数137.100MHz 今朝も海岸線がピタリ合っています。北海道と九州の一部以外は日本列島雲 が掛かっています。天気が悪い。
が掛かっています。天気が悪い。
【AO-91】11:48 U/V ■交信(FM:Tone67.0Hz)JA6EGM JE0KBP BG5UWF ◆Payloads:45
【SO-50】14:10 V/U ■交信(FM:Tone67.0Hz)JA3IKC JA6PL ■受信 JA2IDR
【ISS】21:53 ■交信(FM:Tone67.0Hz)JA3FWT JA0FKM/1 JJ1GLK JI1AAF JO1KVS ■受信 JH3KCW UA0STM JK2XXK UA0LTE JA1VVH JA5〇〇〇 JG2TSL
◆ ↑ このパス、当局を含めて13局がQRVしていたことになります。電波を出したどの局も上がったことは間違いないと思います。しかしおそらく、どう考えてもたぶん、13局が一斉に電波を出していた時間があるのではないでしょうか。輻輳です「ふくそう」とは混みあうことです。これまたどう考えても、この状態でISSのRepeaterが旨く働くはずがありません。結論的にはタイミングですから、皆さんめげずに上がらないからと言ってストレスをためず「上がる時もあるのだから」の希望を持って臨んだほうがいいと思います。
◆ ↑ ISS 昨日の当Blogの画像、宇宙飛行士がCross Band Repeaterアンテナの側に写っている写真。やはりISSは図体(ずうたい)が大きいので、地上から見た場合、アンテナがISSの本体の影になることがありそうです。
◆ ↑ あと、最新の軌道要素を使う。送信周波数は固定にして公称周波数(145.990MHz)を使う。などが基本でしょうか。CALSA32には、衛星に常にドップラーの掛からない周波数を届ける「衛星固定」というモードがあるのですが、この場合「衛星には常に145.990MHzが届くのだから中継が旨く行くはず」なのですが、当局がやって見たところでは、旨く行きませんでした。
◆ ↑ くどい解説 ISSに向けて145.990MHz FMの電波を送ったとします。しかしISSは時速28,000kmの早さで動いていますので、向かって来る時はDopplerで約5kHz高い周波数で受けてしまうはずです。この時、公称周波数の145.990MHzで届かせるには、地上で予めドップラー量を考慮して、5kHz低い周波数で送れば良いことになります。これがCALSAT32の「衛星固定」モードです。しかしISSの場合こんなことをしなくても問題なくアクセス出来る見たいなのです。当局の場合、他のFM衛星の場合は全てこの「衛星固定」でやって旨く行っています。すなわち AO-91 AO-27 SO-50 PO-101 今は止まっていますが、AO-92です。ISSもこれで旨く行くだろうと最初のうちはそうしていたのですが芳しくなく、今は「送信固定」でやっています。それでも上がらない時は上がりません。












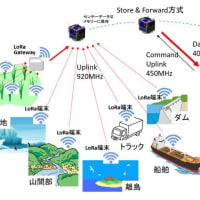



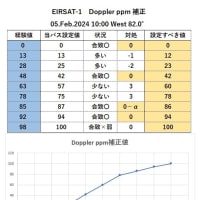
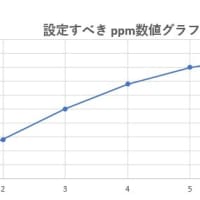

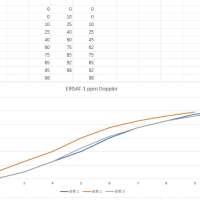





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます