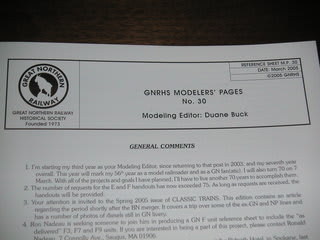最近、オークションにはまっています。特にYahoo!の外国車両のオークションはGNものも多く見ているだけでも楽しいものです。最近、当社の保有するGN以外の外国車両(アメリカ型、ヨーロッパ型等)をオークションに出品してみたところ、結構買い手がつき臨時収入になりました。天賞堂(エバーグリーン)やさかつう、フォムラス等の模型店を巡って中古品の逸品を探すのも楽しいのですが、ネットオークションも結構楽しめます。以下のアドレスをご参照下さい。
http://list5.auctions.yahoo.co.jp/jp/2084036342-category-leaf.html?apg=1&f=&o1=a&alocale=0jp&mode=0
また、アメリカでは、eBayのオークションが有名です。あまりに数が多いので鉄道名等でサーチされることをお勧めします。
http://listings.ebay.com/Model-RR-Trains_W0QQcatrefZC4QQcoactionZcompareQQcoentrypageZsearchQQcopagenumZ1QQfromZR10QQfsooZ1QQfsopZ1QQftrtZ1QQftrvZ1QQga10244Z10425QQsacatZ479QQsocmdZListingItemList
http://list5.auctions.yahoo.co.jp/jp/2084036342-category-leaf.html?apg=1&f=&o1=a&alocale=0jp&mode=0
また、アメリカでは、eBayのオークションが有名です。あまりに数が多いので鉄道名等でサーチされることをお勧めします。
http://listings.ebay.com/Model-RR-Trains_W0QQcatrefZC4QQcoactionZcompareQQcoentrypageZsearchQQcopagenumZ1QQfromZR10QQfsooZ1QQfsopZ1QQftrtZ1QQftrvZ1QQga10244Z10425QQsacatZ479QQsocmdZListingItemList