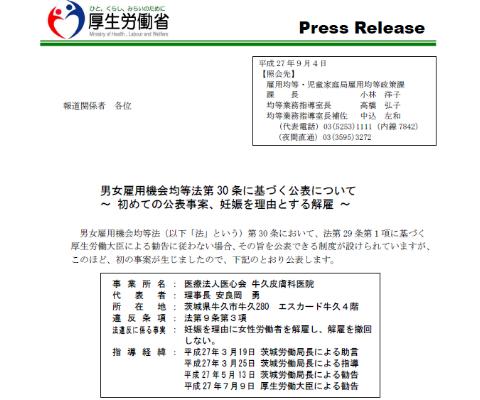厚生労働省は、8月9日、平成28年度に時間外労働などに対する割増賃金を支払っていない企業に対して、労働基準法違反で是正指導した結果を取りまとめて公表した。
平成28年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表
これは、全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、平成28年4月から平成29年3月までの期間に不払いだった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたもの。

【平成28年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント (詳細別紙1、2) 】
(1) 是正企業数 1,349企業 (前年度比 1企業の増)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、184企業
(2) 支払われた割増賃金合計額 127億2,327万円 (同 27億2,904万円の増)
(3) 対象労働者数 9万7,978人 (同 5,266人の増)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり943万円、労働者1人当たり13万円
厚生労働省は、同じく8月9日、全国の労働局や労働基準監督署が、平成28年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導、送検等の状況について取りまとめまて公表した。(別紙1参照)
自動車運転者を使用する事業場に対する平成28年の監督指導、送検等の状況を公表
厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいき、また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくとしている。

平成28年の監督指導・送検の概要
■ 監督指導を実施した事業場は 4,381事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、 3,632事業場(82.9%)。また、改善基準告示違反が認められたのは、 2,699事業場(61.6%)。
■ 主な労働基準関係法令違反事項は、(1)労働時間(55.6%)、(2)割増賃金の支払(21.8%)、 (3)休日(5.0%)。
■ 主な改善基準告示違反事項は、(1)最大拘束時間(45.8%)、(2)総拘束時間(38.4%)、 (3)休息期間(31.9%)。
■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは 68件。
気になるのが、平成26年から平成28年までの3年間における業種ごとの監督実施事業場数、労働基準関係法令違反事業場数及び改善基準告示違反事業場数。
昨今、貸切バスでの重大事故が多発したことから、交通運輸事業者の安全管理とコンプライアンスの強化が取り組まれているはずながら、監督実施事業場数における違反率が、トラック、バス、ハイヤー・タクシーの各モードとも、いっこうに改善していない。
各モードとも、運転者不足という大きな問題があるとはいえ、まだまだコンプライアンス意識が低い事業者が多数存在するといわざるをえない。
ちなみに、それぞれの事業者数は、トラック57,497者(特債280+一般57,217)、バス6,648者(乗合2,171+貸切4,477、民営・公営合わせて)、ハイヤー・タクシー15,923者(個人タクシー除く)。
約8万の事業者、これは事業所数ではないので、事業所数でいうと膨大な数になるのだが、監督に入った事業所は毎年4,000程度。
また、自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働条件の改善を図るため、労働基準監督機関と地方運輸機関が、その監督等の結果(改善基準告示違反等)を相互に通報しているが、労働基準監督機関から通報した件数は867件、労働基準監督機関が通報を受けた件数は351件。
地方運輸機関との合同監督・監査は、トラック90件、バス130件、ハイヤー・タクシー52件。
労働基準監督官が監督指導した事例
事例2(バス)学校から修学旅行などを受注する貸切バス会社に対して、監督指導を実施
〇運転者について、1日の拘束時間が最長18時間、休息期間が8時間未満や連続運転時間が4時間を超える者が複数認められる。
〇雇入時の健康診断や深夜業務に従事する労働者に対する健康診断が実施されておらず、また、定期健康診断の結果、所見があると診断された労働者について対応が
行われていない。
〇常時10人以上の労働者を雇用しているが、安全衛生推進者を選任しておらず、事業場内の安全衛生活動が組織的に行われていない状況が認められる。
【指導内容】
1 運転者の1日の拘束時間が16時間を超えていること、勤務終了後に連続8時間以上の休息期間を与えていないこと、また、連続運転時間が4時間を超えていること
について指導した。 改善基準告示違反(1日の拘束時間、休息期間、連続運転時間)
2 雇入時や深夜業務に従事する労働者に対して、法定の健康診断を実施していないこと、また、定期健康診断の結果、所見があると診断された労働者について、健康診断実施後3か月以内に、医師から就労に関する意見を聴取していないことについて是正勧告した。 労働安全衛生法第66条(健康診断)、同第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
3 安全衛生推進者を選任していないため是正勧告した。 労働安全衛生法第12条の2(安全衛生推進者)
【指導後の会社の取組】
〇労働時間管理を徹底することにより、拘束時間がもっとも長い運転者について1日16時間を下回り、また、休息期間も8時間以上確保され、さらに、パーキングエリア等での休憩を確実に取得するなどにより、連続運転時間も4時間以内となった。
〇健康診断が未実施となっていた労働者に、法定の健康診断を受診させるとともに、所見のあった労働者全員について、医師から意見を聴取した。
〇法定の講習を修了した労働者を安全衛生推進者に選任し、労働災害防止など貸切バスの特性に応じた安全衛生教育に組織的・計画的に取り組んだ。
(参考)バス運転者に係る改善基準告示
4週間を平均した1週間当たりの拘束時間:原則65時間以内(労使協定締結の場合、71.5時間以内)
1日の最大拘束時間:13時間以内を基本とし、延長する場合であっても16時間以内
連続運転時間:4時間以内
休日労働:2週間について1回以内
休息期間:継続8時間以上
事例3(タクシー)累進歩合制度を導入しているタクシー会社に対して、監督指導を実施
〇運転者の賃金について、運賃収入に応じて段階的に支給割合が上がる、いわゆる「累進歩合給」により全額支払われている。
〇時間外労働、深夜労働及び休日労働に対する割増賃金が支払われていない。
〇支払われた賃金を労働時間で除した結果、地域別最低賃金を下回っている。
〇時間外労働時間数が、36協定の限度時間を超えている。
【指導内容】
1 いわゆる「累進歩合給」は、長時間労働等を極端に誘発するおそれがあることから、賃金制度の見直しを指導した。 累進歩合制度の廃止
2 時間外労働等に対する割増賃金を、法定の割増率(時間外労働・午後10時から午前5時までの深夜労働は25%、休日労働は35%)以上で計算して支払っていない
ため、また、適用される最低賃金額以上の賃金を支払っていないため是正勧告した。 労働基準法第37条(割増賃金の支払)、最低賃金法第4条(最低賃金額以上
の支払)
3 36協定の限度時間を超えて違法な時間外労働を行わせていたため、是正勧告した。 労働基準法第32条(労働時間)
【指導後の会社の取組】
〇労働組合と協議し、累進歩合制度を廃止した。
〇過重労働防止の観点から勤務シフトを見直し、車庫待ちを廃止するなどにより労働時間を削減した。また、労働時間を適正に算出したうえで、時間外労働時間数を36協定の範囲内とするよう労働時間管理を徹底した。
〇最低賃金に満たない賃金及び不払となっていた割増賃金等、総額約50万円が支払われた。
(参考)
○ 累進歩合制度の廃止について
累進歩合制度とは、運賃収入等に応じて歩合給が定められている場合に、その歩合給の額が非連続的に増減するいわゆる「累進歩合給」などをいう(下図参照) 。累進歩合制度は、自動車運転者の長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されることから、採用することは望ましくないとして、その廃止を指導している。
○ タクシー運転者に係る改善基準告示
1か月の総拘束時間:原則299時間以内(車庫待ち等の運転者については、労使協定締結の場合、322時間以内)
1日の最大拘束時間:13時間以内を基本とし、延長する場合であっても原則16時間以内
休息期間:継続8時間以上
休日労働:2週間について1回以内
平成28年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表
これは、全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、平成28年4月から平成29年3月までの期間に不払いだった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたもの。

【平成28年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント (詳細別紙1、2) 】
(1) 是正企業数 1,349企業 (前年度比 1企業の増)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、184企業
(2) 支払われた割増賃金合計額 127億2,327万円 (同 27億2,904万円の増)
(3) 対象労働者数 9万7,978人 (同 5,266人の増)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり943万円、労働者1人当たり13万円
厚生労働省は、同じく8月9日、全国の労働局や労働基準監督署が、平成28年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導、送検等の状況について取りまとめまて公表した。(別紙1参照)
自動車運転者を使用する事業場に対する平成28年の監督指導、送検等の状況を公表
厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいき、また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくとしている。

平成28年の監督指導・送検の概要
■ 監督指導を実施した事業場は 4,381事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、 3,632事業場(82.9%)。また、改善基準告示違反が認められたのは、 2,699事業場(61.6%)。
■ 主な労働基準関係法令違反事項は、(1)労働時間(55.6%)、(2)割増賃金の支払(21.8%)、 (3)休日(5.0%)。
■ 主な改善基準告示違反事項は、(1)最大拘束時間(45.8%)、(2)総拘束時間(38.4%)、 (3)休息期間(31.9%)。
■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは 68件。
気になるのが、平成26年から平成28年までの3年間における業種ごとの監督実施事業場数、労働基準関係法令違反事業場数及び改善基準告示違反事業場数。
昨今、貸切バスでの重大事故が多発したことから、交通運輸事業者の安全管理とコンプライアンスの強化が取り組まれているはずながら、監督実施事業場数における違反率が、トラック、バス、ハイヤー・タクシーの各モードとも、いっこうに改善していない。
各モードとも、運転者不足という大きな問題があるとはいえ、まだまだコンプライアンス意識が低い事業者が多数存在するといわざるをえない。
ちなみに、それぞれの事業者数は、トラック57,497者(特債280+一般57,217)、バス6,648者(乗合2,171+貸切4,477、民営・公営合わせて)、ハイヤー・タクシー15,923者(個人タクシー除く)。
約8万の事業者、これは事業所数ではないので、事業所数でいうと膨大な数になるのだが、監督に入った事業所は毎年4,000程度。
また、自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働条件の改善を図るため、労働基準監督機関と地方運輸機関が、その監督等の結果(改善基準告示違反等)を相互に通報しているが、労働基準監督機関から通報した件数は867件、労働基準監督機関が通報を受けた件数は351件。
地方運輸機関との合同監督・監査は、トラック90件、バス130件、ハイヤー・タクシー52件。
労働基準監督官が監督指導した事例
事例2(バス)学校から修学旅行などを受注する貸切バス会社に対して、監督指導を実施
〇運転者について、1日の拘束時間が最長18時間、休息期間が8時間未満や連続運転時間が4時間を超える者が複数認められる。
〇雇入時の健康診断や深夜業務に従事する労働者に対する健康診断が実施されておらず、また、定期健康診断の結果、所見があると診断された労働者について対応が
行われていない。
〇常時10人以上の労働者を雇用しているが、安全衛生推進者を選任しておらず、事業場内の安全衛生活動が組織的に行われていない状況が認められる。
【指導内容】
1 運転者の1日の拘束時間が16時間を超えていること、勤務終了後に連続8時間以上の休息期間を与えていないこと、また、連続運転時間が4時間を超えていること
について指導した。 改善基準告示違反(1日の拘束時間、休息期間、連続運転時間)
2 雇入時や深夜業務に従事する労働者に対して、法定の健康診断を実施していないこと、また、定期健康診断の結果、所見があると診断された労働者について、健康診断実施後3か月以内に、医師から就労に関する意見を聴取していないことについて是正勧告した。 労働安全衛生法第66条(健康診断)、同第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
3 安全衛生推進者を選任していないため是正勧告した。 労働安全衛生法第12条の2(安全衛生推進者)
【指導後の会社の取組】
〇労働時間管理を徹底することにより、拘束時間がもっとも長い運転者について1日16時間を下回り、また、休息期間も8時間以上確保され、さらに、パーキングエリア等での休憩を確実に取得するなどにより、連続運転時間も4時間以内となった。
〇健康診断が未実施となっていた労働者に、法定の健康診断を受診させるとともに、所見のあった労働者全員について、医師から意見を聴取した。
〇法定の講習を修了した労働者を安全衛生推進者に選任し、労働災害防止など貸切バスの特性に応じた安全衛生教育に組織的・計画的に取り組んだ。
(参考)バス運転者に係る改善基準告示
4週間を平均した1週間当たりの拘束時間:原則65時間以内(労使協定締結の場合、71.5時間以内)
1日の最大拘束時間:13時間以内を基本とし、延長する場合であっても16時間以内
連続運転時間:4時間以内
休日労働:2週間について1回以内
休息期間:継続8時間以上
事例3(タクシー)累進歩合制度を導入しているタクシー会社に対して、監督指導を実施
〇運転者の賃金について、運賃収入に応じて段階的に支給割合が上がる、いわゆる「累進歩合給」により全額支払われている。
〇時間外労働、深夜労働及び休日労働に対する割増賃金が支払われていない。
〇支払われた賃金を労働時間で除した結果、地域別最低賃金を下回っている。
〇時間外労働時間数が、36協定の限度時間を超えている。
【指導内容】
1 いわゆる「累進歩合給」は、長時間労働等を極端に誘発するおそれがあることから、賃金制度の見直しを指導した。 累進歩合制度の廃止
2 時間外労働等に対する割増賃金を、法定の割増率(時間外労働・午後10時から午前5時までの深夜労働は25%、休日労働は35%)以上で計算して支払っていない
ため、また、適用される最低賃金額以上の賃金を支払っていないため是正勧告した。 労働基準法第37条(割増賃金の支払)、最低賃金法第4条(最低賃金額以上
の支払)
3 36協定の限度時間を超えて違法な時間外労働を行わせていたため、是正勧告した。 労働基準法第32条(労働時間)
【指導後の会社の取組】
〇労働組合と協議し、累進歩合制度を廃止した。
〇過重労働防止の観点から勤務シフトを見直し、車庫待ちを廃止するなどにより労働時間を削減した。また、労働時間を適正に算出したうえで、時間外労働時間数を36協定の範囲内とするよう労働時間管理を徹底した。
〇最低賃金に満たない賃金及び不払となっていた割増賃金等、総額約50万円が支払われた。
(参考)
○ 累進歩合制度の廃止について
累進歩合制度とは、運賃収入等に応じて歩合給が定められている場合に、その歩合給の額が非連続的に増減するいわゆる「累進歩合給」などをいう(下図参照) 。累進歩合制度は、自動車運転者の長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されることから、採用することは望ましくないとして、その廃止を指導している。
○ タクシー運転者に係る改善基準告示
1か月の総拘束時間:原則299時間以内(車庫待ち等の運転者については、労使協定締結の場合、322時間以内)
1日の最大拘束時間:13時間以内を基本とし、延長する場合であっても原則16時間以内
休息期間:継続8時間以上
休日労働:2週間について1回以内