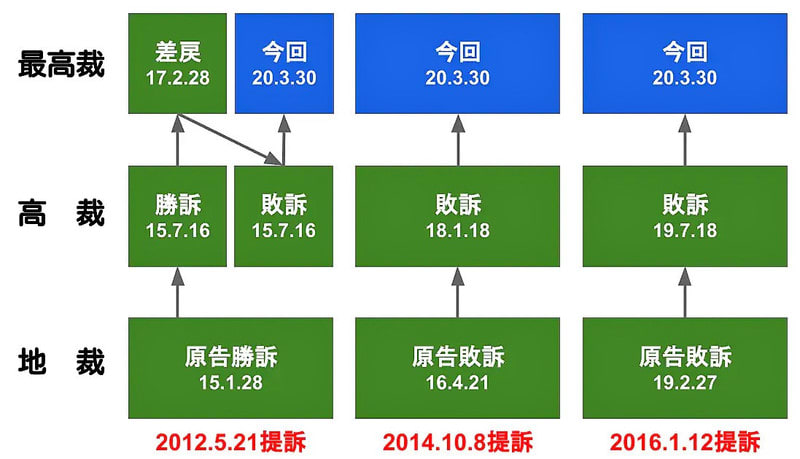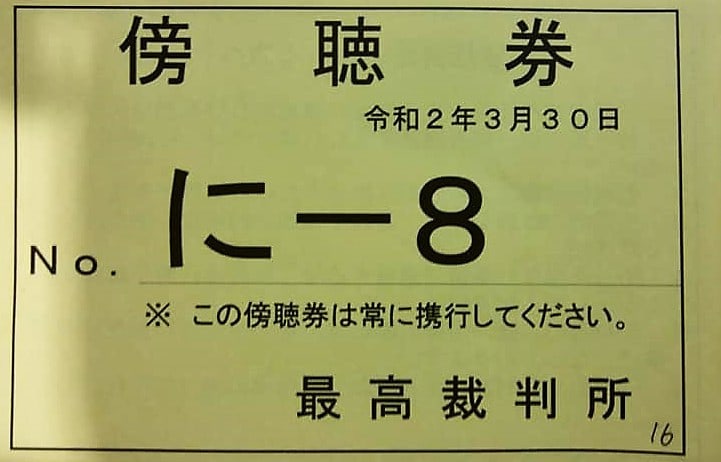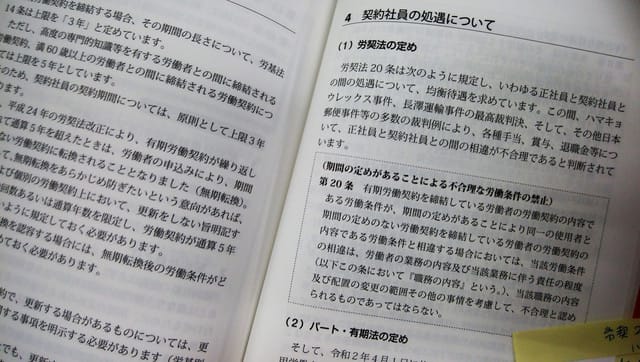昨日から今日、兵庫県加西市で開催された、うちの加盟労組の、60歳定年・再雇用の時期を間近に迎える組合員への準備セミナーにおいて講演。
健康保険、年金制度、雇用保険、介護離職しないための介護保険と介護休業法、ライフプランニングについてなどを135分間、お話しさせてもらった。
話変わって、12月12日、東京都社会保険労務士会の勤務等部会主催研修会で「副業・兼業」について学んできた。
自分たちの職場である鉄軌道・バス・タクシーでは、過労運転によって事故につながってはならないという観点から副業・兼業なんて認められない、というのが当たり前という意識だが。
しかし、働き方改革でも副業・兼業を促進すると言ってるし、カタカナな企業では兼業・副業は認めて当たり前、認めないと優秀な人材が来ない、という。
厚生労働省は、平成30年1月、副業・兼業について、企業や働く方が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかをまとめたガイドラインを作成した。⇒
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf
このガイドラインは、副業・兼業の促進ありきで書かれているので、読むには相当注意が必要なんだが、少し中身をピックアップ(意図的に一部書きぶりを修正している)。
兼業・副業について、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、裁判や学説では一律の禁止や懲戒は難しいとされている。
企業が副業に対して制限を設ける事が許されるケースは
①労務提供上の支障となる場合
②企業秘密が漏洩する場合
③企業の名誉・信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により企業の利益を害する場合
【労働者メリット】①離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、労働者が主体的にキャリアを形成することができる。
②本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求することができる。
③所得が増加する。
④本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた準備・試行ができる。
【労働者デメリット】①長時間労働となって、健康を害すること性がある。
②本業の、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務に違反すると、懲戒処分となることがある。
③雇用保険、労働災害について十分な補償が受けられないことがある。
【企業のメリット】①労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。
②労働者の自律性・自主性を促すことができる。
③優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。
④労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる。
【企業のデメリット】①必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応が困難。
②職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務に違反される可能性がある。
「また、副業・兼業は、社会全体としてみれば、オープンイノベーションや起業の手段としても有効であり、都市部の人材を地方でも活かすという観点から地方創生にも資する面もあると考えられる」としている。
ガイドラインに書かれている「企業の対応」ってのがかなり実務的ではない気がするので、ガイドラインの内容を離れて、この研修会の内容も踏まえて、副業・兼業を考えてみる。
労働基準法38条1項
「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」
⇒法定労働時間を超えているかどうか(36協定の締結・届出義務,割増賃金の支払義務と関係)は、労働者単位で事業場間で通算する
⇒この規定の適用についての行政解釈は「異なる事業主間でも通算する」(昭和23年5月14日基発769号)
⇒しかし学説上では「同一の事業主の範囲でのみ通算する」(菅野和夫「
労働法 第11版」弘文堂,2016年)など異なる事業者間での適用は否定すべきが有力。
⇒行政解釈は実効性に乏しい。有力説を支持すべきである。(判例や行政指導は一例もない)
⇒いずれにしろ、本業の事業主が、副業の労働時間を知らなければ、故意はない。
⇒だとすれば、ガイドラインで推奨されている「副業・兼業を認める場合、副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させる」とすると、本業の事業主は、労働時間把握や割増賃金の支払いなどで違法行為発生リスクが生じるのではないか。
⇒いずれにせよ、自営型副業の場合には、本条の適用はない。
⇒なお、健康管理については、労働時間の通算は不要。(根拠となる法律が異なるため)
労働契約法5条 安全配慮義務(健康配慮義務も含む)
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
判例「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」(電通事件・最2小判平成12年3月24日)
⇒ただし損害賠償責任の成立には、予見可能性が必要。
⇒副業先の勤務状況については、通常、事業主に予見可能性なし。
⇒蓋然性が高いような場合にのみ、勤務の軽減措置などの義務が生じると解される(一般的な解釈と同様)
⇒ガイドラインに書かれている「働き過ぎにならないよう、例えば、自社での労務と副業・兼業先での労務との兼ね合いの中で、時間外・休日労働の免除や抑制等を行う」ことが本業の事業主の責務となるのか。
労災保険 通勤災害については2005年に法改正で対処(事業場間移動も通勤に含める)。
⇒給付基礎日額(平均賃金)の合算がない(現行法では、労災が発生した事業場での賃金をベースに算定。本人の稼得能力の減少に対応できていない)
厚生年金・健康保険 加入は事業所ごとなので労働時間は通算されないが、標準報酬月額は合算
雇用保険 保険関係の成立は事業場単位。被保険者となるには、1週間の所定労働時間が20時間以上、異なる事業主の下での労働時間の合算はされない。
マンナ運輸事件【京都地判平成24年7月13日】
運送会社が、準社員からのアルバイト許可申請を4度にわたって不許可にしたことについて、後2回については不許可の理由はなく、不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容(慰謝料のみ)された事案。
労働者は、勤務時間以外の時間については、事業場の外で自由に利用することができるのであり、使用者は、労働者が他の会社で就労(兼業)するために当該時間を利用することを、原則として許されなければならない。もっとも、労働者が兼業することによって、労働者の使用者に対する労務の提供が不能又は不完全になるような事態が生じたり、使用者の企業秘密が漏洩するなど経営秩序を乱す事態が生じることもあり得るから、このような場合においてのみ、例外的に就業規則をもって兼業を禁止することが許されるものと解するのが相当である。
東京都私立大学教授事件【東京地判平成20年12月5日】
教授が無許可で語学学校講師等の業務に従事し、講義を休講したことを理由として行われた懲戒解雇について、副業は夜間や休日に行われており、本業への支障は認められず、解雇無効とした事案。
兼職(二重就職)は、本来は使用者の労働契約上の権限の及び得ない労働者の私生活における行為であるから、兼職(二重就職)許可制に形式的には違反する場合であっても、職場秩序に影響せず、かつ、使用者に対する労務提供に格別の支障を生ぜしめない程度・態様の二重就職については、兼職(二重就職)を禁止した就業規則の条項には実質的には違反しないものと解するのが相当である。
十和田運輸事件【東京地判平成13年6月5日】
運送会社の運転手が年に1、2回の貨物運送のアルバイトをしたことを理由とする解雇に関して、職務専念義務の違反や信頼関係を破壊したとまでいうことはできないため、解雇無効とした事案。
原告らが行った本件アルバイト行為の回数が年に1、2回の程度の限りで認められるにすぎないことに、証拠及び弁論の全趣旨を併せ考えれば、原告らのこのような行為によって被告の業務に具体的に支障を来したことはなかったこと、原告らは自らのこのような行為について会社が許可、あるいは少なくとも黙認しているとの認識を有していたことが認められるから、原告らが職務専念義務に違反し、あるいは、被告との間の信頼関係を破壊したとまでいうことはできない。
Run3.57km 25min