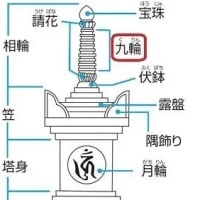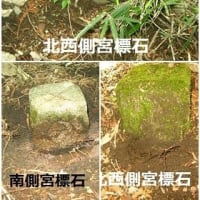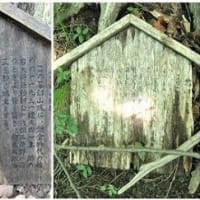先日、朝日岳に登った後、1/11に隣の八束山に行っているが
カメラのセットが狂っているのに気づかず、画像の全てが
白黒に近くて全てボツ。勿論、紀行文も書かなかったが
ある切っ掛けでWIN10に内蔵している「フォト」を
使えば簡単にある程度までは修復できることを知って
時間をかけた作業の末に手直し。で、改めてブログアップ。
r-71で吉井の街中を南下、信越高速を潜って牛伏山方面に
左折、僅かの距離で右折すると八束山登山者専用駐車場。

ここは「まちすい」の活動の一環として場所の確保
がされている。
「まちすい」とは高崎市と合併前の吉井町でH-13年頃に
設立された「吉井町まちづくり推進委員会」のことで、
其の活動の一つである八束山プロジェクト」はH-14年頃
からボランティアで八束山北登山道の整備に着手し、
H-17年頃には西コースの整備まで手がけていたが
現在はHPが見つからないので活動状況は不明。
約130m南下すると標識のある北コース登山口.

道はやや薄暗い竹林の中を伸びていくが雨水に
荒らされてゴロゴロの下地。

先ずは前山的存在の「浅間山 278m」を目指すのだか
比高は110m程度。
途中の竹やぶにこんな道標で分岐。直進は雑木の中を
ジグザグ登り、右折は尾根登り。

今日は右折して通称・見晴らし尾根を使う。
尾根は右が開けて陽光一杯で気分は良いが落葉堆積が厚く
下地はカリカリに固いので軽アイゼン装着。

蚕神社の石碑前を通過。地元の養蚕業の発展を願っての
物らしいが何故この場所に?は判らない。

その少し上で虚空蔵堂跡を通過してきたさっきの直進路が
合流してくる。この虚空蔵堂跡は今は「堂跡」としているが
かってはこんなお堂があった。MHcさんからの借用写真。
「つれづれさん」が未だ御存命の頃だから10年も経つかな。

結構な急登をこなすと浅間山。

ここは展望場所でもあり名物の「天狗の松」も健在。
この枯れ松もかっての姿と比べると撮影角度の差を
考慮しても少し曲がりが大きくなったかな。
左が今の姿、右は7-8年前。

正面は赤城山。

何処かのブログに「枯れた大杉」と書いた御仁が
居られたが地元小学生の設置したこの看板を見て
いない方だろう。

さて、八束山はここからが本格登山。一本尾根だが
予想外に長く、傾斜も緩いとは言いながらアップダウンも
多いので年寄りにはややきつい。
浅間山からは一旦は急下降。

遥か彼方に八束本体らしいむ山容が見える。

其の後はこんな雰囲気の尾根道を延々と進む。

左が開けた直線路では真東に「牛伏山」が形よく見られる。

やがて名物の「羊の足跡」の大岩。羊太夫が都に飛び
立ったときの岩を蹴った羊の足跡と言う伝説。

ここは戦国時代の城郭であることはその遺構から
確認されているのに、築城時期・城主がハッキリ
しない不思議な城址。そんな曖昧さが羊大夫と結び
ついて「羊大夫の居城」という伝説を生んだと推定
できるが地元では暖かくそれを受け入れている。
その後も登りがきつくなる。このルート唯一のロープ。

もう少しだと自分に言い聞かせ突っ張てきた脹脛を
叱咤。頂上の本丸跡が見えた。

一人前に腰曲輪も明確に巻いている。

頂上は少し広い平地。

標識は一枚、西コース案内と一緒。

城址古井戸跡と伝わる場所の石宮で本日の爺イ。

山崎一氏の縄張り図。真北から細い破線を
辿って来たのだ。

休まずロープを使って東肩への堀切を渡る。

東肩の展望場所から榛名・赤城を眺めながら
軽食と休憩。

休憩後、下山に掛かるが今日は西コースではなく
この東肩から急下降する「第二北尾根コース」。
この尾根は左斜面の杉植林地伐採の時に作業者などが
上り下りに使い尾根上の雑木も切り開いたので裸地。
年月の経過で土がながされ小石や岩角のみが残ったので
まともに歩けるルートではない。
いきなり滑り易いザラ場の急降で超スローで進行。
周りには誰も居ないから厳しい所は一旦尻を着いてから
短足延ばしてステップする。
(サムネイル画像は左クリックで拡大、画面左上の左向き矢印で戻る)








もう一息と思われる時、右の落葉に隠れたガードレール
が目についた。こんな所に何のためかは不明だが
面白そうなのでそれを辿ることにした。

道は切り返しから蛇行して北に向かうと思ったら
そのまま南に進む。これでは後戻りだと悟ったが
何処に出るのか確かめたいし戻るのも面倒だから
そのまま。

途中でこんなマネキンに驚かされる。

やがて下の道に合流。

漸く人家の近く、大量の廃棄物が放置されている。

車道に出て東進。人も車も見かけない過疎地帯かな。

見覚えのある四つ角を左折。

林道を北進して浄水場設備を通過して

本日も無事に帰着でメデタシ。
おまけ 1-20
染料工芸館展示室
ご来訪の序に下のバナーをポチッと。 登山・キャンプランキング
登山・キャンプランキング
カメラのセットが狂っているのに気づかず、画像の全てが
白黒に近くて全てボツ。勿論、紀行文も書かなかったが
ある切っ掛けでWIN10に内蔵している「フォト」を
使えば簡単にある程度までは修復できることを知って
時間をかけた作業の末に手直し。で、改めてブログアップ。
r-71で吉井の街中を南下、信越高速を潜って牛伏山方面に
左折、僅かの距離で右折すると八束山登山者専用駐車場。

ここは「まちすい」の活動の一環として場所の確保
がされている。
「まちすい」とは高崎市と合併前の吉井町でH-13年頃に
設立された「吉井町まちづくり推進委員会」のことで、
其の活動の一つである八束山プロジェクト」はH-14年頃
からボランティアで八束山北登山道の整備に着手し、
H-17年頃には西コースの整備まで手がけていたが
現在はHPが見つからないので活動状況は不明。
約130m南下すると標識のある北コース登山口.

道はやや薄暗い竹林の中を伸びていくが雨水に
荒らされてゴロゴロの下地。

先ずは前山的存在の「浅間山 278m」を目指すのだか
比高は110m程度。
途中の竹やぶにこんな道標で分岐。直進は雑木の中を
ジグザグ登り、右折は尾根登り。

今日は右折して通称・見晴らし尾根を使う。
尾根は右が開けて陽光一杯で気分は良いが落葉堆積が厚く
下地はカリカリに固いので軽アイゼン装着。

蚕神社の石碑前を通過。地元の養蚕業の発展を願っての
物らしいが何故この場所に?は判らない。

その少し上で虚空蔵堂跡を通過してきたさっきの直進路が
合流してくる。この虚空蔵堂跡は今は「堂跡」としているが
かってはこんなお堂があった。MHcさんからの借用写真。
「つれづれさん」が未だ御存命の頃だから10年も経つかな。

結構な急登をこなすと浅間山。

ここは展望場所でもあり名物の「天狗の松」も健在。
この枯れ松もかっての姿と比べると撮影角度の差を
考慮しても少し曲がりが大きくなったかな。
左が今の姿、右は7-8年前。

正面は赤城山。

何処かのブログに「枯れた大杉」と書いた御仁が
居られたが地元小学生の設置したこの看板を見て
いない方だろう。

さて、八束山はここからが本格登山。一本尾根だが
予想外に長く、傾斜も緩いとは言いながらアップダウンも
多いので年寄りにはややきつい。
浅間山からは一旦は急下降。

遥か彼方に八束本体らしいむ山容が見える。

其の後はこんな雰囲気の尾根道を延々と進む。

左が開けた直線路では真東に「牛伏山」が形よく見られる。

やがて名物の「羊の足跡」の大岩。羊太夫が都に飛び
立ったときの岩を蹴った羊の足跡と言う伝説。

ここは戦国時代の城郭であることはその遺構から
確認されているのに、築城時期・城主がハッキリ
しない不思議な城址。そんな曖昧さが羊大夫と結び
ついて「羊大夫の居城」という伝説を生んだと推定
できるが地元では暖かくそれを受け入れている。
その後も登りがきつくなる。このルート唯一のロープ。

もう少しだと自分に言い聞かせ突っ張てきた脹脛を
叱咤。頂上の本丸跡が見えた。

一人前に腰曲輪も明確に巻いている。

頂上は少し広い平地。

標識は一枚、西コース案内と一緒。

城址古井戸跡と伝わる場所の石宮で本日の爺イ。

山崎一氏の縄張り図。真北から細い破線を
辿って来たのだ。

休まずロープを使って東肩への堀切を渡る。

東肩の展望場所から榛名・赤城を眺めながら
軽食と休憩。

休憩後、下山に掛かるが今日は西コースではなく
この東肩から急下降する「第二北尾根コース」。
この尾根は左斜面の杉植林地伐採の時に作業者などが
上り下りに使い尾根上の雑木も切り開いたので裸地。
年月の経過で土がながされ小石や岩角のみが残ったので
まともに歩けるルートではない。
いきなり滑り易いザラ場の急降で超スローで進行。
周りには誰も居ないから厳しい所は一旦尻を着いてから
短足延ばしてステップする。
(サムネイル画像は左クリックで拡大、画面左上の左向き矢印で戻る)








もう一息と思われる時、右の落葉に隠れたガードレール
が目についた。こんな所に何のためかは不明だが
面白そうなのでそれを辿ることにした。

道は切り返しから蛇行して北に向かうと思ったら
そのまま南に進む。これでは後戻りだと悟ったが
何処に出るのか確かめたいし戻るのも面倒だから
そのまま。

途中でこんなマネキンに驚かされる。

やがて下の道に合流。

漸く人家の近く、大量の廃棄物が放置されている。

車道に出て東進。人も車も見かけない過疎地帯かな。

見覚えのある四つ角を左折。

林道を北進して浄水場設備を通過して

本日も無事に帰着でメデタシ。
おまけ 1-20
染料工芸館展示室
ご来訪の序に下のバナーをポチッと。