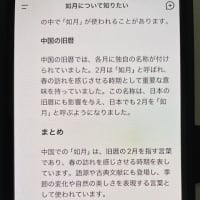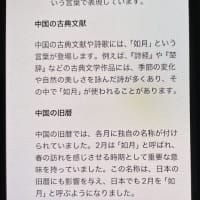文法が移入された学問とその概念であるとして、これまでは文を対象に考えてきた、文成立論をアポリアとみてその文がいわゆる文でなくなると、また文が打ち消されていくような、この議論はこの語をどうとらえてきたのだろうという素朴な疑問である。文法という言葉がこの1語でそれは漢字の熟語と言うのでこれ以上の語の成立にはたどりえない。それを翻訳にして、もともとwritingについての、この語には、the art of writing なり rule なり、そういう語の意味背景があるとしてみれば、文法という概念にもそれを当てはめたということであるから、そのまま近代になっての人々の考え方、とらえ方の工夫であった。
それがそれでよいのだろうけれど、ここにきて文であると思っていたものを文でないと言い出す研究と学説が出てくれば、それでは日本語には文がないわけだから、とは、実は誰も言いださないけれど、文の規定、文の定義というものを変えてしまうという、考えてみると足元からひっくり返すことをして、前提がなくなって、それではどうするのかと、なにやかやと怪しむことになる。その研究と学説をいぶかしんで見てもその議論が積み重ねられていく経過には、まことしやかな理屈がたっていくから、それそうであると意見を戦わす中に、何か、形作られるかと思いながら、どうなったか。
その議論がいっこうに埒が明かぬふうで、結局文法を入れたその議論には文法がなくなってしまうという、そも文がないのであるから、句法となってしまっていることに気づいて気づかぬ風に、語法の議論を展開しているのは、文に程遠いことであるような、これからの日本語はどうなっていくかを日本語教育の論理で展開するようである。つまりは教育文法と規範またはその便宜によるという訳の分からなさである。哲学史を紐解いて、神が死んだのか、神々がいなくなったのかと、哲学そのものの論理にどうにもかかわらない見方もできる。文法そういうことであるなら紆余曲折せぬままに議論の偏りはそれとしての解決がいる。
わたしたちの祖先は字句いや辞句を学び章節を口にしてきたから読み書きするものにおのずと文法を持っていた。それを明らかにするには学びに立ち戻って言葉を知るところから始めることになるだろう。