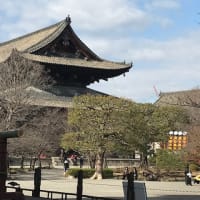論文の語尾を である に統一する添削がある。
どのように文末につけるかは、それは文体による。
また、すべての文末が、である になると限らない。
この文体を、敬体、常体、この二つに対して、とくに である体 ということがある。
日本語教育で、次のような説明がある。
>普通体にはダ体とデアル体があります。小説や日記、また親しい友人間の会話などではダ体を使います。一方、学術的な論文やレポートではふつうデアル体を使います。
http://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/ja/gmod/contents/explanation/090.html
この説明は、学習段階が、ですます体の話し言葉から書き言葉への移行を進めるときに行われる。
話し言葉を注意する項目の一つである。
文法機能を説明する中国文のページから引用すると、次のようである。
维基教科书,自由的教学读本

>
目录 [隐藏]
1 提示助詞[は]
2 提示助詞[も]
3 助詞[が]
3.1 主格助詞[が]
3.2 格助詞[が]
3.3 接續助詞[が]
4 領格助詞[の]
5 終助詞[か]
6 提示助詞[は]
7 接續助詞[から]
8 補格助詞[より]
9 副助詞[ほど]
10 終助詞[ね][よ]
11 傳聞助動詞[そうだ]
12 補格助詞[に]
13 副助詞[か]
14 並列助詞[と]
15 副助詞[や]
16 同位格[の]
17 敬體助動詞[ます]
18 賓格助詞[を]
19 賓格助詞[で]
20 過去完了助動詞 [た]
20.1 [た]的終止形
20.2 [た]的連體形
20.3 [た]的假定形[たら]
21 接續助詞[て]
22 補助動詞[て]
23 補助動詞[ている]
24 補助動詞[てみる]
25 接續助詞[と]
26 補格助詞[に]
27 補格助詞[から]
28 否定助動詞「ない」
28.1 連用形
28.2 連體形
28.3 終止形
28.4 假定形
28.5 推量形
29 判斷助動詞「である」
30 補格助詞「と」
31 補助動詞「(て)いく」、「(て)しまう」
31.1 …(て)いく
31.2 …(て)しまう
32 表示假定的助詞及助動詞「ば•と•なら•たら」
32.1 接續助詞「ば」
32.2 接續助詞「と」
32.3 助動詞「なら」
32.4 助動詞「たら」
33 否定助動詞「ぬ(ん)」
34 樣態助動詞「そうだ」
35 補格助詞「まで」
36 副助詞「だけ」
37 副助詞「でも」
38 接續助詞「のに」
39 補助動詞「(て)くる」、「(て)おる」
39.1 …(て)くる
39.2 …(て)おる
40 願望助動詞「たい」
41 助詞「を」
42 副助詞「くらい•ぐらい」
43 復合助詞「までに」
44 補格助詞「で」
45 補格助詞「と」
46 終助詞「な」
47 補助動詞「(て)ある」
48 表示時間點概數的「ころ•ごろ」
49 補助動詞「(て)おく」
50 補格助詞「に」
51 樣態助動詞「ようだ」
52 副助詞「ほど」
53 副助詞「さえ」
54 接續助詞「ながら」
55 接續助詞「ので」
56 並列助詞「し」
57 接續助詞「きり」
58 補格助詞「へ」
20120820090235日文三大文体 ますです体、だ体、である体
>NHK新聞最常聽到ですます体,連續劇、歌詞、熟友、家人則為だ体,專利、學術報告、論文則用である体
http://blog.xuite.net/jerryinternational/twblog/135514549-35%E6%97%A5%E6%96%87%E4%B8%89%E5%A4%A7%E6%96%87%E4%BD%93++%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%A7%E3%81%99%E4%BD%93%E3%80%81%E3%81%A0%E4%BD%93%E3%80%81%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E4%BD%93
論文における「だ」系と「である」系の 形式の混用について
harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/h-bunkyo/file/.../kokubunngaku55(kuroki).pd...
2014/05/21 - 体(普通体)のうち、レポート・論文においては、「だ・である」体を用いる. ことが望ましいと指導される。そして、これら二つのタイプの文体を一つのレ. ポート・論文において混用することは望ましくないとされる(2)。 一方、普通体で括られる、「だ」と「 ...
文体混用に関する一考察:「だ・である」 体の 「です・ます」 体への ...
eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/49298/.../JISC15_002.pdf
中村重穂 著 - 2011
だ・である」体の「です・ます」体への混用について. 中 村 重 穂. 要 旨. 小論は、文体のift用のうち、「です・ますJ 1本が基調の文章に「だ・. である」体が混用される事例を取り上げ、その構造的・機能的分類と出. 現形態を考察した上で、指導上の対応に言及した ...
公用文の書き方 28 「ます」体で書く場合,「である」体と混用 ...
mbp-okayama.com › 岡山県 › 岡山市 › 岡山市北区 › 菊池捷男 › コラム
2014/10/04 - 公用文を書く場合、文体は「である」体が原則ですが,公告、告示、掲示、通達、通知、伺い、照会、回答、報告などは、できるだけ「ます」体を用いることとされており,最近は「ます」体が増えてきている,といわれています。 「ます」体
>すなわち、isを「は……である」と訳すところで、主体の論理(注:主体・客体モデル)から容器の論理(場所モデル)に移っているのである。言い換えれば、isという主体の論理の表現にもっとも近い容器の論理の表現が「は……である」なのである。
主体の論理では、AとBという個物が存在し、それをisがつなぐ。これに対して、容器の論理では、Aという場所が与えられ、それをBで解説する。この溝は、埋めることができない。
日本語は論理的である 月本洋 講談社新書メチエ p. 125
どのように文末につけるかは、それは文体による。
また、すべての文末が、である になると限らない。
この文体を、敬体、常体、この二つに対して、とくに である体 ということがある。
日本語教育で、次のような説明がある。
>普通体にはダ体とデアル体があります。小説や日記、また親しい友人間の会話などではダ体を使います。一方、学術的な論文やレポートではふつうデアル体を使います。
http://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/ja/gmod/contents/explanation/090.html
この説明は、学習段階が、ですます体の話し言葉から書き言葉への移行を進めるときに行われる。
話し言葉を注意する項目の一つである。
文法機能を説明する中国文のページから引用すると、次のようである。
维基教科书,自由的教学读本


>
目录 [隐藏]
1 提示助詞[は]
2 提示助詞[も]
3 助詞[が]
3.1 主格助詞[が]
3.2 格助詞[が]
3.3 接續助詞[が]
4 領格助詞[の]
5 終助詞[か]
6 提示助詞[は]
7 接續助詞[から]
8 補格助詞[より]
9 副助詞[ほど]
10 終助詞[ね][よ]
11 傳聞助動詞[そうだ]
12 補格助詞[に]
13 副助詞[か]
14 並列助詞[と]
15 副助詞[や]
16 同位格[の]
17 敬體助動詞[ます]
18 賓格助詞[を]
19 賓格助詞[で]
20 過去完了助動詞 [た]
20.1 [た]的終止形
20.2 [た]的連體形
20.3 [た]的假定形[たら]
21 接續助詞[て]
22 補助動詞[て]
23 補助動詞[ている]
24 補助動詞[てみる]
25 接續助詞[と]
26 補格助詞[に]
27 補格助詞[から]
28 否定助動詞「ない」
28.1 連用形
28.2 連體形
28.3 終止形
28.4 假定形
28.5 推量形
29 判斷助動詞「である」
30 補格助詞「と」
31 補助動詞「(て)いく」、「(て)しまう」
31.1 …(て)いく
31.2 …(て)しまう
32 表示假定的助詞及助動詞「ば•と•なら•たら」
32.1 接續助詞「ば」
32.2 接續助詞「と」
32.3 助動詞「なら」
32.4 助動詞「たら」
33 否定助動詞「ぬ(ん)」
34 樣態助動詞「そうだ」
35 補格助詞「まで」
36 副助詞「だけ」
37 副助詞「でも」
38 接續助詞「のに」
39 補助動詞「(て)くる」、「(て)おる」
39.1 …(て)くる
39.2 …(て)おる
40 願望助動詞「たい」
41 助詞「を」
42 副助詞「くらい•ぐらい」
43 復合助詞「までに」
44 補格助詞「で」
45 補格助詞「と」
46 終助詞「な」
47 補助動詞「(て)ある」
48 表示時間點概數的「ころ•ごろ」
49 補助動詞「(て)おく」
50 補格助詞「に」
51 樣態助動詞「ようだ」
52 副助詞「ほど」
53 副助詞「さえ」
54 接續助詞「ながら」
55 接續助詞「ので」
56 並列助詞「し」
57 接續助詞「きり」
58 補格助詞「へ」
20120820090235日文三大文体 ますです体、だ体、である体
>NHK新聞最常聽到ですます体,連續劇、歌詞、熟友、家人則為だ体,專利、學術報告、論文則用である体
http://blog.xuite.net/jerryinternational/twblog/135514549-35%E6%97%A5%E6%96%87%E4%B8%89%E5%A4%A7%E6%96%87%E4%BD%93++%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%A7%E3%81%99%E4%BD%93%E3%80%81%E3%81%A0%E4%BD%93%E3%80%81%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E4%BD%93
論文における「だ」系と「である」系の 形式の混用について
harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/h-bunkyo/file/.../kokubunngaku55(kuroki).pd...
2014/05/21 - 体(普通体)のうち、レポート・論文においては、「だ・である」体を用いる. ことが望ましいと指導される。そして、これら二つのタイプの文体を一つのレ. ポート・論文において混用することは望ましくないとされる(2)。 一方、普通体で括られる、「だ」と「 ...
文体混用に関する一考察:「だ・である」 体の 「です・ます」 体への ...
eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/49298/.../JISC15_002.pdf
中村重穂 著 - 2011
だ・である」体の「です・ます」体への混用について. 中 村 重 穂. 要 旨. 小論は、文体のift用のうち、「です・ますJ 1本が基調の文章に「だ・. である」体が混用される事例を取り上げ、その構造的・機能的分類と出. 現形態を考察した上で、指導上の対応に言及した ...
公用文の書き方 28 「ます」体で書く場合,「である」体と混用 ...
mbp-okayama.com › 岡山県 › 岡山市 › 岡山市北区 › 菊池捷男 › コラム
2014/10/04 - 公用文を書く場合、文体は「である」体が原則ですが,公告、告示、掲示、通達、通知、伺い、照会、回答、報告などは、できるだけ「ます」体を用いることとされており,最近は「ます」体が増えてきている,といわれています。 「ます」体
>すなわち、isを「は……である」と訳すところで、主体の論理(注:主体・客体モデル)から容器の論理(場所モデル)に移っているのである。言い換えれば、isという主体の論理の表現にもっとも近い容器の論理の表現が「は……である」なのである。
主体の論理では、AとBという個物が存在し、それをisがつなぐ。これに対して、容器の論理では、Aという場所が与えられ、それをBで解説する。この溝は、埋めることができない。
日本語は論理的である 月本洋 講談社新書メチエ p. 125