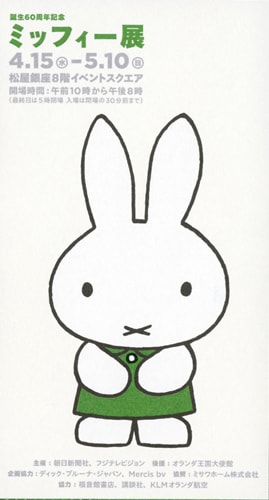今年は酷暑ですね。先日、家族で日中に公園に行ってきましたが、暑すぎて着いて5分くらいで私は帰りたくなりました。
自然と食欲も落ちてしまいます。
そんな時は麺料理!そう、9月号のイオの特集は「朝鮮の麺」特集です。
今回特集デザインの担当は私ではありませんが、人手が足りないこともあり、私も料理撮影に行ってきました♪
ということで、今回のブログは私が個人的におすすめする料理撮影する際のおすすめカメラレンズを紹介したいと思います。
料理撮影する際は、念のためにいつも3本ほどレンズを持っていきます。
今回も持っていて良かった~、助かった~と思ったレンズが、60mm単焦点マクロレンズです。

イオ編集部にも置いてあるレンズですが、実は個人的に持っているレンズの一つでもあります。
私が1眼レフカメラに興味を持ち勉強しようと思った時、朝大時代写真部に在籍していた写真好きである父が、私に買ってくれたのがこのレンズです。
60mm単焦点マクロレンズの利点は、
●接写ができる、●単焦点なので明るい、そしてズームができないので自分の足で動いて写真を撮るようになる=●写真がうまくなる、
ということで最初のレンズとしておすすめされました。
イオ編集部に入る前はフィルムカメラにこのレンズをつけて、近所を散歩したり、甥っ子を撮ったりしてただ楽しんでいました。
仕事でこのレンズを使うようになってからは、このレンズの良さにより気づくことができました。
今回の撮影も麺料理ということで最初は標準の明るいレンズを使っていましたがピントを合わせられる距離がきまっているのでなんとも撮りずらく、
60mmのマクロレンズに交換するとスムーズに撮りたい画が撮れました♪
意外に活躍するレンズの一つです♪
マクロレンズって改めていいな~と思いました。
今度もし、レンズを買い足せる機会が訪れたら(そんな日が来るかは別にして)、また違うマクロレンズを買いたいと思います(愛)

自然と食欲も落ちてしまいます。
そんな時は麺料理!そう、9月号のイオの特集は「朝鮮の麺」特集です。
今回特集デザインの担当は私ではありませんが、人手が足りないこともあり、私も料理撮影に行ってきました♪
ということで、今回のブログは私が個人的におすすめする料理撮影する際のおすすめカメラレンズを紹介したいと思います。
料理撮影する際は、念のためにいつも3本ほどレンズを持っていきます。
今回も持っていて良かった~、助かった~と思ったレンズが、60mm単焦点マクロレンズです。

イオ編集部にも置いてあるレンズですが、実は個人的に持っているレンズの一つでもあります。
私が1眼レフカメラに興味を持ち勉強しようと思った時、朝大時代写真部に在籍していた写真好きである父が、私に買ってくれたのがこのレンズです。
60mm単焦点マクロレンズの利点は、
●接写ができる、●単焦点なので明るい、そしてズームができないので自分の足で動いて写真を撮るようになる=●写真がうまくなる、
ということで最初のレンズとしておすすめされました。
イオ編集部に入る前はフィルムカメラにこのレンズをつけて、近所を散歩したり、甥っ子を撮ったりしてただ楽しんでいました。
仕事でこのレンズを使うようになってからは、このレンズの良さにより気づくことができました。
今回の撮影も麺料理ということで最初は標準の明るいレンズを使っていましたがピントを合わせられる距離がきまっているのでなんとも撮りずらく、
60mmのマクロレンズに交換するとスムーズに撮りたい画が撮れました♪
意外に活躍するレンズの一つです♪
マクロレンズって改めていいな~と思いました。
今度もし、レンズを買い足せる機会が訪れたら(そんな日が来るかは別にして)、また違うマクロレンズを買いたいと思います(愛)
















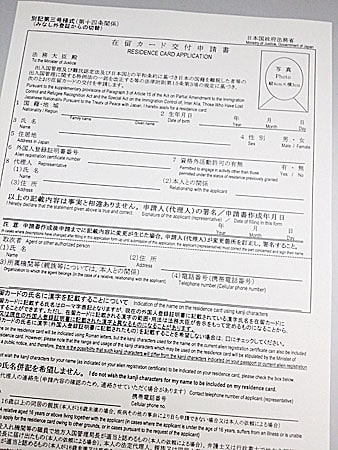
 10分ほどで呼ばれて案内のお姉さんにいろいろ確かめられて、そこから待つこと30分後。。。
10分ほどで呼ばれて案内のお姉さんにいろいろ確かめられて、そこから待つこと30分後。。。