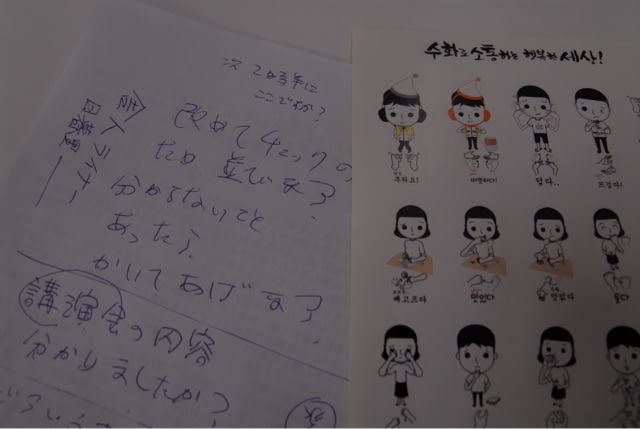先週、大阪地裁で行われた補助金裁判を取材してきました。補助金裁判は、大阪府と大阪市が下した、府・市内の朝鮮学校に対する補助金の不支給処分の取り消しと交付の義務づけを求めて、大阪朝鮮学園が原告となり起こした裁判です。1月21日はその第17回口頭弁論でした。地裁前には同胞、支援者ら約100人が集まりました。
今回、特徴的だったのは府内に10校ある朝鮮学校の学校生活をおさめた映像が法廷で流されたこと。約14分の映像の中で、クラブ活動や授業など生徒たちの日常に加えて、朝鮮学校の歴史や民族教育の意義についても触れられていました。明かりが少し落とされた法廷で、裁判長はじっと画面を見つめていました。傍聴席では、感極まったのか涙をぬぐう人の姿も見られました。
映像に先立って陳述された第13準備書面では、本件補助金が1992年度に創設された際の要件として、「1条校に準ずる」という要素はなく、同年に策定された「大阪府国際化推進基本指針」を踏まえ、「国籍や民族を問わず、すべての人々が同じ人間として尊重し合い、違いを認め合って共生していく地域づくりなど…」という趣旨で、民族教育や国際化教育の振興を図る観点から創設されたものである―としながら、したがって大阪朝鮮高級学校に対してのみ補助金を支給しない措置をとったのは不当だと主張しました。

口頭弁論終了後、報告集会がありました。法廷で流された映像を作った林学さん(49、写真上)は、「民族教育を取り巻く現在の情勢や社会が正常ではないということを、子どもたちのありのままの姿を通して見せたかった。お金をもらおうというのが裁判の本質ではない。大阪府・市に、自分たちの過ちに気づいて欲しい、そういう気持ちを込めて映像を作った」と話していました。
報告集会が終わった後、もう少し詳しく話を聞きに行くと、法廷で映像が流されたのは異例だと仰っていました。原告側は、もともと裁判官に朝鮮学校への訪問を要請していましたが、被告側の反対もあってそれは叶いませんでした。しかし、実情を知るのは重要だという裁判官の判断で、学校と子どもたちの姿を撮った映像のようなものがあれば証拠として提出してもいいということになったそうです。

原告側弁護団の丹羽雅雄弁護団長(写真上)は、「ついに次回、次々回と人証が行われる。裁判長は保護者アンケート(大阪府下10の朝鮮学校に子どもを就学させている保護者を対象に実施したアンケート)に強い関心を持っており、原告からは予想以上に多くの人が出廷してくれる。今年9月頃には判決が出るかもしれない。最後の、本当の踏ん張りどころです」と力強く話しながら支援者たちを鼓舞していました。(理)
↓月刊イオ編集部 編『高校無償化裁判』では、補助金裁判についても詳しく解説しています。詳細は、下記のリンクからぜひチェックしてみて下さい。