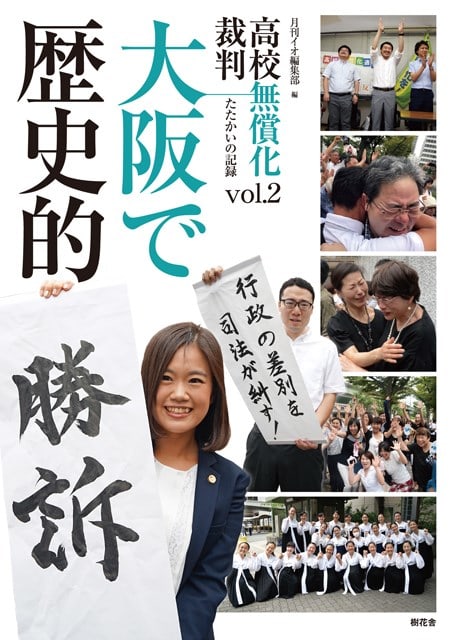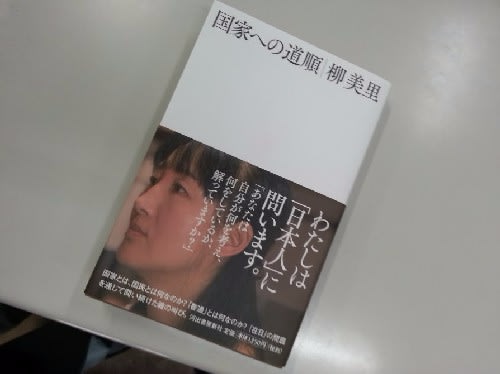以前日刊イオでお知らせした、在日同胞を対象に開かれている手話教室に先日お邪魔しました。
2017/5/31「手話教室が開かれます」(理) ※生徒募集期間は終わりました
主催は在日同胞福祉連絡会の同胞障がい者音楽サークル「Tutti(トゥッティ)」。
今年6月から来年4月まで11回に渡り開催中で、今回はその5回目です。
これまで取材などを通して手話という言語について話を聞く機会がありましたが、手話そのものに触れたのは初めてでした。
「雨の中お疲れ様です。お久しぶりですね」
講師が手話であいさつを始めると、受講生も習った手話を駆使してあいさつを返します。
同胞の手話通訳士の方が隣でフォローしてくれますが、それ以外に「音」はないので、講師の手の動きから目をはなす暇はありません。
机のノートばかり見ずにしっかりと人を見ることから始まるので、学校で受けてきた授業とは感覚が違って新鮮でした。
趣味や好きな食べ物など、講師からの質問に1人ずつ答えて行くだけでも、新しい単語が次々に出てきます。
「キムチ」を表す手話が朝鮮半島の北と南、日本でそれぞれ違ったり、日本の中でも地域や人によって少しずつ表現方法が違ったり。
朝鮮半島と日本の手話は似ているそうですが、その中にも「方言」のような違いがあちこちにあって興味深かったです。
また、単語の意味やようすを“想像する”ことが本当に大切だと感じました。
はじめはちんぷんかんぷんでも、分かってみると、必ずその言葉の特徴が表れています。「なるほど!」と感じられれば記憶にも残ります。
改めて言葉の意味を考えてみたり、他にないその言葉だけの特徴を探してみたり、身近にありすぎて気にかけていなかった「言葉」と出会いなおすような作業に感じられて、これもまた新鮮でした。
過去にブログでも書きましたが、手話はろう者にとって「アイデンティティ言語」だという取材先での話が印象的です。
2017/5/8「漫画『わが指のオーケストラ』、 是非読んでください」(S)
聴覚障がいを持たない人が、ろう者の言葉である手話に触れることは、自分と違う感覚や世界観を持つ「他者」を知り寄り添おうとするための第一歩だということを、手話教室で改めて感じました。
「Tutti」は在日同胞障がい者への福祉活動を行う過程で在日のろう者とも出会いましたが、一方で手話を話せる在日が少ないという現状にも直面したそうです。
手話教室は、在日同胞社会をもう一回り大きく捉えて、もっと大きな輪で同胞たちがつながれる小さなきっかけを作る取り組みだと思います。
何より、受講者の方々が本当に夢中で楽しく手話を習っていました。
外国語を学んだり、新たなことにチャレンジする時に、「手話」という選択肢が自然にあってもいいのではないか、そう感じました。(S)
2017/5/31「手話教室が開かれます」(理) ※生徒募集期間は終わりました
主催は在日同胞福祉連絡会の同胞障がい者音楽サークル「Tutti(トゥッティ)」。
今年6月から来年4月まで11回に渡り開催中で、今回はその5回目です。
これまで取材などを通して手話という言語について話を聞く機会がありましたが、手話そのものに触れたのは初めてでした。
「雨の中お疲れ様です。お久しぶりですね」
講師が手話であいさつを始めると、受講生も習った手話を駆使してあいさつを返します。
同胞の手話通訳士の方が隣でフォローしてくれますが、それ以外に「音」はないので、講師の手の動きから目をはなす暇はありません。
机のノートばかり見ずにしっかりと人を見ることから始まるので、学校で受けてきた授業とは感覚が違って新鮮でした。
趣味や好きな食べ物など、講師からの質問に1人ずつ答えて行くだけでも、新しい単語が次々に出てきます。
「キムチ」を表す手話が朝鮮半島の北と南、日本でそれぞれ違ったり、日本の中でも地域や人によって少しずつ表現方法が違ったり。
朝鮮半島と日本の手話は似ているそうですが、その中にも「方言」のような違いがあちこちにあって興味深かったです。
また、単語の意味やようすを“想像する”ことが本当に大切だと感じました。
はじめはちんぷんかんぷんでも、分かってみると、必ずその言葉の特徴が表れています。「なるほど!」と感じられれば記憶にも残ります。
改めて言葉の意味を考えてみたり、他にないその言葉だけの特徴を探してみたり、身近にありすぎて気にかけていなかった「言葉」と出会いなおすような作業に感じられて、これもまた新鮮でした。
過去にブログでも書きましたが、手話はろう者にとって「アイデンティティ言語」だという取材先での話が印象的です。
2017/5/8「漫画『わが指のオーケストラ』、 是非読んでください」(S)
聴覚障がいを持たない人が、ろう者の言葉である手話に触れることは、自分と違う感覚や世界観を持つ「他者」を知り寄り添おうとするための第一歩だということを、手話教室で改めて感じました。
「Tutti」は在日同胞障がい者への福祉活動を行う過程で在日のろう者とも出会いましたが、一方で手話を話せる在日が少ないという現状にも直面したそうです。
手話教室は、在日同胞社会をもう一回り大きく捉えて、もっと大きな輪で同胞たちがつながれる小さなきっかけを作る取り組みだと思います。
何より、受講者の方々が本当に夢中で楽しく手話を習っていました。
外国語を学んだり、新たなことにチャレンジする時に、「手話」という選択肢が自然にあってもいいのではないか、そう感じました。(S)