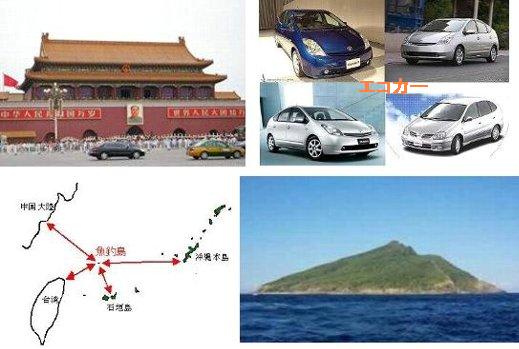山形市中心部の自転車道の社会実験に対し賛否両論が激しく渦巻いていたが、沿道の3つの商店街が25日に「条件付きで実験の継続を求める意見書」を提出した。
提出先は国土交通省山形河川国道事務所、県警本部、山形県、山形市である。
つまり、この社会実験は継続される見通しだが、正式決定は11月1日になる。
しかし、この意見書には歩行者の安全・安心が確保されたことには評価する一方、やはり「クルマでの通行が円滑になるような改善」の要望が盛り込まれており、脱クルマ・自転車利用推進の発想はないようである。
自転車道継続が正式決定される11月1日の会議において「改善に関する検討委員会」も設立されるが、国・県・市・警察・商店会などから構成され、一般市民の参加は見込まれないようだ。
◆写真は国内某市で試行された鉄道車両への自転車持込み。鉄道やバスなどに自転車をも乗り入れられるようになれば、駅前で溢れる駐輪の解消に役立ち、かつクルマから自転車利用への転換の促進が期待できる。
提出先は国土交通省山形河川国道事務所、県警本部、山形県、山形市である。
つまり、この社会実験は継続される見通しだが、正式決定は11月1日になる。
しかし、この意見書には歩行者の安全・安心が確保されたことには評価する一方、やはり「クルマでの通行が円滑になるような改善」の要望が盛り込まれており、脱クルマ・自転車利用推進の発想はないようである。
自転車道継続が正式決定される11月1日の会議において「改善に関する検討委員会」も設立されるが、国・県・市・警察・商店会などから構成され、一般市民の参加は見込まれないようだ。
◆写真は国内某市で試行された鉄道車両への自転車持込み。鉄道やバスなどに自転車をも乗り入れられるようになれば、駅前で溢れる駐輪の解消に役立ち、かつクルマから自転車利用への転換の促進が期待できる。