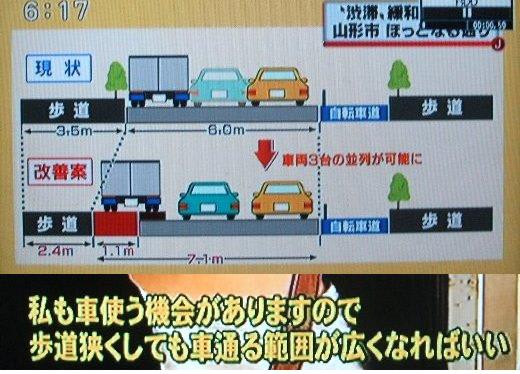山形市中心街自転車道に対して「廃止」や「撤廃」を要望する運動は未だに根強いものがあるようだ。今朝の山形新聞にも「撤廃」を求める陳情がなされたという記事が掲載されていたが、9月の廃止を求める署名活動や陳情がなされた際も、自転車道はクルマでの来街者をますます郊外の店舗に追いやるものだから廃止が必要だという主張だったが、今回もほとんど同じ主張のもとになされている。
このシリーズでは何度も沿道の商店への客足が減少したという主張(これに対して客足が増加している店も少なくないという情報もある)に対しては、自転車道の撤廃によりたとえ渋滞が解消したとしても沿道に出入りに便利な駐車場が少ない限り客足の減少に歯止めがかかる保証はない旨述べてきた。
ともかく、この度の自転車道問題によって明確になったことはクルマ社会是認のもとに進められてきた郊外型商業ゾーンの開発により恐るべき格差の増大が顕著になったことである。
その格差とは駐車場造成環境の格差に他ならない。
上の写真でもわかるように、左が中心市街の駐車ビルであり、右が郊外の商業施設の広大な駐車場である。
中心市街では土地が狭いので高層の駐車ビルが建設されることが多いが、建設費と補修費はむろん高額だし、それに料金徴収の人件費や設備設置にかかる費用も嵩む。さらに固定資産税も高くつくから、有料、または「◎千円以上お買い上げの方には無料」のいずれかにならざるをえなくなる。
でも、多くのドライバーは有料のうえに出入りがめんどうだし、上階に上るのは目が回るようで、空きスペースを探しにくく、できれば避けたいと思うようだ。
これに対して郊外の商業施設の駐車場はほとんどが平面で、しかも無料、さらに広くて見通しがきくし、出入りもしやすい。
これだけで中心市街と郊外では天と地ほどの格差がついてしまっている。だから、クルマ利用者の利便を考えるならば、自転車道を撤廃させたところでとうてい郊外型店舗に対し巻き返しを図ることなどできないのだ。
そもそもどうしてこんな格差の発生が許されているのかにメスを入れて格差解消のための施策を行政に対して強く要望すべきなのである。
例えば、中心市街は空洞化していながら地価と固定資産税は高いままなのに対して、郊外の土地は地価も固定資産税もかなり低いから広大な用地を購入または借地できる。だから広大な駐車場も造成が可能で、客足も多くなるから無料で駐車させられるようになる。となれば、現状に合わせて郊外、中心市街にかかわらず地価と固定資産税を平準化させるべきことになろう。
これで、このシリーズは終わりとさせていただきたいが、中心市街地の賑わい回復を真剣に求めるためにも駐車場の問題をさらに掘り下げて考察していきたいので、次回以降は「駐車場の乱造は日本を滅ぼす」というタイトルの新シリーズとしたい。
このシリーズでは何度も沿道の商店への客足が減少したという主張(これに対して客足が増加している店も少なくないという情報もある)に対しては、自転車道の撤廃によりたとえ渋滞が解消したとしても沿道に出入りに便利な駐車場が少ない限り客足の減少に歯止めがかかる保証はない旨述べてきた。
ともかく、この度の自転車道問題によって明確になったことはクルマ社会是認のもとに進められてきた郊外型商業ゾーンの開発により恐るべき格差の増大が顕著になったことである。
その格差とは駐車場造成環境の格差に他ならない。
上の写真でもわかるように、左が中心市街の駐車ビルであり、右が郊外の商業施設の広大な駐車場である。
中心市街では土地が狭いので高層の駐車ビルが建設されることが多いが、建設費と補修費はむろん高額だし、それに料金徴収の人件費や設備設置にかかる費用も嵩む。さらに固定資産税も高くつくから、有料、または「◎千円以上お買い上げの方には無料」のいずれかにならざるをえなくなる。
でも、多くのドライバーは有料のうえに出入りがめんどうだし、上階に上るのは目が回るようで、空きスペースを探しにくく、できれば避けたいと思うようだ。
これに対して郊外の商業施設の駐車場はほとんどが平面で、しかも無料、さらに広くて見通しがきくし、出入りもしやすい。
これだけで中心市街と郊外では天と地ほどの格差がついてしまっている。だから、クルマ利用者の利便を考えるならば、自転車道を撤廃させたところでとうてい郊外型店舗に対し巻き返しを図ることなどできないのだ。
そもそもどうしてこんな格差の発生が許されているのかにメスを入れて格差解消のための施策を行政に対して強く要望すべきなのである。
例えば、中心市街は空洞化していながら地価と固定資産税は高いままなのに対して、郊外の土地は地価も固定資産税もかなり低いから広大な用地を購入または借地できる。だから広大な駐車場も造成が可能で、客足も多くなるから無料で駐車させられるようになる。となれば、現状に合わせて郊外、中心市街にかかわらず地価と固定資産税を平準化させるべきことになろう。
これで、このシリーズは終わりとさせていただきたいが、中心市街地の賑わい回復を真剣に求めるためにも駐車場の問題をさらに掘り下げて考察していきたいので、次回以降は「駐車場の乱造は日本を滅ぼす」というタイトルの新シリーズとしたい。