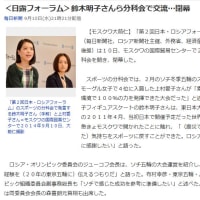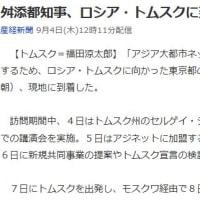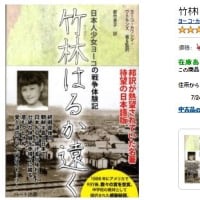「東インド会社と海賊」というタイトルを見て、思い出したのは「トンキンの海賊」という、ルルー「オペラ座の怪人」で「葦の茎を口にくわえて水底に沈む術」(という恥ずかしい、萌えには不要な術)を授けたとエリックに言われている存在です。
で、それを受けた語り手の「新聞記者」は1909年にデ・タム一味もそんな技を使いフランス軍に刃向かい、新聞を賑わせた、というような事を書いていた記憶があります。
昨日の講演で海賊というのは蒸気船等速度の早い高性能の船の出現によって取り締まられやすくなり姿を消していった、というような事を言っていました。
エリックの生きた時代というのはたくさん海賊がいたようですね。当然トンキンの海賊もいたでしょう。「富の偏在」というのが根本にある、とも言ってました。
デ・タム一味も海賊なのか山賊なのか分からないのですが、実在します。

上に「TONKIN」「DE THAM」と書かれています、この人はフランスへの抵抗運動で有名な方のようで「デ・タム通り」という名前の通りがベトナムにあるそうです。
それに20世紀初頭には中国の海賊とかトンキンの海賊の小説も出版されていたようですね。東洋文庫に展示されていました。そのトンキンの海賊が『水遁の術』を使っていたのかは定かではありません。題名をググッたのですがヒットしませんでした。
まあ海で水遁の術が使えるのかも少々疑問です。
でも英語版「オペラ座の怪人」だと「pirates」なので、やっぱり「海賊」なんですよね。でも下の文章を読むと「川」となっているので「川賊」(こんな言葉はないのですが)なのかもしれないですね。そうすると、デ・タムの活動範囲ともルルー「オペラ座の怪人」とも辻褄が合います。
"It's the silliest trick you ever saw," he said, "but it's very useful for breathing and singing in the water. I learned it from the Tonkin pirates, who are able to remain hidden for hours in the beds of the rivers."[8]
---- [8] An official report from Tonkin, received in Paris at the end of July, 1909, relates how the famous pirate chief De Tham was tracked, together with his men, by our soldiers; and how all of them succeeded in escaping, thanks to this trick of the reeds.

ベトナムの河に潜むで、思い出したのが「地獄の黙示録」のこのワンシーン。
ちょっと違いますが、こんな感じで潜んだデ・タム一味がフランス軍を困らせたと。