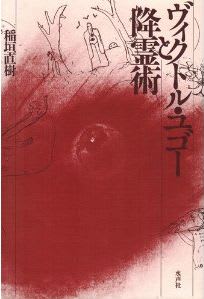覚書です。いい加減です。
チューリンゲンの宮廷での歌合戦で、「愛の本質について」を歌い合う、という場面があります。ここで「愛」は「泉」とも言い換えられています。チューリンゲンの宮殿代表のようなカッコイィ騎士(?)ヴォルフラム役は「愛」「真理」(「泉」)というのは天高いところにあり、拝跪し、讚美し、血の最後の一滴までかけてお守りするものだ、といささか自己陶酔、マゾヒスティックに歌います。すると会場の一同は大感激します。
しかし主人公のハインリッヒは「奇跡の泉に口づけし、その水を飲む」というような事を歌います。彼にとっては「真理」は神棚に飾って崇めるものでなく、味わうもののようです。
すると別の騎士が激昂し、「汚れた唇で触れるなど」と挑みかかり、結局主人公ハインリッヒは剣を突きつけられ、暴力を受けそうになります。
そこで聖女のようなエリーザベトが仲介に入ります。「どんな罪人でも救いに預かる権利がある」と。
しかし実はハインリッヒの歌にエリーザベトは感動しているらしいのです(解説によれば)。
恩赦祭りに行く巡礼者はみな同じ服装で、同じ歌を歌いながらぞろぞろと、神の代理人であるローマ教皇のもとに歩いていきます。
主人公のハインリッヒだけは、その巡礼のマニュアルに沿わず、赦しを得るためには他の人のやらない苦行をせねば、と「自分で考えた」苦行を実践しています。結果、他の全員が恩赦を受け、罪を許されたにも関わらず、ハインリッヒだけには「地獄に落ちろ」的な呪いの言葉が浴びせられます。
個人的な感想ですが、主人公がヴェーヌスベルクに行ったのも、「真理は味わうもの」と考えて、試しに行ったのかも、という事です。
主人公は独自に考えて、行動する人です。教皇は彼に自由とか盲信しない意思を見て、断罪したのでは?とも思ってしまいました。「盲信しない」というのは中世のカトリック世界では悪そのものだったような気もします。
物語は進み、エリーザベトはそんなハインリッヒを思い、彼の歌によって自分の中に芽生えた「自由への憧れ」を償うために、チューリンゲンの城とは違う「谷間」でエリーザベトは祈りの日々をおくっています。しかしハインリッヒが帰ってこず、恩赦が与えられなかった事を知り、「全能の聖母」(ちょっとビックリな言葉です)に祈り、死を持って彼の罪を贖おうと死んでしまいます。具体的にどういうふうに死ぬのかはよくわかりません。舞台の暗闇に退き、見えなくなります。大体「自殺」は罪なのではないでしょうか?それとも願いを聞きいれた全能の聖母が命を召し上げてくださったのでしょうか?
結局ハインリッヒもそれに習ったようです。いつの間にか死んでいました。
「自由という禁断の木の実をエリーザベトに与えておきながら、袋小路に迷い込んでしまったタンホイザー(ハインリッヒ)は、彼女の死を通して贖罪と究極の自由の獲得法を示教され追随する。
幕切れで巡礼者たちは教皇の杖に示された神の恩寵を伝え、悔い改めた者の魂の救済を高らかに歌い上げるが、旅立った者たち(タンホイザーとエリーザベト)の本心を知らないそれは、盲目的な世界に留まり続ける者たちの世界観としてアイロニカルに響いてくるのである」(パンフレットの解説)
確かに巡礼者、騎士道の体現者、護教者としてのチューリンゲンの騎士たちは神に感謝して大合唱してるのですが、その足ものとで主人公の骸が転がっているのは不思議です。一緒に大合唱に加わるのならわかるのですが、エリーザベトもタンホイザー(ハインリッヒ)も、ただただ聖母におすがりして旅立っていった。つまり命ある状態で讚美しなかった。既存の信仰が、生きていく拠り所として機能しなかった、とも思えます。
復活と再生の奇跡を表す「杖」は死体の上に置かれます。そんな奇跡(もしかしたら聖職者の大嘘。死んだものから命が芽生える、という事は「神は死人を蘇たせる力がある」という暗示)に対して湧き上がる群衆は、「死後の永遠の命」を得た、と保証をローマ教会からもらって無邪気に喜んでいる人々とも見えます。
しかしそんな奇跡は起こっても、やっぱりエリーザベトとタンホイザーは死んでしまった。残った人たちは「ハインリッヒも許されて、復活し永遠の命を得るはずだ」と思っているのかもしれません。それはあくまで「死後」であって、生きていく拠り所として機能しなかった、と転がった死体は語っているとも感じられます。
ローマ・カトリック的な世界(ローマ)とプロテスタント的世界(ヴァルストブルグ、チューリンゲン)、官能的ヴェーヌスベルグ、全てにおいて安住の地を見いだせなかったタンホイザーが、そのどれでもなく、すべてが重なった「場所」で召される。エリーザベトも同じ場所で死にます。
ここが、パンフレットにある「精神と官能、神と自然という分かたれた二つの要素が、聖なる和合のための愛の口づけをして抱き合っている」場所なのかな、とも思いました。(1852年のワーグナーの表題的注釈の中の言葉)
つまり聖母の場所でしょうか。
聖母信仰自体が異教的な事なので、そこにすがっていく事態、厳しい人間を罰するヘブライ的な神(父)の支配する世界には、ある種の人間にとって救いがない、ということなのかもしれません。
(原語ではどうかわかりませんが、物語当時にあって処女マリアに対して「全能」などという神に冠するような言葉を付けていいのかも謎です)
または「聖なる結婚」の場所なのかもしれません。
いずれにせよ主人公の死という結末には変わりありません。「素晴らしい!偉大な恩寵だ!!」と大合唱すればするほど、物言わぬ死体と強烈なコントラストだったりします。
うーん、よく分からないながらこんな感想を持ちました。
たしかに今回の演出は「護教的です」と演出のハンス=ペーター・レーマンははっきりパンフレットで述べていて、そんな印象を受けるのですが、パンフレットを読む限りでは、実際の「タンホイザー」自体の狙いは少しズレたところにあったようです。
【追記】
パンフレットによれば、今回のウィーン版でなく最初の「ドレスデン版」では、エリーザベトとヴェーヌスが表裏一体のものとされていたそうです。聖性と官能が表裏一体とは興味深いです。
今回の舞台だと、「聖なるもの」以外はすべて滅ぶべきもの、卑しむべきもの、と鋭い対立関係にあります。
「完全なる聖性」とか「完全なる愛欲世界」というのも観念的で現実的じゃないですよね。不自然なことですから、真剣に追求したら、人格が破綻します。