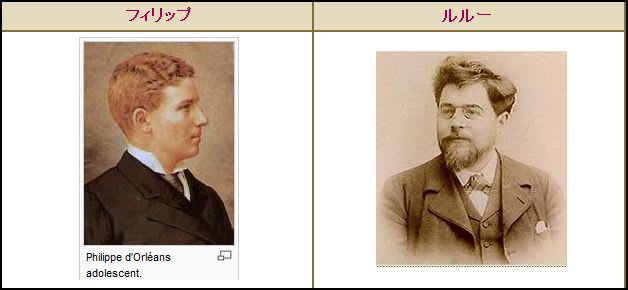ミシャル・ラミ「ジュール・ヴェルヌの暗号」という本を読んでいます。
ヨーロッパ最大のミステリのひとつにレンヌ = ル = シャトー事件があるのですが、この謎めいた事件を背景に、ヴェルヌはフリーメーソンを始めとして、様々な秘密結社と関連していたことを彼の作品は暗号として語っていたらしいです。科学啓蒙家にして生粋の合理主義者と思われていたヴェルヌは、実は、オカルティストであった。また、ヴェルヌばかりか、デュマ、ルルーー、ルブランなどもレンヌ = ル = シャトー事件と秘密結社という視点から再解釈した一冊です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この本からの一節です。
誰でも知っているようにガストン・ルルーは数多くの推理小説や幻想小説を書いた作家で、代表作に「オペラ座の怪人」、「黒衣夫人の香り」「黄色い部屋の謎」がある。私は個人的にルルーの文体があまり好きではないが、もう何年も前からなぜか記憶にこびりついて、ときどき思い出す一文がある。
「司祭館は魅力をうしなっていないし、庭園も輝きを失っていない」(「黄色い部屋の謎」)で、事件の鍵を握る文句)。どうということもない文章ではあるが、何か重要な秘密をほのめかしているような気がするのである。
この司祭館が呼び起こすのはいったいどんな思い出なのだろうか。(ミシャル・ラミ「ジュール・ヴェルヌの暗号」より)
たまたま偶然興味を持って買った本の一節。私もこのフレーズには関心があった上に、フリーメーソンや聖杯伝説といったオカルト的な要素が「オペラ座の怪人」の中には暗示されているかも~、と考えていたので、似たような人がいて嬉しいです。
しかもこの本の中にガストン・ルルーとジュール・ヴェルヌが若い頃にあったことがあるのではないかと示唆。しかもパリ伯(もしかしたらフィリップ・ド・シャニュイのモデル)が間に入って、というのもワクワクさせられます。
そしてこの本によれば、レンヌ・ル・シャトーとガストン・ルルーにはいろいろ関わり合いがあるようですね。レンヌ・シャトーに興味があるならガストン・ルルー全作品を読破すべし、と書かれています。
そうは言っても全作品が日本語翻訳されていないので無理ですが。
レンヌ・ル・シャトー(レンヌ・シャトー)というのは、↓ あたりからググっていただけるとわかりやすいかと。まあ、「ダ・ヴィンチ・コード」っぽいものというか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%8C%EF%BC%9D%E3%83%AB%EF%BC%9D%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%AC%8E
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
司祭館の美しさはいささかも薄れず、その庭のみずみずしさもまた同じ
もともとこのフレーズに関心を持ったのは、このフレーズがベジャールの「バレエ・フォー・ライフ」の原題であり、しかもこのバレエにはフリーメーソンの匂いがする、という誰か知らない方のブログの記事からなのです。
仮にフリーメーソン的な要素をベジャールが詰め込んで、レンヌ・シャトー関連のフレーズを冠したというのなら興味深いです。(でも、このフレーズ使用については特に意味はない、とベジャール自身が言ってます)
フリーメーソンとレンヌ・シャトーが何か関係があるのか、どちらに関してもよく分かっていないので答えられません。
①テンプル騎士団が壊滅された時、財宝をレンヌ・シャトー近くの「ベズ」にあった財宝だけは押収を免れたらしい。
②テンプル騎士団はエルサレムのイエスの墓である聖墳墓教会を守るため、12世紀に結成され、その究極の目的はエルサレムにキリスト教王国を造ることだった。エルサレムがアラブに攻められるとフランスに退き、レンヌ周辺に王国を造ろうとする。また、騎士団最高の総長と言われるブランシュフォールの城も、レンヌ付近にある。
そして、フリーメーソンはもともとテンプル騎士団の生き残りだったという説もあるようです。なんとなく繋がった感じがしなくもないです。

こんな本があるくらいなので関連性があるという人もこの世にはいるっぽいですね。買ってみました。
私は「ダ・ヴィンチ・コード」ファンでもキリスト教徒でもないのですが、どうしてこんなオカルトちっくな事にこだわるのかと言えば、ルルー「オペラ座の怪人」の怪人(エリック)が「石工」であるということ(フリーメーソンは石工集団が起源というのがメジャー)、怪人がクリスと結婚するなら「マドレーヌ寺院」だと名指しで指定、しているからです。
マドレーヌは「マグダラのマリア」の事で、この寺院には大きなマグダラのマリア像がイエス・キリストや聖母を脇役あつかいで大きくドーーーンと祭られています。
正面の壁画にキリストが描かれてはいるのですが、神様と信者席のあいだの主祭壇とも言うべき場所にマグダラの巨大な像が飾られているので、ミサの際にもやっぱりマグダラのマリアが祈りの対象っぽい感じ見えなくもないです。
イエス・キリストは大好きでも、マグダラのマリアは嫌いという信者さんはこの作りはかなり微妙なのでは、と思います。
↓ 教会内、正面。

しかもこの教会の外見がどうみてもローマとかギリシャの神殿っぽい。

ついでにこの建物を建てたといってもいいナポレオンはフリーメーソンだったとか。外観デザインもナポレオンの命令でこんな感じにw

話題のまとまりがなくなってしまいました。
とにかくルルーがテンプル騎士団とかフリーメーソンとか、レンヌ・シャトーとか、もしかしたら聖杯伝説(マグダラのマリアはキリストの子種を宿す聖杯(子宮←この手の聖杯伝説は割とパリでは当たり前らしいとネットで読んだ記憶が)とか、そういったオカルトちっくな事が好きらしいようですね。
今まで漠然とそうなのかも、と考えていたのですが、この本を読んでそんな風に考えている人が自分以外にもいて嬉しいです。
ちなみに「司祭館・・・」のフレーズはもともとはジョルジュ・サンドからの借用で、ただ元のサンドの方は「魅力」が「清潔」なのだそうです。