****** コメント
2次医療圏内に高リスク妊娠・分娩をきちんと管理できる基幹病院が存在し、その基幹病院がきちんとバックアップする体制のもとで、低リスク妊娠・分娩を扱う産科一次施設が地域内に多数存在するのが理想の姿であることは間違いないだろう。
しかし、現実の地域周産期医療の現場の姿は、低リスク妊娠・分娩を扱う産科一次施設がどんどん閉鎖されるのと同時に、高リスク妊娠・分娩を扱う基幹病院もどんどん閉鎖されて、地域内の産科施設がすべて消滅する現象が日本各地で起こっているのだ。
いくら「院内助産院」を作ったとしても、バックアップする基幹病院が地域内に存在しなければ、いざという時には母児の命が失われる大惨事をどうすることもできない。いざという時に命の危機に全く対応できないようなシステムを作り上げても、それが地域のためになるとは思えない。
地域周産期医療滅亡の危機にある今、滅亡の危機を何とか回避するために、今は何を優先すべきか?今は何を実行しなければならないのか?をよくよく考えてみる必要がある。
****** 南信州サイバーニュース、5月30日
「院内助産院」勧める意見も
松川町の下伊那赤十字病院(櫻井道郎院長)の分娩再開を切望する「心あるお産を求める会」(松村道子会長)主催、上伊那郡境7町村と南信州新聞社など後援のシンポジウム「産む安心を求めて」は、このほど約200人が出席して松川町民体育館で開いた。この日は現況報告、行政の対応、意見交換、総合討論などを行い、最後に「良い子育てができる地域づくり」へのアピールを採択した。
シンポジウムの前段では、同会が活動経過を報告。続いて、竜口文昭松川町長が県、国、日赤本部などへ医師確保を要請した経過を報告した。一方、4月から分娩を休止した同病院の櫻井院長は「産科医師がひとりになってしまい、やむなく分娩を休止した。この地域で産院再開を期待する住民は多く、お母さん方のこうした活動が実を結ぶことを願っている」と語った。
シンポジウムは県衛生部の鳥海宏医療医監、信大医学部の小西郁生教授、福岡県春日市の大牟田智子助産院院長、廣瀬健上田産院副院長、植田育也小児科医師の5人のパネリストが「産む安心を求めて」をテーマに、それぞれの立場で意見を発表した。
(中略)
上田産院の廣瀬副院長も「産院の集約化で母親の不満は強い。私も安全のためといって、上田に行った。が、安全とは医療との連携であり、搬送システムを確立すれば助産院でも充分対応できる」とし、助産師による院内助産を勧めた。
(以下略)










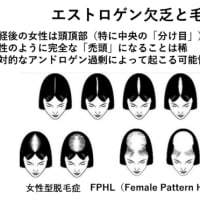


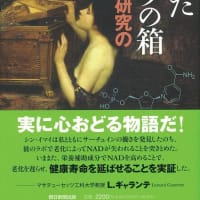
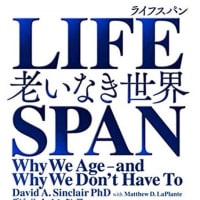
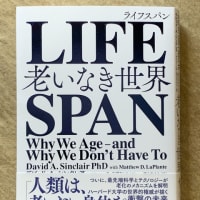
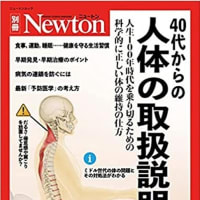
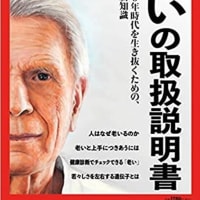
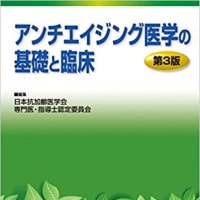

アメリカは検診と分娩施設が別で分娩施設には多数の産科医、麻酔科医、小児科医がいるのが一般的だと思います。
分娩に何を求めるかということだと思うのですが、母親が満足のいくお産ができれば素晴らしいですが、そうでなくとも母子とも安全に生まれればいいのではないのかなあと思いますが、なかなか難しい問題なのでしょうね。
そうでもしないと、お産の時の緊急事態と同じように一刻を争う病気・怪我で救急搬送しないといけない人に救急車が回りませんよ・・・。管轄面積(人口)に対して救急車の台数が少ない地域だってあるのに・・・。
ほとんどの分娩は正常に経過しますが、分娩中の異常も多いです。一口に分娩中の異常と言っても、いろいろです。
妊娠中の体作り・心作りでは予防できないお産の異常(前置胎盤とか、常位胎盤早期剥離とか、癒着胎盤とか、狭骨盤とか)も非常に多いです。
分娩前に診断できる異常(前置胎盤、骨盤位など)も中にはありますが、発症を予測できない異常(羊水塞栓症、癒着胎盤、常位胎盤早期剥離など)も非常に多いです。
羊水塞栓症などのように、分娩場所がどこであってもいまだに母体死亡率がきわめて高く、母体の救命が困難な疾患もあります。
例えば、常位胎盤早期剥離は、自施設での発症例では発症直後の適切な治療で母児を救命できる場合が多いですが、他施設からの母体搬送例では(来院時すでに子宮内胎児死亡となっていることも多く)児の救命率は著明に低下します。
分娩中に何か異常が発生した時に、その場できちんと対応できるかどうか?が人生の大きな分かれ道となる可能性もあります。
従って、分娩が正常に経過しているうちは不必要な医学的処置は一切実施しないが、分娩経過中に医療の助けが必要となった時には直ちに適切な医学的対応が実施できるような分娩環境が理想だと思います。
usiki@篠ノ井様の仰るように、妊婦さまご自身の意識の問題もあります。
>体作り心作りをしっかりして、自分の出産のリスクも考えて出産場所を選び、お産の結果については自分で責任を取って医師・助産師に責任を転化しない
これらができていないと、自分では何もできない、わからないという受け身のお産になってしまい、結局どこで分娩しても、安全なお産であっても不満が残り、何か異常があれば「訴えてやる!」ということになると思います。
助産師の意識も問題だろうと思います。助産師教育の現場では「ケアの対象となる方を怖がらせてはならない」と今でも言われ続けています。怖いことを説明するのは医師の仕事になってしまっているところが多々あります。連綿と受け継がれる経験重視の教育の中でお産は自然なものだけれど、「母子ともに大変危険なもの」というのが一般の認識だったのが、現在では「死ぬはずがない」に変化していることについていけてないのではと感じています。
妊産褥婦さま、ご家族さま、助産師、医師、行政…全ての意識の乖離をなんとかしなければ週産期医療の崩壊をくい止めるのは難しいと思います。