産婦人科医の総数は決まっていて全体として大幅に足りてないのは明らかなので、全部の病院に産婦人科医を十分に配置することはできない。要するに、現状の産婦人科医の総数に対して、病院の数は明らかに多すぎるのである。
この問題の対処は、産婦人科医をいかに適正に再配置するか?という問題につきると思う。広域医療圏ごとに事情は全く異なるので、医療圏内でうまく調整して中核病院を決定し、その中核病院に産婦人科医を集約化して産科滅亡の危機を回避する以外には有効な方策はないように思われる。その調整に失敗した医療圏は、今後、どこにも分娩するところがない産科空白地域になってしまうかもしれない。
****** 長野日報、2006年2月18日
安全なお産を 産婦人科存続訴え
下伊那郡松川町の下伊那赤十字病院が、産婦人科の医師不足から4月からの出産受け入れが難しくなっていることから、飯島町や中川村、下伊那地方の子育て中の母親たちが、産科の存続を訴えて活動を始めた。「心あるお産を求める会」を立ち上げ、署名を集めて県などに働き掛けることにしている。
同病院では産科の常勤医師2人のうちの1人が3月で退職を予定。さらに小児科の診療が昨年10月から非常勤医師による週3回のみとなっているため、安全なお産ができる体制が整わないなどの理由で、4月以降の分娩を原則見合わせることになった。
(中略)
署名は7町村の人口約58000人の6割が目標。3月上旬から中旬にかけ、県知事、県衛生部、県議会に提出する。松村道子会長は、「お産の感動が育児につながると思うのに、お産する場所が選べなくなる。署名活動にとどまらず、安心してお産できる環境について考えていきたい」と話している。
(長野日報、2006年2月18日)










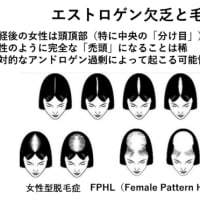


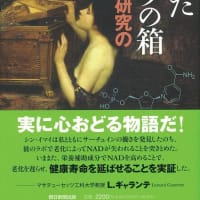
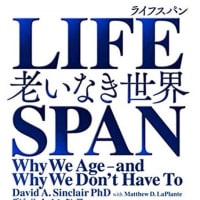
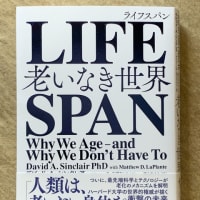
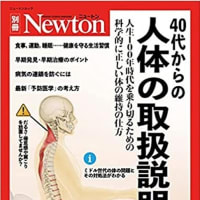
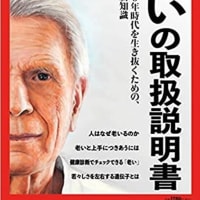
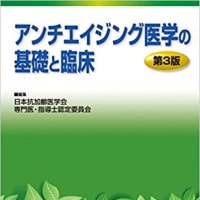

もはやこの手の報道は食傷気味になるほど繰り返されているが、この人達は本当は大して困っていないんだと思う。大体署名署名というけれど当該地区の人口をはるかに超える人数が集まるのがまず怪しいし、署名した一人当たり1000円程度出したら医者2人雇えるくらいのお金あっという間に調達できるのに彼らは肝心なお金はビタ一文払おうとしない。そりゃ名前書くだけならタダだし子供でも出来るからね。つまり、困っているといってもその程度なんですよ。ましてや自治体なんて確保に努める云々なんて全くのポーズ、ホントにどーでもいいんだと思いますよ。医者集められなくても何の責任、罰則もないし、医者不足というのは巡り巡って国民一人一人に厄難をもたらすという発想もないorあっても観念的で全然リアルじゃないんですよw。
こういう「本気じゃない」地域はほっといても医者が消え去って、相対的に「本気な」エリアに医者が「集約化」していくのだと思います。もちろん理想は大局を見据えて組織的に集約化するのがbestですが、、、。
本気で産科医の総数不足を解消したいなら、その地域の子供を選抜して、金銭的に支援して産科医に仕立て上げ、将来的に地元に残ってもらうほうがよほど現実的かもしれません。ただ、先の話にはなりますが。
簡単なことです。
報酬を正当なものにするだけでも、その地で産科をやってもいい、という医師はでてきます。
僻地勤務経験がありますが、勤務医の報酬が1000万円以下であっても、地元の人から「何故医者だけが沢山もらっているのだ」と言われていました。
そんななかで、まず小児科がいなくなって、分娩も中止になり、ついには病院閉鎖になりました。
署名が集まって、別の形で病院は存続しましたが、患者たちは別の病院にかかっているようです。
小児科医も2名いますが、患者はほとんど来ません。
世の中は、きれいごとだけでは進まないと感じています。
地域住民の心情としては、今まで多くの分娩を扱っていた身近な病院が、突然、分娩を取り扱わなくなったり、産婦人科そのものが閉鎖されてしまったりするわけですから、まさに青天のへきれきで、県内の各地域で署名活動が今盛り上がっています。
しかし、現実には、現時点で産婦人科の維持が困難とうわさされている中核病院も少なからずあり、分娩施設の減少はこれからも続くと予想され、県内に産科空白地域が今後急速に広がってゆく可能性も危惧されています。
各広域医療圏で、将来を見すえた抜本的な対応策を実行してゆく必要があると考えています。
長期的に必要なことは、医師の絶対数を増やすこと、これに尽きると思います。そしてこの政策が効果を表すのは、医学部定員を増やしてから10~15年後になります。今から動いても、実効をもつのは2020年ごろの話です。でも、今からそれをしていかないと大変なことになると思います。10年、20年先を見据えた施策をお願いしたいと思うのですが…、次の選挙までしか考えない政治家や、次の配置換えまでのことしか考えない官僚には無理か…。
これは、医師個人が考えることでも、大学医局が考えることでもなく、行政の責任で対応することです。
ただ、これまでの日本の医療行政の結果で産婦人科、小児科、救急などの医師不足となっていますので、無理かもしれません。
署名というのは、一番安易なパフォーマンスなのかもしれません。本気で、経費をかけても医師に赴任してもらいたい思いがあるかどうかは別かも。
医師が不足しているというのは一時的な一部の現象ではないでしょうか?
産科医師になる人は減少していますが、開業したが暇で仕方ないとか、民間病院で暇な勤務医も少なくないようです。
そういうのを厚労省は実は把握しているように思います。
1970年代でしたか、医師の希少価値をなくして厚生省のいいなりになる医師をつくるべく、厚生省が一県一医大構想を打ち立て、見事に医師の上に君臨することに成功しました。
今では、医師が増えすぎてしまい、医師数を制限せねば、医療費が財政を圧迫するので、医師数を制限したいという話を聞いたことがあります。実際、10数年前は、医学部の定員が削減されていました。
そのうち女性医師が増えたので、定員削減しなくても済んでいるという話です。
厚労省は、医師数を今以上に増やすことは考えていないのではないかと思います。
病院の数を減らして赤字を減らすという難しい事案は、研修医制度を利用して成功させたといえるのではないでしょうか?
地方から病院は潰れていく、というシナリオどおりです。
そして、何をするにしても足かせになっている皆保険を医師の側から自由診療、民営化したい気持ちにさせ、皆保険の崩壊、民間保険会社の保険に加入して個人で医療はまかなって下さい(国は最低限の医療は保証しますが、気に入った医療は自腹でね)、という方向にもって行きたいのではないか、と感じますけど、どうなのでしょうか?
勤務者全員、勤務条件が悪くなるようであれば産科はいつでもやめていいと思っています。産科をやるつもりで産婦人科になった人ばかりなのになぜこのようなことになるかといえば、今の日本人の精神構造(人に責任を取ってもらいたがる)に問題の根本はあるような気がします。産科に限らず、「人間は死なないものだ」と思っているような言動を患者家族などから見聞きすることがあります。例えば外科治療が不可能であったがん患者について「抗がん剤投与しているというのに治療しているのにどうして悪化するんだ」など。妊娠すれば一定の割合で死亡がおこるのにすべて医師のせいにしたがります。産科は特に「無事に生まれて当たり前」と思っているからトラブルになりやすい訳です。妻が癒着胎盤だった方(別の日のコメント)のように奇跡的な救命でも医師には何の感謝もないことがすべてを象徴しています。
今のご時世、少人数でましてや一人や二人である程度のハイリスクをみるなど不可能ですから、ローリスクをみる開業産科以外は10名程度以上のセンターしかあり得ないでしょう。ハイリスク妊娠と判断されたらどんなに遠くてもそこにいくしかないんじゃないでしょうか。病気ですから。一人二人の産科医を近くの病院で雇ってもらって中程度リスクならそこでみてもらって何かあったら医者のせいに、なんていう「安全なお産を」などという署名は地域エゴでしかないと思います。
私の世間が狭いからか、人から聞いた話ではなく、実際に困っているという方に今までめぐり合ったことがないのです。横浜市では産科医不足と聞きましたが、横浜在住の友人で現在妊娠中の人がいないためか、依然として誰も困った人にめぐり合わないのです。
おまけに周りにはこれでもかと言わんばかりにどんどん内科、皮膚科、整形外科の開業医が増え、これは産科医不足とは関係ありませんが「医師が余っている」感を醸し出しています。
本当に困っている人(妊婦の方)は新聞紙上以外にどこにいるのでしょうか。困っている医師の方、ではなく、困っている妊婦や患者の方ご本人、ということですが。
しかし、この事件について調べれば調べるほど本当に暗い気持ちになってきます。ある程度ツライ状況でも我慢できる自信はありますが、さすがにこの状況で飛び込む勇気があるかと言えば、正直尻込みしてしまう自分がいます。一方で自分たちの世代の産婦人科が激減することによって先達の先生方の負担がより一層増してしまうことの後ろめたさもあります。
志望科を決めるまで2年ちょっとですが、せめて、興味を持っている者が怯えなくて済むような状況になっていることを望みます・・・。一体どうなってしまうんでしょう・・・。