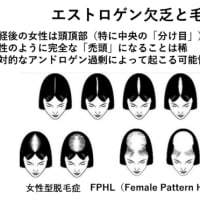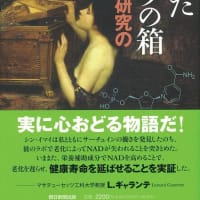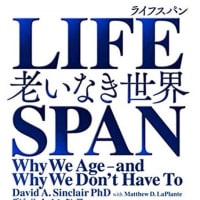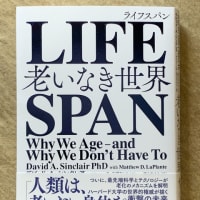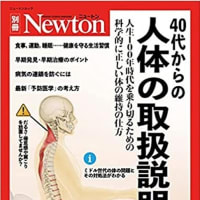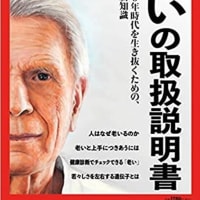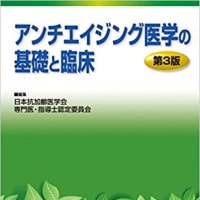****** 共同通信、2006年11月27日
政府・与党の「無過失補償制度」案の概要は次の通り。
【趣旨】
分娩(ぶんべん)時の医療事故では、過失の有無の判断が困難な場合が多く、裁判で争われる傾向があることが産科医不足の一因。このため障害が生じた患者を救済し、早期の紛争解決を図るとともに、事故原因の分析を通して産科医療の質の向上を図る仕組みを創設する。
【運営主体】
「運営機構」を設置し、損害保険会社と医療機関・助産所の間を取り持つとともに、補償対象かどうかの審査や原因分析を実施。
【加入者】
医療機関・助産所単位で加入。
【保険料】
医療機関・助産所が、運営機構を通じて、損保会社に保険料を支払う。保険料の負担で分娩費用が上昇する場合は、健康保険組合の出産一時金増額を検討する。
【補償対象者】
通常の妊娠・分娩で、脳性まひとなった場合を対象とする。通常分娩の定義や障害の程度は、検討する。
【補償額】
保険料額や発生件数を見込んで適切に設定。
【審査】
運営機構が対象かどうか審査し、原因を分析、再発防止の観点から情報公開する。過失があった場合は、医師賠償責任保険などに補償を求める。
【国の支援】
産科医の確保や原因分析を通じ、安心できる産科医療が確保され、少子化対策にも資することから、国は制度設計や事務に要する費用の支援を検討する。
〔無過失補償制度〕 医療事故で障害を負った場合、医師に過失がなくても、患者に補償金が支払われる制度。長期の訴訟を避け、医師・患者双方の救済を図るのが目的で、日本医師会は今年8月、分娩による脳性まひを「最も緊急度の高い事例」と位置づけ独自の制度案を公表、公的資金の投入を唱えた。北欧やニュージーランドでは社会補償制度の一環として取り入れられているほか、英国(重篤な障害のみ)、フランス(国立の医療施設のみ)などでも、部分的に導入されている。
****** 参考