
1963年にノルウェーのオスロで「コルトレーン」のライヴを聴いて、自己の音楽スタイルを「コルトレーン」に啓発された形で、磨いていったアーティストが、今日紹介する「ヤン・ガルバレク」である。
その「ガルバレク」が、ECMレコードにデヴューした、記念すべきアルバムが、この「アフリック・ペッパー・バード」なんです。
「コルトレーン」以上のマルチ・プレイヤーの世界を是非覗いて下さい。
アルバムタイトル…アフリック・ペッパー・バード
パーソネル…リーダー;ヤン・ガルバレク(ts、bs、cl、fl、per)
テリエ・リピダル(g、bugle)
アリルド・アンデルセン(b)
ヨン・クリステンセン(per)
曲目…1.スカラビー、2.マージャン、3.ビースト・オブ・コドモ、4.ブロウ・アウェイ・ゾーン、5.MYB、6.コンセンタス、7.アフリック・ペッパー・バード、8.ブルップ
1970年9月 オスロにて録音
原盤…ECM 発売…ポリドール
CD番号…POCJ-2058
演奏について…まず、アルバム全体を通しての印象だが、演奏者が北欧の「コルトレーン」らしく、又、ECM録音と言う事もあってか、正しく白く透き通った世界が目に浮かぶ様な、クリアーな音の世界が表現されている。
演奏形態、演奏表現は、なるほど、「トレーン」後期の影響をかなり受けていて、似た部分があるのだが、「コルトレーン」の演奏は色で言えば、少なくとも「真っ白」や「透明」では無いんです。
さて、「コルトレーン」の演奏は何色なのかな?…考えると分からないなぁ。
多分、演奏している(聴いている)精神ステージが高すぎて、もはやこの世の音楽では無いんでしょう。
だから、「コルトレーン」の演奏からは、もはや色は見えない。
色がある世界から、遥かに超越しているんです。
言わば、神の音楽なんですね。
しかし、「ガルバレク」の演奏からは、ハッキリと白い世界が見える。
つまり「ガルバレク」の音楽は、人間が奏でている音楽なんです。
何を言いたいか?と言えば、「ガルバレク」を批判したい訳ではなく、全く逆で、「コルトレーン」の演奏形態を踏襲しつつ、「ガルバレク」の世界は、ちゃんと作っていると言う事で、自分のスタイルを持っていると言う事なんです。
極端ですが、演奏だけ「コルトレーン」ソックリで、色が全く出ていないミュージシャンがいる中で、色が見える「ガルバレク」が、優れたアーティストだとも言えるんです。
では詳細の説明をいくつか行きましょう。
個性的な編曲、楽器編成が売りのオープニング曲「スカラベ」…民族系打楽器をリズム・セクションに使用し、非常にアフリカンでエキゾチックな雰囲気の曲で、「ガルバレク」はアフリカ原住民族が吹く、角笛の様なホーン演奏をしている。
「スカラベ」とは、ふんころがしの事だが、エジプトでは神聖な神の使いの昆虫だったはず。
この雰囲気は、何か黒魔術の様なおどろおどろしさもあるが、とても神聖な感じのする曲で、オープニング曲としての掴みはOKです。
3曲目「ビースト・オブ・コドモ」は、重厚なベース「アンデルセン」の名演奏を軸に、渾然一体となったメンバーがハード・ボイルドに決める、かっこいい演奏です。
とにかく、ベースがズシン、ズシンと響き、この曲の大黒柱になって、「ガルバレク」が、最初は尺八の様に、静寂に木霊する様に、静かに吹いて、その後のアドリブでは、正しく後期「コルトレーン」の様に、テナーで絶叫し、のた打ち回る超絶演奏が聴きものです。
それから、この演奏の個性を際立たせているのは、ギター(エレキ)の「リピダル」が曲間に印象的に、エレキ伴奏を入れていて、「コルトレーン」に近い演奏プラス、「エレクトリック・マイルス」が融合されている所でしょう。
私は「エレクトリック・マイルス」が余り好きじゃないんですが、(このブログでも未だ一回も紹介していません。)不思議と、この演奏は嫌いではなく、逆に名演として、何回も聴きたい演奏です。
やはり、前述のアコースティック・ベース「アンデルセン」が、大黒柱の演奏なので、曲に浮いた所がなく、名演奏になったのでしょう。
このアルバムナンバー1の名演、4曲目「ブロウ・アウェイ・ゾーン」…「コルトレーン」後期の演奏が乗り移った様な名演奏です。
このアルバムのメンバー紹介にドラムスが記載されていないんだけど、ここでは前曲同様に「アンデルセン」のバチッっとくるベースに加えて、「エルヴィン」か「ラシッド・アリ」並に、曲を宇宙空間へと導く様な、ドラム演奏が良い味を出しています。
この二つのしっかりしたリズム・セクションをバックに「ガルバレク」がアグレッシヴなアドリブ・ソロを、思い切り良く吹き切ります。
汗と唾が飛び散るのが分かるくらい、アバンギャルドな熱演が、ハートにびんびんと迫って来ます。
フリー・ジャズ好きには堪えられない、バッチグーの名演奏です。
7曲目表題曲でもある「アフリック・ペッパー・バード」…不思議なテーマを掲示した後で、ベース、ドラムス、ギターの3者によって、ややラテン調のリズムがリフレインして演奏される。
その後「ガルバレク」が、またまた搾り出す様な音色のサックスを、カデンツァとして演奏する。
2曲目の「マージャン」…ベースの低音をメインに、ドラムのシンバルとギターが絡むフリー系ジャズの序奏的な短い演奏。
しかし、何故に曲名がマージャンなの?
5曲目「MYB」も、「J・ギャリソン」の様ビシッとベースを弾く「アンデルセン」に「ガルバレク」がシュールに絡む短曲です。
6曲目「コンセンタス」…「ガルバレク」が北欧の朝もやを表現した様な、清々しい1分弱の1曲です。
「ガルバリク」の演奏…流石、ノルウェーの「コルトレーン」と思わせる演奏が随所に見られて、フリー好きな方にはお薦めですが、実はこのアルバムのもう一人の主役は、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、間違い無くベースの「アンデルセン」にあります。
「アンデルセン」の「ジミー・ギャリソン」ばりの超絶技巧と、演奏に対するスピリットが、このアルバムを「後期コルトレーン」の世界観に押し上げている要因でしょう。
その「ガルバレク」が、ECMレコードにデヴューした、記念すべきアルバムが、この「アフリック・ペッパー・バード」なんです。
「コルトレーン」以上のマルチ・プレイヤーの世界を是非覗いて下さい。
アルバムタイトル…アフリック・ペッパー・バード
パーソネル…リーダー;ヤン・ガルバレク(ts、bs、cl、fl、per)
テリエ・リピダル(g、bugle)
アリルド・アンデルセン(b)
ヨン・クリステンセン(per)
曲目…1.スカラビー、2.マージャン、3.ビースト・オブ・コドモ、4.ブロウ・アウェイ・ゾーン、5.MYB、6.コンセンタス、7.アフリック・ペッパー・バード、8.ブルップ
1970年9月 オスロにて録音
原盤…ECM 発売…ポリドール
CD番号…POCJ-2058
演奏について…まず、アルバム全体を通しての印象だが、演奏者が北欧の「コルトレーン」らしく、又、ECM録音と言う事もあってか、正しく白く透き通った世界が目に浮かぶ様な、クリアーな音の世界が表現されている。
演奏形態、演奏表現は、なるほど、「トレーン」後期の影響をかなり受けていて、似た部分があるのだが、「コルトレーン」の演奏は色で言えば、少なくとも「真っ白」や「透明」では無いんです。
さて、「コルトレーン」の演奏は何色なのかな?…考えると分からないなぁ。
多分、演奏している(聴いている)精神ステージが高すぎて、もはやこの世の音楽では無いんでしょう。
だから、「コルトレーン」の演奏からは、もはや色は見えない。
色がある世界から、遥かに超越しているんです。
言わば、神の音楽なんですね。
しかし、「ガルバレク」の演奏からは、ハッキリと白い世界が見える。
つまり「ガルバレク」の音楽は、人間が奏でている音楽なんです。
何を言いたいか?と言えば、「ガルバレク」を批判したい訳ではなく、全く逆で、「コルトレーン」の演奏形態を踏襲しつつ、「ガルバレク」の世界は、ちゃんと作っていると言う事で、自分のスタイルを持っていると言う事なんです。
極端ですが、演奏だけ「コルトレーン」ソックリで、色が全く出ていないミュージシャンがいる中で、色が見える「ガルバレク」が、優れたアーティストだとも言えるんです。
では詳細の説明をいくつか行きましょう。
個性的な編曲、楽器編成が売りのオープニング曲「スカラベ」…民族系打楽器をリズム・セクションに使用し、非常にアフリカンでエキゾチックな雰囲気の曲で、「ガルバレク」はアフリカ原住民族が吹く、角笛の様なホーン演奏をしている。
「スカラベ」とは、ふんころがしの事だが、エジプトでは神聖な神の使いの昆虫だったはず。
この雰囲気は、何か黒魔術の様なおどろおどろしさもあるが、とても神聖な感じのする曲で、オープニング曲としての掴みはOKです。
3曲目「ビースト・オブ・コドモ」は、重厚なベース「アンデルセン」の名演奏を軸に、渾然一体となったメンバーがハード・ボイルドに決める、かっこいい演奏です。
とにかく、ベースがズシン、ズシンと響き、この曲の大黒柱になって、「ガルバレク」が、最初は尺八の様に、静寂に木霊する様に、静かに吹いて、その後のアドリブでは、正しく後期「コルトレーン」の様に、テナーで絶叫し、のた打ち回る超絶演奏が聴きものです。
それから、この演奏の個性を際立たせているのは、ギター(エレキ)の「リピダル」が曲間に印象的に、エレキ伴奏を入れていて、「コルトレーン」に近い演奏プラス、「エレクトリック・マイルス」が融合されている所でしょう。
私は「エレクトリック・マイルス」が余り好きじゃないんですが、(このブログでも未だ一回も紹介していません。)不思議と、この演奏は嫌いではなく、逆に名演として、何回も聴きたい演奏です。
やはり、前述のアコースティック・ベース「アンデルセン」が、大黒柱の演奏なので、曲に浮いた所がなく、名演奏になったのでしょう。
このアルバムナンバー1の名演、4曲目「ブロウ・アウェイ・ゾーン」…「コルトレーン」後期の演奏が乗り移った様な名演奏です。
このアルバムのメンバー紹介にドラムスが記載されていないんだけど、ここでは前曲同様に「アンデルセン」のバチッっとくるベースに加えて、「エルヴィン」か「ラシッド・アリ」並に、曲を宇宙空間へと導く様な、ドラム演奏が良い味を出しています。
この二つのしっかりしたリズム・セクションをバックに「ガルバレク」がアグレッシヴなアドリブ・ソロを、思い切り良く吹き切ります。
汗と唾が飛び散るのが分かるくらい、アバンギャルドな熱演が、ハートにびんびんと迫って来ます。
フリー・ジャズ好きには堪えられない、バッチグーの名演奏です。
7曲目表題曲でもある「アフリック・ペッパー・バード」…不思議なテーマを掲示した後で、ベース、ドラムス、ギターの3者によって、ややラテン調のリズムがリフレインして演奏される。
その後「ガルバレク」が、またまた搾り出す様な音色のサックスを、カデンツァとして演奏する。
2曲目の「マージャン」…ベースの低音をメインに、ドラムのシンバルとギターが絡むフリー系ジャズの序奏的な短い演奏。
しかし、何故に曲名がマージャンなの?
5曲目「MYB」も、「J・ギャリソン」の様ビシッとベースを弾く「アンデルセン」に「ガルバレク」がシュールに絡む短曲です。
6曲目「コンセンタス」…「ガルバレク」が北欧の朝もやを表現した様な、清々しい1分弱の1曲です。
「ガルバリク」の演奏…流石、ノルウェーの「コルトレーン」と思わせる演奏が随所に見られて、フリー好きな方にはお薦めですが、実はこのアルバムのもう一人の主役は、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、間違い無くベースの「アンデルセン」にあります。
「アンデルセン」の「ジミー・ギャリソン」ばりの超絶技巧と、演奏に対するスピリットが、このアルバムを「後期コルトレーン」の世界観に押し上げている要因でしょう。










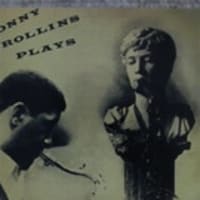

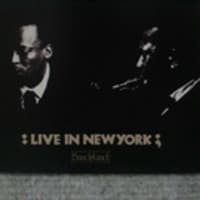
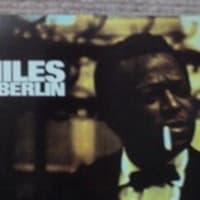
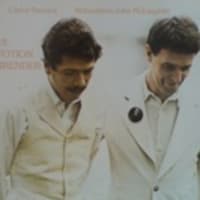
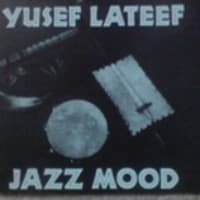
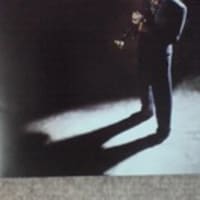
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます