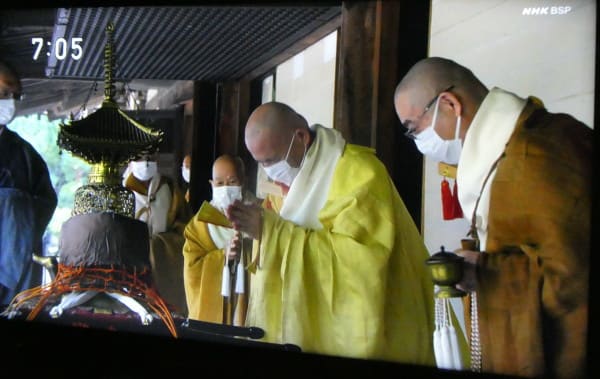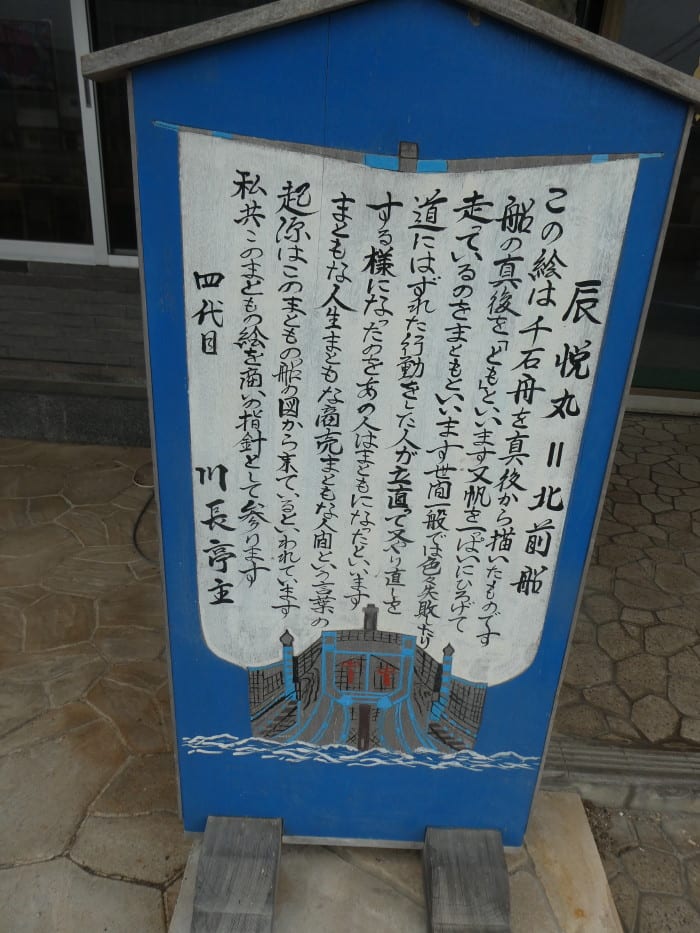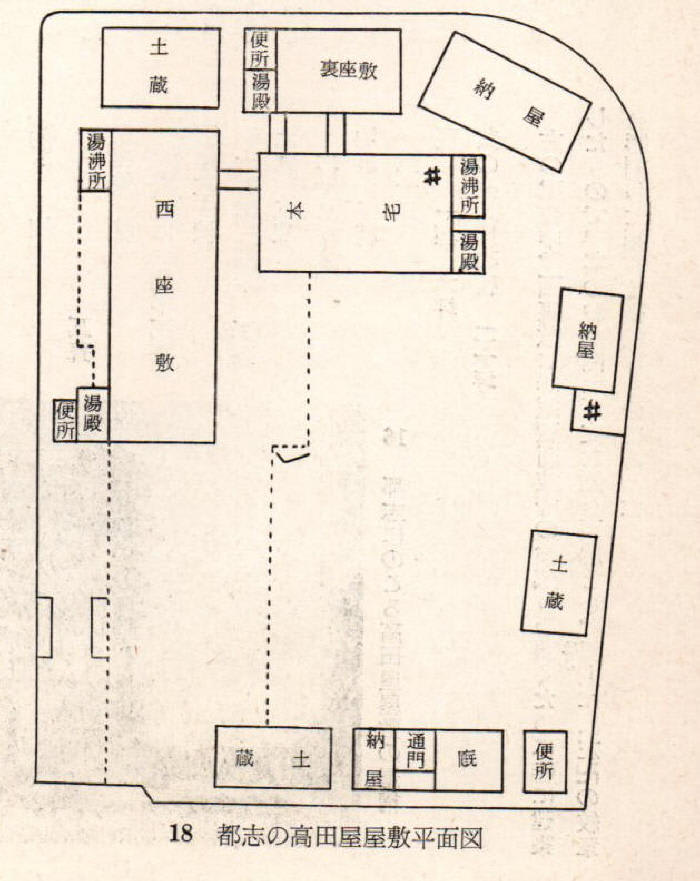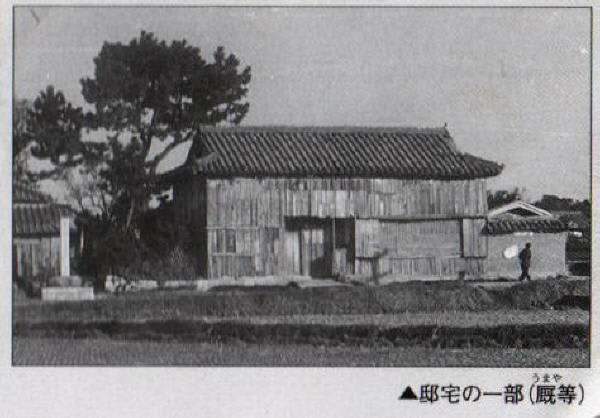2023年6月15日(木)、神戸ジェームス山食堂(まいどおおきに食堂)でランチを
いただきましたので写真紹介します。
定期的によく行く店ですが過去にブログ記事を書いたのは2度で今回が3回目の投稿です。
ついでに7月11日(火)の訪問記も写真紹介します。
神戸ジェームス山食堂の基本情報
住所:神戸市垂水区桃山台2丁目1768−55 TEL:078-706-1807
ジャンル:定食・食堂 営業時間:10:30~21:00 定休日:無休
運営会社:株式会社フジオフードシステム(昭和54年創業)下記のチェーン店を全国展開
「まいどおおきに食堂」「かっぽうぎ」「串家物語」「つるまる」
所在地のGoo地図を添付しておきます。

上の写真は当日、私が選択した品々です。
カレー500円、冷やっこ100円、豚汁230円 合計830円

上の写真は奥様が選んだ品々
食堂のミンチカツ150円、小松菜うす揚げ炒め煮120円、ごはん(小)150円
合計420円 2人の合計1,250円でした。

上の写真は店頭の看板

上の写真はお店の外観
7月11日の訪問記

上の写真は当日私が選んだメニュー
あじフライ120円、ささがき牛蒡きんぴら120円、ごはん(小)150円 豚汁230円 合計620円

上の写真は奥様が選んだメニュー
小松菜うす揚げ炒め煮120円、特製玉子焼き220円、豚&じゃがいも320円、ごはん(小)150円
合計 810円 2人の合計は1,430円(税込)
過去の訪問記