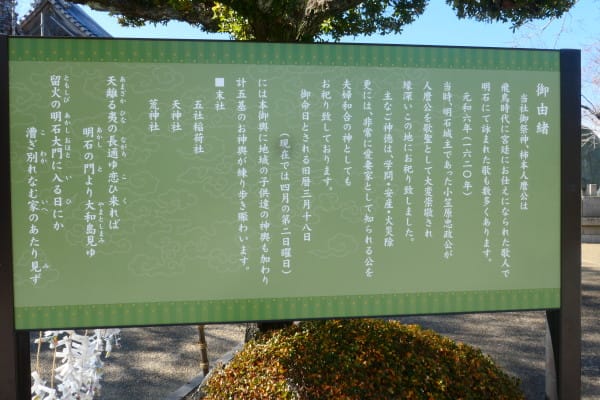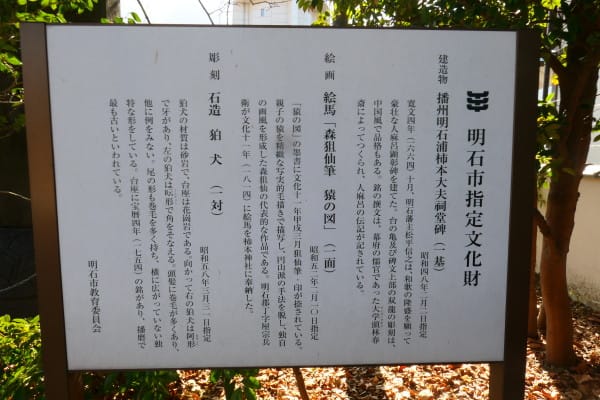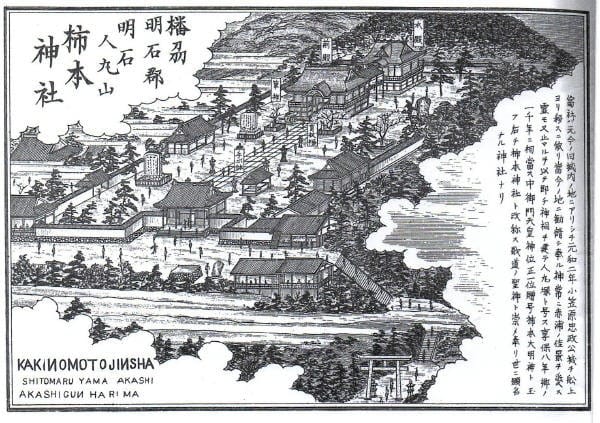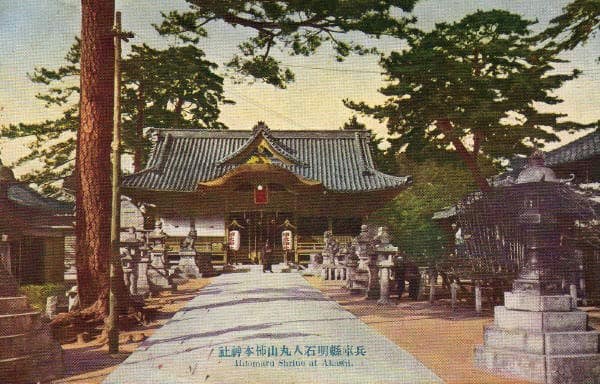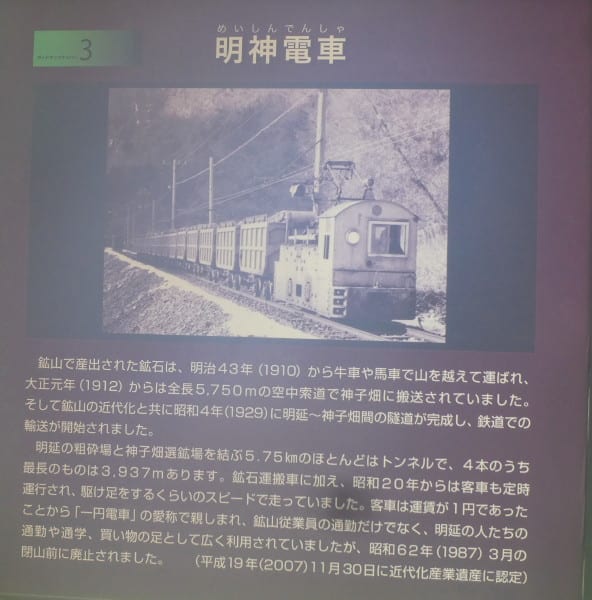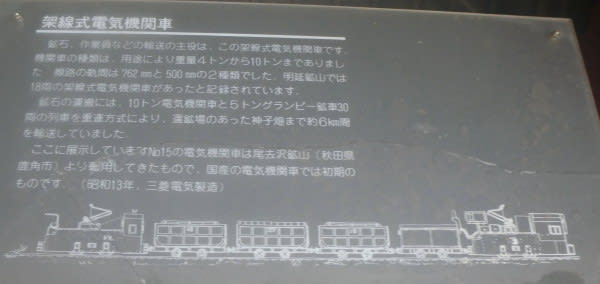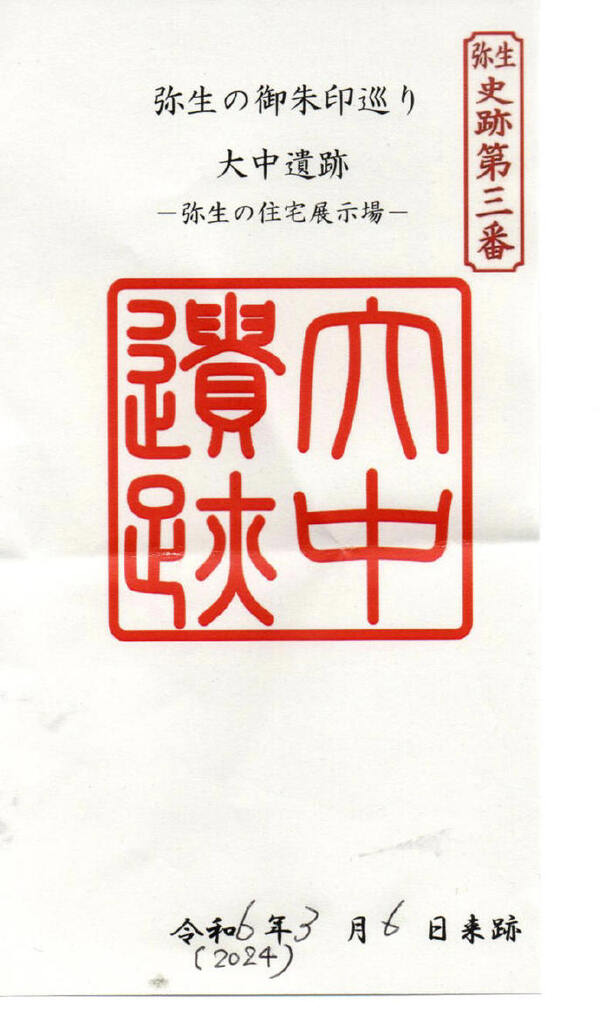2025年6月30日、西脇市の荘林山 荘厳寺(しょうごんじ)を訪問しましたので
写真紹介します。
荘厳寺の基本情報
住所:西脇市黒田庄町黒田1589番地 TEL/FAX:0795-28-4751
宗派:高野山真言宗 山号:荘林山
御本尊:十一面観音
創建:白雉3年(652年) By法道上人
略系図展示室・本堂・多宝塔の内拝 200円
宗派:高野山真言宗 山号:荘林山
御本尊:十一面観音
創建:白雉3年(652年) By法道上人
略系図展示室・本堂・多宝塔の内拝 200円
公式インスタグラム:荘厳寺 - Instagram・写真と動画
所在地のGogleマップを添付しておきます。
境内案内


年中行事

荘厳寺の現地説明板

本堂

上の写真は本堂 御本尊は十一面観世音菩薩 脇侍像仙人
観世音菩薩立像の台座に慶長16年(1611)の銘
多宝塔


鎌倉時代の佐々木高綱により建久年間(1190年代)に建立。本尊は釈迦如来。
現在の建物は正徳元年(1711)に再建。
屋根は桧皮葺きで県下では唯一の多宝塔。雨漏れのため応急処置が施工。
平成12年(2000)、兵庫県重要文化財に指定された。
鐘楼

上の写真は鐘楼。
姫路城主の本多正勝から慶安2年(1649)に寄進されたもの。
弁財天

おふさ地蔵

本堂の敷地内にあります。
八幡宮

宝永5年(1708)に建立された三社八幡宮(上の写真)
持仏堂など

鬼追い行事の面


持仏堂脇のの廊下のショーウィンドーに展示されていました。

上の写真はお寺のリーフレットより鬼追いの説明
黒田官兵衛と荘厳寺




播磨の黒田氏に縁があるとされ、黒田如水、正室・櫛橋光、その父とされる
黒田職隆ら、黒田一族の位牌が納められている
平成23年(2011)に播磨黒田氏研究会が「播磨古事」の研究過程で、
黒田庄町黒田の荘厳寺で所蔵されている「荘厳寺本黒田家略系図」に着目、
その研究を深め、「黒田氏と黒田官兵衛は、西脇市黒田庄町黒田の出自である」
との説を主張されました。