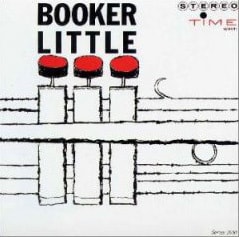この作品の良さがわかるまでには時間がかかった。
このジョン・ウィリアムスのアルバムは以前から通の間で隠れ名盤との評判が高かったので、「どれどれ、どんなものか」と気になって買ってみた。手に入れたのは確か4~5年前、秋葉原だったと思う。
しかし2~3回聴いては見たものの、これといって印象に残るようなものは感じなかったので、そのまま放置してしまっていた。このアルバムはもともと薄い紙ジャケットだったので、いつしか他のCDに紛れ込んでしばらくその存在さえも忘れていたのだ。
しかししばらく経ってから、CDの整理をしようと思って一枚一枚手にとってチェックしていたら棚の奥からこれが出てきた。「お~、こんなのも買ったなぁ~」とか思い出し、久々に聴いてみて「あれっ?」と思った。自分が抱いていた印象とはかなり違ったのだ。
まず驚いたのは鍵盤を叩く指の強さである。特に左手が強い。鍵盤に打ち下ろされる彼の指の角度はほぼ90°なのではないだろうか。そりゃそうだろ、といわれそうだが、ビル・エヴァンスなんかはせいぜい45°くらいの角度しかない。否、エヴァンスの場合はほとんど打ち下ろしがないといっていい。鍵盤と指とがいつも密着している、そんな感じなのだ。
ウィリアムスの場合、これによって曲にメリハリが生まれている。メロディよりもリズムが強調されるのはこうした弾き方のせいだろうと思う。
次に気がついたのは、どこからどこまでがテーマ部分で、どこからがアドリヴ部分なのかが判別しにくいという特徴があることだ。つまり最初から終わりまで小気味よくスイングしておりその境目が見あたらないのである。これは意外と珍しい。私はこうしたピアニストを他に知らない。
ピアニストではないが、こういう類のジャズメンといえばズート・シムズが近い存在かもしれない。もちろんピアノとテナーサックスという楽器の違いはあるものの、私にしてみれば感覚的に同じタイプである。ズート・シムズはロリンズやコルトレーンのような際立った個性の持ち主ではないが、ただただスイングすることだけに執念を燃やした人だった。ジョン・ウィリアムスも同じである。
とにかくこうなると儲けものだ。正に棚からぼた餅(意味が違うか)状態である。
これからは3年経ったら違う耳になっているということを肝に銘じて、しばらく聴いていないアルバムを先入観なしで楽しもうと思っている。