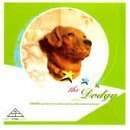90年代のシアトル・ミュージック・シーンは、NirvanaやPearl Jamの出現によって、たくさんの良質のバンドが活躍し、最も盛り上がっていた。
NirvanaやPearl Jamのように世界的にメジャーとなり、人気を博しているバンドはもちろんのこと、インディーズを含め、本当にいいバンドがたくさんあった。もちろん、現在も変わらずに活動しているバンドもたくさんある。
少しここで名前を挙げてみると・・・Green River、Mother Love Bone、Alice In Chains、Sound Garden、The Posies、Mudhoney、The Fastbacks、Young Fresh Fellows、Seaweed、The Squirrels、Love Battery...
私が好きだったり、聴いたことのあるバンドだけでもこれだけある。もちろん他にもまだまだたくさんいる。
グランジというジャンルの草分け的となったシアトル・ミュージック・シーン。Sub Popというレーベルも、当時はかなり盛り上がっていた。
そして、彼らは皆お互い同士の交流がとても深く、必ずどこかで繋がっていた。
そんな中、日本では殆んどメジャーではなかったが、Flopというパワー・ポップ・バンドがいた。
彼らはPosiesと交流が深く、当時PosiesのKen Stringfellowの奥さんだったKim WarnickのバンドThe Fastbacksとシアトルを代表するポップ・グループYoung Fresh FellowsのギタリストKurt Blochのプロデュースで、92年にインディ・レーベルFrontier Recordsからデビューし、翌93年にEpicよりメジャー・デビューした。
今日ここで取り上げるのは、デビュー・アルバム 『flop & the Fall of the Mopsqueezer!』 だが、メジャー・デビュー・アルバム 『Whenever You're Ready』 のジャケなら見たことあるという人もいるかも知れない。(↓)
 『Whenever You're Ready』 1993 試聴はこちら。
『Whenever You're Ready』 1993 試聴はこちら。デビュー・アルバム 『flop & the Fall of the Mopsqueezer!』 の試聴はこちら。
当時の私はわりとシアトル・ミュージック・シーンに精通していて、その頃よく聴いていたPosiesを通じてFlopと出会ったのだが、Posiesが “静” としたら、Flopは “動” 。
Posiesの曲はもちろんパワー・ポップ系もたくさんあるが、どちらかと言えばしっとりと歌う系が多い。ギターの音もディストーションを効かせて少しノイジーだ。
このFlopの音はもっとポップで弾けていて、ギター・メロもストレート。そして私は、Posiesよりも彼らの音楽が好きになった。
私はweezerが好きだが、weezerがここまで人気が出て多くの人に受け入れられているのに反して、Flopは知られないまま・・・というのが少し不思議になる時がある。そしてこの事実にちょっと寂しくなったりすることもある。
weezerに負けず劣らず、良い音楽を作り出している。敢えて違いを述べるなら、やはりRiversの詞の世界かも知れない・・・。
バンドのフロント・マン、Vo.&GのRusty Willoughbyは、Pure Joyというバンドを経て、一時期FastbacksでDrs.を担当し、その後89年にDrs.のNate Johnsonと共にFlopを結成した。
Rustyの書く曲は、とってもポップでちょっとメランコリック。本国では “melodic, driving punk-pop” と言われていた。
単純明快なパンク・ロックとは違い、メロディを大切にしたポップ・ソングが中心なので、そう呼ばれていたのだろう。
もちろん、メジャー・デビュー・アルバム 『Whenever You're Ready』 の方がより良質の曲が詰まっているのだが、インディーズ時代にここまで完成度の高いプレイと楽曲を生み出しているのが凄いと思った。
Soul Asylumにしろ、The Replacementsにしろ、インディーズ時代はまだどこか荒削りで、勢いだけで突っ走ってると感じる部分があったが、このFlopにはそれがなかった。
だから、このアルバムのリリース直後にメジャーからのオファーがあったのかも知れない。
Seattleに遊びに行った時に小さなclubで彼らのライヴを観たが、ライヴでのプレイも完成度が高く、RustyのVo.はとてもホットな気持ちにさせてくれた。
そしてそこには、PosiesやYoung Fresh Fellowsのメンバーを始め、Pearl JamのJef Ament、MudhoneyのMark Armら大勢の彼らの仲間たちが集まっていて、客席は始終盛り上がり、まるで身内のパーティのようだった。仲間同士の交流がいかに深いかということを、この目で実感してきた。
95年に3rdアルバム 『World of Today』 をリリースし、ドライ感とウェット感の両方を持ち合わせた変わらぬいい楽曲を作っていたが、Epicは “シアトル=グランジ” という音を求めていた為、その後Epicを離れて再びFrontier Recordsに戻った。
Rustyのソロが出るとか、数年前までは彼らのニュースもちらほら入ってきていたが、現在は不明。また新しいFlopサウンドを聴きたい。